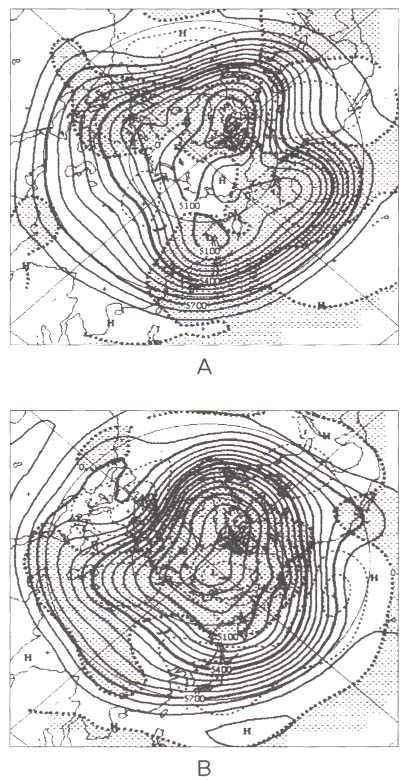練習問題
一般知識
気象学の基礎
ようこそ気象の世界へ
雲ができ、雨が降るしくみ...水の相変化
地球上のH2Oは、気体(水蒸気)、液体(水)、固体(氷)の3つの姿。
| 水蒸気→ | 凝結(600cal/g放出)→ | 水→ | 蒸発(600cal/g吸収)→ | 水蒸気 |
| 水→ | 凝固(80cal/g放出)→ | 氷→ | 融解(80cal/g吸収)→ | 水 |
| 水蒸気→ | 昇華(680cal/g放出)→ | 氷→ | 昇華(680cal/g吸収)→ | 水蒸気 |
飽和水蒸気量[1気圧の場合]
| 空気の温度[℃] |
-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 飽和水蒸気量[g/m^3] |
3.4 | 4.8 | 6.8 | 9.4 | 12.8 | 17.3 | 23.1 | 30.4 | 39.6 |
雲は上昇気流にのってつくられる。雲粒(0.01mmほどの小さな水滴や氷の結晶)
上昇気流が起こる場合
- 地面が強い日射で温められる。
- 低気圧の中心付近に周りから吹き込む。
- 高い山に風がぶつかる(地形的要因)。
- 温かい空気と冷たい空気がぶつかる(前線)。
雲のできる原理
- 日射により地表付近の空気が温められ、上昇する。
- 高度があがると気圧がさがり、膨張、温度が下がる(断熱膨張冷却)。
- 温度が下がると、露点温度に達し、凝結核を中心に水滴ができる(雲粒)。
- さらに空気塊が上昇し、温度が0℃以下になると、凝結核を中心に、小さな氷の結晶もできる。
このように、小さな水や氷の粒(雲粒)が空中に浮かんでいるのが雲。
雲の基本形
| 巻雲(絹雲) | Cirrus
|
| 層雲 | Stratus
|
| 積雲 | Cumulus
|
| 乱雲 | Nimbus
|
| 高い | Alto
|
雲の10種雲形
| 上層(CH) | 巻雲(Cirrus:Ci) | すじ雲 | 雲底6km以上 | 白く細い筋雲
|
| 巻積雲(Cirrocumulus:Cc) | まだら雲 | 白く小さい鱗状の雲
|
| 巻層雲(Cirrostratus:Cs) | うす雲 | 白いベール状の雲
|
| 中層(CM) | 高積雲(Altocumulus:Ac) | むら雲 | 雲底2~6km | 羊の群れ状の塊の雲
|
| 高層雲(Altostratus:As) | おぼろ雲 | 空一面を鼠色に覆う雲
|
| 乱層雲(Nimbostratus:Ns) | あま雲 | 雲底0.6km以下 | 暗い灰色で雨や雪を降らせる雲
|
| 下層(CL) | 層積雲(Stratocumulus:Sc) | くもり雲 | 雲底2km以下 | 決まった形が無く、黒い塊の雲
|
| 層雲(Stratus:St) | きり雲 | 雲底0.6km以下 | 灰色か乳白色で霧雨を降らせる雲
|
| 垂直に伸びる
| 積雲(Cumulus:Cu) | つみ雲 | 雲頂が6kmに伸びることもある | 青空に浮かぶ、白くて大きな塊の雲
|
| 積乱雲(Cumulonimbus:Cb) | 入道雲 | 雲頂が12kmに伸びることもある | 空高くムクムクした雲。雷をともなうことが多い
|
雨は雲粒が成長して雨粒となって落下したもの。雲が浮かんでいるのは、雲粒が非常に小さく、
空気抵抗を受けて落下速度が遅いうえ、上昇気流に支えられているため。したがって、
雲から雨が降ってくるためには、上昇気流に逆らって落下できるほど大きな雨粒である必要がある。
小さな雲粒から大きな雨粒に成長する過程は、以下の二通り。
- 冷たい雨(中・高緯度地方に多い雨)
雲頂の温度が0℃よりもはるかに低温の場合に『冷たい雨』が降る。そうした雲は一番上が氷晶の層、
その下に過冷却水滴の層、さらに下には水滴のままの層というような3層構造になっている。
氷晶と過冷却水滴が共存している雲の中では、過冷却水滴の表面からは蒸発が続き、蒸発した
水蒸気は昇華して氷晶の周りに付着して大きな氷晶(雪片)に成長する。これが落下中に気温0℃以上の地表近くで
融けて雨になって降る。この氷晶が融けずに地表まで降れば、雪。
- 温かい雨(低緯度地方に多い雨)
雲の中の温度が0℃以上で、氷晶を含まない水滴だけの雲から降る雨。
こうした雲の中では様々な大きさの雲粒がそれぞれ違う速度で落下上昇していくときに
大きな雲粒が小さな雲粒にぶつかりそれを取り込んで成長し大きな雨粒になる。こうして降る雨が温かい雨。
雨を降らせる雲は決まっていて、『乱層雲』、『高層雲』、『積乱雲』、一部の『積雲』、など。
風が起こるしくみ...気圧傾度力
基本的には、気圧の高い方から低い方へ吹く。
1気圧=1013.25hPa, 気圧減率:1.2hPa/10m(上空約数kmまで)
コリオリの力→北半球では右にずれる。
気団と前線...巨大な空気塊とその境界
熱帯気団、寒帯気団、極気団、大陸性、海洋性
| シベリア気団 | 主として冬 |
寒冷・乾燥。冬の北西の季節風はこの気団の空気が流れだしたもの。日本海を渡るときに変質する。 |
| オホーツク海気団 | 梅雨期 |
寒冷・多湿。梅雨前線はこの気団と小笠原気団がぶつかった所にできる。陰鬱な天気をもたらす。 |
| 小笠原(太平洋)気団 | 主として夏 |
高温・多湿。夏の南寄りの季節風は、この気団の空気が流れだしたもの。一般に晴天をもたらす。 |
気団と気団の境界面を前線面といい、前線面が地表面と交わる線を前線という。気団と気団の境目は転移層。
| 温暖前線 | 暖気が寒気の上にゆっくり這い上がり、寒気を押し進める。 | 半円 |
| 寒冷前線 | 寒気が暖気の下に潜り込み、暖気を激しく押し上げる。 | ▼ |
| 停滞前線 | 暖気が寒気の上に這い上がるが、境目はほとんど動かない。 | 半円、▼おしくら |
| 閉塞前線 | 寒冷前線が温暖前線に追いついた時にできる。 | 半円▼同方向 |
暖気が寒気の上に這い上がる温暖前線:
- 前線面の傾きは緩やかで、1/100~1/200くらい。
- 前線に伴う雲は前線に近い方から、乱層雲、高層雲、巻層雲、巻雲などであり、広範囲にわたって広がる。
- 前線に伴う雨域は、前線の前方200~300kmに及ぶのが普通で、シトシトと降る穏やかな雨が長時間にわたり降り続くことが多い。
- 温暖前線が通過すると雨が上がり、天気は一旦回復する。その後は暖気域に入るので気温が高くなり、南寄りの風が吹く。
温暖前線面が到達する高さは、普通6kmくらいなので、前線面の水平方向は約1000km前後。
天気変化の激しい寒冷前線:
- 前線の傾きは温暖前線より急で、だいたい1/50-1/100くらい。
- 寒気に潜り込まれた暖気は激しい上昇気流となって積雲や積乱雲などを発生させる。
- 前線が通過する時は風が強まり、激しいにわか雨が降る。時には雷雨や雹が降る事がある。
前線による雨域は数10km程度と狭いので、雨が降る時間はせいぜい1-2時間くらい。
- 前線の通過後は急速に天気が回復するが、寒気域に入るので気温は急激に下がる。風向きは南寄りから北寄りに変る。
- 寒冷前線は暖気の方へ温暖前線より速く進む。
寒冷前線面の傾きが温暖前線よりも急なのは、地表の摩擦の影響があるため。地表付近の寒気は摩擦の影響で進むのが遅い。
温帯低気圧は緯度30-60度付近の前線上で発生する。
- 北からの寒気と南からの暖気がぶつかってできる前線上で発生する。
- 発生後は発達しながら西から東、あるいは北東へ移動する。
- 低気圧の中心から南西方向に伸びる寒冷前線と、南東方向に伸びる温暖前線を伴っている。
- 中心の気圧は熱帯低気圧程低くはならないことが多い。
寒冷前線と温暖前線に挟まれた部分は暖気に、それ以外の部分は寒気に覆われている。
温帯低気圧の影響が及ぶ範囲は、直径2000-3000kmにもなる。
温帯低気圧の一生:
- 発生期:寒気と暖気が接した所に前線(停滞前線)が出来る。前線の一部が波打つと渦ができ、そこに低気圧が発生する。
- 発達期:密度の大きい寒気が暖気の下に潜り込み、暖気が寒気の上に押し上げられ、
反時計回りの渦が発達して中心の気圧がどんどん下がっている。
- 最盛期:温暖前線と寒冷前線が形作る波が大きくなり、寒冷前線が温暖前線に追いつき閉塞前線が出来始める。
中心気圧はさらに下がり、低気圧は最盛期を迎え、風雨ともに最も激しい時期となる。
- 衰弱期:低気圧の中心は、閉塞前線の南西側に取り残され、気圧は上がり始め、低気圧が衰えていく。
日本付近を通る温帯低気圧は上空の西風に流され、西から東または北東に進む。冬に強く夏に弱いので、
平均時速は、春・秋→約30-50km、夏→約20-30km、冬→約50-70km となる。
台風...熱帯生まれの巨大低気圧
赤道をはさんだ南北の緯度が5-25度付近、海面水温が26-27℃以上の海上で発生する低気圧を
熱帯低気圧という。中心に近いほど気圧傾度が大きいので、非常に強い風が吹く。
最大風速が17.2m/s 以上のものを『台風』と呼ぶ。
北半球では7-9月に、南半球では1-3月に、集中して発生する。風は進路の右側で強く、左側で弱くなる。
日射により上昇気流→水蒸気を多量に含んだ空気が流れ込む→自転影響で渦になる。
渦の中心で上昇した多量の水蒸気が上空で冷やされて凝結し、雲粒に変る時に多量の潜熱を出す。
その熱によって周りの空気が温められ、上昇気流はさらに強まり、正のフィードバック。
だから、上陸したり、冷たい海に来たら弱くなる。
台風は積乱雲の集団からなる。巨大な空気の渦巻き。直径100-1500km以上、高さは対流圏界面付近の10-15km。
台風の眼を囲む強い上昇気流の積乱雲→アイウォール。眼の中は下降気流。眼の直径20-50km。
台風の下層では、北半球の場合、温かく湿った空気が左回りに中心に向かって吹きこむ。
眼の壁雲では、対流圏界面近くまで強い上昇気流。上昇した空気は、上層で右回りの流れになって
中心から水平方向に広がる様に吹きだす。
眼が出来る理由:渦の中心近くでは半径が小さくなり、遠心力が強くなるので、それ以上中心に近付けない限界が存在する。
これが台風の眼。勢力が強いとはっきりくっきりする。
太陽系の中の地球
惑星の大気
水金地火:地球型惑星→岩石表面あり、木土天海:木星型惑星→気体で出来ている、冥→準惑星。
K=℃+273.15
金星と火星の大気の主成分は二酸化炭素。残りは窒素とアルゴン。
| 水星: | 重力が小さいため殆ど大気がない。太陽に近く高温(表面温度560K)。 |
| 金星: | CO2を主体とした厚い大気で覆われる。CO2による温室効果で昼夜とも表面温度720K、気圧は地球の90倍。 |
| 火星: | 大気は薄く表面温度180Kと低温。極地では氷(ドライアイス含む)で覆われる。 |
木星や土星の大気成分は主に水素とヘリウム(太陽と同じ)。表面温度は120Kと低温。気体だから、密度は小さい。
| 木星: | 大気の主成分は、H:85%,He:15%、微量のメタン、アンモニアなど。 |
| 土星: | 大気成分の90%以上がH、他はHeなど。 |
地球の大気成分は、中間圏の上限まではどこでもほぼ同じ。N,O,Arの割合は高度約80kmの中間圏界面付近までほぼ一定。
窒素:78%、酸素:21%、アルゴン:0.93%、CO2:0.035%、これは乾燥分の割合。H2Oの量は場所(高度)や時間で大きく変動する。
| 種別 | 赤道半径[km] | 密度[g/cm3] | 表面温度[K] |
表面気圧[気圧] | 大気組成 |
| 地球型 | 水星 | 2440 | 5.43 | 560±20 | ほぼ0 | なし |
| 金星 | 6052 | 5.24 | 720±20 | 90 | CO2,N2 |
| 地球 | 6378 | 5.52 | 280±20 | 1 | N2,O2 |
| 火星 | 3397 | 3.93 | 180±20 | 1/130 | CO2,N2 |
| 木星型 | 木星 | 71492 | 1.33 | - | - | H2,He |
| 土星 | 60268 | 0.69 | - | - | H2,He |
| 天王星 | 25559 | 1.27 | - | - | H2,He,CH4 |
| 海王星 | 24764 | 1.64 | - | - | H2,He,CH4 |
地球大気の起源と進化
地球の大気の起源は火山ガス。原始の地球大気は太陽と同じく水素とヘリウムが主成分。
しかし、太陽風で吹き払われた。その後、火山ガスや温泉ガスが噴出した(脱ガス)。
その成分は、水蒸気:85%、CO2:10%、窒素:5%、硫黄およびその酸化物、鉄、塩素、アルゴンなど。
海洋は火山ガスの主成分である水蒸気が冷えて集まったもの。
誕生したばかりの海洋には火山ガスの微量成分である硫黄、塩素の化合物(亜硫酸ガスや塩化水素ガスなど)
が溶け込んでいたために強い酸性だった。CO2や窒素は酸性の海水には溶けないのでそのまま大気中に残った。
この頃の地球大気は金星や火星とほぼ同じ。
酸性の強い海水に、やがて鉄、アルミニウム、カルシウム、マグネシウムが溶け、その分のアルカリ性で
海水が中和され、大気中のCO2が溶け込んだ。さらに、海水中のカルシウムと溶け込んだCO2が反応して石灰岩が出来た。
| 噴出ガスの成分 | 水蒸気→ | 雨、雪として降って海洋を形成 |
| CO2→ | 大気中に残り、中和した海水に溶け込んだ |
| N2→ | 大気中に残った(現在の地球大気の主成分) |
| 硫黄や塩素の化合物→ | 海水に溶け込んだ |
大気中の酸素は光合成でつくられた。
原始地球の大気には酸素が無く、オゾンも無かったので、紫外線はほとんど減衰せず地表まで来ていた。
だが、海の中までは来ない。海の中で酸素を必要としないバクテリアが最初の生命体として約35億年前に生まれた。
その後光合成をするラン藻類が生まれ、進化した緑藻類が活発に光合成により酸素を発生させ、大気中に酸素が増えた。
酸素が増えると、紫外線との化学反応によりオゾン層が出来て、有害な紫外線がオゾン層に吸収され、地表に達する紫外線が
減り、海面近くでも繁殖できるようになり、酸素の量は、さらに増加した。そういうわけで、CO2は、殆ど光合成によって
消費され、酸素になった。
CO2は温室効果気体として地球温暖化に大きな影響を与える。
現在のCO2の大気に占める割合は、アルゴンより少なく、0.035%しかない。しかし、温室効果ガスとして働く。
温室効果とは、太陽エネルギーを受けた地球表面が放出する赤外線を宇宙空間へ逃がさないようにする働きのこと。
温室効果気体には、CO2の他に、メタン、オゾン、フロンなどがあるがCO2に比べて量が少ない。
H2Oも温室効果気体だが、状況によって量が大幅に変化するので、何とも言えない。
地球全体では、年間降水量と年間蒸発量は等しい。
地球の水の97%は海水。氷河水2.3%、地下水0.61%、湖沼水0.017%、河川水0.002%。
海洋や陸地にある水は、太陽エネルギを受けて蒸発し、水蒸気となって大気中に溶け込み、冷却すると雲になり、雨や雪が降る。
海上への降水は直接海洋に戻り、陸地への降水は地表面を流れる河川などを経て海洋にもどる。また地面に浸透して
地下水となって海洋へ戻る。
大気の鉛直構造
大気圏の層区分
| 熱圏 | 約80kmから大気上限(1000kmとか)。 | 高度と共に気温上昇(-90℃~)。
|
| 中間圏界面
|
| 中間圏 | 約50~80km | 高度と共に気温も低下(0℃~)。ここの上の方から電離層。
|
| 成層圏界面
|
| 成層圏 | 約11~50km | 高度約20kmまでは気温一定(-56.5℃)、それ以上で高度と共に気温上昇。オゾン層はここ。
|
| 対流圏界面
|
| 対流圏 | 地表~平均11(16~8)km | 地表:平均15℃、高度と共に気温低下。
|
成層圏+中間圏+熱圏下層部=中層大気
対流圏:
気温減率:約6.5℃/km(約11km、すなわち対流圏界面まで)、放射で地面が温められて、地面から空気が温められるから。
対流圏界面は、赤道付近の低緯度で約16km、中緯度で約10~12km(変動が大きい)、両極付近の高緯度で約8km、それぞれの間は不連続。
成層圏:
高度約50km付近の成層圏界面で気温極大。対流圏に比べて空気が上下に混ざりにくい。しかし、
強い風が吹いたり、数日で気温が40℃前後も気温変化があったりする。
高度20~30kmにオゾンが多量に存在する(オゾン層)。気温上昇はオゾンが紫外線を吸収して熱
エネルギに変えているから。
中間圏:
気温減率は対流圏の半分以下。中間圏界面(約80km)で気温極小(180K)。大気圏中最低気温。
熱圏:
はっきりした上限はない。高度500kmで1000Kくらい。気温は太陽紫外線の強さによって決まり、一日数100℃も変化。
窒素や酸素の分子や原子が紫外線やX線で電離して電離層を形成。
オゾン層とオゾンホール
オゾン密度極大は高度約25km付近。多いとは言っても大気分子約100万個中一個。
紫外線は上層オゾンに吸収されて次第に弱まりながら下層に達する。つまり、下層よりも上層の方が
紫外線の吸収量が多い。それで、オゾン密度極大高度より、気温極大高度の方が上。
- O2が紫外線(波長0.24μm以下)を吸収してO+Oに(光解離): O2 -(紫外線)-> O + O
- 分解されたOがそれぞれ別のO2と結合してO3に: O2 + O -> O3
- O3は0.25~0.32μmの紫外線を吸収してO2+Oに: O3 -(紫外線)-> O2 + O
対流圏のオゾンは、毒ガス、さらに温室効果気体。
オゾンは低緯度の成層圏でつくられ、大気の流れで成層圏全体に広がる。
平均的には、緯度60度を中心とする高緯度地域で多い。成層圏下層で低緯度から高緯度への流れが
あるから(ハドレー循環がかすめる?)。
冬の間オゾンが蓄積され、春に極大になる。
- (作られるのは低緯度なのに)低緯度で少なく、高緯度で多い。
- 北半球:3~4月に高緯度で極大、南半球:10月に高緯度で極大。
1970年代後半から1980年代にかけて、南極上空春にオゾンホール出現、毎年拡大。
- 成層圏上層に達したフロンは紫外線により分解され、Cl を出す。
- ClはO3と反応してO一個奪って ClO + O2 になる。 Cl + O3 -> ClO + O2
- さらに ClOは O と反応して Cl + O2 になる。 ClO + O -> Cl + O2
- 上3行が延々と繰り返される。つまり、 Cl は O3 を分解して O2 にする触媒として働き、連鎖的にオゾン層を破壊する。
南極の冬は太陽光が射さない極夜のため成層圏の気温が-78℃以下になり、凍った微粒子からなる
極成層圏雲ができる。その雲粒表面で特殊な化学反応が起こり、大気中に多量の塩素分子が放出される。
春(9eから10月)になって紫外線が成層圏に届くと、上記反応により、急激にオゾン層が破壊され、オゾンホールができる。
大気の熱力学
気体の状態方程式と静力学平衡
ボイル・シャルルの法則=気体の状態方程式
P=ρRT, P:気圧、ρ:密度、T:温度(絶対)
静力学平衡(静水圧平衡):ある高度における気圧は、それより上の大気の重さに等しい
⊿p=-ρg⊿z, g:重力加速度
例題1:地表における気圧が1100hPaのとき、その上層1000mの気圧を求めよ。なお、1000mまでの空気密度は1.2kg/m3,g=9.81m/s2
解答:110000-x=1.2*9.81*1000, x=98228Pa=982.3hPa
例題2:地表でも気圧1000hPa, A地点では密度1.1km/m3, B地点では密度1.3kg/m3, g=9.81m/s2, 気圧950hPa となる高度をそれぞれ求めよ。
解答:A:100000-95000=5000=1.1*9.81*Z, Z=463.3.. B:5000=1.3*9.81*Z, Z=392.0...
乾燥断熱減率と温位
乾燥断熱減率:
飽和していない空気塊が断熱的に上昇する場合、断熱減率(9.76≒10℃/km)に従って気温低下する。逆もまたしかり。
温位:
乾燥断熱的に空気塊を1000hPaまで変化させた時の温度。乾燥断熱的な運動では温位は保存される。
高度0m(1000hPa),温度30℃の空気塊A、高度10000m(250hPa),温度-50℃の空気塊B。
Bについて、-50 + 9.76(断熱減率)*10=47.6℃となり、土俵が同じなら、Bの方があったかい。
相変化と空気中の水蒸気
| 水蒸気
|
| ↑蒸発熱2.50*10^6J/kg(597.3cal/g)必要,↓凝結熱、同値 | ↑昇華熱2.84*10^6J/kg(677.0cal/g)必要, ↓昇華熱、同値
|
| 水
|
| ↑融解熱3.34*10^5J/kg(79.7cal/g)必要, ↓凝固熱、同値
|
| 氷
|
蒸発熱(凝結熱)+融解熱(凝固熱)=昇華熱
水蒸気が入っていれば、湿潤空気、飽和水蒸気圧は気温10℃上昇ごとに二倍になる。凝結しなければ、混合比は同じ。
過冷却水に対する飽和水蒸気圧よりも表面に対する飽和水蒸気圧が小さい。
- 相対湿度(湿度)=水蒸気圧(水蒸気量)/飽和水蒸気圧(飽和水蒸気量)
- 混合比:1kgの乾燥空気に対して何gの水蒸気量が混合していか。
- 露点温度:気圧一定で冷却したとき、水蒸気圧が飽和水蒸気圧になったところで凝結する、その温度。
- 湿球温度:乾球温度より低く、乾いているほど乾球温度との差が大きい
| 温度(℃) | 飽和水蒸気圧(hPa)
|
| 50 | 123.3
|
| 40 | 73.7
|
| 30 | 42.43
|
| 28 | 37.78
|
| 26 | 33.65
|
| 24 | 29.82
|
| 22 | 26.40
|
| 20 | 23.37
|
| 18 | 20.61
|
| 16 | 18.16
|
| 14 | 15.98
|
| 12 | 14.03
|
| 10 | 12.28
|
| 8 | 10.73
|
| 6 | 9.35
|
| 4 | 8.13
|
| 2 | 7.05
|
| 0 | 6.105
|
| -2 | 5.27
|
| -4 | 4.54
|
例題:山の最高点:高度1600m,855hPaで8℃、湿度100%,雲粒は存在せず。この空気塊が高度0,1013hPaまで降りた時の相対湿度を求めよ。
ただし、乾燥断熱減率10℃/km、混合比w=0.622*e/p, e:水蒸気分圧, p:大気圧
解答:1.6*10=16, 8+16=24℃, 飽和水蒸気圧:8℃→10.73, 24℃→29.82、
凝結がなく混合比一定なので、0.622*10.73/855=0.622*e/1013。
e=1013*10.73/855、相対湿度は、e/29.82 = 1013*10.73/(855*29.82) = 0.426...≒40%
大気の鉛直安定度
湿潤断熱減率:
空気塊に含まれる水蒸気をすべて凝結させた時の温度を乾燥断熱的に1000hPaまで変化させた時の温度。
水蒸気の凝結、昇華に伴い潜熱が放出されるため、乾燥断熱減率より小さくなる。
水蒸気の凝結量により潜熱が変化するため、空気塊の温度や周囲の気圧で変る。
一般に対流圏下層では水蒸気が多いので 4℃/km、中層では6~7℃/km程度、上層では水蒸気量が少ないので
乾燥断熱減率とほぼ同じ。
本試験では5℃/kmにしてくれている事が多い。
相当温位:
ある点Aの空気塊を乾燥断熱線に沿って上昇していくと、乾燥断熱線と等飽和混合比線との交点Bで飽和に達して
凝結が始まる。このB点を『持ち上げ凝結高度』という。
空気塊はB点から上は凝結を続け、湿潤断熱線に沿って上昇し、乾燥した空気塊になった点をCとする。
Cの乾燥した空気塊を乾燥断熱線に沿って1000hPaまで下降させたD点での温度が相当温位。
持ち上げ凝結高度に達した空気塊を、飽和を保ちながら湿潤断熱線に沿って1000hPaまで下降させた時の温度を湿球温位という。
乾燥大気の静的安定度:
乾燥大気の安定度は、ある空気塊の温度が同じ高さの周囲の温度よりも高いか低いかということ。
周囲より低ければ、安定(ほっといてもそれ以上登らない、負のフィードバック)、高ければ、不安定。
周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率より小さければ安定、そうでなければ不安定。ちょっと、上昇下降させて考えればよい。
湿潤大気の静的安定度:
乾燥断熱減率、湿潤断熱減率、気温減率の大小によって異なり、3種類に分けられる。
- 絶対安定(湿潤断熱減率>気温減率)
空気塊が飽和していてもしていなくても、周囲の大気の気温よりも低くなるので、常に上昇が抑えられる。
- 絶対不安定(気温減率>乾燥断熱減率)
飽和していてもしていなくても、周囲の大気より気温が高くなるので、上昇し続ける。
- 条件付安定(乾燥断熱減率>気温減率>湿潤断熱減率)
飽和していない空気塊に対しては安定だが、飽和している空気塊に対しては不安定になる。
対流不安定:
有る厚さを持った気層A-Bを考える。気層の下部Aは不飽和だが湿度が高く、上部Bは乾燥状態。
今何らかの原因で気層A-BがA'-B'まで持ち上げられたとすると、乾燥した状部Bは乾燥断熱線に沿って温度が低下していき、
B'で持ち上げ凝結高度に達する。
一方湿度の高い上部Aは、まず乾燥断熱線に沿って上昇していき、やがて持ち上げ凝結高度に達し、
そこからは湿潤断熱線に沿って温度が低下してA'に達する
この例の場合持ち上げ後の気層A'-B'の気温減率が湿潤断熱減率より大きければ、その気層は不安定な状態になっているといえる。
このように気層下部の湿球温位が気層状部の湿球温位より高い場合、飽和していない時は絶対安定な気層であっても
気層全体が飽和するまで持ち上げられれば条件付き不安定になる。
これを対流不安定という。湿球温位(相当温位)が高度共に減少している気層は対流不安定。
地形(山)や前線面(寒冷前線)の影響で強制的に上昇させられた空気塊が積雲を生じるのは、対流不安定が原因。
大気の逆転層:
対流圏の温度分布は一般に高度が高くなるにつれて低下するが、特別な気象条件の時に高度に伴って気温が低下する気層が発生する。
これを逆転層と呼ぶ。
- 接地逆転層:
風の無い晴れた夜間における地表面からの放射冷却により、
地表面に近い気層ほど冷却した地面に熱を奪われ逆転層が発生する。逆転層内では気温も露点温度も上空ほど高くなっている。
- 沈降性逆転層:
上空の気層が下降流により下降してくると断熱圧縮で温度が上昇し、下層の温度よりも高くなる。
この結果上層と下層の間に気温の逆転が生じる。これが沈降性逆転層。逆転層内では露点温度が急激に下がっており、上層では
気温と露点温度の差が大きくなり、乾燥している。
- 前線性逆転層:
寒冷な気団の上に温暖な気団が有る時、その境界では上空ほど温度が高くなり、逆転層が形成される。
これが前線性逆転層。逆転層内では気温も露点温度も一様に上昇している。
降水過程
大気中に水蒸気が結構あっても、そう簡単に雨は降らない。
水滴の生成
表面張力が、水滴の表面積を大きくさせないように働くため、水蒸気分子は水滴の中になかなか入れない。
水滴の半径が小さいほど成長しにくい。蒸発は逆に簡単。
過飽和度=(水蒸気圧-飽和水蒸気圧)/飽和水蒸気圧
水蒸気だけでは、まず水滴は成長できない。
エーロゾルと凝結核:
実際の大気にはチリやほこりがある。
| グループ | エイトケン核 | 大核 | 巨大核
|
| 半径 | 0.005-0.2μm | 0.2-1μm | 1μm以上
|
エイトケン核が最も数が多いが、質量では大核が大部分。しかも、大核の半径は可視光線の波長領域と
ほぼ同じ(0.38-0.76μm)なので地表面に到達する日射量や空気の視程などにも大きく影響している。
エーロゾルの起源には以下の物が有る。
- 陸地の地表面から吹き上げられた土壌粒子
- 海水のしぶきが蒸発して出来た海塩粒子
- 火山の爆発噴火によって空気中に放出された火山灰
- 車・工場・焼却などの人間活動に伴い放出された汚染粒子
- 気体として発生したものがその後の化学反応や光化学反応によって微粒子になったもの
(硫酸アンモニウム粒子、硫酸粒子、硝酸ナトリウム粒子など)
エーロゾル粒子の数は、海洋上-10^9個/m3, 陸上-10^10個/m3, 市街地-10^11個/m3
吸湿性、水溶性エーロゾルは、吸湿性のよい半径0.3μmのエーロゾルは、表面が水を吸収して薄い水の被膜が
できると、約0.4%という少ない過飽和度でも平衡状態になれる。これ以上の過飽和度があれば、さらに水蒸気が
凝結し、またもとのエーロゾルがある程度の大きさを持っているので、
水滴はより大きくなる。このように吸湿性のエーロゾルは水蒸気が凝結する時の核の役割を果たす。
このエーロゾルを凝結核という。
たとえば海塩粒子であるNaClなどは、それが溶けた水に対する飽和水蒸気圧を純粋な水の場合よりも低くするという
役割を果たす。
エーロゾルのおかげで過飽和度が小さくても水滴、雲粒を作る事ができる。こうしたエーロゾルの事を
凝結核、雲核、雲粒核と呼ぶ。
通常の雨や雪はpH5,6程度の弱酸性だが、硫酸アンモニウム粒子、硫酸粒子その他の酸性を示すエーロゾルが
凝結核になると、pH2-4の強い酸性を示す雨や雪が降る。これを酸性雨という。
水滴の成長と雨粒の成長
凝結過程による水滴の成長:
水蒸気を含んだ空気塊が上昇すると、断熱膨張して気温が低下する。それにともない相対湿度は大きくなり、やがて
凝結高度に達するとついに飽和する。凝結核が存在すれば、水滴が生成される。
過飽和度が一定であれば、半径の小さい水滴ほど単位時間に半径が増加する割合は大きくなる。
はじめにうちは急速に成長するが、やがて遅くなる。雲粒は0.01-0.1mm, 雨粒は2mmくらいの半径。この差を埋めることが必要。
水滴の落下速度:
空気の粘性による抵抗力は F=6πηrV, η:空気の粘性係数
重力との釣り合いで mg=6πηrV, V=(2ρr^2g)/(9η) つまり、終端速度は半径の二乗に比例する。
併合過程による雨粒の成長(暖かい雨):
水滴だけでできている(氷ではない)雲が大きさの異なる水滴をたくさん含んでいるとき、
大きい水滴は小さい水滴よりも落下の終端速度がずっと大きいので、大きい水滴は小さい水滴に追いつく。
そして合体する。するとさらに終端速度が大きくなる。このようにして水滴は加速度的に成長する。
しかし、実際には雲の中の上昇気流に逆らって落ちるまで成長する。
こうして降る雨が『暖かい雨』である。凝結から降水まで一度も氷の結晶を生じない。
熱帯や夏の温帯に降る。雲頂の気温が0℃以上で雲頂高度もそれほど高くない。
氷晶の生成と成長
過冷却水滴は不純物がなければ-33~-40℃にならなければ氷晶にならない。しかし、
氷晶核があればもっと高い温度で氷晶が生じる。
-40℃以下の雲の中では雲粒はすべて氷晶から構成される。たとえば巻積雲、しかし
積乱雲のように下層から発生する雲の場合には、不純物が氷晶核になるので、もっと低い温度で氷晶が生成される。
- 昇華核:水蒸気が直接昇華し、氷晶の核となる微粒子
- 凍結核:過冷却水滴内に取り込まれ、水滴を凍結させる働きのある非吸湿性微粒子
- 凝結凍結核:凝結核と凍結核の両方の性質を併せ持つ微粒子で、先に水溶性物質が水蒸気から水滴を生成し、
次いで不溶性物質が凍結核として水滴を凍結させる
- 接触凍結核:水滴と衝突して水滴を凍結させる非吸湿性微粒子
氷晶核の数は、場所にもよるが、凝結核に比べてかなり少ない。
氷晶核として有効に働く温度の事を作用温度と言うが、これは氷晶核の種類によって異なる。
土の一種のカオリナイト:-9℃、黄砂:-12~-15℃、火山灰:-13℃
氷晶の成長:
(1)水蒸気の昇華凝結による成長:
空気中の水蒸気が氷晶に向かって拡散して氷晶に直接結合し昇華して成長する過程。
過冷却雲の中で水滴と氷晶が共存する場合、氷晶の方が早く成長する(氷面の方が水面よりも飽和水蒸気圧が小さい)。
(2)過冷却水滴の捕捉による成長:
昇華凝結過程によって大きく成長した氷晶派雪の結晶となり、雲の中の上昇、下降気流にもまれるうちに、
過冷却水滴と衝突してこれを凍結させ、さらに大きくなって結晶の形が分からなくなるくらい丸くなる。これが霰。
積乱雲の場合だと、強い上昇気流が有るため、さらに大きく成長する。直径5mm以上の大きさになって、これが雹。
(3)氷晶同士の衝突・結合による成長:
氷晶の落下速度は水滴同様その形や大きさで異なるため、氷晶同士が衝突し、結合して大きくなる。
冷たい雨:
上記の過程で成長した氷晶が温度の高い空気中を落下している間に融けて雨として地上に降ると『冷たい雨』。
融けずに地上まで達したものが、雹や霰。中緯度から高緯度にかけて降る。日本では、降る雨の80%が冷たい雨。
雪や霰が融ける早さは氷晶が周りの空気から熱伝導で受け取る熱と氷面から水が蒸発するときに奪われる
潜熱の大小関係によって決まる。したがって空気が乾燥している時には昇華蒸発が活発に行われ、気化熱による冷却が強くなるので
氷晶は溶けにくくなる。
| | 暖かい雨 | 冷たい雨
|
| 降水の過程 | 氷晶の状態が無い | 氷晶の状態を経て落下中に融ける
|
| 雲粒の生成 | 凝結核に水蒸気がつく | 過冷却水滴が氷晶核に付着するか、約-40℃以下で凍結
|
| 降水地域 | 低緯度から中緯度 | 中緯度から高緯度
|
対流雲と層状の雲
積雲系の対流雲:
対流不安定な成層のなかで強い上昇気流が起こると、鉛直方向に発達した積乱雲が生じる。
夏の強い日差しによる上昇気流、寒冷前線の接近で暖かい空気が押し上げられる、
上空に寒気が流入して下層の暖気が不安定になる、台風のような発達した低気圧の中心付近での激しい上昇気流など。
上層では0℃以下になっており、過冷却水と氷晶が共存、それ以上では氷晶だけ。
時間が経つと周囲の乾いた空気が流入し、雨滴や雲粒を蒸発させながら冷却、下降するので
上昇気流もなくなり雲粒も生成されなくなって衰退・消滅する。寿命は30min~1h。ただし、スーパーセル型になると、長く続く。
層状の雲:
温暖前線の前線面を空気塊が上昇する場合、前線の接近に連れて、上層雲→中層雲→下層雲の順で通過していき、
天気も緩やかに変化する。
まず、巻雲(氷晶雲)が上層に、次に薄いベール状の巻層雲(氷晶雲)が、次に厚さ2~3kmの高層雲が空全体を覆い、雲底が次第に
地表へ近づいてくると、冷たい雨が降り始める。これは、雨雲と呼ばれる乱層雲。
| | 対流雲 | 層状の雲
|
| 特徴 | 強い上昇気流により鉛直に発達する積雲系の雲 | 広範囲に水平に広がって層を成す雲
|
| 発生条件 | 夏の強い日射
寒冷前線の接近による暖気の上昇
上空の寒気流入による不安定
発達した低気圧の上昇気流 | 温帯低気圧に伴う温暖前線の前線面を空気塊が上昇する場合
|
| 雲の種類 | 積雲、積乱雲 | 上層雲:巻雲
中層雲:高層雲、高積雲、乱層雲
下層雲:層積雲、層雲
|
霧
直径数10μm以下の小さな水滴(or氷晶)が地表面付近の空気中に浮かんでいて、
地表面付近における水平方向の視程が1km未満となる現象(1km以上の場合は『もや』)。
湿った空気が冷やされて気温が露点温度まで下がるか、空気が飽和に達するまで水蒸気が補給されるか、
あるいはこの両者が同時に起こって発生する。
霧の中に多量のちりやほこりや煤煙が混じって視程が2km以下になったものをスモッグという。スモッグは
空気中に多量の石炭の燃えカスである粉塵が放出され、その微粒子が水蒸気の凝結核となった事により発生する。
霧の中に多量の煤煙と亜硫酸ガスが溶け込んでいるものであり、ちりやほこりや煤煙が地表近くに漂う条件
(上空に逆転層が有る場合)と霧の発生条件とが一緒になった時に発生する。
| 放射霧 | 移動性高気圧に覆われた風の無い晴天の夜間などには地表面(海面)からの
赤外放射による放射冷却で地表面付近の空気の温度が下がり、明け方に発生する霧。日の出後は
気温が上がり、霧粒は蒸発して消える。
|
| 移流霧 | 湿った暖かい空気が温度の低い地表面上に移動して冷やされて発生する霧。
北海道近海や東北日本の太平洋上や日本海上で暖かい南の海洋上にあった温暖な空気が北上し、
冷たい海洋上で冷やされて発生する海霧はその典型。
|
| 蒸気(蒸発)霧 | 移流霧とは反対に暖かい水面上に冷たい空気が流れ込んだ時に
暖かい水面から蒸発した水蒸気が冷たい空気中に入って冷えた為に発生する霧。川霧などが代表。
|
| 前線霧 | 温暖前線に伴って発生する。温暖前線の上側の暖かい空気中に出来た雨粒が
前線面の下にある冷たい空気中で蒸発し、それが再び凝結して発生する。
|
| 混合霧 | 温度の異なる二つの湿った空気が混合する時に発生する霧。
|
| 滑昇(上昇)霧 | 湿った空気が山の斜面や温暖前線を這い上がる時に断熱膨張によって
気温が下がり、そのために発生する霧。山霧はその典型。
|
大気における放射
地球が太陽から受けているエネルギは、全体の20億分の1。全世界で消費されるエネルギは地球が受ける太陽放射エネルギの15000分の1。
入射する太陽放射量
地表における放射強度:
地球大気の上端において太陽光線に垂直な単位面積が単位時間に受ける太陽放射エネルギ量を太陽定数といい、1.4kW/m2。
また、ある平面の単位面積に単位時間当たり入射する放射エネルギ量を放射強度I(W/m2)という。
一般に放射強度は途中の経路での散乱・吸収を無視すると、エネルギ源からの距離dの2乗に反比例する。
太陽高度と放射強度:
太陽高度が90°に近いほど太陽放射エネルギを受ける量は大きい。0°になれば、0。
太陽高度角をα、太陽光線に対して垂直な平面の面積So、それが受ける放射強度Io とすると、地表面に達する放射強度 I は、
Io*So = I*Se, I = Io*(So/Se) = Lo*sinα
- 緯度による太陽高度角の変化:
春分秋分のとき、sin(90-α)倍になるので、赤道に近い程受け取るエネルギが多い。
- 季節による太陽高度角の変化:
自転軸は23.5度傾いている。06/20:夏至の頃最大、12/22:冬至のころ最小、09/23,03/20:春分秋分で中くらい。
- 1日の時刻による太陽高度角の変化:
正午に高度角最大で受けるエネルギも最大だが、熱容量が有るので、気温最高は13:00~14:00位の時刻。
- 地球が受け取る太陽放射量:
地球が受け取る太陽放射のエネルギ量は、太陽高度角の要因によるもののほか、太陽と地球の距離による差がある。
地球の公転軌道は楕円なので、近日点と遠日点で受け取るエネルギは変化する。
黒体の放射特性
全ての波長の電磁波を完全に吸収する仮想的な物体。これは与えられた温度で理論上最大のエネルギを放射する物体でもある。
太陽や地球は黒体で近似できるらしい。
黒体の放射特性に関する法則:
黒体が放射する全エネルギは絶対温度の4乗に比例する。
- プランクの法則
I(ν,T)=(2hν^3/c^2)*(1/(e^(hν/(kT)) -1)), ν:周波数, T:温度, h:プランク定数, k:ボルツマン定数, c:光速
さまざまな温度における、波長と単位波長あたりの放射強度の関係を理論的に指数関数として表した法則。
- ステファン・ボルツマンの法則
I=σT^4 放射強度は絶対温度の4乗に比例。σ:ステファン・ボルツマン定数=5.67*10^-8[W/m^2*K4]
- ウィーンの変位則
λm=2897/T 単位波長あたりの放射強度が最大となる波長λm[μm]は、黒体の表面温度Tに反比例する。
ex. 太陽の表面温度=5780K, 2897/5780≒0.5μm, 地球の平衡温度=255K, 2897/255≒11μm。
- キルヒホッフの法則
αλ=ελ, 放射率と吸収率は等しい。
放射平衡温度と太陽放射・地球放射
アルベド(反射能):地球の大気上端に達した太陽放射量に対する、反射によって宇宙空間に戻される分の比。一般に0.3。
陸の方が海よりよく反射する。
S(1-A)=4I, S:太陽定数, A:アルベド, I:地球放射強度、I≒240[W/m^2](円の面積*4=球の表面積/4)
ステファン・ボルツマンの法則を用いて、
240=(5.67*10^-8)*T^4, T=255K
太陽放射は主に可視光(短波放射)波長:0.5μmピーク、地球放射は主に赤外線(長波放射)波長:11μmピーク。
地球大気による吸収
太陽放射の内訳:46.6%が可視光線(0.38-0.74μm)、46.6%が赤外線(>0.74μm)、7%が紫外線。
波長0.3μm以下の紫外線は対流圏界面(11km)に達する前にO2, O3にほぼ完全に吸収される。可視光線領域はほとんど吸収されない。
赤外領域は主に水蒸気に吸収される。
地球放射に対する大気の吸収は主に水蒸気とCO2。波長11μmを中心とした8~12μmの赤外領域は地球大気に
吸収されずに宇宙空間に出ていく。この領域を窓領域(大気の窓)という。
温室効果:
CO2とH2Oは、可視光は透して赤外線は吸収する。地球の放射平衡温度の実測値は、288Kで、前述の計算値の255Kよりもずいぶん高い。
これは温室効果のせい。他に、メタン,フロン,N2O,O3 等がある。成層圏では、このメカニズムは逆に温度を下げる。
大気による散乱
レイリー散乱:
入射してくる電磁波の波長がそれを散乱させる粒子の半径よりもずっと大きい(10倍以上くらい)のが、レイリー散乱。
空気分子や、エーロゾルよりずいぶん小さい粒子による散乱。
散乱した電磁場の強度はその波長の4乗に反比例する。空が青く見えるのや、日の出日没で空が赤く見えるのは、レイリー散乱。
ミー散乱:
波長と粒子の半径がほぼ同じくらいのがミー散乱。ミー散乱の強さは、波長によらずほぼ同じ。エーロゾルによる散乱。
中国の空が白く見えるのや、雲が白く見えるのはミー散乱。
地球大気の熱収支
地球全体でのエネルギ収支はつりあっているはず。
太陽放射の受け取り:
地球の半径:r, 断面積:πr^2, で受けた太陽放射が、球の表面積の半分:4πr^2 に行きわたる。4で割ればいいから、
太陽放射の平均値は≒342W/m^2、このうち77W/m^2(22%)が雲、エーロゾル、大気による反射と散乱で宇宙に戻される。
また地表面からの反射で30W/m^2(9%)が戻される。足したら31%となり、これがアルベド。
残り235W/m^2(69%)のうち、地表面が吸収するのは168W/m^2(49%)、雲を含んで大気に吸収されるのは67W/m^2(20%)になっている。
地球表面の熱収支:
地表面は地球放射として390W/m^2を放射しており、大気から324W/m^2を吸収している。一方水の蒸発による潜熱
の形で78W/m^2が地表面から大気に移動する。さらに、伝導(地表面→大気)で顕熱として24W/m^2移動する。
計算すると、-390+324-78-24=-168W/m^2 の熱が地表面から失われている。これが太陽放射を地表面が受け取る分とつりあっている。
大気圏の熱収支:
大気による太陽放射の吸収が67W/m^2、地表からの潜熱と顕熱が78+24W/m^2、地表面からの長波放射が350W/m^2、
合計して519W/m^2。一方大気圏から地表面へ -324W/m^2、宇宙空間へ(-165-30)W/m^2、合計して -519W/m^2。
つりあっている。
大気圏外でも 342-(107+235)=0 でつりあっている。
大気力学の基礎
ニュートンの力学とベクトル
- 慣性の法則
- 運動方程式:F=ma, F:力, m:質量, a:加速度
- 作用・反作用の法則
コリオリの力
北半球で進行方向右向き、南半球で左向きに、作用する。
F = m * 2 * V * ω
地球上では: C = 2 * m * V * Ω * sinφ
C:コリオリの力の大きさ, m:質量, V:速度(風速), Ω:自転速度(7.294*10^-5/s), φ:緯度
f=2Ωsinφ:コリオリ・パラメータを使って C=fmV, 単位質量あたりなら C=fV
地衡風・傾度風・旋衡風
気圧傾度力:
Pn=-1/ρ*⊿P/⊿n, ρ:密度, ⊿P:気圧差, ⊿n:距離
地衡風とその風速:
気圧傾度力とコリオリの力がつり合う。地衡風の速度:Vgとすると、
-m/ρ・⊿P/⊿n = 2mVgΩsinφ → Vg = -1/(2ρΩsinφ)・⊿P/⊿n
通常は、密度を考えなくてよい Vg=-g/f*⊿z/⊿n, ⊿z:等圧面高度差 を使う。
傾度風:
等圧線が曲線の時に、気圧傾度力、コリオリの力、遠心力の3力がつり合う。高気圧の時に強く吹く。
- 高圧部...(気圧傾度力) + (遠心力) = (コリオリの力)
- 低圧部...(気圧傾度力) = (遠心力) + (コリオリの力)
遠心力:rω^2 = V^2/r
- 高気圧では Pn = fV - V^2/r
- 低気圧では Pn = fV + V^2/r
Pn:気圧傾度力, V^2/r:遠心力, fV:単位質量にかかるコリオリの力
旋衡風:
遠心力と気圧傾度力のつり合い。半径が小さい時。竜巻とか。
Pn = V^2/r
地衡風と温度風の関係
中緯度地方においては、温度傾度が大きいので上空にいくほど地衡風の西風成分が増す。
層厚:
二つの等圧面の高度差、等圧面間の平均温度に比例。あったかいと厚い。つまり低緯度で大きく高緯度で小さい。
層厚の水平傾度と地衡風の強さ:
上空に行くほど、傾き(気圧傾度)は大きくなる→地衡風速も大きくなる。
温度風:
上空に行くほどベクトル差が大きくなる。差分ベクトルは等温線に沿って、北半球では高温側を右に、南半球では左に
見るようなベクトルとなる。この仮想的な差分ベクトルを温度風という。温度風は南北の温度傾度が大きい地域ほど
大きくなる。北緯30-60度付近。
地表付近の風
地上風:
摩擦力が働くため等圧線と平行にならない。摩擦力とコリオリの力のベクトルの合成が気圧傾度力
とつり合うように吹く。
F = Pn sinα, C = fV = Pn cosα
F:摩擦力, Pn:気圧傾度力, α:等圧面に対する角度, C:コリオリの力, f:コリオリパラメータ, V:風速
地衡風と比べて摩擦力の分弱くなる。αは、陸上では30-45度程度、海上では平坦な為15-30度程度。
大気境界層:
接地層の上にエクマン層。高度50-100mが境目。高度があがるにつれ、地衡風に近い風向風速になる。
いろいろな気象現象のスケール
| マクロスケール(2000km以上) | 地球規模(プラネタリー・スケール) | エンソ
|
| 総観規模(シノプティック・スケール,2000-数千km) | モンスーン
|
| メソスケール(2-2000km) | メソα | 台風
|
| メソβ | 海陸風,山谷風,メソ対流系(雷雨,集中豪雨,スコールライン)
|
| メソγ | 積乱雲
|
| ミクロスケール(-2km) | 竜巻,つむじ風,大気境界層内の乱れ
|
発散・収束と渦度
地表で上昇気流→収束、下降気流→発散
反時計回り(低気圧性の回転)→正の渦度、時計回り(高気圧性の回転)→負の渦度
気象現象の実際
大規模な大気の運動
梅雨前線、秋雨前線、温暖前線、寒冷前線、温帯低気圧、日本海側の大雪→大規模な大気の運動。
大気の大循環
太陽放射→緯度による差→温度差→有効位置エネルギや熱の輸送。
地球の年間熱収支:
低緯度(北緯38-南緯38度)で+、それより高緯度でー。熱エネルギーは様々な形で
運搬されるため地球全体で収支は0。
南北方向の循環(平均子午面循環):
ハドレー循環、フェレル循環、極循環
- ハドレー循環:
低緯度地域の循環。赤道付近で暖められた空気が上昇して上空で高緯度側に移動するが、
緯度20-30度で亜熱帯ジェット気流に遮られて下降する。地表付近では逆に北東の風(貿易風、偏東風)が吹く。
これは北半球の話で、南半球では南東の風になる。
- フェレル循環:
中緯度地域の循環。緯度20-30度(亜熱帯高圧帯)と緯度50-60度(寒帯低圧帯)。地表では西風。
一年を平均すると、温度の高い空気が下降し、温度の低い空気が上昇していることになるが、これは見掛け上のもの。
- 極循環:
極地方の弱い循環。緯度50-60度で上昇し、極地方で下降し、地表でまた緯度50-60度に戻る(極偏東風)。
| 熱帯収束帯 | 赤道付近 | 地表が太陽放射で加熱され上昇気流で低圧になり南北の亜熱帯低圧帯から貿易風がふきこんでくる。海洋上で顕著。
|
| 亜熱帯高圧帯 | 緯度20-30度 | ハドレー循環により下降気流が生じて出来る高圧帯。
|
| 寒帯低圧帯 | 緯度50-60度 | 極付近で低温空気が滞留する(極高圧帯から中緯度への流れ)のと亜熱帯高圧帯から
高緯度への流れが衝突してできる上昇気流。
|
東西方向の循環
東西方向に吹く風の原動力は、緯度の差による温まり方の違いが生み出す気圧傾度力。それとコリオリの力によって吹く地衡風。大体平均すると、
赤道側で気圧は高く、極側で気圧は低い。さらに、対流圏上空ほど西風成分が卓越する。それは赤道から極に向かう温度傾度による温度風
が生じるから。特に中緯度では、西風は強くかつ定常的に吹く。これを偏西風という。
北半球冬の等圧面上の投稿度線が歪むのは、山脈などの地形の力学的効果や、海と陸の分布による熱的効果のため。
偏西風が大きく蛇行し、かつ強く吹く。夏は、温度傾度が緩やかになるので、偏西風は穏やかになる。
モンスーン循環
大陸と海洋の比熱の差による季節風、つまり、海陸風の地球規模の奴。アジアにおける夏は、インド洋や西部太平洋から
相対的に暖かいチベット高原に向かって吹く(南西季節風)。海から吹いてくる風により大陸に
雨季(日本の梅雨にも影響)をもたらし、潜熱の放出に
より正のフィードバック。対流圏界面ではチベット高気圧が発達し、逆に海に向かって循環する。
冬は、シベリア高気圧から相対的に暖かい太平洋に向かって吹く(北西季節風)。日本海を通過する時に水分を補給し、
日本海側に雪を降らせる。
中緯度における大気の擾乱
偏西風は南北に蛇行しながら中緯度上空で地球を一周する。
それにより地上では前線が形成され温帯低気圧や移動性高気圧が生じる。
超長波と長波:
偏西風帯の大規模な波動。赤道から極への温度傾度により傾圧不安定が生じ
これを解消するために南北方向への循環が起こる。実際には、地球の自転軸の
傾きに起因する季節の変化や地表面の海陸分布による大気の流れへの影響
などにより、大気の大循環だけでは不安定は解消しきれない。
そのためさまざまな大気の擾乱が生じる。その中で最も大規模なものが、
超長波と長波。
| 超長波 | 水平波長7000-30000km程度、寿命は数10日、水平波長は地球の半径と同程度。
地衡風に近似する。中緯度の偏西風波動や成層圏の準二年周期振動が代表。
|
| 長波 | 水平波動3000-8000km程度、寿命は一週間程度。傾圧不安定波。超長波
程ではないが、地衡風に近似する。温帯低気圧や移動性高気圧を発生させる傾圧不安定波が長波の代表。
|
波数:地球一周の間の波の数。波数1-3(超長波)→プラネタリー波。
傾圧不安定波:
温度傾度を解消しようとして生じる波動。南北に熱を輸送する。
中緯度上空で4-6回蛇行する波長数千kmのスケールのものが最も発達しやすい。
傾圧不安定波は温度傾度だけで発生するが、プラネタリー波は、地形や海陸分布などの外部的要因がなければ発生しない。
ジェット気流と偏西風波動:
対流圏の大部分では、等高度線に沿って偏西風が波打って吹いている。その風速は
鉛直方向上層に行くほど強く、水平方向では亜熱帯から中緯度にかけて強くなる。
とくに幅が狭く風速の大きい流れをジェット気流という。緯度30度付近に沿って吹く
亜熱帯ジェット気流と、寒帯前線付近を吹く寒帯前線ジェット気流などがある。
北半球中緯度冬の等圧面上の等高度線は、日本列島と北米大陸東岸上空で大きく南側へ張り出している。
そのため偏西風も南北方向へ蛇行している。これを偏西風波動という。
偏西風波動はハドレー循環によって亜熱帯高圧帯まで運ばれてきた熱を高緯度地域に輸送する。
この熱輸送をロスビー循環という。
亜熱帯ジェット気流の方が寒帯前線ジェット気流よりも明瞭。
寒帯前線:寒帯気団と熱帯気団の境界に出来る前線。この前線上で温帯低気圧が発生する。
気圧の谷(トラフ)と尾根(リッジ):
地衡風+低気圧(反時計回りの渦)+高気圧(時計回りの渦)=偏西風波動。
高緯度から低緯度に波打っている所がトラフ、低緯度から高緯度に波打っているところがリッジ。
地上の低気圧が発達中の時、気圧の谷の軸は上空に向かって西に傾いている。そのため、
その前方(東)には暖かい南風(暖気移流)と、それにともなう上昇気流が、
後方には冷たい北風(寒気移流)と、それにともなう下降気流がある。
気圧の谷は地上の低気圧と、尾根は地上の高気圧と結びついている。
| 気圧の谷(トラフ) | 低気圧や低圧部から細長く伸びる気圧の低い地域。
気圧の谷がのびる方向に直行する断面をとると、気圧の谷の所が気圧の最小となる。また
上層の気圧の谷の東側では、地上低気圧の発生、発達が多く見られる。
|
| 気圧の尾根(リッジ) | 高気圧や高圧部から細長くのびる気圧の高い地域。
気圧の尾根がのびる方向に直行する断面をとると、気圧の尾根の所が気圧の最大となる。
また上層の気圧の尾根は、その東側の地上に移動性高気圧を伴う。
|
前線の形成と温帯低気圧
温帯低気圧→東西2500kmの傾圧不安定波。
温帯低気圧のエネルギー源:
水平温度傾度による有効位置エネルギー。寒気が下に、暖気が上に回り込み、運動エネルギーに変換→風。
実際には、ちとややこしい螺旋の動き(コリオリの力)。
北半球中緯度の場合、低緯度側の暖気を前方(東側)から取り入れて高緯度側に運び、
高緯度側の寒気を後方(西側)から取り入れて低緯度側へ運んでいる。このとき、低緯度側から取り入れた
暖気は渦を巻いて上昇し、高緯度側からの寒気は渦を巻いて下降する。
温帯低気圧のライフサイクル:
地上天気図と高層天気図を同時に観て立体的に把握し判断することが必要。発達衰退の進行につれて、
偏西風の蛇行がきつくなる。
- 第1期(発達初期):
500hPaの高層天気図における気圧の谷の西側では西から東への気流が収束し、北西側にある寒気が南下しようとする。
一方気圧の谷の南側にある暖気の北上に伴い、気圧の谷の下になる地上天気図では、低気圧性の
反時計回りの渦が生じやすくなる。
この渦は地上天気図では北西側からの寒気が暖気側へ張り出す事によって寒冷前線を形成し、
南東側からの暖気が寒気の上へ流れ込むことによって温暖前線を形成する。この渦により、地表付近の暖気と寒気は
反時計周りの上昇気流が生じると、温帯低気圧を発生させる。
- 第2期(発達中):
上層の気圧の谷で生じた渦によって寒気が南下し、偏西風の波動は大きく低緯度側へ蛇行して渦が強まる。
これにともない地上天気図の温帯低気圧の中心に対して、寒冷前線では寒気が暖気の下に潜り込んで
南から南東方向に移り、温暖前線では暖気が寒気の上を滑昇し北上する。
反時計回りの渦である低気圧の上昇気流が強まり、寒冷前線と温暖前線が長く伸びて温帯低気圧としての勢力は
大きく発達する。また、地上天気図の温帯低気圧の中心は上層の気圧の谷の東側にある。つまり、
地上と上層の低気圧の中心を結んだ軸は、高度と共に西に傾いている。
- 第3期(発達期から衰退期へ):
上層の気圧の谷に寄る偏西風の波動は発達期よりもさらに南へ蛇行し、寒気の渦は極側の寒気から分離して
上層気流も弱まる。
一方地上天気図では移動の早い寒冷前線が温暖前線に追いついて閉塞前線を形成する。
温帯低気圧から閉塞前線が長くなるとともに前線による反時計回りの渦が弱まり、温帯低気圧の勢力は
次第に衰弱して消滅してしまう。またこの頃には、気圧の谷の軸はほとんど垂直になる。
閉塞前線において、
- 寒冷前線北側の大気が温暖前線北側の大気より冷たい場合→寒冷前線に似る
- 寒冷前線北側の大気が温暖前線北側の大気より暖かい場合→温暖前線に似る
前線の形成過程:
前線とは、異なる性質の二つの気団(水平スケール数千kmの高気圧としての発現地の性質を保持した空気塊)の
地表における境界線のこと。また、その上空には気団の境界面があり、これが前線面。
前線面は、温度や密度が隣接する両方の気団へと徐々に変化している転移層。
時と場所によっては、大気の流れの中に転移層の幅を時間と共に小さく(水平温度傾度を大きく)
しようとする働きをもつものがある。このように、前線の形成、強化させる過程を前線形成過程(前線強化過程)
という。
大部分の温帯低気圧は偏西風の波動が傾圧不安定によって発達したものだが、この流れの中に前線形成過程を
生じる気象要素が含まれている。本来の傾圧大気中の緩やかな水平温度傾度が徐々に強化されることで、
1-2程度の比較的短い期間に 10-100km程度の範囲で帯状に強い温度傾度が形成される事がある。
これが温帯低気圧にともなって形成される温暖前線や寒冷前線ということになる。
なお、反対に前線における温度傾度を弱めようとする過程もある。これは前線消滅過程(前線衰弱過程)という。
前線の形成過程も消滅過程も大気の流れと温度分布との相互関係によって決まる。
移動性高気圧
温帯低気圧の前後を低気圧と共に移動していく高気圧の事を言う。
同じく傾圧不安定波で、直径数千kmの規模。偏西風帯の波長が5000km程度の波動に反応し、3-5日くらいの
間隔で周期的に通過する。
温帯低気圧とは逆に、前方で寒気に寄る下降気流を伴う。そのため日中は爽やかな天気だが、夜間は放射冷却により冷える。
後方は次の温帯低気圧の前方にあたるため、上空には南西から暖湿な空気が入り入り始めるので、上層雲や中層雲が
広がって来て天気は下り坂になる。このとき前方で生じる寒気は暖かい空気の下に潜り込みながら、
低緯度側へ吹きだしている。このように温帯低気圧と同じく、移動性高気圧も中緯度における
南北方向の温度傾度を弱め、熱輸送を担っている。
移動性高気圧に対して、地形や海陸分布の要因による、シベリア高気圧や太平洋高気圧などは、停滞性高気圧という。
大気中の熱輸送と水蒸気の循環
大気中の熱輸送最大は、北半球では緯度50度付近。主に傾圧不安定波が極向きに輸送。
緯度30度までは、南北の循環(平均子午線面循環→ハドレー循環)の方が大きな役割を果たすが、それより高緯度では、擾乱すなわち
傾圧不安定波などの方が役割が多い。
水蒸気の循環:
水蒸気の不足は大気の循環によって補われる。
亜熱帯高圧帯のある場所では水の蒸発量が多い。陸地なら砂漠が多い。
赤道付近→熱帯収束帯では降水量が蒸発量を大幅に上回る。逆に緯度20-30度→亜熱帯高圧帯では蒸発量の方が多い。
エントロピ増大の法則により、亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に吹く貿易風(ハドレー循環)が、水蒸気も輸送してくれる。
中緯度地域で降水量が蒸発量を上回っているのは温帯低気圧や前線による降水のため。
北半球の場合、北緯40度以北では降水量が
蒸発量を上回っているので、大気中の水蒸気は不足していく。不足した水蒸気は、そのすぐ南の、蒸発量が
降水量を上回る(大気中の水蒸気が過剰)地域から大気の循環に伴って水蒸気が補われている、というように
考える。同様に、赤道地域の水蒸気の不足は、やはり北緯20度くらいまでの亜熱帯高圧帯から吹いてくる
風に伴って補われている、と考える。
中小規模の大気の運動
台風、梅雨前線に伴う集中豪雨、冬の日本海の筋状の雲、時として気象災害をもたらす中小規模の大気の運動。
中小規模の大気運動の特徴
対流圏の厚さ≒10km、中小規模の大気の運動では鉛直方向の運動が無視できない。
水平スケール≒2000km以下。
区分:
オーランスキー1975、メソαβγ。
| メソα | 200-2000km | 数日 | 台風、前線、梅雨前線上の低気圧、ポーラーロー
|
| メソβ | 20-200km | 数時間~半日 | 海陸風、クラウドクラスター、スコールライン、ジェット気流
|
| メソγ | 2-20km | 数時間 | 積乱雲、ガストフロント、筋状の雲、オープン・セル、クローズド・セル
|
| ミクロα | 200m-2km | 一時間前後 | 竜巻、積雲、山岳波
|
| ミクロβ | 20m-200m | 数10分 | つむじ風、乱気流
|
| ミクロγ | 2m-20m | 数分 | ごく小さなつむじ風
|
中小規模の大気の運動は、より大きな規模の大気の運動に含まれて出現する。内部構造やライフサイクルも
大きな規模の大気の運動に大きく影響される。またメソβやγの運動がまとまってメソαの運動になるなど、
d中小規模の大気の相互間で影響し合ったりする。したがって、中小規模の大気の運動を考える場合は、個別の
メカニズムだけを考えるだけでなく、さまざまなスケールの運動相互の繋がりも常に頭に入れておかなければならない。
メソスケールの運動エネルギー源→傾圧不安定と静力学不安定:
大気の有効位置エネルギ→水平温度傾度と鉛直温度傾度。メソスケールの場合は、水平スケールに比べて鉛直方向の
運動が無視できないため、この2種類。鉛直温度傾度に起因する有効位置エネルギは静力学不安定→対流。
自由擾乱と強制擾乱:
大気内部の力学的不安定による要因と、大気外部からの力学的・熱的強制力による要因。
大気内部の要因→主に大気の力学的不安定によるもの(傾圧不安定、静力学不安定、水の相変化など)→自由擾乱。
大気外部の要因→大気の運動を外から引き起こす力(地形分布:力学的強制力、海陸分布:熱的強制力)→強制擾乱。代表:山岳波
対流
熱伝導が、閾値(臨界値)を超えると対流が始まる。
ベナール型対流:
蜂の巣状構造の二種類。
- 中心部で下降流、周辺部で上昇流→オープン・セル(開細胞、周辺部に雲)、寒冷な季節風が海上を吹走するとき
対流不安定が起こり、対流雲が発生するが、気温と海面水温の差が比較的大きい場合に出来る。
- 中心部で上昇流、周辺部で下降流→クローズド・セル(閉細胞、中心部に雲)、気温と海水面の差が小さい時に出来る。
ロール状対流:
静力学的に不安定波成層をした一定の鉛直シヤーをもつ流れは上空で垂直方向より水平方向の流れが強くなる。
そこに発現する対流はセル状ではなく流れに対して平行なロール状になる。ベナール型対流の中でも
対流がロール状(螺旋)になるものを特にロール状対流という。
冬の西高東低の気圧配置の時に日本海に発生する筋状の雲、シベリア大陸からの冷たい空気が暖かい
日本海の海水面によって下から暖められてできたロール状対流。
積雲対流:
ベナール型対流は乾燥した空気でも起こりうるが、湿潤な空気では水蒸気の凝結と降水が起こるため、
一般には対流は積雲対流と言う形をとる。
地表近くの湿った空気塊を上空に持ち上げると、その温度は初めのうちは乾燥断熱減率に従って下がる。
温度が下がると共に空気塊の湿度が高くなり、やがて飽和する。水蒸気は雲粒になり、凝結熱を放出
するようになる(持ち上げ凝結高度)。
これ以降は湿潤断熱減率にしたがって上昇し、空気塊の気温は下がり、周囲の大気の気温減率は通常
湿潤断熱減率より大きいので、空気塊の温度は次第に周囲の大気の温度に追いつき、
やがて周囲の大気と等しくなる(自由対流高度)。自由対流高度を超えると、空気塊の温度は周囲の大気よりも高くなり、
浮力の為に上昇し続け、安定は成層に達してしばらく上昇した所で止まる。
一方上昇気流を補う形で下降する空気塊の大部分は、上層では水蒸気をわずかしか含んでおらず、成層は安定なので
下降気流は広範囲にわたり弱いものになる。ただし、積雲の直下では雨粒が蒸発するため空気塊が冷やされて重くなり、
強い下降気流が作られる事がある。これが積雲対流の原理。
積乱雲(降水セル)
CAPE:Convective Available Potential Energy 対流有効位置エネルギ。積雲対流が発達するためのエネルギ量。
湿潤断熱減率と気温分布に囲まれた部分の面積に比例する。この面積が大きいほど空気塊は大きな上昇速度を持ち、
対流が発達して大気の成層が不安定である。
降水セル:
雷雲は多くの場合いくつかの積乱雲の塊。それを構成する個々の積乱雲を降水セル(or対流セル)という。
降水セルは、積雲対流によって発生・発達するが、対流圏界面に達すると水平に広がる。降水セル
の中を上昇する空気塊に含まれる水蒸気や雲粒は気温の低い上空に運ばれたのち、雪や霰や雹に成長して
落下を始める。
雲や霰は落下しながら融けて雨粒になり、蒸発・融解による冷却などによって下降気流を作りだす。
下降気流は上昇気流の源となる暖かく湿った空気の流入を絶ってしまうので、降水セルは急激に衰弱して一生を終える。
一般に降水セルの寿命は数10分~一時間で、水平スケールは10km程度。
ガストフロント:
雷雲から吹きだす冷たい湿った空気が暖かい湿った空気の下に潜り込み暖気を上昇させる。
降水セルは、その成熟期において生成された氷粒子が0℃の層を通過すると、融解して周りの空気から
潜熱を吸収し空気を冷やすため、下降気流が強まる。また、雨粒も雲底下の飽和していない空気中に
入ると蒸発するものがあり、そのときに周囲の空気から潜熱を吸収して空気を冷やすため、下降気流は
ますます強まる。
こうして出来た冷たい空気は雲底下に溜まり、冷気プールあるいは冷気ドームを形成する。
この部分の空気は低温のために周囲よりも気圧が高く、局地的な高気圧となる。この高気圧を
雷雨性高気圧あるいはメソ高気圧という。
雷雨性高気圧から地表に沿って放射状に吹きだす冷気の先端が周囲の暖かい空気と衝突した時にできる
境界線をガストフロント(突風前線)という。ガストフロントでは、雷雲から吹き出す冷たい湿った空気が
暖かい湿った空気の下に潜り込み、暖気を上昇させる。またガストフロントは、ミニ寒冷前線の様に
進行し、その通過時に地表では突風が吹いて気温が急降下する。ガストフロント通過の少し前からは気圧が上昇する。
積乱雲や積雲などの対流性の雲からときに雷雨を伴いながら吹く強い下降気流のことを
ダウンバーストといい、地面に衝突したあと週にに水平に発散する。ダウンバーストは離着陸中の航空機にとって危険。
農作物に被害をもたらすこともある。水平に発散する領域の広さは1km未満のものから、数10kmに及ぶ。強風域の直径が
約4km以上のものをマクロバースト、約4km以下のものをマイクロバーストという。
降水セルの世代交代:
世代交代する降水セルは普通の降水セルより寿命が長い。
個々の降水セルの寿命は一般に数10分~1時間だが、鉛直シヤーが強い時には降水系全体の寿命は長くなる。
一般風が西風で風速は地表面でゼロで高度と共に増加しているとする。普通降水セルは対流圏の中層の風、あるいは
雲がある層全体の平均的な風で流される。したがって、流されている降水セルに相対的な(つまり移動中の降水セルから
見た)一般風は上層では左から右へ吹いているが、下層では反対に右から左へ降水セルに吹きこむように吹いている。
この下層の一般風は降水セルから吹き出している冷気と衝突し、ガストフロントのところで上昇気流となる。
この上昇気流が十分強く、下層の空気が十分湿っていれば、上昇気流は凝結高度に達して雲が生じる。
大気が対流不安定の時、ガストフロントで強制的に発生した上昇気流が強いと下層空気が自由対流高度まで上昇するので、
その高度で新しく降水セルを生じる事になる。もとの降水セルを親雲とすると、親雲から子雲が生まれた事になる。
こうして子雲ができると、水蒸気をたくさん含んだ下層の一般風の空気は子雲に吸収され、親雲の方には行かないので、
親雲は次第に衰退し、子雲の方が成長する事になる。この事を降水セルの世代交代、あるいは自己増殖
という。
多重降水セルの移動:
子セルは、下層の一般風に逆らう方向に出来る。降水セル全体は中層の一般風に流される。降水セル全体は、その合成
の方向に進む。
世代交代する積乱雲は、複数が集まって積乱雲群を組織する。これを多重セル型積乱雲群という。
多重セル型積乱雲群は周辺を吹く一般風が比較的大きい鉛直シヤーを持っている時に形成・維持される。
また、積乱雲が世代交代するために積乱雲群の移動は個々の積乱雲の移動とは異なる。
個々の積乱雲は対流圏中層の一般風に沿って移動する。しかし、積乱雲群の中では世代交代の最、新しい
積乱雲は水蒸気をたくさん吹くんている下層の一般風が流入してくる方向(風上)に発生するため、
積乱雲群の移動方向は、個々の積乱雲群の移動方向より下層の一般風のの風上側にずれる。
中層の一般風に流され、下層の一般風に逆らって(風のエネルギを原動力に)進む。
メソ対流系
複数の降水セルが同時に存在して、メソ対流系を構成することが多い。水平スケール10km~数10kmの団塊状メソ対流系と、
活発な降水セルが線状に並んでいる線状メソ対流系とがある。
団塊状のメソ対流系:
主に三種類に分類される。
- 気団性雷雨:
複数の降水セルが雑然と集合している。内部にはそれぞれの降水セルの発達段階が異なるため、
成長期、成熟期、衰退期の降水セルが気団性雷雨の中で存在している。特定の地域が単一の気団に覆われ、
一般風の鉛直シヤーが弱い状況の時に発生しやすい。
- マルチセル型ストーム:
複数の降水セルが発生順に並ぶため、規則的に組織がされているもの。後ろの方では
古い降水セルがどんどん消滅するが、進行方向に対して前の方に新しい降水セルが次々と作られ、
系統的な世代交代を繰り返すため、ストーム全体として長時間維持される。それぞれの降水セルの中の
風も相互に関連し合っている。一般風の鉛直シヤーが強い時に発生しやすい(風向きがそろうから?)。
- スーパーセル型ストーム:
ストーム全体が回転している。回転方向はほとんど反時計回り(コリオリ?)。
それぞれの降水セルに上昇・下降気流が有るのではなく、ストーム全体で単一の上昇・下降気流を持っている。
そのため寿命が数時間におよぶ。孤立した降水セルは1時間以内の寿命。
水平スケールが数10kmの巨大な雲の塊。一般風の鉛直シヤーも大気の不安定度も強い状況で発達する。
雹や竜巻、ダウンバーストなどの現象をしばしばともなう。
線状のメソ対流系:
スコールラインと降水バンド。
線状のメソ対流系の中でその線に対して直角方向に比較的早く移動する物をスコールラインという。
移動しているスコールラインの先端には強い対流性の降雨領域が有る。その構造はマルチセル型ストーム
に似ており、ガストフロントの部分に新しい降水セルが発生して、それがガストフロントに対して
相対的に後方へ移動する間に成長・成熟してやがて衰退する。対流性の降雨領域の後方では、
層状の雲が長さ数10~100km以上にまで延びており、小雨がしとしと降る。
スコールラインに対して、線に対して直角方向に比較的遅く移動するものを降水バンドという。
前線に関連する現象で、集中豪雨をもたらし、大きな被害を与える要因になる。ただし、スコールラインと
降水バンドを分ける明確な基準は無い。
メソ対流複合体
多くの積乱雲が接近して存在する場合、気象衛星の雲画像ではその上部のかなとこ雲が連結して大きな雲の
塊に見える事がある。この雲の上面の空間スケールや時間スケールが一定の条件を満たしたものを
メソ対流複合体(MCC)という。その発生数や地域分布が降水をもたらす対流活動の一つの指標となる。
寿命は6時間以上のものもある。
クラウドクラスター:
いろいろな形態のメソ対流系から成り立つ。
個々の積乱雲は時間・空間的にばらばらに分布している事もあるが、数個以上の積乱雲が群れをなして
組織化されている事の方が多い。これを気象衛星の雲画像で見ると、隣接する積乱雲上部が連結する
などして、一つの大きな雲の塊に見える。これをクラウドクラスター(積乱雲群)という。
クラウドクラスターの水平スケールは通常数10km~数100km。内部を気象レーダーで見て見ると、いろいろな形態の
メソ対流系から成り立っている。
台風の構造と発達
温帯低気圧のエネルギ源→水平温度傾度(有効位置エネルギ)、台風のエネルギ源→潜熱(凝結熱)。
台風の発生過程:
海面水温26.5℃以上、積雲対流にともなって放出される潜熱をエネルギとして発達する巨大な渦。
北太平洋の北緯10度付近で北東貿易風と南半球から赤道を越えて来た南東貿易風が収束し、
水蒸気を多量に含んだ空気が上昇する。こうして熱帯収束帯に積乱雲ができ、組織化されて
クラウドクラスターが形成される。これにコリオリの力が働いて渦運動が生じる。
地表付近の空気は、渦の中心に向かって吹きこみ、中心付近で収束して強い上昇気流となる。
上昇気流中で雲が出来る際に放出される潜熱の影響で、中心付近は周辺部に比べて高温となり、
空気の密度が減少して地上に低気圧が形成される。中心気圧が下がると、
中心に向かって収束する風が強まり、対流活動が一層強化される(正のフィードバック)。
このサイクルを繰り返して台風は発達する。
赤道付近では海面水温が高いが、南北緯度5度くらいまではコリオリの力が弱いので台風は滅多に発生しない。
台風は、地表で周囲との気圧差最大。上空に行くほど気圧差は小さくなり、やがて逆転し、上層では周囲より
気圧が高くなり、風は吹き出し、その向きは当然逆回り(時計回り)になる。
アイウォールとスパイラルバンド:
成熟期の台風は温帯低気圧と違って前線を伴わない。雲や風速、降雨の分布は中心に対して軸対象。
等圧線の形もほぼ円形。低気圧性の回転は地上から上空に真っ直ぐに立っている。
台風の中心部には雲のほとんどない部分がある。これが台風の眼、その周囲には密集した積乱雲群からなる
目の壁雲(アイウォール)がある。この部分は高さ12km以上、ときには16kmにも達し、大雨を降らせる部分。
気圧傾度が大きく、極めて強い風が反時計回り(北半球)に吹いている。
アイウォールの外側にはスパイラルバンドがあるのが普通で、一般的にはアイウォールよりも
背が低い積乱雲からなっていて、北半球では反時計回りに回転している。スパイラルバンドの
風上の端では新しい積乱雲が次々と発生し、台風周辺の風で流されて、風下の端で消滅する。
そのためスパイラルバンドの速度は、台風周辺の風速よりもかなり遅くなる。
局地風
メソスケールの範囲に限定された局地的に吹く風。海陸風、山谷風が代表。メソスケールの強制擾乱の代表例。
そのメカニズム:
地形に起因する力学的作用や熱的効果によって吹く。
海陸風:
昼間の海風と夜間の陸風は、海と陸の比熱の差によって生じる。海風の方が強い。海風は数10km程内陸に吹きこむが、陸風は10km程度。
- 陸地は海水よりも比熱が小さい。
- 陸地は海面よりも蒸発量が少なく、吸収した熱を蒸発時の潜熱として奪われにくい。
- 波や風によって海水がかき混ぜられるため、熱が海中に逃げてしまう海面とは違い、
陸地では吸収した熱が比較的地表面近くにとどまっている。
日中は比熱の小さい陸面の温度が高くなり、昼間は陸地の気圧の下がり方が大きく、それを
補うため、海から陸へ空気が移動する。これが海風。日の出から数時間後に陸面の温度が
海面の温度よりも高くなると吹き始める。
夜は放射冷却により陸面温度は海面温度より低くなり、日没から数時間後に海に向かって
陸風が吹く。
海風、陸風両方とも、上空には、逆向きの風が吹き、循環する。
山谷風:
日中は、日射により山の斜面が温められ、谷から山に風が吹く。夜間は放射冷却により山の斜面が冷えて
逆に吹く。
成層圏と中間圏の大規模運動
成層圏と中間圏の温度と風
成層圏と中間圏の鉛直温度分布と風:
成層圏は20kmまではほぼ一定で、それ以上は上層ほど高温(紫外線が吸収される)。
成層圏と中間圏の鉛直温度分布と風:
オゾンによる太陽放射の紫外線吸収に伴う加熱と、大気の赤外線放射による冷却で成層圏、中間圏の鉛直温度分布が決まる。
地表付近の影響はほぼ無いので、北半球、南半球の差は無く、夏冬で対象になるので、夏半球、冬半球という言い方をする。
夏半球の方が冬半球より高温になっている高度50km付近が成層圏界面。
逆に、冬半球の方が夏半球より高温になっている高度80km付近が中間圏界面。
- 高度10-20km:
赤道付近上空の10-20kmは対流圏におけるハドレー循環の
上昇流域の上部にあたるので、対流圏の気温減率が影響してもっとも気温が低くなる。
一方、中・高緯度では対流圏界面が最も低く、高度10-20kmでは既に成層圏になるので、高度が上がっても気温が下がらない。
このため、この高度では赤道付近上空の方が気温が低い。
- 高度20-60km:
夏半球から冬半球にかけて温度が低くなっており、夏極が最高温度、冬極が最低温度で、その差は50Kくらい。
これは夏極に近いほど、入射している太陽からの放射エネルギが大きく、オゾンによる紫外線吸収による
加熱が大きくなるため。風は夏半球で東風、冬半球で西風。
- 高度70-100km:
逆に、夏半球が低温、冬半球が高温。温度分布は 20-60kmの層と反対になる。高度約90kmまでは夏半球で東風、冬半球で西風が
卓越しているが、それ以上では夏半球で西風、冬半球で東風が卓越する。
成層圏と中間圏における大循環:
成層圏下層では低緯度から高緯度の循環(ブリューワー・ドブソン循環)がある。成層圏中・上層から中間圏にかけて
夏半球から冬半球への大規模な循環が有る。この循環は低緯度上空の成層圏下層で生成されたオゾンを高緯度上空に
輸送する役目を果たす。成層圏+中間圏=中層大気。
成層圏の突然昇温
冬から春先にかけて極域で突然気温が上昇する(20-40℃)。
高緯度の成層圏の気温は冬半球の時には低く、夏半球の時には高くなる。これは規則的。
しかし、冬の北半球では、春先にかけて、その規則的な変化に対して、10日位で変化する
短い変動が重なり、気温が突然大きく上昇する。これが成層圏の突然昇温。
冬の北半球の高緯度の成層圏では通常、極を取り巻いて流れる西風が渦を形成している。
しかし、冬から春先にかけて、対流圏内の超長波(プラネタリー波)の活動を受けて
崩壊する事がある。その際、極側に下降流が発生し、断熱昇温が起こるため、大きな
昇温が生じる。
突然昇温が1か月ほど続くと対流圏の天気にも影響を及ぼす事がある。たとえば北米の低気圧は
通常より北で発生する傾向が有ったりする。
準二年周期振動
赤道上空の成層圏下層では東風と西風が交代する準二年周期振動(約26か月周期)という現象が観測される。
赤道付近上空の成層圏下層では、東風から西風へほぼ一年ごとに変動している。この周期は年によって少し
異なるが、平均約26か月となる。変動は成層圏上層で始まり、下層へ移動する。一つの風系が約18kmまで下がった頃には
既に次の風系(逆方向)が成層圏上層で始まっている。東風の最大時における風速は30m/s、西風は20m/s。
振幅最大になるのは、高度25kmくらい。
気候の変動
気候とは「長期間にわたる気象要素の平均値」、統計的な性質を論じることができる範囲の長期間にわたる天気。
異常気象→過去30年間の気候に対して著しい偏りを示した天候。
太陽活動と地球軌道要素
太陽の活動:
太陽の黒点の温度は周囲の表面温度(6000K)より低い(約1500~2000K低い)。
黒点数は平均すると約11年の周期太陽の磁場はこの周期ごとに逆転するので、
磁場の周期は約22年。黒点数が多いと、太陽面から放射される電磁場、太陽風の量が増大する。
黒点数(太陽活動)と気候の相関は、現在まだ明確ではない。
地球軌道要素の変化:
地球の公転軌道(離心率、近日点の位置)や自転軸の傾きによって、地球が受け取る太陽放射エネルギ量が変り、気候の変化を引き起こす。
これらの地球の軌道要素の周期は数万年。
- 離心率:
10-40万年周期で地球の公転軌道は円形(離心率=0)から楕円形(離心率=0.068)で変化する。現在は0.0167。
- 近日点の移動(歳差):
1.9-2.3万年周期で各季節の地球-太陽間の距離が変化する。
- 地軸の傾斜:
4.1万年周期で地軸の傾斜角は22.1-24.5度の間を変化する。現在は23.5度。
火山噴火とエーロゾル
大規模な火山噴火が気候変動に及びス影響は、太陽活動の影響に比べるとずっと明確。
火山噴火は多量の火山ガスを放出し、それが成層圏下層にまで達し、エーロゾルを生成し、
太陽放射を反射、吸収、散乱する。これで、歴史上多くの飢饉が起こった。
火山性エーロゾルと気候の変動:
太陽光の散乱による日傘効果が温室効果よりきつく、寒冷になる。
火山ガス→二酸化硫黄、硫化水素、塩酸、二酸化炭素、硫黄化合物が成層圏の大気中で反応して
硫酸塩エーロゾルになる。
大規模な爆発噴火によって対流圏界面や成層圏下層部に達した火山灰や火山ガスから作られる
火山性エーロゾルは、温度を下げる遮蔽効果(日傘効果)と、温室効果がある。
火山性エーロゾルが対流圏上層や成層圏下層部に達し長期間大気圏に滞留すると、太陽光線は散乱(ミー散乱)
されるため、地表面に達する散乱日射量は増加するが、直達日射量は減少する。
このため、地表面が受け取るエネルギ量は減少する。
一方火山性エーロゾルは地表面からの赤外放射を吸収する働きもある。しかし、火山性エーロゾルは
太陽放射エネルギを遮蔽する効果の方が大きいのでトータルすると、気候の寒冷化をもたらす。
大規模な火山噴火により成層圏内に分散したエーロゾルで大きなものは短期間に地表へ降下するが、
数μmだと半年くらい、1μm以下だと数年成層圏内に滞留し、地球全体を覆う。
このため、地表に達する太陽放射エネルギのうち、直達日射量は20-30%減少する事がある。
おそらくこれが原因で、場合によっては一年、時として数年寒冷な気候が続く。
エルニーニョ現象・テレコネクション
エルニーニョ現象とウォーカー循環:
太平洋赤道域の年平均海面水温は、西半分で28℃を超える暖水、東半分では低く、22℃以下のところも。
これはペルー沖で深いところから冷たい海水が湧昇してくるため(ハドレー循環の偏東風(貿易風)の影響)。毎年12月頃になると、深海からの湧昇が
衰えて同時に北から暖流が流れ込んでくるので、沿岸近くの海面水温が高くなる。12-1月のピーク時には
最大2-5℃上昇する。3月頃には元に戻る。
数年に一度くらいの間隔で、これが崩れ、3月になっても暖水が消滅せずに水温が高いままの状態が続く。これがエルニーニョ。
逆に貿易風が強まると、下から冷たい海水がさらに湧昇して、中部から東部太平洋の低緯度の海面水温が下降し、
ペルー沖の水温が異常に低くなる。これがラニーニャ現象。
海面水温が相対的に高い西部太平洋で上昇気流が、低い東部太平洋で下降気流が起こり、対流圏上層では西風、
下層では東風が吹く。この赤道上の東西循環を「ウォーカー循環」という。エルニーニョが発生すると、
西部太平洋の暖水域は東へ広がり、中部太平洋域では海面水温が上昇して低圧部となり、上昇気流が起こる。
東側に逆向きの循環が起こる。つまり、ウォーカー循環が逆向きの二つの循環に分断される。
貿易風は、全体として弱まる。
エルニーニョ現象が起こると、日本では暖冬、長梅雨、冷夏になりやすい(全体的に風が弱いから停滞性の気象?)。
テレコネクション:
ある場所で起こった変化が遠隔地に伝達される現象。
地球が自転しているおかげで、結構中高緯度地域に赤道付近の影響が及んでくれる。地球上で
何千km以上も離れた地点の気象や海洋現象の変化が互いに関連していること。
エルニーニョ、ラニーニャの場合、具体的には、熱帯地域の循環の変化が対流圏上層を中心に大きな波動を起こす事が原因。
その波動によって、エネルギが伝播するため、温帯地域にも異常気象をもたらす。
エルニーニョ現象が起こると、日本では暖冬、長梅雨、冷夏が、
東南アジア、オーストラリア、インド、西アフリカ、南アフリカでは干ばつが、
南米大陸西岸では大雨が起きやすくなる。
ラニーニャ現象が起こると、東南アジアでは多雨、日本では猛暑になりやすくなる。
ただし、これらの異常気象が発生したからと言って、地球大気の温度や水蒸気の総量に目立った変化はない。
熱収支や水蒸気収支の地域配分が数カ月単位でずれることによって発生したと考える事もできる。
人間活動と地球温暖化
近年の地球温暖化は、温室効果気体の増加のためらしい。
地球温暖化と温室効果気体:
温室効果気体は、地球放射を吸収し、ふたたび地表面に対して放射を行う。
地球の気温に変化をもたらす人為的な要因は、エーロゾル、人工熱(ヒートアイランド)、土地利用(森林減少、焼畑)等が有るが、
温室効果気体の増加が最も注目されている。
H2O, Co2, CH4, N2O, O3, フロンなどがある。水蒸気以外は、増加傾向にある。
二酸化炭素:
季節によって増えたり減ったりするが(夏は減って冬は増える→植物の活動)、季節の変動を平均すると、じわじわ増えている。
水蒸気とならんで影響が大きい。過去一億年間現象を続けて来た。19世紀に入って増加に転じ、しかもこの100年で
過去数100万年間の減少分を補う増加量を示す。さらに年を追うごとに増加率が上昇している。
化石燃料の大量消費による排出量増加が原因。また、砂漠化や森林の減少、海洋汚染などによる植物の炭酸同化作用が弱く
なっていることも原因らしい。
人間の活動がほとんどない南極でも増加している。増加率も他の地域と同じ。ちゃんと循環しているね。
水蒸気:
水蒸気は赤外線をよく吸収する。しかし、その増減が自然的要因のため、人間の活動によらない。
いろいろややこしいが、地球温暖化の原因として議論できるわけではない。
地表面の変化:
半乾燥地域における過剰牧畜は砂漠化を招き、アルベドを変化させる。
砂漠化と森林減少が注目されている。特に森林減少は、CO2を吸収する機能も失われるため、二重に効いてくる。超やばい。
雪氷面の増減もアルベドを変化させる。温暖化が生じると、雪氷面が減少するのでアルベドが減少し、
そのため地球表面はいっそう多くの太陽放射エネルギを吸収する事になり、正のフィードバックで超ヤバい、既に北極の
氷融けている。逆に寒冷化すると、アイス・アルベド・フィードバックで、全球凍結の危機。
人間活動と大気汚染
光化学スモッグ、オゾン層破壊、酸性雨、人間活動によって合成されたもともと自然界には存在しなかった気体が
多くの大気汚染を引き起こしている。
- 光化学スモッグ:
工場や自動車から排出された窒素酸化物(NOx)などが太陽からの紫外線に反応して化学変化を起こし、
有害な光化学オキシダントが作られる事によって発生する。夏の日中(日差しが強く風が弱い)に発生しやすく、
屋外にいる人の目や喉などに刺激を与え、涙が止まらなかったり、息苦しいといった症状をもたらす。
- オゾン層の破壊:
フロンがオゾン層を破壊する。壊れないで成層圏に達し、紫外線で分解され、塩素がオゾンを連鎖的に分解する。
有害な紫外線が降り注ぐ。皮膚癌、致死性突然変異の可能性。
- 酸性雨:
化石燃料の燃焼に伴う硫黄酸化物や窒素酸化物などが雲粒や雨粒に溶け込み、強い酸性(pH5.6以下)となって
降る雨。湖沼、湿原、森林、田畑の土壌を酸性化させる。湖沼水の酸性化が進行すると、魚類や微生物が住めなくなり、
土壌の酸性化は樹木の枯死、農作物の不作をもたらす。
光化学オキシダント:
光化学反応によって大機中に生成される酸化性のガス状物質。窒素酸化物(NO,NO2)や硫黄酸化物など。
酸性雨は大理石の建造物を溶かす。コンクリートも溶かす。金属は腐食する。
気象業務関連法
気象業務法
気象業務法の概要
気象業務法は昭和27年(1952年)に制定された。気象業務全般にわたる基本的な制度を定めたもの。
気象庁の行う気象業務のすべてと気象庁以外のものが行う気象に関する業務を規定している。
気象予報士制度は天気予報の一部自由化を目的に導入されたもの。その基盤となる。
気象業務法は、我が国の気象業務に関して「だれが、何についての業務を行ってよいか(行わなければならないか)」を
規定し、気象業務に携わる者の義務を定めるとともに、違反した者に対する罰則規定を定めている。
気象業務法とは:
その目的は、災害の予防・交通の安全確保・産業の興隆に寄与すること。
気象業務法の第一条では、気象業務法の目的→「気象業務の健全な発達」を図り、
「公共の福祉の増進に寄与する」と規定。気象業務は公共性の高い業務。
公共の福祉→災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆。国民生活の安全や社会のニーズに役立つ。
気象情報は人々の日々の生活に大きな影響を与える。気象庁はもちろん、
気象庁以外に気象業務を行うすべてのもの(政府機関、地方公共団体、会社、団体、個人)に対しても、
一定の技術上の基準に従って気象業務を行う事定めている。
気象業務に関する国際協力を行う事もこの法律の目的。気象業務が対象としている自然現象は
地球的規模の現象なので、国際的に行通の観測基準を設定したり、データを交換したり、
技術者の交流や共同研究などが行われている。一例として、気象観測衛星ひまわりを東アジア、オセアニア諸国
も利用しているということがあげられる。
気象業務とは:
対象は「気象」、「地象」、「水象」。「気象」とは、大気(電離層を除く)中の諸現象。
- 気象: 大気(電離層を除く)中の諸現象。
- 地象: 地震や火山現象および気象に密接に関係する地面および地中の諸現象。
- 地動: 地滑りや山崩れなどのこと。
- 水象: 陸水(池や河川など)および海洋の諸現象。
「気象」という単語は「地象」「水象」とセットになっている。しかし、「気象業務」という
場合には、気象・地象・水象がすべて含まれる。気象業務法では気象業務について
次のように定義している。
- 気象、地象、地動、水象における「観測」と観測の成果の収集と発表
- 気象、地象、水象の「予報」や「警報」(ただし地象のうちの「地震」と「火山現象」は除く)
- 気象、地象、水象の情報の収集や発表
- これら事象についての統計の作成や調査、その成果の発表
地震と火山現象の予報や警報を行わないのは、まだその技術水準にない、という理由。
気象庁の業務
気象庁にしか認められていない気象業務が有る。
観測および予報・注意報・警報:
「観測」とは「自然科学的方法による現象の観察及び測定」をいう。
気象業務の大きな流れは「観測」し、「予報」して、必要が有れば「警報」を出して
災害への注意を促すこと。
- 観測: 自然科学的な方法による現象の観察及び測定
- 予報: 観測の成果に基づく現象の予想の発表
- 警報: 重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報
- 注意報: 予想される気象現象によって、
警報を発表するほどではないが災害が起こるおそれがあるときに、その旨を
注意するように行う予報
テレビ番組なので気象庁の予報を天気図などと共に解説する事も予報業務には当たらない。
注意報は予報の範疇に属す。
| 予報 | 予報 | 天気予報 | 当日から3日以内における風、天気、気温等の予報
|
| 週間天気予報 | 当日から7日間の天気、気温等の予報
|
| 季節予報 | 当日から1か月間、当日から3か月間、暖候期、寒候期、
梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の総括的な予報
|
| 波浪予報 | 当日から3日以内における波浪、うねり等の予報
|
| 注意報 | 気象注意報 | 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって
災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
|
| 地面現象注意報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって
災害が起こるおそれが有る場合にその旨を注意して行う予報
|
| 津波注意報 | 津波の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
|
| 高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
|
| 波浪注意報 | 風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
|
| 浸水注意報 | 浸水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
|
| 洪水注意報 | 洪水によって災害が起こるおそれが有る場合に、その旨を注意して行う予報
|
| 警報 | 警報 | 気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報
|
| 地面現象警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報
|
| 津波警報 | 津波に関する警報
|
| 高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報
|
| 波浪警報 | 風浪、うねり等に関する警報
|
| 浸水警報 | 浸水に関する警報
|
| 洪水警報 | 洪水に関する警報
|
気象庁が行う気象業務:
気象・津波・高潮・波浪・洪水の警報は気象庁しか出せない。
- 気象注意報は、風雪注意報、強風注意報、大雨注意報および大雪注意報ならびに雷、霜等の現象名を冠した注意報とする。
- 気象警報は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報および大雪警報の4種とする。
津波・高潮・波浪・洪水を除く水象についての予報や警報には、浸水注意報・警報、海上注意報・警報、海流予報、
海氷予報などがある。
予報や警報は、大きく分けて2種類。
- 気象庁が行わなければならない: 気象・地象(地震・火山現象は除く)・津波・高潮・波浪・洪水の予報や警報
- 気象庁が行うことができる: 津波・高潮・波浪・洪水を除く水象についての予報や警報
気象・津波・高潮・波浪・洪水の警報については、災害発生等の緊急時に異なる内容の警報が2つ以上のところから
出されると大きな混乱が生じ得るので、「気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪および洪水
の警報をしてはならない」とされている。
気象庁は、予報や警報を行った場合には自ら周知するほか、報道機関の協力を得て、これを
公衆に周知させるように努めなければならない。特に警報の場合は、NTT東日本、NTT西日本、警察庁、NHKなどを通して
確実に周知されるような特別な伝達体制が設けられている。
注意報については、気象業務法では特別な伝達体制は設けられていない。しかし、災害対策基本法に
もとづいて作成されている地域防災計画において伝達体制を定めて災害対策の活用が図られている。
| 気象庁→ | NTT | 気象・高潮・波浪・津波・洪水・水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水、の各警報
| 市町村長→ | 公衆、所在の官公署
|
| 警察庁 | 津波警報
|
| 都道府県 | 気象・高潮・波浪・洪水・水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水、の各警報
|
| 海上保安庁 | 気象・高潮・波浪・津波・海上の各警報 | 航海中・入港中の船舶
|
| 国土交通省 | 飛行場・空域・航空路の各警報 | 航行中の航空機
|
| NHK | 気象・高潮・波浪・津波・洪水の各警報 | (放送)
|
| 国土交通省 | 水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水の各警報 |
|
予報業務の許可(気象庁以外の者が行う気象業務)
業務→『反復・継続して行う』こと。平成5年度気象業務法一部改正→対象地域を特定した局地的な天気予報を
民間気象事業者が可能に。
予報業務の許可:
予報業務を行おうとする場合には、気象庁長官の許可が必要。
気象業務法第17条「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を
行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」申請書に予報業務の目的と範囲を
記載する必要がある。気象庁長官がその目的と範囲を審査して許可を出す。目的→特定向けや一般向けなど予報業務の提供の目的。
範囲→予報の種類(気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水)、期間、対象となる地域
許可条件:
- 予報業務を的確に行うために必要な施設や要員を確保しているかどうか。
- 許可を受けようとする予報業務の目的や範囲について気象庁が出す警報を迅速に受ける事が出来る施設や要員があるかどうか。
- 気象予報を行う事業所ごとに気象予報士を置いているかどうか。
予報業務を行う者の義務:
気象庁の警報を受けたら、利用者に迅速に伝えるように努めること。
予報業務:「観測→データの集計→現象の予想→予想の発表」。現象の予想については、気象予報士に行わせる必要あり(業務に
支障のない範囲で気象予報士以外の補助者を用いることは差し支えない)。
気象観測は一定の技術上の基準に従って行い、気象庁長官の行う検定に合格した気象測器を使用する必要あり。
気象庁が出した警報が、許可されている予報業務の目的や範囲にかかわる警報である場合、利用者に迅速に
伝達するように努めなければならない。
自分自身、家庭、所属する会社・団体のために天気の予測を行う事は、予報業務ではない。
予報業務の目的・範囲変更、休止・廃止:
目的・範囲の変更は、気象庁長官の認可が必要。
予報業務を始めようと新たに気象庁長官に届け出て認められるのが「許可」。その許可を既に受けて業務を
行っている者が予報業務の目的・範囲の変更を届け出て認められるのが「認可」。認可も上の3個の許可要件に従って決定される。
予報業務を休止・廃止した場合には、その日から30日以内に気象庁長官に届け出なければならない。
予報業務許可の取り消し:
気象業務法に違反すると予報業務の許可を取り消される事がある。
気象業務法の規定に違反した場合、気象庁長官は期間を定めて業務を停止させたり、許可を取り消したりできる。
たとえば、予報業務の許可・認可を受ける際の条件に違反したり、気象業務法に定められている罰則規定にある
行為を行ったりした場合には、許可や認可が取り消される場合がある。
また、許可・認可を受けて予報業務を行っている者が法人(会社・団体)の場合には、その法人に属している役員が
気象業務法に違反すると、法人の許可・認可が取り消される。
気象予報士
気象予報士となるには、気象予報士試験に合格して気象予報士となる資格を得て、登録申請書を提出し、
気象庁長官の登録を受ける必要がある。一定の業務経歴や資格を有する場合、試験の一部が免除される事がある。
- 気象予報士になろうとする者は、まず気象庁長官の行う気象予報士試験に合格しなければならない。
なお、気象予報士の試験を受けるには、年齢・学歴などの制限は一切設けられていない。
- 試験に合格すると、気象予報士となる資格を有する事になる。なお、不正な手段を用いて試験を受けたりあるいは
受けようとした者は合格を取り消される。
- 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
その際には、気象予報士試験合格証明書を添付した登録申請書と、住所・氏名・生年月日が証明できる
書類を提出する必要がある。
- 書類が提出されると、気象庁長官はその者を気象予報士名簿に登録しなければならない。登録にあたって新たに
研修を受けたりすることはない。
登録の欠格事由は、
- 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わるか、その執行を受けることが無くなった日から
2年経っていない者
- 過去に不正な手段を用いて気象予報士の登録を受けた為、その登録を抹消され、処分を受けてから2年経っていない者
気象予報士の設置:
許可を得た民間気象事業者が実際に予報業務を行う場合には、「当該予報業務を行う事業所ごとに
気象予報士を置かなければならない」という規定がある。さらに、「当該気象業務のうち現象の予想については気象
予報士に行わせなければならない」。従来、気象予報士が一般向けに行う予報は特定の範囲を対象とする局地的な予報に
限られていたが、2000(H.12)の気象業務法の改正によって局地予報の限定が解除となり、都道府県以上の
広範囲に及ぶような一般向けの天気予報が可能となった。
気象予報士の登録事項変更と登録抹消:
登録名簿に登録した事項に変更が生じた場合(氏名や住所の変更など)、気象予報士は登録変更の内容をすみやかに気象庁長官に
届け出なければならない。
登録の抹消は、
- 自分から「気象予報士登録抹消申請書」を気象庁長官に提出する。
- 気象業務法の条項に挙げられている以下のような事項に該当した場合。
- 気象予報士が死亡したとき(相続人が気象庁長官に届け出る)
- 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた時(本人が届け出る)
- 偽りその他不正な手段により気象予報士の登録を受けていた事がわかったとき
- 不正な手段によって気象予報士の試験を受けた為試験の合格が取り消された時
気象業務法における義務と罰則規定
義務事項:
気象庁以外の者が気象観測を行うに当たっての義務事項がある。気象測器→温度計・気圧計・湿度系・風速計・日射計・雨量計・雪量計。
- 気象庁以外の政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合は、国土交通省令(気象業務法施行規則)で
定める技術上の基準に従って行わなければならない。
- 政府機関および地方公共団体以外の者がその成果の発表や災害防止などに利用する場合にも技術上の基準に従って
行わなければならない。
- 政府機関、地方公共団体およびそれ以外の者が観測施設を設置したときは、気象庁長官に届け出なければならない。
- 政府機関、地方公共団体およびそれ以外の者が観測する気象測器は、検定に合格したものでなければならない。
政府機関や地方公共団体であっても、研究や教育のために行う気象観測である場合は、技術上の基準に
従わなくてもよいことになっている。たとえば、学校での百葉箱とか。
罰則規定:
気象業務法に定められている罰則規定に触れると、罰金刑などが科されることに加えて、予報業務の許可が取り消されたり、
気象予報士登録を抹消されることになる。
| 罰則例1 | アメダスの観測機器を壊した
|
| 気象業務法第37条「気象庁が屋外に設置する気象危機または気象警報等の標識を壊したり移したりして、
これらの効用を害する行為をしてはならない」に違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその併科)
|
| 罰則例2 | 気象庁長官の許可を受けずに、フェリー会社に対して波浪の予報業務を行った
|
| 気象業務法第17条「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の
予報の業務を行おうとする場合は、気象庁間の許可を受けなければならない」に違反(50万円以下の罰金)
|
| 罰則例3 | 予報業務の許可を得た者が、警報基準に従って大雨警報を出した
|
| 気象業務法第23条「気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報を
してはならない」に違反(50万円以下の罰金)
|
| 罰則例4 | 認可を受けないで予報業務の目的・範囲の変更を行った
|
| 気象業務法第19条「気象庁長官の許可を受けて予報業務を行う者が、予報業務の目的または範囲を
変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない」に違反(50万円以下の罰金)
|
| 罰則例5 | 予報業務のうち現象の予想を気象予報士の資格の無い者に行わせた
|
| 気象業務法第19条の3「当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に
行わせなければならない」に違反(50万円以下の罰金)
|
| 罰則例6 | 気象庁長官の命を受けて私人の所有地で観測を行おうとした職員の立ち入りを拒んだ
|
| 気象業務法第38条「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の
観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体、又は私人が所有し、
占有し、又は占有する土地又は水面に立ち入らせる事ができる」に違反(30万円以下の罰金)
|
災害対策基本法・水防法・消防法
- 災害対策基本法→集中豪雨、台風などさまざまな自然災害
- 水防法→洪水や高潮
- 消防法→火災対策
災害対策基本法
昭和36年(1961)制定。基本的な災害対策を決めた法律。防災情報における国、気象庁、都道府県、市町村などの
役割や伝達システムについての基本的な枠組みも定められている。
国と地方公共団体の役割:
市町村長は、人命保護のための立ち退きの勧告・指示・命令ができるほか、災害が既に発生、もしくは
発生しようとしている場合、警戒区域を設け、立ち入りの制限・禁止・退去を命ずることができる。
国・都道府県・市町村は、防災計画や災害時の緊急措置の計画を作成・実施、関係各機関の連絡調整のための常設機関の設置。
- 国→中央防災会議(内閣総理大臣が会長)、地方防災会議に対する勧告・指示。
- 都道府県→都道府県防災会議(都道府県知事が会長)
- 市町村→市町村防災会議(市町村長が会長)
災害の発生時、現地に最も近い市町村長が第1次的な責任者として災害応急措置活動を実施する必要がある。
市町村長には「災害対策本部」の設置、人命保護のための立ち退きの勧告・指示・命令、消防機関などに対する
出動命令などの権限が与えられている。また、市町村長は普段から消防機関や水防団などの組織の整備に努めることと
されている。
都道府県が果たすべき役割は、
- 都道府県内の市町村・公共機関の防災事務の実施を助け、総合調整を図る
- 災害発生時に「災害対策本部」を設置する
- 気象庁から警報事項の通達(気象警報・高潮警報・波浪警報・洪水警報・
水防活動用気象警報・水防活動用高潮警報・水防活動用洪水警報。
ただし、津波警報は含まれない)を受けた時には、各市町村に必要な通知を行う
行政機関の役割:
指定行政機関→国の行政機関、指定地方行政機関→指定行政機関の地方支部局と、国の地方行政機関。
内閣総理大臣が指定する。たとえば、気象庁や国土交通省は指定行政機関。管区気象台(札幌、仙台、東京、大阪、福岡)・沖縄気象台、
地方運輸局は視程地方行政機関。
管区気象台は地方気象台を指導監督するほか、所在している地域の地方気象台の役割も果たす。
指定行政機関や指定地方行政機関は、防災に関する国の責務が十分果たされるよう相互に協力するとともに、
地域防災計画の作成・実施が円滑に行われるよう、都道府県・市町村に対して勧告や指導などを行うこととされている。
なお、指定行政機関の中には、気象庁から該当する警報事項の通知を受けた場合、下図のように、気象業務法第15条で
定められている対象に対して必要な通知を行う期間がある。
気象庁から指定行政機関への伝達体制:
| | | 警報 | | 指定行政機関 | | 伝達先
|
| 気象庁 | → | 津波警報 | → | 警察庁 | → | 市町村長
|
| → | 気象・高潮・波浪・津波・海上の各警報 | → | 海上保安庁 | → | 航海中・入港中の船舶
|
| → | 飛行場警報・空域警報・航空路警報 | → | 国土交通省 | → | 航行中の航空機
|
「飛行場警報」とは公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する
警報のこと。「空域警報」は、国土交通省令で定める空域を、「航空路警報」は国土交通大臣が指定した
航空路を対象とする気象に関する警報の事。
公共機関の役割:
「指定公共機関(内閣総理大臣が指定)」や「指定地方公共機関(都道府県知事が指定)」は、電気、ガス、輸送、
通信などの事業を行う法人。特に、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会(NHK)は指定公共団体として法律の条文に
明記されている。他に、日本道路公団、新東京国際空港公団、JR各社、NTT、東京電力、日本通運、東京瓦斯など、60法人。
指定公共機関や指定地方公共機関は、自らの防災業務計画を作成し、それを実施する(防災訓練など)とともに、
国・都道府県・市町村の防災計画の作成・実施が円滑に行えるように、都道府県・市町村に対して協力しなければならない。
また、その業務の公共性や公益性から、業務を通じて防災に寄与しなければならない。
特に、NTT と NHK は、気象庁から警報事項を受けた場合には、
| NTT | 以下の警報事項を受けたら直ちに市町村長に通知するよう努めなければならない
|
| 気象警報・高潮警報・波浪警報・津波警報・洪水警報・水防活動用気象警報・水防活動用高潮警報・水防活動用洪水警報
|
| NHK | 以下の警報事項を受けたら直ちにその旨を放送しなければならない
|
| 気象警報・高潮警報・波浪警報・津波警報・洪水警報
|
上記は気象業務法第15条で、災害対策基本法の規定ではない。
その他の者の役割:
災害対策基本法第7条では「地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自主的な防災活動への
参加等防災に寄与するよう努めなければならない」と、一般人に自分のための防災対策を行うよう求めている。
第54条では、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は誰であっても、市町村長や警察官や
海上保安官へ通報しなければならない。その通報を受けた警察官や海上保安官は、その旨を
市町村長に伝えなければならない。さらに、市町村長は気象庁や関係機関へ伝達しなければならない。
水防法
洪水や高潮などの水災(浸水や土砂崩れなど)を警戒・防御するとともに、こうした水災によってもたらされる被害
(家屋や農地の被害)を軽減し、公共の安全を守る事を目的として、昭和24年(1949)に制定。
洪水予報:
気象庁長官は、気象などの状況によって洪水または高潮のおそれがあると認められるときに
洪水予報を発表する。国土交通大臣、関係都道府県知事に通知、報道機関の協力により一般にも周知(気象業務法)。
具体的には、大雨注意報、大雨警報、高潮注意報、高潮警報、洪水注意報、洪水警報として行われる。
ただし、洪水のおそれのある河川が2以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川(指定河川)で、洪水により
国民経済上重大な損害を生ずる恐れのある場合は、気象庁長官と国土交通大臣が共同してその
状況を関係都道府県知事に通知し、報道機関の協力により一般にも周知させることになっている。また、
洪水予報は洪水により災害が起こるおそれのあることについての注意を促したり警報を発する役割のもので、
水防活動を指示するものではない。
指定河川は、現在、阿武隈川、利根川、信濃川、木曽川、吉野川など全国で193河川。
水防警報:
水防警報は、洪水や高潮により災害の出るおそれがあるときに、河川・湖沼・海岸について水防を行う
必要がある事を知らせるもの。国土交通大臣か都道府県知事によって出される。その際、洪水警報のほか、
水位の状況なども判断して出される。
国土交通大臣は、洪水又は高潮が発生した時に、国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定している河川・湖沼・海岸
について水防警報をださなければならない。また、都道府県知事は国土交通大臣が指定したもの以外で、
都道府県知事が指定している河川・湖沼・海岸について水防警報をを出さなければならない。
なお、都道府県知事は、国土交通大臣から水防警報の通知を受けた場合、また自ら水防警報を出した場合には、
水防管理者などに通知しなければならない。
- 洪水予報の対象→2以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川
- 水防警報の対象→洪水または高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川・湖沼・海岸
消防法
火災の予防・警戒・火災の鎮圧および、火災や地震などの災害によって引き起こされる被害を軽減し、国民の
生命・身体・財産の保護、国民生活の安全や安定を守ることを目的に昭和23年(1948)に制定。
火災警報:
火災警報は、火災の予防上危険である場合に、市町村長が出す。乾燥注意報や強風注意報などの気象注意報が防災気象情報として
使われる。
気象の状況が、火災の予防上危険であると認められる場合、気象庁長官、各気象台長、測候所長は、その状況を
関係都道府県知事に通報する。これを受けて都道府県知事は市町村長に通報し、市町村長はこの通報に基づいて、
あるいは自ら気象の状況が火災予防上危険であると認める場合には、火災警報を行う事ができる。
この火災警報が発せられた時は、当該地域内での火の使用が制限される。
警報の発表機関と伝達先のまとめ(→発表、---周知)
| 警報 | 警報の発表機関 | 法定伝達期間 | | 伝達先
|
気象警報
高潮警報
波浪警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶
|
| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆
|
| NTT--- | 所在の官公署
|
| NHK--- | | (放送)
|
| 津波警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶
|
| 警察庁--- | 市町村長--- | 公衆
|
| NTT--- | 所在の官公署
|
| NHK--- | | (放送)
|
| 洪水警報 | 気象庁→ | 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆
|
| NTT--- | 所在の官公署
|
| NHK--- | | (放送)
|
飛行場警報
航空路警報
空域警報 | 気象庁→ | 国土交通省--- | | 航行中の航空機
|
| 海上警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶
|
水防活動用気象警報
水防活動用高潮警報
水防活動用洪水警報 | 気象庁→
| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆
|
| NTT--- | 所在の官公署
|
| 国土交通省 | |
|
| 指定河川に対する水防活動用洪水警報 | 気象庁と
国土交通大臣→
| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆
|
| NTT--- | 所在の官公署
|
| 指定河川に対する水防警報 | (水防活動用洪水警報)
(河川の水位の状況)
| 国土交通大臣→ | 都道府県知事--- | 水防管理者
|
| 水防関係者
|
| 指定河川以外の河川に対する水防警報 | (水防活動用洪水警報)
(河川の水位の状況)
| 都道府県知事→ | | 水防管理者
|
| 水防関係者
|
| 火災警報 | 気象庁(気象情報の通報) | 都道府県知事(通知) | 市町村長→ | 住民など
|
専門知識
気象観測の実際
地上気象観測
気象観測の概要
国連の下部組織である世界気象機関(WMO)が中心となって観測方法を国際的に統一している。
- 通報観測
- 毎日定時に行う定時通報観測
- 台風の接近時等に行う臨時通報観測
- 毎正時に自動的に行われる自動通報観測
の3種類がある。
- 気候観測
長期にわたる大気の変動を観察・把握するために、観測結果を統計処理し、気候資料として
さまざまな分野で利用される。
| 0-30km | 高層気象観測、オゾン観測 | 気温、風向風速、気圧、湿度、オゾン鉛直分布、オゾン全量など
|
| 0-15km | 気象衛星観測(静止気象衛星36000km上空) | 雲の分布、海面・雲頂温度、風向風速など気象資料の収集
|
| 0-10km | 気象レーダー観測 | 降水現象
|
| 0-5km | ウィンドプロファイラ観測 | 風向風速
|
| 地上・海面上 | 地上気象観測 | 気温、風向風速、気圧、湿度、降水量、天気など
|
| 地域気象観測 | 降水量、気温、風向風速、日照、積雪深
|
| 温室効果気体等の観測(大気バックグラウンド汚染観測) | 二酸化炭素など大気微量成分、大気混濁度、降水成分など
|
| 海面下・海底 | 海洋気象ブイロボット | 気温、水温(0~-100m)、風向風速、気圧、波浪
|
| 海洋気象観測船 | 気温・水温(0-海底)、気圧、風向風速、波浪、天気、海流、塩分など、レーダー・高速気象観測
|
気象測器による地上気象観測
地上気象観測は観測点における地表付近の気象要素を対象とするもので、気象観測の中で
最も基本となる。気圧計や温度計などの気象測器を用いるものと、観測員の目で観測する目視による
ものとがあり、国際的な取り決めに基づいて行われる。
気象測器を用いて観測する項目には、気圧、気温、風向・風速、降水量、湿度、日照時間、日射量などがある。
測器によるこれらの自動観測は連続的に記録され、毎正時の値が気象庁本庁に通報される。
気圧:
高度がばらばらな現地気圧は平均海面(0m、日本の場合は東京湾の平均海面)の気圧に換算する。
地上天気図で使用されている気圧は、海面気圧。
日本では海抜800m以上の高さにある観測地点で測定した気圧は、海面気圧を求めない。
現地気圧から海面気圧への換算は、静力学平衡の式と大気の状態方程式で産出する。
気圧計の種類は
| 電気式気圧計(静電容量型) | 真空部の上下の電極間の静電容量が気圧の変化によって変わり、その変化を
電気信号によって取り出して気圧を測定する。
|
| ファルタン型水銀気圧計 | 大気の圧力とつり合った水銀柱の高さを測定して気圧を求める。電気式や円筒振動式を補正するための
比較観測に用いられる。
|
| 円筒振動式気圧計 | 内筒と外筒の間を真空にした二重円筒は気圧の変化により内筒と外筒の間の
圧力が変るため、円筒の固有振動数が変る。その振動数を測定することにより気圧を求める。
|
| アネロイド型気圧計 | 気圧計内部にあるほぼ真空の容器が、気圧の変化でわずかにふくらんだりへこんだりする。
その動きを拡大させて気圧を測定する。主に船舶での観測に用いられる。
|
気温:
気温は地上約1.5m(多雪地では雪面上約1.5m)を基準にして測定する。観測場所は平坦、周囲の建物の影響を受けない場所、地面に芝草を
植えた「露場」と呼ばれる場所に測器を配置し、ここを中心に観測を行う。0.1℃単位。
| 電気式温度計(白金抵抗型)、気象庁の正規 | 白金線をセンサーとした電気抵抗の変化で気温を測定。通風筒に入れて
使用する。
|
| ガラス製温度計、比較観測用 | 棒状のガラス容器に水銀やエタノールを入れたもの。熱膨張が原理。比較的高温が水銀で、
低温がエタノール。主に百葉箱に入れて使用。
|
| 携帯用通風乾湿計 | 室内や野外での観測。気温、水蒸気圧、露点温度、相対湿度などが観測できる。
|
風向・風速:
地上10mで観測。水平成分(垂直成分は上昇流、下降流)。
風向:
風が吹いてくる風下の方向。真北を基準に時計回り8,16,36分割、通報には36分割。
風速:
0.1m/s単位、通報はノット(kt)、換算は 1m/s=1.944kt。
風向、風速は観測する時刻の前10minの平均値(風向は最多風向)。平均風速という。これに対し、瞬間風速。
最大瞬間風速は平均風速の1.5~2.0倍。この倍率を「突風率」という。風速が0.2m/s以下の場合は「静穏」として
風向は観測しない。
風の観測は、露場または開けた場所に塔または支柱を建て、地上10mの高さに測器を設置して風向風速計で測る。
| 風車型風向風速計 | 流線型胴体と鉛直な尾翼からなる風向感部、および4枚のプロペラの風速感部で構成。
風向に正しく向き、胴体と尾翼が周り、風速に比例してプロペラが回転して風向・風速を測る。
|
降水量:
降水量の観測:
降水は雨、雪、霰、雹など水になるものすべて。降水量:露場に作られた水平な地面に、ある時間内に
溜まった水の量。mm単位で測る。雨だけは雨量。雪などは、固形の深さを測り、溶かして水にした時の量が降水量。
できるだけ気流が水平で局所的な乱れが少ない所。ビルの屋上や高い場所はNG。周囲に建物や立木が有る場合は、
その高さの4倍以上離れた場所が望ましい。
| 転倒ます型雨量計 | 内径20cmの受水口から入った雨水は降水量が0.5mmに達すると、
左右2個の転倒ますに交互に注がれ、転倒・排水を繰り返す。その回数から降水量を測る。受水口の
高さは地表から約50cmが基準。
|
| 感雨計(平面型) | 感部にはセラミックス製の基盤に降水による通電を検知するための電極が付けてある。
降水を検知するとパルス信号を出し、その信号から降水現象の有無を観測する。
|
風の影響を避けるため、地面からの跳ね返りなどがない範囲でできるだけ受水口を低く。
積雪と降雪の深さの観測:
積雪の深さと降雪の深さ。降った雪などが露場などの観測場所の面積の半分以上を覆う状態を積雪と言い、その
積雪の深さは、ある時刻に積もっている雪の深さ。cmの目盛の付いた雪尺と積雪計が用いられる。
降雪の深さは、ある時間内に降り積もった雪の深さ。既に降り積もった雪の上に雪板を置いて新雪の深さを測る。
雪板:平らな板の中央にcmの目盛が付いた柱を鉛直に立てたもの。
地面や雪面上に新しい雪が降っても風で吹き払われたり融けたりして積もらなかった場合は、降雪0cmとし、
降雪無しと区別。
湿度:
相対湿度=水蒸気圧/その気温での飽和水蒸気圧
比湿、混合比、露点温度。
| 電気式温度計(静電容量型) | 感部は高分子フィルムの吸湿性を利用し、
相対湿度の変化による静電容量の変化を電気信号に変え、処理して算出。
|
| 携帯用通風乾湿計 | 水蒸気が少ないと湿球から蒸発が多くなり、気化熱が奪われて湿球温度が下がる事を利用した乾湿計。
乾球温度と湿球温度の差によって相対湿度、水蒸気圧、露点温度を求める。
|
| 塩化リチウム露点計 | 塩化リチウムの吸湿性を利用した露点温度を求める。従来は正規機器。まだ一部の気象官署で使用。
|
日射量:
可視光線域を中心として約0.3μm~約3μmの波長帯域を日射として観測。
日射:太陽放射が地表面を照射すること。そのエネルギの大きさが日射量。
地表に達する日射=直達光+散乱光。
- 直達光:太陽面から直接地表に達する日射。
- 散乱光:大気や雲、エーロゾルなどによって
散乱・反射され太陽面以外から入射する日射。
- 全天日射=直達日射+散乱日射
瞬間の日射量:kW/m^2、積算日射量:MJ/m^2。
直達日射を遮ったり強い反射光の影響を与えたり、天空を覆ったりする建物や木立、煙の発生源等の無い露場や
屋上を選んで設置。
| 全天電気式日射計 | 放射エネルギーを感部にある黒色の受光面に付けた熱電堆(熱電対直列array)によって電気信号に変換
|
| 直達電気式日射計 | 日射計感部、太陽追跡部、データ処理部で構成されており、直達日射量、直達日射積算量、
大気透過率などを測る。
|
| 日射日照計 | 全天電気式日射量と太陽追尾式日射計を一体化
|
日照時間:
直達日射量が、ある一定の値(120/m^2)以上の時間。
太陽の中心が東の地平線または水平線に現れてから西の地平線または水平線に沈むまでの時間→可照時間。
日照率=日照時間/可照時間。
直射日光が遮られない露場または屋上などを選び、設置台に測器を固定する。
| 太陽追尾式日照計 | 日照計感部、太陽自動追尾装置、制御部から構成され、
太陽からの直達光を日照計感部で取り入れて制御部で直達日射量と日射の一定の値(120w/m^2)を比較し、日照の有無を観測。
|
| 日射日照計 | 太陽追尾式日照計と全天日照計を一体化。
|
| 回転式日照計 | 従来の正規機器。まだ一部の気象官署で使用。
|
目視による観測
主に雲。
- 黄砂:春先に中国の黄河流域で吹きあげられた細かい砂塵が、上空の風に乗って日本(特に西)に運ばれてくる現象。
- 雷電:雷鳴が聞こえ、電光が見える現象。
- 視程:空を背景にした目標物の形を肉眼で確かめられる最大の距離のこと。つまり地表付近の大気の透明度。
雲の観測:
視程の広い場所を選んで、全雲量、雲形別の雲量、雲形、雲の高さ、雲の向きを観測。
全雲量:
空をひとわたり見回して全天の何割くらいが雲に覆われているかを 0~10の整数で表す。四捨五入。
全天空が雲で隙間なく覆われている時、雲量10。隙間が有ったら10-。雲がまったくなければ0だが、0.1-0.4なら0+。
地上実況気象通報式で通報する場合には、全天空が雲に覆われている時を8とし、0~8の階級への返還を行う。
雲形別の雲量:
ある雲形の雲だけで覆われた部分の全天空に対する割合。雲の高さが地上に近い物から高い物へ順に行う。
雲は部分的に重なっている事が多いので、それぞれの雲量の合計と全雲量は一致しない場合がある。
煙霧:煤煙や排気ガス含有粒子など微細な乾燥した塵あいが大気中に浮かんでいると空気が濁って視程が悪くなる状態。
雲形:
WHOの規定で10種類。
| 上層 | 巻雲(Ci)
巻積雲(Cc)
巻層雲(Cs) | 極地方:3-8km
温帯地方:5-13km
熱帯地方:6-18km
|
| 中層 | 高積雲(Ac) | 極地方:2-4km
温帯地方:2-7km
熱帯地方:2-8km
|
| 高層雲(As) | 普通は中層に見られるが、上層まで広がっている事が多い。
|
| 乱層雲(Ns) | 普通は中層に見られるが、上層及び下層に広がっている事が多い。
|
| 下層 | 層積雲(Sc)
層雲(St) | 極地方:地面付近-2km
温帯地方:地面付近-2km
熱帯地方:地面付近-2km
|
積雲(Cu)
積乱雲(Cb) | 雲底は普通下層にあるが、雲蝶は中層および上層まで達していることが多い。
|
まず上層の雲、次いで中層の雲という順番で現れるので、天気が悪くなる目安となる。
- 巻雲:氷晶が集まってできている。最も高い所に出現する(除-夜光雲)。繊維状の構造。
- 巻積雲:氷晶で出来ている薄く小さな丸い塊が規則正しく集まっている。さざ波状、鱗状、レンズ状などの形になる事が多い。
- 巻層雲:氷晶で出来ており、透き通った繊維状または層状の白っぽい雲。空の一部または全部を覆う。特に
太陽や月を覆うと、かさ現象(太陽光が屈折反射して起こる輪や筋)。
- 高積雲:白または灰色の雲で、一般に陰が有り薄い片、丸い塊などからなる層状の雲。レンズ状になることも。
- 高層雲:灰色あるいは青味がかった薄黒色で、繊維状または一様な層をなしており、空の一部または全部を覆う。
太陽や月のかさ現象は現れない。
- 乱層雲:暗灰色の層状の雲。太陽や月を完全に覆い隠す厚い雲。連続的な降水を伴う事多し。
- 層積雲:灰色または灰白色の雲。薄い板状、層状などをしている。比較的規則正しく配列した雲の塊。
レンズ状になることもある。通常、陰が有る。
- 層雲:通常、雲底の高度が一様な灰色の雲で、霧雨などが降る事がある。かさ現象は一般には現れない。
- 積雲:通常は濃密で輪郭がはっきりし、こぶのように盛り上がり、鉛直上方に発達する。
太陽に照らされた部分は白く輝くが、雲底は相対的に暗い。発達の過程により、平らな積雲、並み程度の積雲、
雄大な積雲の3つに分けられる。
- 積乱雲:鉛直上方に大きく発達した巨大な塔のような濃密な雲。雲蝶はかなとこ状または羽毛状に広がり、
高さ10km状に達する事が有る。突風、雷電、強い降水を伴う事がある。
雲の高さ:
地上から雲底までの高さをm単位で行う。できるだけ近くの山や高い建造物などを目安にする。また、
高層気象観測の結果から高さを推定できる場合も多いので参考にする。
雲の向き:
雲片または雲塊が進行してくる方向。北から8方位に分けて、雲形別に観測。不明の場合は×。殆ど静止していて
向きが分からない場合は-。
天気の観測:
気象庁では15種類。国際式天気記号は別にある。
| 快晴 | ○ | 雲量1以下
|
| 晴 | ○+| | 雲量2以上8以下
|
| 薄曇 | ○+|| | 雲量9以上であって、巻雲・巻積雲・巻層雲が見掛け上最も多い場合
|
| 曇り | ◎ | 雲量9以上であって、高積雲・高層雲・乱層雲・層積雲・層雲・積雲・積乱雲が見掛け上最も多い場合
|
| 煙霧 | ∞ | 視程が1km未満の場合
|
| 砂塵あらし | →+S
|
| 地吹雪 | →+↑
|
| 霧 | 三
|
| 霧雨 | 勾玉 | まとめて「降水現象」という
|
| 雨 | ●
|
| 霙 | ●+雪の結晶
|
| 雪 | 雪の結晶
|
| 霰 | △
|
| 雹 | ▲
|
| 雷 | Rの斜め線が矢印 |
|
地域気象観測システム(アメダス)
Automated Meteorological Data Acqusition System の略。
降水量、気温、風向・風速、日照時間、積雪を観測する自動気象観測装置で観測された気象データを自動的に収集するシステム。
WMOの基準で150km以下の間隔で配置する事が望ましいとされている。3時間ごとの定時通報観測を実施している気象官署約60個所で
この基準は満たしているが、メソスケール現象の予報には粗すぎる。
アメダスは全国約1310ヶ所で降水量、このうち約850ヶ所では気温、風向・風速、日照時間(4要素)も、豪雪地帯の約290ヶ所では積雪計も
観測する。
降水量の観測は約17km四方に1ヶ所、4要素の観測は約21km四方に1ヶ所の割合で実施。10分ごとに自動計測。毎正時に電話回線で
東京大手町の地域気象観測センターに自動収集、品質管理の後、気象庁の気象資料自動編集装置(アデス)によって、
全国の気象官署や自治体、報道機関などに配信(定時集配信)。
一定の基準値を超えた場合は、毎正時以外でも臨時報として送信(臨時集配信)。大雨や強風の監視に威力を発揮。
| 10分ごとに自動計測 | アメダス観測所
|
| 降水量 | 約1310ヶ所(約17km四方に1ヶ所)
|
| 降水量、気温、風向・風速、日照時間 | 約1310ヶ所のうちの約850ヶ所(約21km四方に1ヶ所)
|
| 降雪量 | 約1310ヶ所のうちの豪雪地帯の約290ヶ所
|
| ↓電話回線で毎正時に送信、基準値を超えた場合は、その都度臨時報
|
地域気象観測センター(大手町)
データの集計→
| 気象資料自動編集装置(アデス)
データの編集→配信 | 全国の気象官署
|
| 自治体
|
| 報道機関など
|
高層気象観測
1862年アメリカのグレーシアとコックスウェルが気球に乗って最初の高空気象観測を行った。8900mまで上昇したが、
空気が薄くなる事が知られていなかったので、死にかけた。
高層気象観測の方法
対流圏から成層圏にかけての高層における気温、風向・風速などの気象要素を観測すること。
水平スケール数千kmの気象現象の把握が目的。気球に測器を吊下げて上昇している間に
送られてくる信号を気象観測所で受信して観測。高度約5kmまでの風向・風速については、電波(レーダー)を利用した
ウィンドプロファイラ観測がおこなわれている。
一般に高気圧や低気圧、前線や台風などの気象現象はそれぞれ固有の3次元の立体構造を持っている。したがって
天気予報を行うためには必要なデータを収集・分析するためには地上気象観測だけでなく高層気象観測により
十分なデータを得る必要がある。
世界気象機関(WMO)は高層気象観測所を、陸上300km、海上1000km程度の間隔で設置する事を勧告している(可能なら一日4回、だめなら2回お願い)。
現在日本では全国に18ヶ所の高層気象観測所が配置され、勧告の基準を満たしている(稚内、根室、札幌、秋田、仙台、輪島、舘野、
米子、潮岬、八丈島、福岡、鹿児島、名塩、南鳥島、父島、那覇、南大東島、石垣島)。
高層気象観測には気球、電波(レーダー)、飛行中の航空機に頼むものなど、色々あるが、
特に重要なのが、ラジオゾンデ観測、ウィンドプロファイラ観測。
ラジオゾンデ観測:
気圧面の高度を静力学平衡の式と気体の状態方程式を用いて計算する。
- 観測項目:
ラジオゾンデとは、気圧センサー(静電容量式空盒気圧計)、気温センサー(サーミスタ温度計)、
湿度センサー(静電容量変化式湿度系)と、
これらの測定値を送信するための無線送信機などで構成される観測機器。これを気球に吊り下げ飛揚させ、自動追跡型
方向探知機を用いて追跡することで、地上から高度約30kmまでの気圧、気温、湿度、風向・風速を観測する。
直接測定できるのは、気圧、気温、湿度および観測所からラジオゾンデまでの高度角、方位角。
高度、風向・風速は、直接測定した観測項目から間接的に求める。
- 日射補正:
昼間に気温の測定を行う際、気温センサーの感部(サーミスタ)が日射を受けて周囲の空気よりも高くなるために、
日射誤差が生じる。この日射誤差を除去する作業。
日射の強さと感部と周囲の空気との熱伝導率に関係する。日射量は上空ほど強いので、補正量は高度が高いほど
大きくなる。また、上昇速度が遅いほど大きくなる(速いと冷える)。
- 間接測定(高度と風向・風速):
高度は、気圧、気温、湿度の観測値に基づいて、静力学平衡の式と気体の状態方程式を利用して求める。つまり、
気圧面間の空気の密度がわかると、その気圧差に相当する気層の厚さが計算できるので、
これを積分して地上から気球までの高度を求める。
また、風向・風速(高層風)については、計算して求めた高度と地上の方向探知機で測定されるラジオゾンデの
方位角、高度角から計算して求める。
湿度については、気温が-40℃以下に低下すると正確な測定が困難になるので、-40℃以下では湿度の測定は行わない。
ラジオゾンデ観測は、日本標準時の0900(00UTC)と2100(12UTC)の毎日2回、全国の高層気象観測所で行われている。
| 観測項目 | 気圧、気温、湿度、風向・風速
|
| 観測高度 | 地上~高度約30km
|
| 計測方法 | 気球で上昇中に計測
|
| 観測時間 | 毎日0900JST(00UTC), 2100JST(12UTC)
|
ウィンドプロファイラ観測:
集中豪雨などで重要な役割を果たす下層大気の流れを連続的に把握できる。上空約5kmまでの風向・風速を観測する。
ウィンドプロファイラとは、風の鉛直分布(プロファイル)を測定する機器。気象ドップラーレーダーの一種。
気象庁では全国31ヶ所に配置したウィンドプロファイラにより上空の風を観測する気象観測網
「局地的気象監視システム」を運用しており、その観測データはメソ数値予報モデルの初期値として利用される。
地上から上空(東西南北の方向)に向けて電波を発射した時の周波数と、大気の乱流によって散乱された電波を
受信したときの周波数の違いから、観測点上空の風向・風速を測定するもの。気象庁では
1.3GHzの電波を使って、高度約5kmまでの風を時間的にほぼ連続的(10minごと)に測定している。
各観測所で10minごとに観測された上空の風向・風速(10min平均値)の鉛直分布は、1hごとにまとめられて気象庁にある
中央監視局に伝送される。これらの観測データを鉛直シヤーのチェックなどの品質管理を行った後、メソ数値予報モデル
に入力・解析され、実況監視資料として1hごとに配信される。
ウィンドプロファイラは、災害をもたらす集中豪雨の発生や維持に重要な役割を果たす "下層大気の流れ" を精密に
観測できることから、豪雨や豪雪などのメソスケール現象の予測精度の向上に特に大きな効果がある。
配信される資料は、多画面平面図形式で、配信高度面は975,950,925,850,700,500hPaの各等圧面。
航空機観測:
海洋上空の観測データが送られてくる。
対地速度ベクトルから対気速度をベクトル引き算したら風ベクトルになる。
気球観測を捕捉する意味で、データの少ない海洋上空の航空機観測も重要。パイロットによる報告と、
飛行機の装置が自動的に行う報告がある。気象庁でなく、民間の航空会社が行っている。
高層気象観測結果の利用
観測されたデータは国際気象通報式に基づいて、指定気圧面の値(気温、風向、風速など)と
特異点の値に分けて世界中に通報されている。指定気圧面とは、気圧が1000,925,850,700,500hPaなどの等圧面の事。
また特異点とは、気温や湿度の特異点(逆転層、等温層などを示す変動点)および風の特異点(最大風速の点、
風速が静穏であることを示す点など)のことをいう。なお、高層実況通報式に従って観測結果を通報する時には、
高層風の風速はkt単位で、湿度は湿数として表現(気温と露点温度の差の事。
気圧を保ったまま温度が何度下がれば飽和するかということ)される。
高層気象観測で得られたデータは、数値予報の初期値として毎日の天気予報や、地球温暖化等の気候変動の解析などに役立てられる。
また観測結果は大気の立体構造を解析(高層解析)することにも用いられている。
高層解析で用いられる資料には、高層気象観測や航空機による観測によって得られるもののほかに、
山岳の気象官署で収集される観測資料などがある。高層解析を行う時は高層天気図のほかにエマグラム、鉛直断面図なども
併用され、より正確な気象予報がおこなわれる。
- 高層天気図:
高層大気の状態を示す天気図で、850,700,500,300hPaなど、気圧が一定の面(等圧面)について作られている。
天気図には、高層気象観測によって得られた各等圧面における風向・風速・高度、気温、湿数などの観測値が記入され、
等高度線や等温線などが描かれる。それぞれの等圧面で特定の大気現象を読み取ることができるため、
利用の仕方が違う。たとえば、850hPa面は前線や気流の解析、700hPa面は気温や湿潤域の分布状態の把握、
500hPa面は気圧の谷や尾根とそれにともなう渦度の解析、300hPa面はジェット気流の解析などに利用される。
- エマグラム:
横軸に気温を等間隔目盛に取り、縦軸に気圧を対数目盛でとった大気の熱力学的状態を解析するための線図。
図中には乾燥断熱線(等温位線)、湿潤断熱線(等湿球温位線)、等飽和混合比線が描かれており、
大気が安定か不安定かを判断する場合などに使われます。
- 鉛直断面図:
複数の地点を結ぶ水平線上の各地点における気象要素の鉛直分布を示した図。図中には等温線、等温位線、等風速線などが
描かれ、前線やジェット気流の把握などに役立てられている。
気象レーダー観測
全国20ヶ所にあり、ほぼ日本全国をカバーしている。RADAR(Radio Detection And Ranging)、気象レーダー→雲の中の
雨粒や氷粒などに当たって返って来る反射波(レーダーエコー)をキャッチし、連続的に観測。
気象レーダー観測の特徴
気象レーダーの探知範囲は半径数100km(限度300km)。メソスケール現象(数10km-数100km)の観測に適しており、
主として大気中の降水粒子の分布状況や集中豪雨、雷雲などの激しい気象の観測に利用される。
現在、気象庁の気象レーダー(20ヶ所)からの全てのデータはコンピュータで合成され、「レーダーエコー合成図」
として全国の各気象台などに送信される。
気象レーダーの原理:
気象レーダーは、レーダーアンテナからパルス状の電波(レーダービーム)を発射し、その電波が大気中の
降水粒子(雨粒、雹、霰、雪片など)によって反射されて戻って来るまでの時間から
降水粒子までの距離と方位を測定する。
気象レーダーには一般に3~10cmのマイクロ波という電波が用いられる。この波長を利用するのは、
直進性に優れているので、目標物の位置の測定が正確に出来ることと、雨や雪などの降水の探知に適した
長さの波長であるため。波長の長い方が遠距離まで観測できるが、感度は悪くなる。
気象レーダーの探知範囲:
半径300kmの円内に限られる。実はその理由は地球の丸味によりレーダービームが降水粒子よりも上空に行ってしまうから。
発射地点から300km離れると、高さは6kmになる。雨雲の中で降水粒子が存在するのは、一般に数kmの高さなので。
ということは、レーダーを設置する地点が高ければ探知範囲は大きくなる。アンテナの直径が大きい
場合も探知範囲が大きくなる。逆にビルや山などの障害物がある場合は、レーダービームの探知範囲は小さくなる。
地形エコーの除去:
地形エコーを完全には除去しきれない。降水粒子から返って来るレーダービームの反射のことを降水エコーという。
気象レーダーは、これをキャッチする事を本来の目的とするが、同時に山や高層ビルなどから
反射してくるエコー、つまり地形エコーもとらえてしまう。これは降水の観測にとって大きな障害になる。
現在では、エコー強度の大小によって地形エコーと降水エコーを識別している。また、降水粒子群からの
エコー強度が時間的に激しく変動する性質があることを利用して、地形エコーを識別し自動的に取り除いている。
つまり、降水粒子が大気の乱流や風速の変化により激しく運動するため、レーダーエコー内の降水エコーは
激しく変動する。それに対して、地形エコーはほぼ静止しており、そのエコーには変動がない。この差を
利用して、地形エコーの除去が可能となった。
ただし、シークラッター(海面の波浪によるエコー)やエンゼルエコー(大気中の密度差による屈折率の異常な違いや、
昆虫や鳥の集団飛行による電波散乱が原因のエコー、クリアー・クリアー・エコーとも)などの非降水エコーは、
パルスごとにエコーの強さが変化するので除去できない。
エコー強度:
レーダーエコーが観測されていても、上空のみに降水粒子が有って、地上では降水が観測されない場合がある。冬に発生する積雲や
積乱雲は、夏に比べて雲頂高度が低く、レーダービームが降水粒子の上を通過する場合が多くなるため、地上で観測される降水量に
エコーが相対的に弱くなる場合がある。
気象レーダー観測では、受信したレーダーエコーの強さによって、降水の程度を判断する。
受信したレーダーエコーの強さの事をエコー強度(受信電力)という。これは発射したレーダービームの強さ(送信電力)、
目標までの距離、波長、アンテナ(空中線)の大きさ、目標の大きさ・種類、途中の電波の減衰などにより異なる。
基本的にはエコー強度が強いほど大きな雨粒が多量に降っていると判断するが、判断にはさまざまな要素が必要。
たとえば、降水域が遠ければ、レーダービームの高度が高くなるので、上空しか観測できない。ところが、
実際には上空のみに降水粒子が有って、地上では降水が無い、ということもある。また、レーダーと目標とする降水粒子
との間に降水や雲、霧などが多い場合は、電波が減衰されエコーは弱くなる。
| 要因の種類 | エコー強度
|
| 発射したレーダービームの強さ | 強いほど強い
|
| 目標までの距離 | 近いほど強い
|
| 波長 | 短いほど強い
|
| アンテナの大きさ | 大きいほど強い
|
| 目標の大きさ | 大きいほど強い
|
| 途中の減衰 | 中間の物質が少ないほど強い
|
気象レーダー方程式:
気象レーダー方程式は、平均エコー強度がレーダーからの距離の2乗に反比例し、レーダー反射因子に比例する事を表す。
Pr=CI2 * Z / r2, Pr:平均エコー強度, C:定数,
I:途中の大気ガスによる減衰, Z:レーダー反射因子, r:反射体までの距離
定数Cは、光速度やレーダー特性(発射したレーダービームの強さ、アンテナ特性、波長、パルス幅など)によって決められる。
またレーダー反射因子Zは、単位体積中の降水粒子の直径Dの6乗の総和に比例する(Z∝ΣD^6)という関係があることから、
これを用いて平均エコー強度を求める。
すなわち、降水からのエコー強度は雨粒が大きいほど、あるいは数が多いほど大きくなる。距離が遠いほど小さくなる。
ブライトバンドとは、雨滴の方が雪や霰よりエコー強度が大きい事に起因し、落下している雪片が融けて雨になる
融解層に対応してエコーが大きくなること。雪や霰から雨滴に変るとエコー強度は5~6倍になる。
気象レーダーは気象レーダー方程式を用いて降水エコーの分布を自動的に計算・表示する。
雲粒は粒子の直径が小さすぎるため、通常の気象レーダーでは捉えられない。
レーダーによる雨量測定:
エコー強度から降水強度を算出する際には、統計的に決められた定数を用いる。
雨や雪などが単位時間内(通常1時間単位)に降る量を降水強度という。これまでの雨滴観測結果から、
降水強度R(mm/h)とレーダー反射因子Zの間には統計的関係(Z-R関係)が認められている。
Z=axRb, Z:レーダー反射因子, R:降水強度
a,bは降水の種類によって本来は異なっているが、気象庁のレーダー観測では降水の種類にかかわらず、
a=200, b=1.6 を使って降水強度を算出している。
現在、エコー強度から降水強度への換算は、Z-R関係を用いた換算を行った後、さらに
レーダー・アメダス解析雨量の作成によって得られた統計値(Z-R関係を用いたレーダーデータから推定した
降水量と地上で観測された降水量との比の統計値)を乗じるという所理を行うように変更している。
これによって、以前よりも降水強度の精度が改善されている。
レーダー・アメダス解析雨量図
レーダーによる雨量をアメダスで補正して作られている。
レーダー・アメダス解析雨量図:
全国約1310ヶ所(17km四方に1ヶ所)に展開されているアメダス観測所から、観測約10分後には
降水量をはじめとする様々な気象データが気象庁に送られてくる。これによってたとえば大雨などを短時間のうちに
しかも正確に把握する事が出来るが、アメダス観測所以外の場所で局地的な大雨が降った場合、雨の様子を
正確に把握することはできない。
一方、気象庁のレーダー観測では、1hに6回の降水強度を観測していて、これを積算して1時間雨量が求められている。
このように計算された雨量をレーダー雨量と呼ぶ。レーダー雨量は、海上を含む広範囲にわたって計算が可能で、
かつ2.5km四方と細かく計算されるので、空間的に連続した雨の分布を知る事ができる。しかし、実測した数値ではないため、
精度についてはアメダス雨量より劣る。
そこで、両者の長所を生かしてレーダー・アメダス解析雨量図が作成される。これは、レーダー観測で得た雨量をアメダス観測点の実測雨量で
補正して、2.5km四方の区域ごとに前1hの雨量を解析して作られた雨量分布図。言いかえれば、
レーダー・アメダス解析雨量図は、降水量の絶対値はアメダスに、強弱のパターンは気象レーダーに基づいている
降水量分布図といえる。
気象庁では、降水エコーをデジタル化する装置を全国のレーダーに導入・整備し、レーダーで観測される各地域のエコー強度を
数値化している。この装置では、レーダーの探知範囲を2.5km四方に分割し、そこでのエコーの強さを雨の
強さに換算して、定められた区分に従ってデジタル化する。
気象ドップラーレーダー
レーダーエコーの波長が送信時の波長と異なるばあい、降水粒子の移動を観測する事ができる。
気象ドップラーレーダーの原理:
雨滴や雪片は、雲の中にある時や降水のときには、通常移動している。気象ドップラーレーダー
は、目標とする移動中の降水粒子から反射される電波のドップラー効果を利用して降水粒子の速度を測定する測器。
受信時の電波の周波数と送信時の電波の周波数のずれの大きさが、降水粒子の移動速度を反映している。接近で周波数が高くなる。
気象ドップラーレーダーによる風速測定:
測定できるのは、レーダーと降水粒子を結ぶ方向の速度成分、つまり動径方向の速度成分(動径速度/ドップラー速度)
に限られる。
ある周波数でレーダーから発射した送信電波は、降水粒子に当たって反射して、受信機に戻って来るが、その際
ドップラー効果によって変化した周波数をドップラー周波数と言う。この
ドップラー周波数 fd は、受信電波の周波数-送信電波の周波数、で求められる。fd と 送信電波の波長λから、
降水粒子の動径速度 Vr を求める事ができる。
Vr = - fd * λ / 2
空港気象ドップラーレーダー:
空港気象ドップラーレーダは、低層ウインドシヤーを監視する。
空港付近の高度数100mまでで吹く風の変化は、揚力を増減させるため、航空機の離着陸に大きな影響を与える。
そこで、大気下層の風の急変(ウインドシヤー)やダウンバースト、その他のメソスケール現象の観測・解析
を目的に、空港気象ドップラーレーダーが、東京航空地方気象台(羽田空港)、新東京航空地方気象台(成田空港)、
関西航空地方気象台(関西国際空港)、新千歳航空測候所、大阪航空測候所、那覇航空測候所に整備されている。
空港気象ドップラーレーダーで得られた情報は、航空管制官を通じて機上のパイロットに通報される。
気象衛星観測
2013/03現在、ひまわり6号(MTSAT-1R:米国産)とひまわり7号(MTSAT-2:国産)の2台運用。7号は航空機の航法情報の提供も、運輸多目的衛星。
気象衛星による観測
世界の衛星観測網
静止衛星と極軌道気象衛星がある。1973年1月にWMOに提唱され決定した世界気象衛星観測網の計画に基づいて実施。
海や砂漠など、衛星からでないと観測できない部分をカバーするために、世界共同で行われている。
- 静止気象衛星:
静止気象衛星は、赤道上空約36000kmにあって、地球の自転と同じ各速度と向きで地球の周りを回る。
観測範囲は、衛星の直下点を中心とした半径6000kmにおよぶ。一点から観測するので、同一領域上での
気象変化が常に把握できるが、赤道上空にしか居られないので、高緯度地域は斜めの観測となり、
低緯度に比べ観測精度が良くない。
- 極軌道(太陽同期軌道)気象衛星:
赤道に対して垂直方向に周回しながら、地球表面を真下に見て観測する。極地方や高緯度地方でも
精度のよいデータを収集する事ができる。静止気象衛星でカバーしきれない地方の気象観測を行う。
アメリカのNOAAなど。静止しなくてもいいから、約850kmの高さで高精度。約14周/day。雲分布、
鉛直温度分布、水蒸気量、地表温度などを観測。近いので、一度に広い範囲の観測は無理。
静止気象衛星「ひまわり」の機能:
西太平洋、東アジア、オセアニア地域を観測。
雲画像のもとになるデータを送信。一時間ごとに作成。雲画像は、太陽からの可視光線の反射の強さによって
雲の状態を観測する「可視画像」と、赤外線の強さ、つまり温度に対応して作られる「赤外画像」および
「水蒸気画像」がある。
気象庁の気象衛星センターでは、送られてきたデータを処理し、画像の形にして、雲画像を1hおきに完成させる。
雲画像からは、雲の分布・高さ、地面・海面・雲頂の温度が分かるだけでなく、雲の動きを連続的に観測する事もできる(風向・風速の推定)。
また、ひまわりは中継機能を持っており、浅薄、ブイ、離島、航空機などで観測した気象資料を中継して、
気象センターのデータ処理センターへ送信する。さらに衛星観測によって得られた雲の画像を利用者にFAXするための
中継も行う。
可視画像:
可視画像は分解能(複数雲塊を一つ一つの雲塊として識別できる限界の能力)が良く、中、下層雲の観測に適している。
分解能が良いのは、赤外画像に比べて放射エネルギが大きいのと、波長が短いから。
- 可視画像の特徴:
可視光(0.55~0.90μm)の反射光の強さを、直下点での分解能1.25kmの可視放射計で測定し、
そのデータを地上のコンピュータで合成して作成する。
雲や地表などからの太陽光の反射をとらえるので、太陽に照らされている地球部分だけが表現される。
夜間はだめ。反射光が弱いほど暗い灰色に、強いほど白く表現される。厚い雲や下層雲、新しい雪氷などは白く写る。
- 可視画像の作成:
反射光の放射エネルギをコンピュータで処理して画像に変換する。アルベドは、0(全吸収)~100(全反射)%までで
あらわされるが、可視画像の場合はこれに黒から白の64段階の諧調を割り当てる。
可視画像では、多くの雲のアルベドは70~80%であり、地表面(約30%)や海面(約5~8%)のアルベドに比べて非常に高いので、
アルベドの大部分を64段階の会長に割り当てて雲を表現する事が出来る。このため、コントラストの
はっきりした雲画像を得られる。
画像の鮮明度も、分解能の良い可視画像の方が赤外画像よりも良好。
赤外画像:
昼でも夜でも観測できる。上層雲や鉛直に発達した対流雲の観測に適している。
結局、雲の温度を観測している。大気に吸収されない「大気の窓」の波長領域を観測している。IR1とIR2に分けて観測している。
| 赤外1(IR1) | 10.5~11.5μm
|
| 赤外2(IR2) | 11.5~12.5μm
|
- 赤外画像の特徴:
地球表面や雲から放射される10.5~12.5μmの赤外線の強さ(等価黒体温度)を、直下点での分解能5kmの赤外放射計で
測定し、そのデータを地上のコンピュータで処理して画像化。可視光線のエネルギに比べて極めて小さい。
それで分解能も小さくなる。
- 赤外画像の作成:
昼夜を問わず観測が行える。温度の低いところほど白く、温度の高いところほど黒くなるよう諧調を割り付けている。
一般に上空の雲ほど温度は低いので上空ほど白く、低空ほど黒くなる。地表面は暖かいので、黒くなるが、
冬のシベリア大陸や寒冷な陸地は灰色になる。
赤外画像は、黒体放射をかていした物体の温度が30~-80℃までを想定した256段階の諧調が割り当てられているが、
実際にはこのうちの半分から1/3しか使わない事が多いので、赤外画像はコントラストの少ない画像となり、
鮮明度は可視画像より劣る。
| | 可視画像 | 赤外画像
|
| データ | 可視光線の反射光強度 | 地球表面や雲からの赤外放射の強度
|
| 画像に白く写るもの | 下層雲、厚い雲(反射光が強い) | 中層から上空の雲(低温)
|
| 作成できる時間帯 | 昼のみ | 昼夜を問わず一日中
|
| 観測直下点での分解能 | 1.25km | 5km
|
ひまわりのデータから作成された画像から得られる情報の一つに、オホーツク海の海氷分布がある。
海氷の動きが雲の動きに比べて遅いことから識別できる。
可視画像・赤外画像に表現される雲の特徴:
可視画像では厚い雲ほど白く、赤外画像では高い(冷たい)雲ほど白く写る。
霧と下層の層雲は識別できない。
可視画像も赤外画像も、白く写る部分は雲。しかし、
- 上層雲:
対流圏の上層にあらわれ、-40~-50℃と非常に低温なので、厚い上層雲の場合、赤外画像では真っ白に写るが、
薄い雲の場合下層から来る赤外線の影響(透ける)もあって、明るさが落ちる。可視画像では、上層だけにある
薄い雲は良く写らないが、低気圧などの擾乱の厚い雲域は、アルベドが大きいので白く写る。
- 中層雲:
一般に雲は厚く、雲頂温度は -5~-20℃なので、可視画像では真っ白に、赤外画像では、ややくすんだ白に写る。
- 下層雲:
可視画像では白く、不規則な形の雲として映る。赤外画像では地表との温度差が5~10℃しかないので、
雲として識別することは困難。
- 霧:
地表面や海表面に接して発生している薄い下層雲といえる。雲頂温度が低く、地表面・海表面温度と差が無い。
可視画像では、一応白く写るが、赤外画像では黒くて地表面と区別できない。
- 発達した対流雲:
積乱雲や雄大積雲(積雲の中で著しく発達している物)は、雲頂高度が高く(雲頂温度が低い)、
太陽光をよく反射する(厚くて下が透けない)ので、可視画像・赤外画像ともに真っ白に写る。
| | 可視画像 | 赤外画像
|
| 上層雲 | 厚い雲は白く | 厚い雲は真っ白に、薄い雲は白の明るさが落ちる(下が透ける)
|
| 中層雲 | 真っ白になる | ややくすんだ白に写る
|
| 下層雲 | 白く写る(不規則な形として) | 識別できない(黒く写る)
|
| 霧 | 白く写る | 識別できない(黒く写る)
|
| 発達した対流雲 | 真っ白に写る | 真っ白に写る
|
- 日本海にある[A]は、可視画像では淡い灰色だが、赤外画像では真っ白に写っているので
比較的厚い上層雲と判断される。この雲はジェット気流の流れにほぼ直角な走向を持った巻雲の雲列(線状に並んだ
雲。トラバース・ライン)。
- 黄海にある[B]は、可視画像では一様に灰色に写っており、輪郭が鮮明。しかし赤外画像では
識別が困難。したがって、背の低い霧か層雲(下層雲)と判断できる。
- 東日本南部中心の[C]は、可視画像も赤外画像も真っ白。厚い雲。本州南岸には前線がのびており、これに
対応する厚い雲域(雲バンド)。
- 南西諸島の東海上にある[D]は、可視画像、赤外画像共に真っ白で輪郭が際立っている。
活発な積乱雲。筆の穂先上または人参状、テーパリング・クラウドというもの。天気図では寒冷前線の東側の暖域内に位置する。
- 東シナ海にある[E]は、可視画像では白く団塊状に移り、赤外画像では一様に暗灰色として写る。層積雲が広範囲に
広がっているとみられる。
- 華中の[F]は、可視画像も赤外画像も黒範囲に灰色が広がっているので、蜘蛛は高い中・上層雲主体の雲域と
判断される。天気図では、中国大陸奥地にある気圧の谷の前面に対応している。
- 南西諸島に長くのびている[G]は、寒冷前線に沿って発生している対流雲列。可視画像では細かい対流雲の
塊が見られ、赤外画像では明るい灰色の列に見えるので、この対流雲は比較的発達していると判断できる。
水蒸気画像の特徴:
水蒸気センサーによる画像。6.5~7.0μmという特定の波長帯の赤外放射エネルギの強さを測定。
この波長帯は水蒸気に吸収されやすい。高度400hPa付近における大気からの赤外放射が
衛星に最も大きく影響する事が知られている。水蒸気画像では、気象衛星に届く赤外放射の
強弱を白黒の濃淡で表現しており、中・上層に水蒸気が多く、温度の高い下層からの放射が届かない
部分は白に、そうでない部分は黒に割り付けられる。一般に黒く割りつけられるところは
乾燥域や中・上層雲や上層寒気の下降流域を表し、白いところは、湿潤域や積乱雲・下層雲や
下層からの水蒸気を運ぶ上昇流域を表す。また、中・上層に雲が無い場合は、乾燥域から
湿潤域になるにつれて次第に明るくなるように見える。
このように、水蒸気画像は、水蒸気の分布を知るだけでなく、上・中層の大気の流れも把握できる。
黒い所:暗域、白い所:明域、ジェット気流の軸の高緯度側が暗域、低緯度側が明域というのが特徴的なパターン
| 水蒸気画像の特徴
|
| 白いところ | 湿潤域、積乱雲・下層雲、下層からの水蒸気を運ぶ上昇流域
|
| 黒いところ | 乾燥域、中・上層雲、上層寒気の下降流域
|
| 黒→白 | 中・上層に雲が無く、乾燥域→湿潤域
|
| 高緯度:黒、低緯度:白 | ジェット気流の軸
|
気象衛星資料の利用
ひまわりからは1hごとの、同じ範囲の気象データが送られる。毎時間の雲画像が作成される。雲の動きを
観測できる。通常の天気予報のみならず、災害を伴う大雨、台風、発達した低気圧の接近などの
ときには、注意報や警報、気象情報の作成に欠かせない資料になっている。また、観測地点が
設置しにくい所の情報も得られて助かる。
- 雲域の予測への利用:
現在の天気と今後の変化を理解するに当たっては、可視画像・赤外画像・水蒸気画像に表現される雲分布、雲の高さ、雲の動き
に基づいて計算した風のデータなどが利用されている。特に雲パターンは、地上天気図、高層天気図などを
併用しながら利用すると大変有効。
たとえば低気圧にともなう雲域が北東方向に広がりながら拡大するような場合、この低気圧は発達段階にあると理解したり、
またそのほかの雲パターンなどから気象擾乱の位置や発達の段階・程度などを推定することができる。
さらに、海面水温や高層の風向・風速などの資料は、数値予報の精度向上に役立てられる。
- 台風の観測への利用:
台風は熱帯の海洋で発生・発達するが、発生地域では観測地点が少ないため、ひまわりからの情報は、
台風予報に欠かせない。台風が洋上で発生する初期のころに積乱雲の集団(クラスター)が画像に現れるが、
それが台風まで発達するかどうかの判断基準はない。しかし、台風の発達段階での特徴ある雲の分類は
整備されており、また雲パターンと台風の中心気圧、最大風速との関係もしられているので、これらを
総合して判断する事ができる。
| 温帯低気圧の発達に伴う雲域(赤外画像)のスケッチ
|
| (1)発生期 | (2)発達期 | (3)最盛期 | (4)衰弱期
|
| 気圧系としてまとまっていないため、雲分布は広がっているが、次第に前線に沿った雲域がまとまる。
| 低気圧として中心がはっきりし、前面の雲域は北へ盛り上がり、流線型の弧状となる。
| 発達がさらに進むと、雲の集中と盛り上がりが強まり、雲域は「ク」字型になることも。
| 最初の低気圧は後方に取り残され、雲は中心付近に円形(渦巻き)状になる。前方に新しい波動が形成され始める。
|
| 代表的な雲パターンとその特徴
|
| トランスバース・ライン
| - ジェット気流に沿い、流れの方向に対してほぼ直角の走向を持っている、規模の小さい巻雲の列。
- 強いジェット気流の強風軸は、この雲の北側にある事が多い。
|
| テーパリング・クラウド
| - 活発な積乱雲が連なり、毛筆の穂先あるいはにんじんの様な形をした雲域。
- 帯状の雲域の中や、その南側に現れる事が多く、強い雷雨や突風等を伴う事が多い。
|
| オープンセル
| - 洋上の広い範囲に見られ、雲の無い領域を発達した対流雲による雲の壁が取り囲み、
全体として蜂の巣状のパターンをした雲域。個の積雲をオープンセルという。強い寒気移流域に現れる。
|
| カルマン渦
| - 孤立した高さ約2km程度の島の風下側に、小さな雲域が列状に並ぶ事が有る。冬季に済州島や屋久島などの風下に見られる。
- この雲域は、主として層積雲で構成され、渦列の走向は対流圏下層の風向に沿っている。
|
| バルジ(気圧の谷の前面の雲域)
| - 気圧の谷が接近すると、その前面で暖気移流が生じ、上昇流が強まって雲が発生する。
- 気圧の谷が深まるにつれて、前面の暖気移流が強まり、それにともなう雲域が極側に次第に
拡大する(これをバルジという)。この雲域は主として中・上層雲の場合に多い。
|
天気予報の実際
様々な観測方法によって得られたデータを実際の天気予報にするまでの基本的な作業。
今日から明後日まで→短期予報。
数値予報:観測データ→品質管理→初期値化→客観解析→数値予報モデル→格子点値→翻訳・ガイダンス→予想の発表。
| 予報作業の種類と手順
|
| 世界各国の気象庁で | → | 気象庁で | → | 気象庁/気象予報士→利用者
|
| 観測およびデータの準備 | 数値予報モデル | 発表される予報
|
| 数値予報モデルへの入力のためデータを収集し、正しいデータの作成作業。
| - 全球モデル
- 領域モデル
- メソ数値予報モデル
- 台風モデル
- 1か月アンサンブル予報モデル
などのコンピュータ・プログラムが稼働し、右の各種天気予報のため翻訳やガイダンス、予報文などの資料を作成。
| - 天気予報(短期予報)本日・明日・明後日の予報、短時間予報、分布予報/時系列予報
- 週間天気予報
- 季節予報(1か月予報など)
- 注意報・警報
- 気象情報
など。
|
気象現象と予測可能性
気象現象の時間・空間スケール
時間スケール→現象の発生から消滅までの寿命。空間スケール→現象の空間的な広がり。
気象現象のスケール:
現象のスケールと空間スケールとの間には正の相関がある。
空間スケール(水平距離)を縦軸に、時間スケールを横軸にとると、各気象現象は左下から右上へ、ほぼ
対角線上に並ぶ。大きな空間スケールの現象は時間スケールが長く、反対に小さな現象は寿命も短くなる。
数値予報モデルの機能・性能には限界があり、予想対象とされている現象は、
- 時間スケール→半日から数日
- 空間スケール→数100kmから数千km
数値モデルでは、あらかじめ大気中に細かな3次元的な格子点網を設定しておき、これらの格子点上の気象要素
(風向・風速、温度など)の値によって、大気の連続的な状態を表現する事が出来るが、数値予報において、ある
擾乱を表現するには、そのスケール内に格子点が最小でも5格子点を必要とする。これ以下のスケールの
現象は、その現象を認識できても数値的に表現する事が出来ない。
擾乱の存在する時間と空間の「場」について:
大小様々な擾乱は、時間と空間の「場」の中に存在し、その中で気象要素によって表現される。
- 「場」とは、気象要素を表現する時間・空間のこと
大気中の大小様々な擾乱は、それぞれに固有の発生メカニズムや運動学的な特徴を持っており、それらは
全て物理法則に従った数式で関係づけられ、気象要素によって表現される。主な気象要素には、
風向・風速、温度、気圧、水蒸気量などがあり、これらは地上・高層気象観測によって測定され、数値予報の計算のための
初期値として格子点上にあらわされる。ただし、格子点で表現できない現象は物理過程として数式の中に関係づけられている。
この「気象要素で語る時間・空間」のことを気象要素の「場」という。現象を検討したり予想したりする場合、どのような
「場」において、どんな気象要素の値がどの程度のものなのかを、はっきり認識する事が大切。また、気象現象の特徴を
言葉で表現する時には、「数値で表現するとどうなるか」ということを必ずその裏付けとして持っておく必要がある。
- 大・中・小の「場」の包含関係
一般に、予報可能な気象現象の規模は、地球規模、総監規模、メソスケールの3つに分類される。
総監規模の現象は地球規模的な「場」に含まれ、それより小さいメソスケールの現象は、総監規模の「場」に含まれるという
包含関係にある。つまり、下位の現象は、その境界を通して上位の現象の影響を受けたり、
その反対に下位の現象が上位の現象に影響を与える事もある。
このように気象現象は、スケールの異なる擾乱がお互いに影響しあいながら存在しているので、
ある現象を表現する時には、常に「場」がどんなものであるかを明確にする必要がある。
スケールによる現象の特徴:
大気中の様々な現象(擾乱)は、それぞれに固有の発生メカニズムや運動学的な特徴を持っている。
- スケールが大きいと、地球の自転の影響が大きくなって、コリオリの力が効いてくる。
そして広域の面における温度・エネルギー輸送が問題となる。
- スケールが小さいと、曲率による遠心力の効果が大きくなり、コリオリの力はあまり効かなくなり、
局所的な風のシヤーは温度傾度に左右されやすくなる。
地球規模の現象:
水平スケール5000km以上の地球全体あるいはその大部分にわたって起こる現象。次のような、大陸と海洋の
分布が支配するモンスーン(季節風)や超長波、ブロッキング等が代表的。
| モンスーン(季節風) | 地表における大陸と海洋の大きな熱的コントラストにより生じた気圧分布によって
引き起こされる大規模な循環。夏と冬とでは風向きがほぼ逆転し、それにともなう降水などの気象に顕著な季節変化が起こる現象。
|
| 超長波 | 大気中にみられる波長の長い擾乱で最大規模のもの。地球を取り巻く波数1~3の波長で、
水平波長が1万kmにもなり、ヒマラヤやロッキーなどの大山塊によって励起される。
|
| ブロッキング | 中・高緯度偏西風帯のジェット気流が南北に大きく蛇行する事により、上層の長波とそれに
ともなう移動性高・低気圧が停滞し、数日以上もそれらが持続する現象。同じ天候が長く続くことから、異常気象の原因になる。
|
| 夏冬の気団(高気圧) | 太平洋高気圧(亜熱帯高気圧)は、対流圏上層まで存在する高気圧で、
シベリア高気圧は、対流圏下層にしか存在しない高気圧。
|
偏西風:一般に、中緯度対流圏の中・上層および成層圏、中間圏において、地球の自転や南北の温度差により発生し、
地球を西から東へ周回して吹いている風のこと。南北両半球に存在し、超長波や長波などの波動は、この偏西風帯の中で
発生している。
総監規模の現象:
温帯高・低気圧、移動性高気圧やそれに関わる長波の規模が総監規模。2000~5000km程度が代表的で、日本列島の数倍くらい。
| 温帯高・低気圧 | 傾圧不安定場、偏西風帯内で発生する。通常、温帯低気圧は寒冷前線・温暖前線をともなう。
|
| 寒冷渦 | 偏西風蛇行が大きくなり、気圧の谷から切り離されて形成されることが多い。
|
メソスケールの現象:
水平スケールが約2km~2000kmまでの現象をいう。さらにα(200~2000km)、β(20~200km)、γ(2~20km)の3つに分けられる。
メソα
(200~2000km) | 熱帯低気圧(台風) | 熱帯地方で発生し、北上する。
日本に接近あるいは上陸すると大きな被害をもたらすことがある。
|
| 梅雨前線上の小低気圧 | 水平スケール1000km前後、鉛直スケールが5km程度までの小低気圧。
対流圏上層では明瞭でなくなる事が多い。
|
| ポーラーロー | 寒気団内に発生する前線をともなわない小低気圧。高緯度~中緯度の海域に発生する事が多い。
|
| 集中豪雨・豪雪 | 集中豪雨は梅雨時のローカルな現象、豪雪は冬季のローカルな現象。
|
| 雲クラスター | 対流雲(積雲)が集まってできた水平スケール数100kmの巨大な雲の塊のこと。特に
梅雨末期の集中豪雨の際や熱帯地方で多く見られる。
|
| メソβ(20~200km) | フェーン現象 | 台風や低気圧の通過する際、湿った空気が山を越えると、乾燥した熱風に変化する現象。
|
| メソγ(2~20km) | 積乱雲 | 大気の成層が不安定の場で発生し、発達する(数km~数10km)。積乱雲の場合、
気流の上昇速度が大きすぎて静力学平衡は成立しない。
|
ミクロスケールの現象:
| 重力波 | 風が山岳に衝突したとき発生し、その衝突エネルギーは対流圏より上層まで伝播する。
|
| 晴天乱気流 | 雲の無いところに起こる乱気流で、上空のジェット気流付近で発生する。
予測が困難なため、航空機の運航に大きな影響を与える。
|
| 竜巻 | 局地的なスケールでは最も激しい。
|
| ダウンバースト | 積乱雲の下で発生した激しい下降流が地表面にぶつかって水平方向に広がって行く現象。
|
| 突風 | 非常に局地的な現象で、数分で終わる。
|
予測可能性
数値予報による予想結果には、必ず「あたり・はずれ」の問題がつきまとう。つまり、数値予報モデルの精密性、
観測点の間隔やコンピュータの性能の限界などによって、どの程度先の期間まで正確に気象現象を予想できるか
という「予想可能性」が問題となる。
天気の予想は「観測値+数値予報モデル→天気の予想」の関係にある。
数値予報を使う場合は「できること・できないこと」を判断し、できるとしてもどの程度信頼できる予想なのかを
把握しておく必要がある。
数値予報による気象現象の予測の精度が、気候値予報(平年値のこと。気象要素の30年間の累計平均値のこと)の
精度にまで落ちてしまう期間を「予報の有効期間」とよぶ。それ以上の数値予報の期間を延ばしても
精度がさらに落ちてしまうので、予報として意味が無い。
なお、予測精度に影響を与える要因には、大気自身のカオス的な性質(系に非線形性による、挙動の質的差異)によるものと、
観測値の誤差や数値予報モデルの性能によるものとがある。
数値予報でできること:
予測する期間が長くなるほど、数値予防の精度は低くなる。数値予報における天気変化の予測は、10日~2週間程度が限界といわれている。
数値予報は、総監規模の現象を予想対象としており、数値予報モデルで表現できる現象の最小の水平スケールは、
そのモデルの格子間隔の5~8倍とされている。つまり、格子5点以上のスケールの現象が対象となる。たとえば、格子間隔
20kmの数値予報モデルで予報できるのは、およそ100kmより大きいスケールを持つ現象といえる。
また予測精度は、時間的には半日~数日先までの「短期予報」が最も高く、週間予報になると最後には60%程度になってしまう。
中期・長期予報の場合、精度はさらに低下する。これらは、観測誤差や大気のカオス的性質によるもので、
日々の天気変化の予測は 10日~2週間程度が限度とされている。
このように、予想には時間・空間において予測可能限界があるので、限界を超える部分についての対応については次に、
数値予報でできないことへの対応:
直接表現できない小さな現象もなんとか表現したい。数値予報モデルでは、格子間隔以下のスケールの現象の効果を
パラメタリゼーションで取り入れている。
パラメタリゼーション:スケールの小さな現象は、格子間隔の中にうずもれ、数値予報モデルでは表現できない。
しかしその小さな現象が、格子間隔よりスケールの大きな気象現象に影響を及ぼす事が有る。
たとえば雷雨の様な激しい降雨があると、多量の潜熱が放出されて、それが温帯低気圧の発達に大きく影響する。
このため格子間隔以下の現象でも、格子間隔より大きい現象に及ぼす影響は、単純化して数値予報モデルに
取り入れるように工夫されている。これがパラメタリゼーション。
- 数値予報モデルでは、格子間隔よりも小さな現象は直接表現することが困難。
このため、小さなスケールの現象による影響(物理的効果)を取り入れるパラメタリゼーションという手法を使う。
- 週間予報や1か月予報は精度が落ちるので、複数の初期値を用いたアンサンブル予報という手法が使われている。
アンサンブル予報は、複数の初期値によって得られる予報値の集団(アンサンブル)の平均値を最終的な予報とする
手法(カオスに対応する苦肉の策)。
- 数時間先の短時間の予想においては、現在の数値予報モデルでは予測不可能な部分もあるため、
なうキャストとして気象レーダーや気象衛星、アメダスなどリアルタイムに入電される観測データを
数値予報結果に加味して修正し、出来る限り信頼性の高い予測作業が行われる。
- 現在の数値予報モデルは、局地的な大雨に対しては時間的空間的な誤差が大きいため予測が困難だが、
大雨の潜在性(ポテンシャリティー)はある程度予想できる。つまり、大雨となる可能性を予想する事は可能。
数値予報の方法
19世紀に既に数値予報を試みたリチャードソンは、6時間後の地上気圧の変化の予想を6週間かけて人力で行った。
しかも、計算はうまくいかなかった。だが、現代のコンピュータ技術が彼の夢を可能にした。
数値予報の原理
データ入力
(観測値) | → | データ処理
(数値予報モデル) | → | データ出力
(予想値)
|
数値予報のしくみ:
大気の状態は、3次元の格子点ごとの気象要素の値(物理量)で把握する。数値予報は、気象現象の時間変化を
物理学の法則に従って計算し、大気の将来の状態を予測する方法。
大気の状態は格子点で表される:
大気の状態は、運動方程式、空気および水蒸気の連続の式、熱力学方程式などの物理学の法則にしたがって変化する。
これらの方程式は、ある時刻の気象要素の値(物理量)が決まれば、微小時間後の大気の状態の変化が求められるようになっている。
ただし、方程式から微小時間後の変化量を計算するには、大気中のあらゆる点で現在の大気の状態を知っておく必要があるが、
実際の気象観測においてはそれは不可能。
そこで、大気中に、水平方向・鉛直方向に規則的な格子点網を設定する。その各格子点ごとに
気象要素(風向・風速、気圧、温度、水蒸気量など)の値を求めれば、ある瞬間の大気全体の状態を把握でき、
それによって物理量の変化量も計算できる。つまり、格子点は方程式の計算に必要な気象要素の値を求めるために
仮想的に設けられた点。
実際の観測地点は必ずしも格子点にあるわけではないので、各格子点の周囲にある観測地点で測定した値を用いて、
各格子点における気象要素の代表的な値を求める。
こうして求められた大気の状態の値を初期値と言う。それを方程式にあてはめて計算する。
その結果、計算を始めた時刻(ex.0900)の大気の状態が、微小時間後(ex.+0005)にどんな状態に変化するか、
その変化量を各格子点で求める事ができる。すなわち、初期値と微小時間後の変化量から、
0905の大気の状態がわかる。このような計算を、タイムステップと呼ばれる小さな時間間隔で繰り返し行えば、
24時間後や48時間後の各格子点の値が得られ、大気の将来の状態を予測する事ができる。
物理量の時間変化の表現:
以上の事を式で表現してみる。ある固定点でみた物理量の時間変化は、物理量の移流に密接に関連している。
まず、物理量の移流量は、
[物理量の移流量 = 物理量の傾度 x 傾度方向の風速]
という式で表せる。物理量の傾度については、隣接格子点の物理量の差によって求める。物理量の時間変化は
[物理量の時間変化 = 物理量の移流量 x 経過時間 + 物理過程による変化]
という式で表せる。物理過程とは、地表・海表面の摩擦、大気乱流による熱・水蒸気輸送、大気境界面を通じて
流入する顕熱や潜熱、上昇流や積雲対流にともなう凝結熱の放出、雨滴の蒸発、太陽放射の影響などのこと。これらは
格子点では表せない現象だが、大気に影響を与えるため、数式化されて数値予報モデルに組み込まれている。
たとえば、ある格子点での温位の時間変化は、
[温位の時間変化 = 移流による変化(温位の移流量 x 経過時間) + 物理過程による変化]
で表されることになる。
ここで、移流は断熱変化、物理過程は非断熱変化としてとして扱われる。現象によっては、移流と物理過程の影響が同程度ではなく、
特定の項だけが卓越していることがある。たとえば、晴天の夜間に地上付近で気温が下がる現象は、放射冷却のような
非断熱変化の影響が大きく、風に左右される移流の効果は相対的に小さいと言える。このような移流の大小は、
数値予報における予想を左右する重要な要素になっている。
さらに予想値は、物理量の変化後の値ということになるので、初期値に物理量の時間変化を加えればよいことになる。つまり、
[予想値(物理量の変化後の値) = 初期値 + 物理量の時間変化]
と言う式が成り立ち、この式から予測が可能となる。
数値予報で使われている基礎方程式(プリミティブ方程式):
数値予報では、運動方程式、熱力学の第一法則、空気および水蒸気についての連続の式、気体の状態方程式が使われる。
- 運動方程式
- 水平方向(ニュートンの運動方程式)
- 鉛直方向(静力学平衡)
- 空気の連続の式(質量保存の法則)
- 熱力学方程式(熱力学の第一法則、熱エネルギ保存の法則)
- 水蒸気の連続の式(水蒸気保存の法則)
- 気体の状態方程式(ボイル・シャルルの法則)
| x: | 直交座標系の原点からの東西方向の距離
|
| y: | 直交座標系の原点からの南北方向の距離
|
| z: | 直交座標系の原点からの鉛直方向の距離
|
| p: | 気圧
|
| t: | 時間
|
| u: | x方向の速度、u=dx/dt
|
| v: | y方向の速度、v=dy/dt
|
| w: | z方向の速度、w=dz/dt
|
| Ω: | 地球の回転角速度
|
| φ: | 緯度
|
| ρ: | 密度
|
| α: | 比容(密度の逆数、α=1/ρ)
|
| θ: | 温位
|
※印は、物理過程であることを示す。
全微分記号dと偏微分記号∂の違いについて:
空気塊の気圧や気温、速度などのように、時間的・空間的に絶えず動いている物理量の変化を表すには二つの方法がある。
- 空気塊そのものの変化量を、直接空気塊を追跡しながら測る方法。たとえば、ある空気塊の物理量Mの時間変化は
[dM/dt]で表される(d:全微分記号)。この方法は、空気塊そのものを直接表現するので、空気塊の運動や気団の移動を調べるのに
便利。しかし個々の空気塊を常に識別して観測するのは大変困難。
- 実際の観測値を適用しやすくするため、偏微分記号∂(ラウンドディー)を使って、[∂M/∂t]と表すのがもう一つの方法。
これは、ある固定点で観測した物理量Mの値の時間変化率のこと。たとえば気温の観測値が0850にT1、0900にT2であったとすると、
∂M/∂tは[(T2-T1)/600s]なので、観測値から容易に変化率が分かる。
運動方程式(水平方向、ニュートンの運動方程式):
ニュートンの運動の第二法則「力=質量X加速度」を水平方向に適用したもの。固定点で見た水平方向の風速の時間変化は、
速度移流・コリオリの力・気圧傾度力・摩擦力の和に等しいものとして表される。
| ∂u/∂t | = | -u・∂u/∂x -v・∂u/∂y -w・∂u/∂z | +2Ωsinφ・v | -1/ρ・∂p/∂x | +Fx
|
固定点で見た
x方向の風速の
時間変化 | | 速度移流 | コリオリの力 | 水平方向の
気圧傾度力 | 摩擦力※
|
| ∂v/∂t | = | -u・∂v/∂x -v・∂v/∂y -w・∂v/∂z | +2Ωsinφ・u | -1/ρ・∂p/∂y | +Fy
|
固定点で見た
y方向の風速の
時間変化 | | 速度移流 | コリオリの力 | 水平方向の
気圧傾度力 | 摩擦力※
|
運動方程式(鉛直方向、静力学平衡):
ニュートンの運動の第二法則を鉛直方向に適用したもので、鉛直の気圧傾度力と重力の二つがつり合っている式。
鉛直スケールが水平スケールに比べてはるかに小さい現象について成立する。
| -1/ρ・∂p/∂z | = | g
|
鉛直方向の
気圧傾度力 | | 重力
|
空気の連続の式(質量保存の法則):
空気の質量は運動によって変らない事を表す。固定点で見た空気密度の時間変化が、移動に伴う
密度移流と、風の収束・発散による密度変化との輪で表される。
| ∂ρ/∂t | = | -u・∂ρ/∂x -v・∂ρ/∂y -w・∂ρ/∂z | -ρ・(∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z)
|
固定点で見た
密度ρの時間変化 | | 密度移流 | 収束・発散による密度変化
|
熱力学方程式(熱力学の第一法則、熱エネルギ保存の法則):
外部からの加熱が無ければ、熱エネルギは保存される。これを温位によって表すと、固定点で見た温位の時間変化は、
温位の移流効果と、非断熱変化に伴う加熱との和で表される。ちなみに、水平移流と鉛直移流の影響はほぼ同程度。
| ∂θ/∂t | = | -u・∂θ/∂x -v・∂θ/∂y -w・∂θ/∂z | +Q
|
固定点で見た
温位θの時間変化 | | 温位の移流効果 | 非断熱変化に伴う加熱※
|
水蒸気の連続の式(水蒸気保存の法則):
外部からの加湿がなければ水蒸気量は保存されるということを表す。これを比湿によって表すと、固定点でみた
比湿の時間変化は、比湿の移流効果と、非断熱変化にともなう加湿との和で表される。
| ∂q/∂t | = | -u・∂q/∂x -v・∂q/∂y -w・∂q/∂z | +M
|
固定点で見た
比湿qの時間変化 | | 比湿の移流効果 | 非断熱変化に伴う加湿※
|
気体の状態方程式:
「気体の圧力は、密度 x (絶対)温度 に比例する」という、ボイル・シャルルの法則を大気に適用したもの。式には
時間変化の要素は入っていないが、気圧、密度、温度のうち任意の2つの物理量の値を与えると、残りの物理量の値が
一意に決まるという重要な式。
| プリミティブ方程式で求められる物理量
|
| 水平方向の運動方程式 | 風向・風速
|
| 鉛直方向の運動方程式 | 気圧
|
| 空気の連続の式 | 密度
|
| 熱力学方程式 | 温位
|
| 水蒸気の連続の式 | 比湿
|
| 気体の状態方程式 | 気圧・密度・温度
|
数値予報の手順
プリミティブ方程式に初期値を与えると、任意の時刻の予想値が算出される。
数値予報の流れ:
予報精度を高めるための様々な工夫。データ収集→品質管理→客観解析→初期値化→予測。
数値予報の作業には、観測から始まって数値予報モデルの稼働で終了するという基本的な流れがある。
その中で、特に大切な作業である品質管理、客観解析、初期値化について記述する。
- 品質管理:
観測データには、観測機器による誤差や人為的なミスなど、多少の誤差は含まれうる。こうしたデータに
大きな誤りが無いかどうかのチェック。したがって、観測データの品質管理は精度の高い予報を行うために
非常に重要な作業。
- 客観解析:
品質管理された観測データにもとづいて、3次元的に規則正しく並んだ格子点での気象要素(物理量)の値を求める過程。
客観解析によって得られた各格子点における気温や風などの物理量を解析値といい、数値予報のための初期値を作成する
ために利用される。客観解析における解析値は、前回計算された数値予報モデルの予想値(第一推定値)と、格子点周辺の
観測データとの誤差を考慮して求める。ただし、海上などの観測データの少ない場所では、第一推定値をそのまま
解析値として使用する。
また、多くの場合、客観解析の行われる格子点と観測地点の空間的な位置が一致することはないが、たとえ両者が
一致しても観測値がただちに解析値とはならない。それは、格子点における物理量はその周辺領域の代表地であるため、
格子点値は格子点を中心にして、値が平均化されているから。
- 初期値化(イニシャリゼーション):
客観解析された各格子点の解析値は、数値予報モデルの初期値として、そのままでは使われない。初期値化と言う作業を経て
はじめて初期値となる。初期値化の主な目的は、数値予報の結果に大きな誤差を生じさせる重力波ノイズの除去を行う事。
予報解析サイクル:
客観解析で得られた結果は、初期値化を経て数値予報の初期値となり、それをもとに6時間後の数値予報を行う。
そして、6時間後には、その予想値と実際の観測データとの誤差をとり、その誤差を次回の解析に反映させる。
これを繰り返していくことにより、より精度の高い解析値が得られ、数値予報の精度も向上する。このような
解析の進め方を「予報解析サイクル」という。
数値予報の作業の流れ:
全体のながれ。基本的な作業の流れは、観測データの収集から始まり、品質管理、客観解析、初期値化、予測、の順に行われる。
| 数値予報の作業の流れ
|
| 1.観測データの収集 | 気象庁では、地上気象観測、高層気象観測、船舶、航空機、気象衛星、気象レーダーなどから
数値予報の初期値とするための観測データを収集している。
|
| ↓ |
|
| 2.品質管理 | 観測データには様々な誤差が含まれている。気候値や周囲の観測点のデータと比較し、「誤り」と
判定されたデータは客観解析には使われない(その場合第一推定値が使われる)。
|
| ↓ |
|
| 3.客観解析 | 時間的・空間的に不規則に存在しているデータや、観測値の無い地点には、前回の予想値(第一推定値)を
使って解析し、初期値のためのデータを格子点に割り付ける(格子点の値を決める)。
|
| ↓ |
|
| 4.初期値化 | 客観解析値をそのまま初期値として使用すると、予測結果に誤差を生じさせる「重力波ノイズ」という
波が現れる。この波を除去する作業。
|
| ↓ |
|
| 予測(数値予報) | プリミティプ方程式(運動方程式・熱力学方程式・空気および水蒸気の連続の式・
気体の状態方程式)を数値的に解いて、格子点ごとの予測結果を数値で(GPVとして)得る。
|
このような手順によって得られた数値予報の結果、つまり予報値は、格子点値(Grid Point Value)として数値で
出力される。しかし、数値のままよりも天気図のような形にして表現する方が分かりやすいため、それぞれの
気象要素にふさわしい予想図などに変換して出力される。また格子点値は、コンピュータでの処理が可能なので、
そのまま数値データとしても提供される。
さらに、気象庁の予報官や気象予報士は、出力された予想図などの解釈や修正のためにリアルタイムデータや
ガイダンスなどを支援資料として使い、かつ気象理論の知識を生かして予報文を作成する。
| ↑→ | 数値予報モデルを用いた時間的数値積分、大気現象を支配する物理法則を適用 | →↓
|
初期値
(予報計算開始時の気象要素を初期値化したもの) | 気象要素や物理量の時間変化量を
時間間隔ごとに計算し、その時刻の値に加えられることで微小時間後の予測値が得られる。この過程を予測時間まで繰り返す。
| 予測値(予報対象時間の天気図や物理量を出力する)
|
| ↑ | ↓
|
観測データの
品質管理・客観解析 | ← | 天気予報(ガイダンス資料)
|
| ↑ | | ↓
|
| 観測データの収集 | | 発表
|
数値予報モデル
数値予報は、大気の状態を支配する物理法則に基づいて、さまざまな気象要素(物理量)の時間変化をコンピュータを用いて
数値的に解いて、将来の大気の状態を予測するもの。
その大気の状態を支配する方程式を数値的に解くためのプログラムを数値予報モデルといい、現在気象庁は
- 全球モデル(GSM)
- 領域モデル(RSM)
- メソ数値予報モデル(MSM)
- 台風モデル(TYM)
- 一か月アンサンブル予報モデル
の5種類を稼働させている。将来的には、
- 非静力学モデル:
積雲対流による集中豪雨などの顕著な降水現象の多くは、水平スケールが通常数kmで、こうした現象では
鉛直方向の運動が相対的に大きくなるので、静力学平衡の式が成り立たない。このためメソスケール以下の詳細な大気の
運動を予報するには、対流活動などによる鉛直の大気の運動(上昇流や下降流)を直接計算する事ができる数値予報モデルである
必要がある。こうした数値予報モデルを「非静力学モデル」といい、気象庁では2006年からの稼働を目指している。
も。
2013/03現在、以下の通り。
| モデル名 | 予報領域 | 水平格子間隔 | 鉛直層数 | 予報期間 | 計算頻度
|
| メソモデル(MSM) | 日本周辺 | 5km | 50層 | 15h
33h | 4回/日
4回/日
|
| 全球モデル(GSM) | 地球全体 | 20km | 60層 | 84時間
9日間 | 3回/日
1回/日
|
| 週間アンサンブル予報モデル | 60km | 9日x51メンバー | 1回/日
|
| 1か月アンサンブル予報モデル | 110km | 40層 | 17日x50メンバー
34日x50メンバー | 毎週日・月
毎週水・木
|
| 3か月アンサンブル予報モデル | 180km | 120日x51メンバー | 1回/月
|
| 暖寒候期アンサンブル予報モデル | 150~210日x51メンバー | 1回/月(2,3,4,9,10月)
|
| 台風アンサンブルモデル | 中緯度及び台風周辺 | 60km | 60層 | 5.5日x11メンバー | 4回/日
|
このほかに、気象研究所/数値予報課非静力学モデル(MRI/NPD-NHM)、エルニーニョ予測モデルがある。
数値予報モデルの種類:
全球モデルは地球規模や総監規模、領域モデルは総監規模や水平スケール100km以上のメソスケール現象が予報対象。
台風の進路予報においては、積雲対流の表現だけでなく、太平洋高気圧の消長や中緯度の偏西風擾乱の動向など、
台風を取り巻く周囲の大規模な風の場が適切に予測されていることが重要になる。また、積雲対流はスケールが小さいため
格子点で表現できない。このため、パラメタリゼーションで取りこまれているが、台風の目の構造は直接表現できない。
- 全球モデル:
地球規模や総監規模の気象現象を予報の対象としたもので、主に週間天気予報と台風進路予報に使われる。
予報期間は216時間(9日)先までで、計算範囲は地球全体となる。水平格子間隔は約55km、鉛直方向は40層。
- 領域モデル:
総監規模および水平スケール数100km以上のメソスケール現象を対象としたもので、主に明日までの天気予報
(短期予報)などに使われる。予報期間は51時間先まで。日本周辺の気象を細かく予測するため、日本やアジア地域を、
全球モデルよりも細かい水平格子間隔20km、鉛直方向40層でおおっている。
- メソ数値予報モデル:
水平スケール数10km~数100km程度で、寿命が数時間のメソスケール現象を予報の対象としたもので、
主に降水短時間予報の入力データや防災気象情報の支援などに使われる。水平格子間隔10km、4回/1日稼働される。
- 台風モデル:
台風の進路と強さの詳細な予報に使われる。予報時間は84時間で、気象庁が必要と認める時に、最大で 4回/日、2個
までの台風に付いて稼働される。台風は、その中心付近で気圧傾度が高く、強風・強雨域の水平規模が小さいので、
予報精度を向上させるため、水平格子間隔は24kmになっている。また、中心部の初期値の精度をよくするため、
台風の気圧分布を仮定して取り入れている(台風ボーガス)。台風の進路予報においては、全球モデルの予測結果を併用して
予報精度の向上を図っている。
- 1か月アンサンブル予報モデル:
全球モデルの水平格子間隔を約110kmに広げたもので、アンサンブル予報の手法による1カ月予報に使われる。
数値予報モデルの稼働:
領域モデルは、全球モデルから境界条件を貰い受け、2回/日、0900JST(0000UTC)と2100JST(1200UTC)のデータを初期値として稼働し、
全球モデルと共に天気予報(短期予報)や週間予報などに利用されている。
このほかに、短時間予報のためにメソ数値予報モデルが稼働され、また季節予報や台風予報のための数値予報モデルも適宜
稼働される。
数値予報モデルでは、大気下面の境界条件として「海陸分布、地形、海面水温分布、陸面の粗度、アルベド、雪氷分布」などが
与えられる。そして、風、気圧、温度、水蒸気量の3次元分布のほか、雲や降水量、地面温度などの分布の時間変化が
計算される。なお、予報領域の狭い予報モデルでは、側面の境界条件も重要となる。一般に領域モデルでは領域の側面境界
での時間変化を計算するために、領域モデルよりも広い予報領域を持つ全球モデルの予報値が使用される。
数値予報の結果は、たとえば次のような予報に利用される。
- 天気予報:
全球モデルを境界条件として、領域モデルが稼働され、当日、明日、明後日を対象期間として風、天気、気温等の
予報が、3回/日、毎日発表される。
- 週間予報:
全球モデルが稼働され、7日間の天気、気温等の予報が毎日1回11時に発表される。予報の精度は、週の後半になると
60%程度まで低下するといわれている。予報精度の低下を補うため、アンサンブル予報と言う手法が使われている。
- 季節予報:
このうち1か月予報は、1か月アンサンブル予報モデルが稼働され、アンサンブル予報と言う手法により、
天気、気温、降水量、日照時間などの概括的な予報が、毎週金曜日に発表される。もっと長期の寒候期、温暖期の
概括的な予報は、従来通り統計的手法により行われる。
| 数値予報モデルのまとめ
|
| 予報モデル | 水平格子間隔 | 鉛直層数 | 予報領域(格子数) | 予報時間(初期時刻) | 目的
|
| 全球モデル | 約55km | 0.4hPaまで40層 | 640x320 | 90時間(00UTC),216時間(12UTC) | 週間天気予報、台風進路予報
|
| 領域モデル | 20km | 10hPaまで40層 | 325x257 | 51時間(00,12UTC) | 天気予報(短期予報)
|
| メソ数値予報モデル | 10km | 10hPaまで40層 | 361x289 | 18時間(00,06,12,18UTC) | 降水短時間予報、防災気象情報
|
| 台風モデル | 24km | 17.5hPaまで25層 | 271x271 | 84時間(00,06,12,18UTC) | 台風の進路と強さの詳細な予報
|
| 1か月アンサンブル予報モデル | 約110km | 0.4hPaまで40層 | 320x160 | 34日(12UTC,水・木曜日) | 1か月予報
|
数値予報プロダクト
数値予報モデルから出力される GPV(格子点値)と、GPVから作られる天気図。
天気図には用途に応じて色々な種類がある。
数値予報プロダクトの種類と物理量
観測された現況はその物理量が格子点に配置され、初期値とされた上で数値予報モデルが稼働し、
格子点における予想値=GPVが得られる。GPVは、風や気温や水蒸気量などの数値だが、この数値から地上天気図や
高層天気図などの数値予報プロダクトが作成され、配信される。
もともと大気は連続した物質で、物理量(風、温度、気圧、水蒸気量ほか)も連続的な分布をしているが、
格子点の値は、ある範囲の大気の状態を代表していると言える。このように連続している大気の状態を飛び飛びに作られた
格子点で表現する事を「離散化」という。
代表的な天気図(プロダクト)
- アジア地上天気図
- アジア850hPa、700hPa、500hPa、300hPa天気図
- 北半球500hPa高度・気温天気図
- 高層断面図
- レーダーエコー合成図
- 極東500hPa高度・渦度解析図
- 極東850hPa気温・風、700hPa鉛直P速度解析図
- 極東500hPa高度・渦度12・24・36・48時間予想図
- 極東850hPa気温・風、700hPa鉛直P速度12・24・36・48時間予想図
- 極東500hPa気温、700hPa湿数12・24・36・48時間予想図
- 日本850hPa風・相当温位12・24・36・48時間予想図
- 極東地上気圧、降水量、海上風12・24・36・48時間予想図
主な物理量
- 風向・風速(UV)
- 高度(Z)
- 温度(T)
- 気圧(P)
- 海面気圧(Ps)
- 風速(V)
- 地上風速(Vs)
- 鉛直P速度(ω)
- 相対渦度(ζ)
- 温位(θ)
- 相当温位(θe)
- 湿数(T-TD)
各種プロダクトに表現される物理量
ここで説明するのは、重要度の高い代表的なもの。詳細は実技で。
地上気圧P(地上天気図):
総監規模の現象を把握するのに欠かせない。天気図上に等圧線によって示された気圧分布は、
広範囲な気象状況を把握する時の必須の情報。地上気圧は、海面構成されてhPaで表される。
温度T・相当温位θe(地上天気図、850hPa高層天気図など):
相当温位は凝結を伴う湿潤断熱変化においても保存される。
- 温度T:
温度Tは、地上天気図、850hPaや500hPaなどの高層天気図に記載されている。850hPaや700hPaの等圧面で等高度線が
お互いに交わっているような場合には、暖気移流や寒気移流が存在し、擾乱の発達につながりやすい
状態になっている。たとえば、温帯低気圧が発達する場合は、等温位線を横切る風が強く、暖気移流や寒気移流が見られる。
- 相当温位θe
相当温位は、空気の性質(寒暖、乾湿など)を識別するのに有効。以下のような現象が見られる。
- 集中豪雨をもたらすような気象条件のもとでは、大気下層に相当温位の高い空気の流入が見られる。
- 等相当温位線が混み合っていて、それに交差して吹いている風が時間と共に強まっている場合、
相当温位の水平移流が強化されていると考えられる。
- 850hPa面の前線は等相当温位線の集中帯の暖気側(相当温位の高い側)の端に存在している。
- 大陸上の梅雨前線は、温度場で見るとあまり明瞭ではないが、相当温位の場でみると等相当温位線の集中帯として
明瞭に把握できる場合が多い。
相当温位線の集中帯の把握は、気象現象を理解するうえでの重要なポイントになる。
- 鉛直P速度ω(850hPa気温・風、700hPa鉛直P速度図):
鉛直P速度は、空気塊の気圧の鉛直方向の時間変化率を表すもので、1hあたりの気圧変化量で示される。
下降流は正(+)、上昇流は負(-)の値で示される。
また、数値予報プロダクトで表現される上昇流の大きさは、積雲や積乱雲の中で実際に観測される上昇流の
大きさに比べてオーダーが小さくなる。その理由は、格子点の上昇流の値は、格子点周辺の
平均値であって、個々の対流雲の上昇流ではないから。具体的には、数値予報モデルにおける計算上の
上昇流速度はせいぜい数10cm/s だが、実際の積雲対流の上昇速度は、桁違いの 数10m/s になっている。
- 渦度ζ(500hPa高度・渦度図):
絶対値の大きさと共に移流の把握が大切。流れの回転の強さを示す物理量。北半球では、高気圧性回転(時計回り)は負、
低気圧性回転(反時計回り)は正。
500hPa高層天気図に描かれている渦度は、大気の流れの強さを表す物理量で、相対渦度のこと。
大気の流れに大きな変化が無い偏西風帯において、500hPa面では総監規模擾乱に対しての水平発散が小さいので、渦度は
ほぼ保存されて流されるという特徴がある。このため、500hPa面で渦度を追跡する事によって、総監規模擾乱
の移動を検出できる事が多々ある。ただし、中小規模擾乱については500hPa面の渦度場の追跡は一般には有効ではない。
渦度の移流は、下層大気の状態に大きな影響を与える。たとえば、正の渦度移流のある所では、上昇流が生じ、
同時に地上では収束が起こって低気圧性の回転が生まれる。つまり、地上低気圧が発生・発達するわけ。
このように渦度は、その絶対値の大きさと共に「正の渦度移流」あるいは「負の渦度移流」を
把握する事が、天気図を読む上で大切。
- 温位:
天気図には描かれていないが、等温線と同じ形になる。大気の安定性や前線解析、相当温位の算出に使われる。
- 風向・風速:
収束・発散や渦度の表現、前線やジェット気流の解析、温度や水蒸気の移流量の見積もりなどに必要となる。
- 露点:
大気の水蒸気含有量を算出するのに用いる。
- 降水量:
予報対象時刻より前の時刻からの積算雨量を表示しているので、他の要素と重ね合わせて見る場合は注意が必要。
- 温域:
"気温 - 露点温度 < 3℃" の地域の事で、天気図上に点線で示される。上昇流・下降流と組み合わせ、降水の予想に用いる。
強風軸:
高層天気図上などで強風の中心を連ねた線のこと。偏西風帯のジェット気流の中心線は、典型的な強風軸。
実況値:
気象観測値あるいは観測にもとづく解析値。予報値(予測値、予想値)と対比的に使われる。
数値予報プロダクトの利用上の留意事項
観測データの誤差や数値予報モデルで表した大気構造の誤差、数値計算上の問題などにより、数値予報で得られた脚気には
「誤差」が含まれている。天気図などの数値予報プロダクトを利用する場合には、この誤差が含まれていることを
考慮して予想作業をする必要がある。
数値予報モデルの誤差:
誤差の原因は、地形や予報時間、観測データなどいろいろ。数値予報の誤差は予報時間と共に増大するため、
予報の有効性も予報時間と共に失われている。数値予報モデルでの格子点での予報値は、その格子点の緯度経度にあたる
地点に対する予想値でなく、その周り(1格子間隔程度)の空間での「代表地」を表している(客観解析と同じ)。
- 地形について:
数値予報モデルの地形は、格子間隔より小さいスケールのものを表現する事が出来ない。したがって、細かい部分で
実際の地形とは異なっている為、格子点によっては気温等の予想値が実際と異なる事が有る。また、数値予報モデルに組み込まれている地形では、
山の高さが実際より低かったり、小さな谷が表現されていないことなどにより、地形が主な原因となって生じる現象の表現が
十分でない場合がある。
- 予報時間について:
数値予報の誤差は、予報時間が長くなるほど増大する。このため、予報の有効性も予報時間と共に失われていくが、一般に
水平スケールの大きい擾乱程有効性が長く持続する。また、大気中の大小の乱れが複雑な相互作用を起こし、
予報時間と共に誤差が急激に増大する事が有る。
- 観測データその他:
- 数値予報モデルの分解能が高くても、観測データの不足などにより初期状態の表現が不十分の場合、
高い精度で現象が予想されているとは言えない。
- 水平スケールと鉛直スケールが同程度の現象(発達した対流雲など)に対して、数値予報モデルで
仮定している静力学平衡の近似を適用することは、大きな誤差要因となる。
数値予報モデルにおける分解能とは、格子点間の間隔の細かさのことで、数値予報の精度を大きく左右する。解像度ともいう。
出力される数値の大小の傾向:
モデルによって予想数値は大きくなったり小さくなったりする。数値予報では、上昇流の大きさは、
実際に観測される大きさよりも小さい事が多い。プロダクトとして出力される数値には、次のような傾向が有る。
- 数値予報モデルによる予想雨量は、格子点間隔の平均雨量なので、一般に、それに対応する擾乱に伴って観測される
地点の最大雨量に比べて小さくなる。
- 数値予報プロダクトで表現される上昇流の大きさは、積雲中で実際に観測される大きさと比べてオーダーは小さくなる。
- 数値予報の特性として、予報初期時刻から2~3時間は、上昇流や降水量がその後の値に比べて平均的に小さく予想される傾向が有る。
- 数値予報では、格子点に物理量が割り付けられる。そして、たとえば10min後の予想値が算出される。
次に、その算出された結果を初期値として、次の10min後の予想値が算出される。こうして、必要とする予報対象時刻に至るまで、
繰り返し計算される。しかし、前述の「10min」とした計算時間間隔と現象の速度、格子間隔の間には CFL条件というものがあり、
積分時間をある程度以上大きくする事はできない。
数値予報モデルにより予測可能な時間は現象のスケールに依存し、一般に大きいスケールの現象ほど予測可能な時間は長くなる。
CFL条件:
数値予報の計算において、現象の速度を V, 計算時間間隔を T, 格子間隔を X とするとき、
[ V * T < X ]
でなければならない。これは、現象の移動(変化量)が格子間隔より大きくなってはいけないことを示している。たとえば、
風速 V=50m/s, 格子間隔 X=20km のとき、
50m/s * T < 20000m
であることから、計算時間間隔は
T < 400s
つまり、積分時間を 6min40sec より短くする必要がある(CFL→Courant, Friedrich, Lewy(人名))。
天気予報の種類
予報の種類:
数値予報プロダクトなどをもとにして発表される「予報」には、様々な種類がある。これらは絶対的な分類ではなく、
一つの目安。この中で、気象予報士が最も必要とする予報は、天気予報、短期予報、短時間予報、降水短時間予報、
週間天気予報、季節予報(長期予報)、数値予報など。
| 予報の分類
|
| (1)気象業務法上の用語 | (2)用途を意識した用語 | (3)予報作成を意識した用語
|
●天気予報
・地方天気予報
・府県天気予報など
●週間天気予報
●季節予報
●波浪予報
●気象注意報
●気象警報
●洪水注意報
●洪水警報
●飛行場予報
●海上予報
●水防活動用気象注意報
●水防活動用洪水警報
●気象情報
| ●短期予報
●短時間予報
●降水短時間予報
●降水確率予報
●分布予報
●時系列予報
●局地予報
●中期・長期予報
●全球予報
●領域予報
●1か月アンサンブル予報
●台風予報
●台風に関する情報
●記録的短時間大雨情報
| ●アンサンブル予報
●持続予報
●気候値予報
●数値予報
●メソ数値予報
●カテゴリー予報
●量的予報
●確立予報
|
予報の利用と応用:
天気の予報は、防災をはじめ、農林水産・鉱工業・電力・交通・流通・情報など様々な産業分野で利用される。また、
個人の活動はもちろんのこと、企業・団体・学校などにおける諸活動が天気に左右される。つまり、
天気の予報自体が大きな社会的意味・意義をもつことになり、しかも様々な活動の拘束条件にもなっている。
最近は、企業などにおける投資リスクの事前評価を行うため、数値で出される予報、たとえば降水確率予報を
積極的に利用し、意思決定の支援を行う事もできるようになった。このため、コスト/ロス・モデルなどの意思決定支援
ツールなどの利用が考えられている。
コスト/ロス・モデル:
企業投資の危険度を見積もる手法の一つ。確率予報を利用してたとえば、損害の生じる気象現象の発生確率がAと
予報された場合、その対策に要する費用(コスト)と、対策を講じない事による損失額(ロス)の比がAより小さい時は、
対策を講じて、Aより大きい時は対策を講じないというもの。このようにコスト/ロス・モデルは、投資と損失の比較
によって、経営者の判断材料とする物。
天気への翻訳とガイダンス
数値予報で予測された数値群を「晴れ・曇り・雨」などの天気要素に置き換える事を翻訳という。
こうした天気要素のために作成される資料がガイダンスと呼ばれる。
天気への翻訳とは
「天気への翻訳」とは、数値予報モデルの稼働によって出力された格子点値(GPV)を、晴れ・曇り・雨などの「天気」に
変換する作業。「数字の集まり」である予想値を、どんな天気であるのか分かりやすく表現すること。
この作業をガイダンス(予報支援資料)を作成するという。
数値予報モデルの予測結果は、予想天気図などに表せるが、そのままでは天気予報にならない。
- 数値予報モデルは、気温や風速・風向などの物理量を出力するだけ。
- 各地の天気は、小さなスケールの現象や地形の影響を受ける事が多く、現在の数値予報モデルでは十分に扱えない。
- 天気予報の量的予報の対象である気温や風については、数値予報モデルで直接出力されるのは各格子点の周りの
代表地や平均値であるため、天気予報にそのまま利用するには十分でない。
数値予報の予測結果をもとに各地の天気を把握する作業が必要になり、それが「天気への翻訳」。ガイダンス(天気予報ガイダンス)は2回/日、
0900JST, 2100JSTを初期値とする数値予報が計算されたのち、初期値となる時刻から約5時間後に出力される。
| 観測データ | --そのまま使う--→ | ↓
|
| ↓ |
|
| 客観解析 | → | GPV
数値で出力されるので
どんな天気かわからない。
| → | 数値予報図 | → | 予報の発表等
・分布予報
・時系列予報など
数値ではなく、
晴れ・雨等の天気や
降水量などとして見やすく表示
|
| → | 翻訳
GPVを組み合わせ、
対応する天気を求める | → | ガイダンス
予報支援資料 | →
|
※観測データは、客観解析に用いられるほか、そのまま予報の発表などの資料として用いられる事もある。
翻訳の方式と天気予報ガイダンス
翻訳作業→GPVの数値データなどの情報から、目的とする情報(天気)を求める事。具体的には、「統計的関係式」で
計算する。大きく分けて、MOS方式とPPM方式がある。二つの違いは、統計的関係式における予測因子(関係式に入力する気象要素)
の取り扱い。
さらにMOS方式における統計的関係式の統計手法には、従来のMOS(線形重回帰式)に加えて、1996/03から、カルマンフィルターと
ニューラルネットワークという手法が採用されている。
| 方式 | 統計手法
|
| MOS方式 | 従来のMOS(線形重回帰式)
|
| カルマンフィルター(線形重回帰式)
|
| ニューラルネットワーク(非線形関数)
|
| PPM方式 | PPM(線形重回帰式)
|
カルマンフィルター、ニューラルネットワーク→統計手法、重回帰式=重相関回帰式
天気ガイダンスの作成手順:
現在、天気への翻訳作業は、天気予報ガイダンスを用いた方式が主流になっている。予報支援資料として作成される
天気予報ガイダンスには、それぞれの予報地域、予報期間について、降水量、降水確率、最高(最低)気温などの
値が示されており、天気予報にそのまま使えるような形で表現されている。実際には以下の手順。
- まず、数値予報の予測値や気象要素の観測値を予測因子として、予測の対象となる時刻の気象要素(気温・気圧・降水量など)の
観測値との間で統計的関係式を前もって作成しておく。
- この式に毎日の数値予報で得られる予測値を入力して、降水量、降水確率、最高(最低)気温、最大風速などの天気要素の予測値を求める。
天気予報ガイダンスの特徴は、数値予報では十分表現できない地形的な効果を関係式の中に取り込むことができ、また
天気の予報(カテゴリー予報)だけでなく、気温や降水量などの予報(量的予報)にも十分利用できる事。また、
数値予報では直接予測できない降水確率などを計算できる利点もある。
線形重回帰式:
たとえば、従来のMOSやカルマンフィルタでは、統計的関係式を次のような線形の関係式で仮定する。
[降水量 = a x 気温 + b x 湿度 + c x 上昇流]
この式のそれぞれの予測因子(気温、湿度、上昇流)に観測値またはGPVを代入し、最もそれらしい推定値を得る。
予測因子の係数は、目的とする物(この場合は降水量)に対する物理量の寄与の程度を重みづけするため。
「最もそれらしい」とは、[予測値 - 実況値]が最小になる様に計数 a, b, c を算出・決定する事を意味する。
カルマンフィルタでは予報のたびに、これらの係数を更新していく。上記のような式を「線形重回帰式」という。「重」とは、
目的とする値に寄与する予測因子が複数個あるという意味。
MOS方式とPPM方式の違い:
MOS方式は、過去の数値予報の予測値と観測値から統計的関係式を作り、数値予報の予測値から天気要素を予測する方式。
- MOS方式:
過去の数年分の数値予報モデルの予測結果(予測値)と、対応する時刻の観測値との間で統計的関係式を作成し、
そこに日々の数値予報モデルの予測値を入力して、天気要素の予測値を求める方式。
一般に PPM方式よりも予測精度は良いが、数値予報モデルが変更になった場合には、そのつど新しい統計的
関係式を作成する必要があり、その関係式の係数が確定するのに数年の数値予報結果を蓄積しなければならない。
しかし、MOS方式では、数値予報モデルが持っている系統的誤差(バイアス)を取り除く事ができる。
- PPM方式:
MOS方式における数値予報モデルの予測値の代わりに、各気象要素の観測値(または数値予報の初期値)と、
対応する時刻の観測値との間の統計的関係式を作成し、そこに日々の数値予報モデルの予測値を入力して
天気要素の予測値を求めるもの。MOS方式と違って数値予報モデルが変更されても統計的関係式を作り直す必要が無い。
しかし、数値予報モデルに系統的誤差があれば、それから得られる予測値にも誤差が入りこんでしまう。
PPM方式は、天気予報には使われていないが、季節予報などの長期予報で使われている。なお、天気予報ガイダンス作成における
統計的手法は現在カルマンフィルタやニューラルネットワークが主流。
系統的誤差(バイアス):
数値予報の予測結果と実況値の間に一定の誤差傾向が有る事をいう。従来のMOS、カルマンフィルタ、ニューラルネットワークの翻訳過程には
バイアス修正の機能が組み込まれているので、予測値が補正されている。
| MOS方式の流れ | PPM方式の流れ
|
過去の
数値予報
の予測値 | +↓+ | 対応時刻
の観測値
| 観測値また
は数値予報
の初期値 | +↓+ | 対応時刻
の観測値
|
| 統計的関係式 | 統計的関係式
|
数値予報
の予測値→ | ↓ | | 数値予報
の予測値→ | ↓ |
|
| ガイダンス | ガイダンス
|
カルマンフィルター(KLM):
従来のMOSの欠点をカバーするために開発されたガイダンス作成手法。数値予報モデルの変更による影響を受けにくい。
線形重回帰式を用いて統計的関係式を作成するのは、従来のMOSと同じ。しかし、従来のMOSの場合は、線形重回帰式の
係数を過去数年分のデータを用いて求めるのに対し、カルマンフィルターの場合はガイダンス作成の都度
係数を更新し、逐次学習して統計的関係式を求めていく。つまり、予測結果と実況との誤差から、より適した係数を割り出し、
次回の予測値の計算に用いるわけ。このため、カルマンフィルターは、数値予報モデルの変更にも
数週間から1か月程度で対応できる。
また、カルマンフィルターの係数は、逐次学習しながら更新されるので、「場」の大きな変化にすぐ対応できない傾向が有り、
係数がその変化に対応するまでに数日から数週間の時間が必要とされている。しかし、実況に対する追随性は速く、
気温等のGPVを補正して出力する事も出来る。
現在、カルマンフィルターで作成されている天気ガイダンスには、次のようなものがある。
| カルマンフィルターによるガイダンス(領域モデルの場合)
|
| ガイダンス | 予想時間 | 予想単位 | 予想地点
|
| 6h降水確率 | 6hごと48h先まで | 1%単位 | 格子点ごと
|
| 3h降水確率 | 3hごと51h先まで | 1mm単位
|
| 最高気温 | 今日、明日の日中(9~18時)の最高気温 | 0.1℃単位 | アメダス観測所
(842地点)
|
| 最低気温 | 今日、明日の朝(0~9時)の最低気温 | 0.1℃単位
|
| 3h気温 | 3hごと51h先まで | 0.1℃単位
|
| 3h風向風速 | 3hごと51h先まで | 風向方位、風速0.1m/s
|
現在のガイダンス(カルマンフィルタ、ニューラルネットワーク)では、数値予報が予想する擾乱の位相(位置)のずれを
統計的関係式に組み入れることはできないので、そのずれを補正する事はできない。
誤差について:
翻訳のベースとなる数値予報の結果は、100%完全とはいえない。したがって、その次工程の翻訳作業結果のガイダンスに
誤差は避けられない。
- 前線通過による気団の交替
- 低気圧による急激な暖気流入
- 数値予報で表現されない局地的な現象の発現
などの場合は、ガイダンスを使っても予想がずれることがある。誤差を少なくするため、数値予報モデルの改良と共に
予報精度の評価作業が行われ、ガイダンスの改善も行われる。
ニューラルネットワーク(NRN):
ニューラルネットワークの手法は、数値予報モデルやそれから構成される各種の予測因子と実況との間の対応関係を求め、
これを毎回繰り返す事によって、逐次学習しながら対応関係を見つけ出していくもの。過去数年分の気象現象を学習させた
結果得られる人工知能(ニューロン)の係数は、ガイダンス作成のたびに予報誤差が最小になる様に最適化され、
次回のガイダンス作成時に用いられる。
ニューラルネットワークは、非線形の統計的関係式を使う利点を生かした晴雨等の天気の予想を得意としており、
カルマンフィルターと同じく数値予報モデルの変更にも柔軟に対応できるという特徴がある。また、
急激な天候変化が発現しても大きな誤差が出ないようになっている。
現在、ニューラルネットワークで作成されている天気予報ガイダンスには、次のようなものがある。
| ニューラルネットワークによるガイダンス(領域モデルの場合)
|
| ガイダンス | 予想時間 | 予想単位 | 予想地点
|
| 3h天気 | 3hごと51hまで | 晴れ、曇り、雨、雨か雪、雪の5カテゴリ | 格子点ごと
|
| 最小湿度 | 今日、明日の1日の最小湿度(0~24時) | 1%単位 | 気象官署
(71地点)
|
| 3h大雨確率 | 3hごと51h先まで | 1%単位 | 二次細分区域
(192地域)
|
| 3h発雷確率 | 3hごと51h先まで | 1%単位
|
3h大雨確率とは、予報対象地域内の少なくとも1地点で3hに、暖候期は30mm、寒候期は20mm以上の大雨が
降る確率のこと。また3h発雷確率とは、予報対象地域内の少なくとも1地点で2hに、雷が発生する確率のことを
「地域確率」という。
明後日天気予報ガイダンス:
気象庁では2001/03から、従来の明日までの天気予報ガイダンスとは別に、線球モデルの格子点をもとにして
カルマンフィルターまたはニューラルネットワークで明後日天気予報ガイダンス(基本的には6h単位で51h~75hまで)を
作成している。その概要は以下の通り。
- カルマンフィルター
- 平均降水量、降水確率(20km格子・6hごと)
- 風向風速、気温(アメダス地点・6hごと)
- 最高・最低気温(アメダス地点)
- ニューラルネットワーク
- 天気(20km格子・6hごと)、降雪量(アメダス地点・6hごと)
- 最小湿度(気象官署)
なお、予想単位、予想地点は従来の天気予報ガイダンスと同じ。
確率予報
天気予報には、天気を晴れ・曇り・雨などいくつかのカテゴリ(種別)に分けて表現するカテゴリ予報のほかに、
ある現象が発生する確からしさを確率値で表現する予報が有る。特に、降水確率予報が重要。
降水確率は、数値予報プロダクトとして出されていない。数値予報結果の予想値がGPVとして出力され、その
数値がカルマンフィルタによって翻訳され、確率表現されている。このため降水確率予報の問題は、翻訳方式と
結びつけて出題されている。特に、統計的関係式の作成、確率の意味、降水量の基準値等が問われる事が多い。
降水確率予報のガイダンスでは、1%単位で予想(計算)しているが、発表は10%きざみになっていることに注意。
降水確率予報:
降水確率は、あらかじめ求めておいた数値予報の予想値と実際の観測値との統計的関係式を使って、
数値予報の予想値から計算される。現在、気象庁が発表している降水についての確率予報は、カルマンフィルターにより
「6時間降水確率予報」として作成されている。
降水確率予報とは、予報対象時間(短期予報では6h)に1mm以上の雨または雪の降る確率を0%から100%まで10%きざみで発表するもので、
予報対象地域内での地点確率の平均値を表している。たとえば、ある予報区に対する「降水確率が80%」という予報は、
その予報区内のどの地点でも予報時間内に1mm以上の雨または雪の降る確率が80%であることを示している。
ここで注意すべき点は、降水確率予報は、降水量の多少や降水時間の長短を予報するものではなく、
また降水確率の数値が大きくても雨や雪が強く降るという意味でもないということ。それに、予報対象地域の
面積が大きくなれば、降水確率も大きくなるという事は無く、地域の広さには無関係。
なお、週間天気予報で発表される降水確率予報は、対象時間とする24時間に1mm以上の雨または雪の降る確率を示している。
地点確率と地域確率:
地点確率とは、予報対象地域内のどの地点でも現象が発生する確率の事で、たとえば地点確率30%とは、予報対象地域内のどの
地点でも同じ「確率30%」という意味。
また、地域内に複数の地点が有る場合、ガイダンスは「平均の地点確率」を示す。なお、地点確率は、
地域確率(予報対象地域のどこかで現象が発生する確率の事で、大雨確率や発雷確率で使われている)に比べて
予報精度が良いといわれている。
短時間予報
1~6時間くらい先までの予報。気象レーダーやアメダスの観測データとメソ数値予報の結果をもとにして発表される「降水短時間予報」が
中心。
短時間予報とは
一般に短時間予報とは、1~6h程度先までの予想を対象にしているが、半日(12h)くらい先まで含める事が有る。短時間予報の中でも、
特に3h程度先までのものを「ナウキャスト(now cast)」という。
数値予報は、明後日くらいまでの総観規模の現象を最も精度よく予想できるが、総観規模であっても予測時間が長くなれば
予想は困難。また、メソβ・γのように総観規模よりも小さなスケールの場合は、現象の時間・空間スケールが小さすぎたり、
プリミティブ方程式に使われている静力学平衡の式があてはまらない場合が多い等の理由により、これまた予想が困難。
しかし、メソβ・γスケールの現象の予報については、総観規模の予想で大局的な「場」の可能性が予想されているので、
それにリアルタイムデータとして気象レーダーやアメダス、気象衛星などの最新の観測データを加味し、数値予報の予測結果を
一部修正したり、観測結果をそのまま時間的に外挿したりして、数時間先までの気象現象の予想を行う。これが短時間予報。
| 短時間予報の位置づけ
|
| 短時間予報 | 天気予報
短期予報
(本日、明日、明後日)
| 週間天気予報 | 季節予報
1か月予報等
|
ナウキャスト
(3h先まで) | 降水短時間予報
(6h先まで)
|
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑
|
数値予報(領域モデル)で
カバーする事は困難
●時間・空間スケールは小さいが
現象は激しい事が多い
| 数値予報でカバーできる
●総観規模現象を
最も精度よく予想できる
| 数値予報でほぼカバーできる | 1か月先までの予報は
数値予報でカバーしているが、
精度は先にいくほど低下する
|
短時間予報の基本となるものは、レーダーエコー合成図、この図をアメダスデータで補正して作成したレーダー・アメダス解析雨量図、
およびメソ数値予報モデル。
現在、レーダー・アメダス解析雨量図とメソ数値予報の結果をもとにして、6h先までの降水短時間予想図を出力し、
集中豪雨などに対応する迅速かつ的確な防災気象情報の作成に利用されている。降水短時間予報における
予報作業の流れや、各図の特徴などについて学習する。
降水短時間予報
降水短時間予報とは:
日本全国を2.5km四方に区切った地域を対象として、レーダー・アメダス解析雨量の実況補外(外挿)による予測とメソ数値予報モデルによる
予測とを、それぞれの精度に応じた重みを決めて結合し、1時間ごとの降水量を6時間先まで予報するもの。以下の手順。
| メソ数値予報 | 実況補外予測
|
| メソ数値予報モデルの初期値を決める。
| まず、予報の初期時刻における気象レーダーの観測値とアメダスの雨量データを使用して、前1hの雨量分布(降水域)を作成する。
|
| ↓ | ↓
|
| 6h先までの数値予報結果を決める。
| 次に、実況降水域の移動速度を決める。移動速度の計算にはパターン・マッチング法が用いられる。
その際、数値予報による風の予想値を補足的に用いる。
|
| ↓ | ↓
|
| 計算した移動速度によって初期時刻の降水域を時間補外するとともに、風や湿度などの数値予報結果を使って、
6h先までの2.5km四方の1hごとの雨量を予測する。
|
| ↓
|
| 実況補外予測とメソ数値予報の重みを決めて結合する。
|
| ↓
|
| 降水短時間予報
|
この手順において用いられる初期時刻の雨量分布は、レーダー・アメダス解析雨量。これをもとに作成したレーダー・アメダス解析雨量図を
初期値とし、実況補外予測とメソ数値予報とを結合し、降水域の今後1hから6h先の移動・発達を予測するのが、降水短時間予報。
気象庁では2001/03から、メソ数値予報モデルの予測結果を導入して、従来の降水短時間予報における予報期間後半の
精度低下を補い、予測時間を3hから6hに延長している。
パターン・マッチング:
現在と1h前の2つのレーダー・アメダス解析雨量図から、移動速度計算の対象領域(全国を100km四方の領域に分割している)
ごとに降水域のパターン(記号による模様)を比較して、最もパターンが一致した時の位置のずれをその時間までの
移動距離とみなす方法の事。その時間と移動距離から移動速度を計算する。
降水短時間予報におけるデータ処理の流れ:
降水短時間予報の基本的なデータ処理の流れには、各地の気象レーダーによる観測から始り
「レーダーエコー合成図→レーダー・アメダス解析雨量図」という実況補外と、メソ数値予報モデルの稼働と言う2つの流れが有る。
この基本的な流れにおいて、「降水量・降水域の予想、降水の発達・衰弱の予想」作業、さらに「観測」「数値予報」「補正」
などの作業を加えて、運用スケジュールの中でまとめて図示すると次のようになる。
| メソ数値予報モデル稼働・気象レーダー観測から降水短時間予報までの流れ
|
| メソ数値予報モデル | 各地の気象レーダー | (1)降水強度の算出(気象レーダー観測から)
●エコー強度の時間変動の特性の違いを利用して
レーダーエコーに含まれる地形エコーを除去。
●エコー強度データ、1h積算降水強度データ
などを作成する。
●複数のレーダーデータを合成し、
単独のレーダーでは山岳などの影響で
観測が困難な領域を他のレーダーでカバーする。
|
| ↓4回/日 | ↓(1)10minごと
|
| レーダーエコー合成図
|
| アメダス雨量データ→↓
|
| 数値予報結果 | ↓(2)1hごと(毎正時) | (2)解析雨量値の算出(アメダス観測で降水強度を更正)
●レーダーエコーから推定される1h積算降水強度データを、
アメダスの1h雨量データと比較して補正し、
レーダー・アメダス解析雨量値を算出する。
その結果を雨量初期値とする。
(3)降水域の予想、予報精度の向上
●パターンマッチングを利用したエコーの動きや
数値予報の風の予想値を使って、
降水域の移動を時間外挿し、
6h先までの2.5km四方の雨量を予測する。
●数値予報による気温や風の予想値を利用して
地形による降水の発達・衰弱の
効果を取り込んで(計算して)、
予報の精度を高めている。
|
| ↓6h先まで | レーダー・アメダス解析雨量図
|
| 数値予報の予想値→↓
|
| 地形データ→↓
|
| 実況補外予測
|
| ↓
|
| 重みを決めて結合
|
| ↓
|
| 降水短時間予報
|
なお、これらの降水短時間予報の作業において、雨雪の判断はされない。また、数値予報の降水予想値は初期値とはされない。
地形の影響によって気流が上昇する時は降水が強化され、反対に気流が下降するときは降水は衰弱する。
降水短時間予報では、こうした地形の効果を取り込んで予報精度を高めている。降水短時間予報では、
初期時刻以後に新たに発生する降水系(エコーシステム)による降水量は予測する事はできない。
レーダー・アメダス解析雨量について:
レーダー・アメダス解析雨量(以下、解析雨量)とは、約2.5km四方の格子ごとに示された雨量の事で、解析にあたっては、
気象レーダーのデータを1hに6回観測し、それぞれのエコー強度を降水強度に換算し、それを1hにわたり積算した値と、
アメダスの1hごとの雨量観測値とを比較して、解析雨量値になるよう補正して算出される。
陸上にある格子では、近くのアメダス雨量計(平均して約17km四方に1ヶ所の割合で設置)を含む
いくつかの格子について実測雨量と気象レーダーによる観測データの関係を調べ、その関係を利用して解析雨量を求めている。
このため、実測雨量と解析雨量とが一致しないことがある。また、アメダス観測点のない海上では、陸上で得られた
レーダーデータの降水強度とアメダスの実測雨量との関係を当てはめて解析雨量を算出している。
水平スケールが大きい降水では、レーダーデータをアメダス雨量計の実測雨量で補正できるので、解析雨量の精度は高くなる。
また、地上のアメダス雨量計による実測値は、その雨量計を含む格子よりも隣の格子の解析雨量と対応がよいことがある。
これは、気象レーダーで観測した上空の降水粒子が落下途中の風によって隣の格子で地上に達するのが原因の一つと
考えられる
アメダス(地域気象観測システム)は全国約840ヶ所で、降水量、風向・風速、気温、日照時間の4要素を21km間隔の
観測網で観測する。このうち、降水量については上記の観測点を含めて全国約1300ヶ所、17km間隔の観測網で観測する。
また、積雪の深さの観測点は全国で約200ヶ所ある。
予報の誤差について:
気象レーダーを使用すると、集中豪雨時等に見られる規模の小さな降水域の観測もできるが、
レーダーで観測される降水強度にはレーダー電波の減衰、観測対象の雨雲の性質の違いなどに起因する誤差が含まれる。
これらの誤差は、アメダスの雨量計の観測値で補正される。
また、レーダーエコーに含まれる地形エコーは、エコー強度の時間変動の特性の違いを利用して除去されるが、
レーダー観測所における処理で消え残った地形エコーやシークラッター(海面の波やしぶきからのエコー)、
エンゼルエコー(大気の屈折率に異常な違いが有る時に現れるエコー)などは、解析の際に除去されないため、
解析雨量として出力されて誤差要因になる。
気象レーダー観測では、レーダー観測所から遠くなるほど、ビームが広がる事に起因する誤差もある。
また、レーダー・アメダス解析雨量は、気象レーダーの観測値をアメダスの雨量計の観測値で補正して算出している為、
アメダスデータの無い山岳部や海上での解析雨量値は誤差が大きい可能性がある。
レーダーエコー合成図とレーダー・アメダス解析雨量図
レーダーエコー合成図:
レーダーエコー合成図は、気象庁の気象レーダー(全国に20ヶ所)の探知結果を合成し、1枚の図にしたもの。
この合成図により、1つの気象レーダーの範囲外の状況もわかるので、全体的な降水域の規模の把握、
降水強度や移動方向・速度の推定などができる。さらにレーダーエコー合成図にアメダスデータを加えた
レーダー・アメダス解析雨量図を用いると、より正確な降水状況の予想ができる。
また、複数のレーダーデータを合成するため、単独のレーダーでは山岳などの影響で観測が困難な領域も
他のレーダーでカバーする事ができる。さらに、雨量計の無い海上などでも、降水強度とアメダス雨量データの
関係から雨量の推定ができる。特に、近海の雨量を推定できる事は、海上からの降水域の予想と言う観点からも
大事なこと。
レーダーエコー合成図では、降水強度を4種類の記号で、エコー頂高度(エコーを生じさせる降水が存在する上限の高度)
を8段階の数字(単位は1000フィート)で表す。
レーダー・アメダス解析雨量図:
レーダー・アメダス解析雨量図は、レーダーエコー合成図とアメダスの雨量データから作成された予想図で、
1時間積算降水量が2.5km四方ごとに記号で表示されている。これをもとに、数値予報の予測値や地形データなどを加味して、
降水短時間予想図が作成される。
また、レーダー・アメダス解析雨量図により、アメダスの間隔の17kmより小さなスケールの降水域も把握できるようになり、
集中豪雨は精度よく把握できるようになっている。
降水短時間予想図の記号は、レーダー・アメダス解析雨量図のものと同じ。
予報精度の評価
制度評価の必要性
予報精度の評価を客観的な方法で行う事や、予報の有効性や技術の改善度を量的に測れるようにすることが必要。
現在気象庁では、予報技術および予報精度の向上を図る上での基礎資料とするために、天気予報、
週間天気予報、注意報・警報、天気予報ガイダンスを対象として定常的に予報精度の検証・評価を行っている。
一般的に予報の有効性の評価は、発表された気象予報と、特別な予測技術を必要としない
持続予報(現在の状態がそのまま持続するものと仮定して行う予報)や
気候値予報(雨や曇りの気候的な現れ方に基づいて行う予報)と比較して、どの程度改善されたかによって行う。
一方、技術の評価は、予報作成にあたって各種予測資料の利用法がいかに改善されたかによって行う。
予報精度の検証・評価方法
気象庁が発表する予報には、カテゴリー予報、量的予報、確率予報があり、予報精度の検証方法及び評価方法がそれぞれ
定められている。
- カテゴリー予報: 「曇り時々雨」「気温が高い」などの状態や性質を言葉で表現する。
- 量的予報: 降水量何mmや最高気温何℃という数値で表す。
- 確率予報: 降水確率 ??%で表す。
- 検証: 予報精度を数値で算出すること。
- 評価: 有効性の判定や精度改善のための問題提起のこと。
検証作業、つまり評価のための数値を算出する作業、あるいは検証の各方法の特徴や用途などに関して、記述分の正誤を問う
などの問題が多く出題されている。特に検証作業には、用途に応じて各種の「数式(定義式)」が出てくる。これらの式は
丸暗記でなく、用途・意味をよく理解して覚えるようにすること。
カテゴリー予報の精度評価:
スレットスコアは、「予報なし・実況なし」を除いた場合の適中率。スレットスコアは、降水の有無の予報のように、
2つの階級値をとる予報の検証に用いられる。
天気予報における降水の有無、各種警報等の現象の発生の有無、週間天気予報における気温(高い・平年並み・低い)
などを予想したものをカテゴリー予報と言う。
カテゴリー予報の精度評価は、予報と実況のそれぞれの「現象あり」「現象無し」の回数から、
下表のような 2x2 分割表を作成し、その表中の数値から適中率、見逃し率、空振り率、スレットスコアなどの
指数を算出して総合的に行う。
たとえば、降水有無の予報の場合、天気の予報文の中に、雨または雪という表現が有れば「降水あり」の
予報とし、その表現が無い場合と「ところにより一時雨」という場合は「降水無し」の予報として、
2つのカテゴリー予報に変換し、実況との比較を行う。
| 降水有無予報の2x2分割表
|
| | 予報
|
| 降水あり | 降水無し | 計
|
| 実況 | 降水あり | A | B | N1
|
| 降水無し | C | D | N2
|
| 計 | M1 | M2 | N
|
| ●適中率= | (A + D)/N | :「予報あり・実況あり」と「予報無し・実況無し」の合計の全体に占める割合。
|
| ●見逃し率= | B/N | :「予報無し・実況あり」の全体に占める割合。
|
| ●空振り率= | C/N | :「予報あり・実況無し」の船体に占める割合。
|
| ●スレットスコア= | A/(A+B+C) or A/(N-D) | :「予報無し・実況無し」を除外した適中率。
|
スレットスコアは、「予報無し・実況無し」の場合に適中しても意味の無い現象、たとえば冬の太平洋側の
降水や雷のように発生頻度が低い現象の精度評価に用いられている。こうした現象は、「発生しない」と
予報した場合は適中率が非常に高くなってしまうため、技術的にも利用価値の点からもあまり意味が無い。
スレットスコアは、数値が大きいほど精度が良い事を意味する。ただし、予測の系統的な偏りはわからないので、
空振りや見逃しの程度を見る事も大切。実況に対する予想の系統的な偏りをみるためには、平均誤差(ME)を使う。
(1)降水有無予報の精度評価:
天気予報における降水有無の予報に対する精度評価は前述のように予報対実況の 2x2 分割表を使い、それぞれの
定義式に当てはめて行う。
[例題1]次の降水の有無に関する予報対実況の事例について、
- 2x2分割表を完成せよ。
- 適中率を算出せよ。
- 空振り率を算出せよ。
- スレットスコアを算出せよ。
予想全数=30, 実況降水あり=9, 予想降水あり=6, 見逃し率=10%
9+N2=30,6+M2=30,→N2=21,M2=24,B/30=0.1→B=3→A=6,C=0,D=21
- 適中率=(A+D)/(A+B+C+D)=(6+21)/30=0.9=90%
- 空振り率=C/N=0/30=0=0%
- スレットスコア=A/(A+B+C)=6/(6+3+0)=6/9=2/3=66.7%
(2)注意報・警報の精度評価:
降水の有無のように毎日必ず発表される予報と、大雨注意報や大雨警報のように、
ある現象が起こると予想される場合のみ発表する予報とでは、評価の方法が異なる。
注意報や警報に対する精度評価は、通常、実況値がそれぞれの発表基準値に達したか達しないかで区別した、
予報対実況の 2x2 分割表で行われる。ただし、分割表や精度評価のための指数の定義式が、
前述の降水有無予報の場合と異なるので注意が必要。
下表の「現象」とは、注意報・警報の基準値に達した大雨や強風の事を指す。
| 注意報・警報の2x2分割表
|
| | 注意報・警報
|
| 現象あり | 現象無し | 計
|
| 実況 | 現象あり | A | B | N1
|
| 現象無し | C | - | -
|
| 計 | M1 | - | -
|
| ●適中率= | A/M1
|
| ●見逃し率= | B/N1
|
| ●空振り率= | C/M1
|
| ●捕捉率= | 1-見逃し率=1-(B/N1)=A/N1
|
- A:捕捉回数、適中回数
- B:見逃し回数
- C:空振り回数
- 適中:注意報・警報の発表機関内に予想した現象が発生した場合。
- 見逃し:現象発生時に注意報・警報が発表されていなかった場合。
- 空振り:注意報・警報の発表期間内に予想した現象が発生しなかった場合。
- 捕捉:現象発生時に注意報・警報が発表されていた場合。
[例題2]次の大雨注意報・警報に関する事例について、適中率、空振り率、捕捉率を算出せよ。
現象発現回数=60回、予想を発表したが現象が発現しなかった回数=18回、見逃し率=15%
解:N1=60, C=18, B/N1=0.15→B=9,A=51,M1=69→
適中率=A/M1=51/69=17/23=73.91%,空振り率=C/M1=18/69=6/23=26.09,捕捉率=A/N1=51/60=17/20=85%
量的予報の精度評価:
誤差を最小限に。気温予報等の量的予報の精度の指標に用いられる2乗平均平方根誤差の値が小さいほど精度が良い。
量的予報の評価の対象は、最高・最低気温、最小湿度、最大風速、3時間降水量等の予報。
これらの予報では、予報値と実況値の差が予報誤差となり、それをできるだけ小さくする事が「良い予報」となる。
予報誤差を月単位あるいは年単位にまとめて統計する事によって、予報精度の有効性の評価に利用される。
気温等の数値による予報の精度評価:
気温の予報のように予報値と実況値の差があまりなく、ほぼ連続的に分布する量的予報の精度を表す指標として用いられるのが、
平均誤差と2乗平均平方根誤差である。それぞれの誤差は、予報値と実況値を定義式に代入して求める。
(1)平均誤差(ME,バイアス):
予報値から実況値を差し引いた予報誤差の合計を、予報回数で割ったものが平均誤差。これは、予報値の系統的な偏り(バイアス)の
大きさを表すもの。計算された誤差の絶対値は、正の誤差と負の誤差が打ち消し合う場合は小さくなるので、数値が
小さいほど予報精度が良いとは言えない。平均誤差の定義式は
[ 平均誤差 = Σ(Fi - Ai) / N ]...Fi:予報値, Ai:実況値, N:予報回数。
気温の予報の場合の計算例:
| | 1日 | 2日 | 3日
|
| 予報値(Fi) | 20℃ | 22℃ | 19℃
|
| 実況値(Ai) | 19℃ | 20℃ | 20℃
|
(20-19) + (22-20) + (19 - 20) / 3 = (1 + 2 + (-1))/3 = 0.66...
(2)2乗平均平方根誤差(RMSE:Root Men Square Error):
予報値から実況値を差し引いた予報誤差を2乗し、その値の合計を予報回数で割ったものの平方根が、2乗平均平方根誤差。
これは予報の標準的な誤差幅を表すもので、数値が小さいほど予報精度が良くなる。平均誤差における正負の誤差の
相殺性を排除したもの。定義式は
[ 2乗平均平方根誤差 = √(Σ(Fi - Ai)2/N) ]
平均誤差の場合と同様に計算してみる。
√((20-19)2 + (22-20)2 + (19-20)2/3) = √((1 + 4 + 1)/3) = √2 = 1.414
例題:
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日
|
| 予報値 | 15 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 18
|
| 実況値 | 14 | 15 | 17 | 18 | 12 | 15 | 16
|
(1)2 + (3)2 + (-2)2 + (-1)2 + (1)2 + (1)2 + (2)2
1+9+4+1+1+1+4=21,21/7=3,2乗平均平方根誤差=√3=1.732
平均誤差=(1+3-2-1+1+1+2)/7=5/7=0.714...
確率予報の精度評価:
ブライアスコアは、予報が完全に適中したら0,すべて外れたら1。小さいほど精度は良い。
降水の有無を確率で表す「降水確率予報」の精度評価に用いられるのがブライアスコア。
降水の実況と降水確率値との差の2乗の和を平均して求める。
[ ブライアスコア=Σ(Fi-Ai)2/N ]...Fi:降水確率(小数)、Ai:降水の実況(あり=1,無し=0)、N:予報回数
ブライアスコアは 0~1 の値を平均しているので、0~1 になる。0に近いほど予報精度がよいことになる。
例として計算プロセスを示す。
| | 予報 | 実況
|
| 1日 | 50% | 1
|
| 2日 | 30% | 0
|
| 3日 | 100% | 1
|
((0.5 -1)2 + (0.3 -0)2 + (1 -1)2) /3 = (0.5*0.5 + 0.3*0.3 +0*0)/3 =0.113333.
例題:
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日
|
| 予報[%] | 0 | 30 | 60 | 100 | 30 | 30 | 50 | 50
|
| 実況 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
0*0 + 0.3*0.3 + 0.4*0.4 + 0*0 + 0.7*0.7 + 0.3*0.3 + 0.5*0.5 + 0.5*0.5 = 0.09 + 0.16 + 0.49 + 0.09 + 0.25 + 0.25 = 1.33, 1.33/8=0.166.
総観気象(短期予報・中期予報)
総観規模の気象は最も精度よく予想される。傾圧不安定波、温帯低気圧、寒冷低気圧(寒冷渦)の出題頻度が高い。
総観気象の特徴
総観規模の天気の予想は、プリミティブ方程式を用いて、現象の時間スケールや空間スケールが現在の格子点間隔で
十分表現できるので、「数値予報モデル」で最も精度よく予想できる。
たとえば、水平スケールが2000~5000kmで、寿命が半日~10日程度の現象(温帯高気圧、温帯低気圧などがその
代表例)。
また、メソスケールの現象については、メソα程度(200~2000km)の現象は数値予報で十分に表現できるが、
メソβ・γの現象は、時間・空間スケールが小さいので、現在の格子間隔では表現できない、プリミティブ方程式で使われている
静力学平衡の式が当てはまらないことが多いなどの理由から、数値予報での予想が困難。
このように、数値予報で取り扱えるスケールの代表が総観規模の現象。その中でも重要な傾圧不安定波、温帯低気圧を
中心に見ていく。
総観気象の現象
傾圧不安定波:
南北の温度傾度が増大して、風の鉛直シヤーがある限度を超えると、波長数千kmの傾圧不安定波が発生する。
傾圧不安定性によって発生・発達する大気の波動現象。中緯度偏西風帯の温帯低気圧および高気圧は、その代表例。
(1)傾圧不安定波の発生・発達
地球大気は、太陽放射エネルギを受けて、その緯度方向の不均一な加熱により、両半球とも低緯度側で高温、高緯度側で低温
となる。これが南北方向の温度傾度。
また、地球大気は、静力学平衡および地衡風平衡を前提として、この南北の温度傾度や地球の自転によって、
大気の水平方向と鉛直方向の物理量が相互に関係づけられている。この関係は「温度風の関係」として
知られている。
この温度風の関係から上層ほど西風(偏西風)が強くなっているが、南北の温度傾度が増大して風の鉛直シヤー(あるいは風速)が
ある限界を超えると大気は不安定となり、波長が数千kmの傾圧不安定波が発生・発達する。そして傾圧不安定波は、
南北の温度傾度を弱めようとして、暖気を北へ、寒気を南へ輸送(南北の温度交換)する。このように、傾圧不安定性とは、
安定へ向かうための自然が持っている調整機能といえる。
傾圧不安定波を高層天気図で見るには、500hPa北半球天気図が適している。この天気図から特定高度、たとえば5580mと
5400mに着目してみると、流れの蛇行状況が浮き彫りにされる。大気の蛇行状況と共に、気圧の谷(トラフ)や
気圧の尾根(リッジ)の状況も一目でわかる。天気の予想は、こうした大局的な観点から状況把握をする事が重要。
偏西風帯の中で、中緯度対流圏の上層で特に強く吹く気流の事をジェット気流と言い、温度風の関係が生じている。
日本付近のジェット気流には、対流圏上部を拭く寒帯前線ジェット気流と、圏界面付近を吹く亜熱帯ジェット気流があり、
前者は後者に比べて季節により位置や強さが大きく変動する。また、寒帯前線ジェット気流の周辺では、
鉛直方向にも水平方向にも大きな風のシヤーが存在しており、しばしば乱気流が発生する。
(2)傾圧不安定波と温帯低気圧の関係
中緯度偏西風帯において発生・発達する温帯低気圧は、傾圧不安定波の一部(残りの一部は移動性高気圧)として
理解される。つまり、温帯低気圧の発生・発達はこの傾圧不安定波と深く関わっていて、北半球では温帯低気圧の
東側で暖気が上昇しながら北へ運ばれ、西側では寒気が下降しながら南に運ばれている。密度の大きい寒気が下降し、
密度の小さい暖気が上昇することにより、有効位置エネルギが運動エネルギへ返還され、低気圧の発達に寄与する。
このの仕組みは、台風の仕組みとは根本的に異なる。
総観気象の中で頻出テーマである傾圧不安定波のポイントは、
- 南北の温度傾度
- 波動現象の発生
- 南北の熱輸送(温度交換)
- 有効位置エネルギへの変換
- 温帯低気圧の発達
などがあげられる。
温帯低気圧:
低気圧のライフサイクルは、気圧の谷の軸の傾きを追跡すればわかる。地上低気圧と上層のトラフを結ぶ軸が西に傾いているほど
低気圧は発達するが、閉塞過程に入ると軸は直立するようになる。
温帯低気圧は傾圧不安定波の中で発生・消滅する。特に北半球の冬は、夏に比べて南北の温度傾度が大きいため
傾圧不安定性が増幅され、偏西風の南北波動が大きくなり、温帯低気圧が発生しやすくなる。
地上低気圧の中心と上層のトラフを結ぶ軸が、上層ほど西側に傾いていると低気圧は発達するが、閉塞過程に入ると、この
軸が直立するようになる。温帯低気圧の構造を把握する時には、500hPa, 700hPa, 850hPa,の各高層天気図および
地上天気図を重ねて見る必要がある。なお、天気図を見る時は、各高度における代表的な物理量を目的に応じて
読みとる事が大切。
- 渦度→500hPa高層天気図
- 鉛直P速度→700hPa高層天気図
- 相当温位→850hPa高層天気図
- 地上気圧→地上天気図
- 渦度:
温帯低気圧における渦度分布は、下層では低気圧の中心付近で正渦度が最も大きく、上層では地上低気圧の中心よりやや西側で
正渦度が最も大きくなる。
- トラフと鉛直流:
地上低気圧の中心からみると、上層のトラフは西側に位置する。これを東西方向の鉛直断面図で見ると、トラフの東側に比べて
西側では空気の密度が大きく、2つの等圧面で挟まれた層厚(大気の厚さ)は薄くなっている。このため、
各高度で気圧が極小となる点を結んだトラフの軸の東側では、相対的に暖かい空気が上昇し、西側では相対的に冷たい空気が
下降する場となっている。こうした構造が、有効位置エネルギから運動エネルギへのエネルギ転換を生み、低気圧を発達させる。
- 移流と前線、風向:
低気圧の発達期において、500hPa高層天気図を見ると、トラフの西側では北西風が強まり寒気の移流が有り、
東側では暖気の移流がある。このとき、地上天気図では低気圧が発達し、寒冷前線と温暖前線の活動が活発になっている。
この2つの前線に挟まれた温度の高い部分は「暖域」と呼ばれており、大気の成層は鉛直方向に不安定となる。また、
発達中の低気圧に伴う温暖前線のすぐ東側の地点では、地上から上層に向かって風向が時計回りに変化しており、逆に
寒冷前線のすぐ西側の地点では風向が反時計回りに変化している。
- 収束・発散と鉛直流:
低気圧の進行前面にあたる東側では、下層に収束域、上層に発散域があり、西側ではこれと逆に下層に発散域、上層に収束域がある。
また、鉛直方向に収束域と発散域が存在する時には、その間の中層に「非発散層」と呼ばれる収束・発散の小さい層が有り、
鉛直流の速さ(鉛直P速度)は、この付近で最大となる。
発達中の低気圧では、地上低気圧の中心付近に当たる対流圏の上層において強い暖気移流が見られる。
また、気象衛星の赤外画像で見ると、低気圧の発達期には地上低気圧の中心の東側の雲域は、北縁が寒気側に膨らむ。
寒冷低気圧(寒冷渦):
低気圧内の温度分布は対流圏内では低いが、成層圏では高い。寒冷低気圧は、上層の偏西風の蛇行が大きくなり、
やがて寒気が偏西風帯から切り離されて形成される低気圧である。
寒冷低気圧は、中心部の温度が周囲より低い温帯低気圧の事で、「切離低気圧」とも呼ばれ、偏西風の蛇行が
南北に大きくなった時などに形成される。寒冷低気圧の名称は、気温と気圧に着目したもので、
これに対して風の流れと気温に着目した場合の名称を「寒冷渦」という。
一般に寒冷低気圧は、対流圏内では周囲より気温が低くなっているが、圏界面より上の層(成層圏)では大気の下降による
断熱昇温のため、周囲に比べて気温が高くなっている。これを「暖気核」あるいは「温暖核」という。
また、寒冷低気圧の南東側から東側にかけて(南東象限)は、雷や突風などを伴った激しい対流現象が発生しやすい領域。
寒冷低気圧は、偏西風帯から切り離されている為、通常の温帯低気圧に比べて移動速度が遅く、停滞したり西進したりすることもある。
また、地上天気図では明瞭な低気圧として現れないことがあるが、500hPa面では顕著な低気圧が解析される事が有る。
寒冷低気圧には、台風と似たような「暖気核」があるが、その生成要因は全く異なる。寒冷低気圧の場合は、成層圏下部の
大気の下降によるものだが、台風は水蒸気の凝結の潜熱放出によるもの。
高気圧:
形成される場所によって性質がかなり違う。気団または移動性高気圧として好天をもたらす。
高気圧は、中心付近の下降流によって一般に好天をもたらすが、吹き出す風が湿潤大気を運んでくると悪天をもたらすこともある。
日本付近には次のような高気圧が形成される。
- シベリア高気圧
冬季、高緯度の大陸上で発達するシベリア高気圧は、対流圏の下層に形成される非常に冷たい空気に満たされた背の低い高気圧で、
海上を吹走する変質した気団が日本海側の地方に大雪をもたらし、山越えした気流は乾燥した風となる。
- 太平洋高気圧(亜熱帯高気圧)
対流圏上層の大規模な収束によって作られた太平洋高気圧の圏内では、広範囲にわたり下降流が存在しているので
好天をもたらす。この下降流は、南方洋上から湿潤大気を日本列島へ送り込み、集中豪雨をもたらす。さらに、
三陸沖を含む日本の東海上からベーリング海までの広範囲な海上に濃霧(移流霧)を発生させる原因ともなる。また、台風が
この太平洋高気圧の縁に沿って北上することがある。
- オホーツク海高気圧
梅雨期にオホーツク海に現れる高気圧は、対流圏の下層では冷たい高気圧だが、中層から上層にかけては周囲より暖かく、
日本付近で太平洋高気圧との間に梅雨前線を形成する。また、冷害や日照不足などをもたらす北東気流の原因ともなる。
- 移動性高気圧
シベリア高気圧や太平洋高気圧のように、長い間ほぼ一定の場所に存在する高気圧に対して、移動性高気圧とは、
前後2つの低気圧に挟まれて移動していく高気圧の事を言う。日本付近で春や秋によくあらわれる移動性高気圧は、
上層の気圧の尾根(リッジ)に対応して西から東へ移動し、リッジの前面にあたる高気圧の中心の東側では
下降流が卓越して、晴天のところが多くなる。しかし、高気圧の西側(後面)は後ろの低気圧の前面にあたるため、
高気圧の中心部が通過すると次第に雲が低く厚くなり、天気は下り坂に向かう。
- ブロッキング高気圧(切離高気圧)
偏西風の蛇行が大きくなると、ブロッキング高気圧が形成され、10日から2週間ほど持続し、長い時には1か月以上も継続する。
このため、移動してくる低気圧の東進を妨げたり(ブロッキングといわれる理由)、高気圧の西側で悪い天気が続く原因となる。
一方、高気圧の中心あるいは東側では、乾燥した好天が続く。
移動性高気圧は、上層の偏西風の波長5000kmくらいの波動に対する周期で通過し、天気の周期的な変化をもたらす。
メソスケール気象(短期予報・局地予報)
雷発生時の周囲の気域温度は30000℃、発電能力は1000000kW。
メソスケール気象の特徴
水平スケール2~2000kmの規模の現象。総観規模と比べて時間・空間スケールが小さいので 100km以下の現象は
数値予報プロダクト(高層天気図やGPV)では十分に表現できない。しかし、一般に気象現象は、相対的に大きな現象の内部に小さな
現象が発生するので、メソスケールの現象は、総観規模の現象に含まれる。このことは、総観規模の現象がメソスケール現象の
発生に都合のよい気象条件をつくっていることを意味する。
そこで、総観規模の天気図から、どんな気象現象が起こっているかを把握しようとする場合、その天気図からポテンシャリティー
は推定できるが、具体的にはわからない。このため、数時間先の気象現象を予想するには気象レーダー、アメダス、気象衛星画像
などの最新情報を利用する。
主なメソスケール気象の現象
メソスケール現象は数多くある。ここでは集中豪雨、降雪、積乱雲、局地風(海陸風)、地表付近の現象(逆転層、収束)などを中心に説明する。
集中豪雨:
集中豪雨は、狭い地域に集中的に降る豪雨の事で、多くは短時間の現象。雨域のサイズは、メソβからγの規模で、具体的には
10~100km程度の空間的な広がりをもった擾乱。
日本付近の集中豪雨は、ほとんどの場合、次々に発生する積乱雲群により起こっている。そのためには、下層に湿潤な空気が
次々と供給され、大気の成層の不安定な状態が維持される事が必要。また、集中豪雨は、梅雨前線など前線付近で発生するほか、
台風や太平洋高気圧の縁辺に沿って流れ込む暖かく湿った気流によっても発生する。
また集中豪雨は、たとえば弱い熱帯低気圧など規模が小さい擾乱であっても、局地的に非常に強い降水現象として発生する事が有る。
さらに、地形の影響を受けて降水が強化される事もあるので、予報作業に際しては、地形と下層の風向・風速との関係に
着目することが重要。なお、集中豪雨の発生に前後して、下層ジェットと呼ばれる非常に湿度の高い強風が観測される事が有る。
これも注目すべき事。
集中豪雨が発生している時の気象衛星の赤外画像を見ると、雲頂温度(等価黒体温度)が非常に低い雲クラスター(積乱雲群)があるが、
これは雲頂高度が非常に高い事を示している。
集中豪雨の雨域のサイズは、メソβ~γ規模だが、雨に関する予報を行う場合、湿潤大気の運搬に加えて、地形の影響を無視することは
できない。つまり、『地形効果』→『上昇流』→『水蒸気の凝結』→『降水』という一連のパターンは、「降水現象を
強化させる、あるいは衰弱させる事に密接に関係」しているので、非常に重要。
下層ジェット、湿舌:
大気下層の700~850hPa付近に出現し、狭い領域に集中して吹く強風帯を下層ジェット(気流)という。
梅雨期などの集中豪雨のときにしばしばあらわれる。場所としては、東シナ海から九州、四国・本州にかけて「湿舌」を伴って流れている。
湿舌とは、湿潤域が温度と水蒸気の移流に伴ってかなりの広さで舌状(あるいは帯状)にのびている所。この湿舌に含まれる水蒸気は、
太平洋高気圧の西縁を回る暖湿気流によってもたらされる事が多いようである。
降雪(大雪):
降雪の中でも、重大な災害をもたらす大雪(豪雪)は、北日本の日本海側に顕著に発生するメソスケールの擾乱だが、
大局的には高気圧や低気圧などの総観規模的な現象によって、降りやすい条件が形成されている。
たとえば、総観規模の低気圧が千島列島近海やカムチャッカ半島付近で発達する時、日本海北部で小低気圧が発生して、
北日本の日本海側に局地的な大雪や突風をもたらすことがある。また、大陸から吹き出す季節風は、暖かい日本海から
顕熱や潜熱の補給を受けて大気下層の成層が不安定となり、活発な対流活動を引き起こす。このとき、日本海で
大気中層に寒冷渦や切離低気圧があると対流活動が強化され、日本海側の地方では大雪になる事が有る。
雨雪の判断について:
降雪は、降水現象の一種だが、「液体の水」ではなくて「固体の水」である雪は、水とは異なった災害をもたらす。
特に、太平洋側での降雪は、その備えが万全でない場合、大きな社会的影響が生じる。このため、雨雪の判断・予想は非常に重要。
一般に 850hPa面の気温がマイナス6℃よりも低い箇所では雪、高い箇所では雨と判断される。しかし、実際の雨か雪かの判断は、
850hPa面の気温だけではなく、大気下層の湿度や地上に入りこむ寒気、地上から850hPa面までの気温鉛直分布などのデータを
用いて、総合的な判断が必要。
降雪には、次のようなパターンが有る。
- 山雪型...冬季に、低気圧が日本の東海上や千島方面で発達し、日本付近で季節風の吹き出しが強まると、日本海側の地方で
「山雪型」と呼ばれる大雪が降る。主として山岳部に多く降雪がある。
- 里雪型...季節風の吹き出しが弱く、寒気の中心が日本海から日本列島上にあるとき、日本海上の渦状や筋状の雪雲が
日本海側の地方に上陸してもたらされるのが「里雪型」と呼ばれる大雪。主として平野部に降る。
- 太平洋側の降雪...低気圧が春先に日本列島の南側を通過する時に多く発現する。雨になるか雪になるかは、地上の気温と共に
下層の湿度が影響し、気温と湿度が低い(落下中に昇華熱が奪われるから)ほど雪になる可能性が高くなる。
| 降雪の3パターン
|
| 山雪型 | 里雪型 | 太平洋側の降雪
|
中国大陸に高気圧
→日本海わたって吹きこむ
北海道の東に低気圧
| 中国大陸に高気圧
日本海に低気圧
| 東海沖に低気圧→北東方向に通過
|
| 典型的な西高東低の冬型の気圧配置。日本海には、筋状の雲列が形成され、脊梁山脈に直角に当たる風が山雪をもたらす。
| 低気圧(低圧部)は、日本海西部にある。日本海収束帯が形成されている。
| 低気圧が、春先に日本の南岸を通過する場合、関東地方等が大雪となる。
|
なお、北海道の西部や北陸・山陰地方などでは、水平スケールが数10~100km程度のメソβスケールの小低気圧によって、
局地的な大雪や突風等がもたらされることがある。
脊梁山脈:
奥羽山脈や中部山岳など本州の中央に連なり、日本海側と太平洋側とを分ける山岳のこと。
日本海収束帯:
冬季に北西風が強まる時、白頭山で左右に分かれた気流が、日本海西部で合流し、帯状に収束する。この収束帯を
日本海収束帯と呼ぶことがある。
太平洋側に降雪をもたらす、表のような低気圧を「南岸低気圧」という。この低気圧は、東シナ海や四国沖などで発生し、
発達しながら本州の南岸沖を東北東~北東に進み、三陸沖や北海道の近海に達して台風並みに発達する事もある。
ポーラーロー:
冬季、相対的に暖かい海上の寒帯気団内に形成される前線を伴わない小低気圧の事。渦状やコンマ状の形の雲を伴う
小さな激しい擾乱で、寿命は1~2日。日本海周辺の海域、特に朝鮮半島東方や北海道西方によく発生する。
ポーラーローの発生条件には、海面からの顕熱・潜熱補給のほかに、水平温度傾度に起因する有効位置エネルギーや水平シヤーの
運動エネルギーなどがある。そして、傾圧不安定波や第二種条件付き不安定によって発達すると考えられている。
発達の程度によって、小型台風並みの形になって、眼を持つ事もあり、強風や降水を伴う事が有る。
シベリア高気圧と主低気圧(北海道の東に中心)の間の日本海に、ポーラーローができる(ポーラーローの代表的な配置)。
北東気流:
北日本や東日本に北東方向から流入する寒気のことで、縁辺流の一種。この現象は、大陸やオホーツク海の高気圧からの
冷たい気流が流入して起こるもので、この北東気流の寒気は東北地方の脊梁山脈や中部山岳にせき止められて下層に滞留する。
この北東気流は、寒気を送り出している高気圧が移動しない限り継続するので、東北の太平洋側や関東地方ではぐずついた
天気が続く事になる。
また、梅雨時に、オホーツク海高気圧によって北東気流の冷気が北日本に送り込まれると「やませ」で代表される
冷夏となることが知られている。
爆弾低気圧:
比較的短時間のうちに急激に発達する、暴風を伴う温帯低気圧の事で、爆発的な勢いで発達するところから、こう呼ばれる。
その多くは、傾圧不安定の場における寒気移流と暖気移流の強さが大きい時に発生し、発達中は移動速度が速く、
激しさは台風並みで、特に海や山は大荒れとなる。
梅雨前線:
東アジア全域において初夏から夏にかけて発生する、顕著な長雨や大雨をもたらす停滞前線で、日本付近では北の
オホーツク海高気圧と南の太平洋高気圧に挟まれた部分に形成される。この南北二つの高気圧の勢力が釣り合っている場合は、
梅雨前線は日本付近に停滞したままだが、オホーツク海高気圧の勢力が弱まると、梅雨前線が北上して梅雨明けとなる。
前線上には1000~2000kmごとにメソαスケール規模の低気圧が発生しやすく、この低気圧は温帯低気圧とは異なり、
背の低い雲クラスター(積乱雲群)をともない激しい降水現象を起こす。この付近では 850~700hPaの高度において、下層ジェットが
南西寄りの風として吹き込んでくる。また、梅雨前線の南北方向の気象要素に着目してみると、前線の東の部分に当たる
日本付近から東では、前線をはさんだ二つの高気圧の温度差は比較的大きいが、前線の西の部分にあたる中国大陸から西日本にかけては
逆に温度差は小さく、特に梅雨末期にはそれが顕著である。
しかし、二つの高気圧の相当温位(or 湿度)の差は非常に大きく、特にこの傾向は前線の西の部分で明瞭に現れ、梅雨末期には
さらに顕著になる。
また、梅雨末期の前線付近では、積乱雲がほとんど同じ場所で次々に発生し、発達しながらある同一地点を通る事によって、
集中豪雨になる事例が数多くある。
梅雨前線付近の発達したクラウドクラスターは、積乱雲の集合体。この中では、多量の凝結の潜熱が放出されるので、
総観規模の運動や大気の大循環のエネルギー源となる。
このクラウドクラスターは階層構造になっており、メソαのクラウドクラスターの中にメソβのクラウドクラスターがあり、さらに
その中にメソγのクラウドクラスターが存在している。そのうち、メソβ・γのクラウドクラスターは、数時間で
発生・消滅を繰り返す。
| 梅雨前線の典型例
|
←↓変質したシベリア高気圧(温暖乾燥)↓→
中国、ロシア
| ←オホーツク海高気圧(寒冷湿潤)↓→
オホーツク海から吹き込み、日本列島を覆う
|
| ↑モンスーン(高温多湿)↑ | ↑太平洋高気圧(温暖湿潤)↑
|
夏季に、北のオホーツク海高気圧からの冷気(湿潤寒気流)が日本列島を覆うと、冷夏になることがある。
積乱雲、雷雨:
冬季にも発生する。梅雨前線付近などで集中豪雨が発生する時には、強い積乱雲が線状に並んだり、団塊状に組織化される事が多い。
(1)積乱雲
積乱雲とは、鉛直方向に発達する濃密な雲の事。豪雨、雷、雹、霰、強風などの激しい擾乱を起こす。
積乱雲が発生する大きな要因に、大気の上層・下層の不安定性がある。条件さえ整えば、季節あるいは昼夜を問わずに発生する。
| 夏季の積乱雲 | 太平洋高気圧の西側縁辺を北上する暖湿気流が、日本の山岳斜面を上昇して発生・発達するものや、
地表面が夏の強い太陽熱を受けて大気が絶対不安定となり、熱せられた大気が上昇して、雄大積雲が発達して雷雨になることがある。
|
| 冬季の積乱雲 | シベリアからの寒冷な気団が日本海からの湿潤な大気により気団が変質し、上層寒冷・下層暖湿のため
大気が不安定となり、積乱雲が発生・発達する。
|
個々の積乱雲のライフサイクルは、発達期・成長期には雲の中のどこでも上昇流が有るが、最盛期には下降流が主として
中・下層に見られ、衰弱期(消滅期)には下降流だけになる。また、積乱雲と梅雨前線は密接に関係しており、
前線付近では多数の積乱雲が組織化されると、水平スケール100km程度の擾乱が発生する。
(2)雷雲
積乱雲が、マルチセル型ストームあるいはスーパーセル型ストームなどと呼ばれる強い雷雲となって数時間にわたる
強い上昇流を維持するためには、雷雲の周辺の風の鉛直シヤーが強い事が必要。特に、スーパーセル型ストームは
一般場の風の鉛直シヤーが強い状況で発生し、一つの上昇流域を持つ一個の巨大な積乱雲からなっている。
長時間にわたって持続し、ダウンバーストや竜巻などを伴う現象がしばしばある。
また、発達した雷雲から冷たい下降流が周辺に吹きだす時、周囲の湿った暖かい空気と衝突して新たな雷雲の発生がみられる事が有る。
大気の成層が不安定な時に、積乱雲から雷を伴って激しく降る雨を雷雨という。雷雨は、雷雲を形成する上昇流の成因によって
渦雷、界雷、熱雷の3つに分類される。
- 渦雷:台風や寒冷低気圧(寒冷渦)など、低気圧に伴って発生する。
- 界雷(前線雷):寒暖気温の異なる二つの気団の境界面で発生する事が多く、激しい雷雨は寒冷前線上によく発生する。
- 熱雷:強い日射により大気下層が熱せられて発生する雷で、夏の晴天日の午後に内陸や山岳地域で発生する。
夏季の熱雷の場合、その発生から上昇流が弱まって衰弱するまで、個々の雷雲の寿命はせいぜい30~40分程度。
海陸風:
沿岸地域で海面と陸地の温度差によって生じる局地風で、日中は気温の低い海面から気温の高い陸地に向かって
「海風」が吹き、逆に夜間は気温の低くなる陸地から気温の高い海面へ「陸風」が吹く。
典型的な海陸風は、北半球において、総観規模の「場」で気圧傾度が小さい時の平らな地形で発生するが、
日本では、冬季に比べて平均的に風の弱い夏季に明瞭に現れる。海陸風の発生メカニズムは以下のとおり。
- 晴れた日の日中は、地面と海面とでは太陽放射による過熱のされ方が異なり、地面温度の方が海面温度よりも高くなる。
- このため、地表付近では地面と海面の間で水平方向に温度差、つまり気圧差が生じ、海から陸に向かって海風が吹く。
- 一方、夜間は放射冷却によって地面温度が下がるが、海面温度はほとんど変化しないので、日中とは反対の温度(気圧)差が生じて
逆向きの陸風が起こる。
こうした海風と陸風には、次のような特徴がある。
- 風が吹き始める時間は、海岸付近での海風は日出後3~4時間で始まり、陸風は日没後1~2時間で始まる。
- 海陸風の強さは、季節や気象状態や地形などによって違うが、大まかにいうと、海風は厚さが200~1000m、風速が5~6m/sec程度。
陸風は海風に比べて弱く、厚さが100m前後、風速が2~3m/sec程度。
- 風の及ぶ距離は、海風は陸地に向かって海岸線から約20~40kmまたはそれ以上まで及ぶが、陸風はずっと規模が小さく、海岸線から
10km以下までしか及ばない。ない。海風は広い平野部や大きな川筋に沿って海岸がら数10km先まで達する事もある。
- 海風の先端(海風前線)では、水平収束が大きく、対流が発生しやすくなる。また、半島では両側の海岸から流入する
海風が収束して上昇流を作り、積乱雲が発達する事が有る。
局地風とは、一般場の風が弱い時に局地的に吹く風の事。スケールは、メソβ(100km)程度で、地形効果の力学的影響を
強く受けて形成される。フェーン、ボラ、山岳波、山谷風などがあげられる。さらに、水平対流をする郊外風(都市~郊外の間の
水平方向の温度差が出て気圧傾度力が生じ、大気が移動して吹く風の事)もあげられる。その他にも、「○○おろし」「××だし」
「▽▽あらし」などのローカルな局地風がある。
フェーンとボラ:
湿った風が山岳などに当たり、その風が山を超えると、風下側では気温が上昇し、高温で乾燥した風が吹き下りる。
この風を「フェーン」という。
一方、フェーンとは反対に、山を越えると風下川の気温が低下し、低温で乾燥した強い風が吹く事が有る。この風は、「ボラ」
という。これは、山越えした空気の温度が上昇(断熱昇温)しても、もともとの空気自身が極めて低温であるため、風下側では風の
吹き出しに伴って気温が下降し、非常に冷たい風として感じられる。
逆転層:
対流圏では、大気の温度(気温)はおおむね高度があがるとともに低下していくが、さまざまな要因で温度分布が逆転することがある。
このような高度が上がるにつれて温度も上昇する気層のことを逆転層という。逆転層では、気温減率が湿潤断熱減率よりも
小さいので、熱力学的には「絶対安定」の成層となる。このため、対流現象が抑えられ、霧などが発生しているときは、
スモッグなどによる大気汚染を助長する。
逆転層は転移層の一種。転移層とは、一般に特定の気象要素が一様になっている二つの領域の境界層の事で、気象要素の不連続な部分を指す。
この不連続な部分は線や面ではなく、ある程度の厚さを持った層のこと。
逆転層には、主として次のような種類がある。
- 前線性逆転層
水平方向に寒気、暖気が存在していて、両者が衝突すると、その境界で下層の冷たい空気の上に暖かい空気が滑昇して、上層が相対的に
暖かくなる場合に形成される。この層が地表面に接する部分が「前線」。
- 接地逆転層
夜間の放射冷却によって地表面に接する空気が冷やされ、その上にある空気よりも気温が低下することで形成される逆転層。これは大きな場
の風や気温の変動などで、層の境界が崩れる事により解消する。
- 沈降性逆転層
高気圧の圏内などで、上層の空気が断熱的に下降してくる事により気温が上昇して形成される逆転層。
逆転層の検出について:
気温の鉛直分布を示した状態曲線から逆転層を検出する事は可能。しかし、一つの観測地点における状態曲線だけから
逆転層の成因を判断することは困難な場合がある。つまり、天気図類、天気や気温・風の時間変化、下降流の有無
などが分からなければ、逆転層の成因を特定することはできない。
逆転層の乾湿について:
- 前線性逆転層内では、気温も露点温度も一様に上昇しているが、高度と共にその差が小さくなっている為、上層ほど湿度が
高くなっている。
- 接地逆転層内では、気温も露点温度も上空ほど高くなっている。
- 沈降性逆転層内では、気温の上昇とは対照的に露点温度が急激に低下しており、上昇ではその差が大きくなっている為、
かなり乾燥している。
地表付近の現象(収束):
空気や水蒸気などが一定の領域に集まって来る事を言い、この収束域が細長く線状に延びた領域を収束帯、あるいは収束ラインという。
地表付近の収束ラインは、総観規模の天気図上に前線が解析されていなくても、地形効果等による小規模な気流の
収束・前線の形成がよくある。それらの代表的な形成パターンは次の通り。
- ある地域において、その南側には日本海の低気圧にともなう南風が吹いており、北側には放射冷却によって生じた
メソスケールの寒気域が澱んでいるような場合、小規模な収束帯が形成される。
- 気流が山岳や陸地に衝突して収束し上昇流となる事が有る。
- 半島などにおいて、その両側から海風が吹き寄せてくると、陸地上で気流が収束し、上昇流が発生する事が有る。
収束ラインと局地前線について:
地表付近の二つの大気の塊が接する時、山の影響による風向きの変化や、地表面の加熱・冷却による気温の違いによって、
その境界付近に収束ラインや前線が形成される。こうした地形や温度差の影響で形成される規模の小さい前線のことを
「局地前線」といい、房総半島沖、土佐沖など各地に発生する。
長期予報
30年間の期間で平均した気象要素→「平年値」。10年ごとに古い10年の資料を捨てて更新。
現在に最も近い末尾が0で終わる西暦年までの30年間。異常気象とは、この平年値から大きく外れた気象の事。
季節予報
気象庁の行う予報の種類に「季節予報」がある。長期予報は、この季節予報に該当するが、予報地域のスケールによって
全般と地方に、また時間スケールによって、それぞれ1か月、3か月、暖候期、寒候期に分けられる。
季節予報の予測対象は、技術的な限界から、短期・中期の予報を対象とした高気圧・低気圧の盛衰などの総観気象に
直結した天気変化ではなく、ある期間の平均気温や雨量の多寡などが平年値より高いか、低いかなどの
「気象要素の平均状態」ということになる。また、空間的なスケールにおいては地方単位までで、府県単位までの季節予報は
行われていない。
予報技術としては、過去の類似したパターンなどを参考にする統計的手法がとられてきたが、1か月予報については現在では
「アンサンブル予報」という手法が用いられ、発表は確率表現で行われる。たとえば、ある時期の気温を平均値より
「高い」、「並」、「低い」の3ランクで予報するとすると、同じ「高い」という予報でも、確率予報であれば、
高くなる確率が80%、あるいは50%と数字で示されるとこになる。
コスト対ロスの関係を考慮すると、季節予報の様な不確実性を含む情報には、カテゴリー表現ではなく「確率表現」
で発表した方が、予報の積極的利用の面から考えると有効といえる。
季節予報と長期予報は、ニュアンスのことなることもあるが、簡単にはほぼ同義と考えても構わない。
| 気象庁が発表する全般季節予報の種類
|
| 種類 | 発表日 | 予報内容 | 予報手法
|
| 1か月 | 毎週金曜日
| 月平均気温、月降水量、月日照時間、日本海側の月降雪量(確率表現)、気温(第1週、第2週、第3~4週) | 力学的(アンサンブル予報)
|
| 3か月 | 毎月20日頃 | 3か月平均気温(確率表現)、3か月降水量、各月の気温と降水量 | 統計的
|
| 暖候期 | 毎年3月10日頃 | 6~8月の平均気温(確率表現)、梅雨期の降水量 | 統計的
|
| 寒候期 | 毎年10月9日頃 | 12~2月の平均気温(確率表現)、12~2月の降水量および日本海側の降雪量 | 統計的
|
1か月予報
気象庁が発表する1か月予報については、1996年3月から従来の統計的手法に代わり、力学的手法を基礎とした
アンサンブル予報が実用化された。
1か月を超える長期予報においても、短期・中期予報の様な決定論的な数値予報を軸とした予報技術の開発が期待されたが、
数値予報が精度を維持できるのはせいぜい10日先程度までで、それを越すと気候値予報の精度と同程度になり、
精度のよい1か月予報は不可能となる。まず、1か月予報の手法としてのアンサンブル予報の概要を学習する。
アンサンブル予報:
天気のモデルは非線形微分方程式なので、初期値の微妙な違いにより、特に予報期間が長くなると、質的に全く異なる結果
になり、予想は非常に困難。そこで、初期値を少しずつ変えて数値予報をする。初期値を変えるとは、
予報開始時の初期値に適切な人工ノイズを加えたり、初期時刻の異なる初期値を用意することを意味する。
初期値を変えた数だけ、数値予報の結果が計算されるが、その平均を予想値とすることで、予想期間の延長を図る。
まあ、苦肉の策である。これがアンサンブル予報の考え方の基本。
人工ノイズとは、初期値に観測誤差程度のごくわずかな誤差を人為的に加えたもの。
数値予報は、流体力学や熱力学の理論をもとにして行われるので、力学的手法ともいわれる。これが、力学的手法による
アンサンブル予報と呼ばれるゆえん。それぞれの数値予報をメンバー、メンバー全体の集団をアンサンブルと言う。
数値予報の初期値となる解析値に含まれる微小な誤差は、大気の持つカオス的性質のため、時間と共に増大していく。
観測時の誤差は不可避のものであり、また数値予報モデル自身にも物理的な近似があったり、方程式を数値的に近似して
解いたりしているので、数値予報の有効な時間には限度がある。現在の計算機の性能や予報モデルでは、
およそ「1週間から10日前後」が予報可能な限界といわれている。つまり、将来の解析図とぴったり合致する完全な予想天気図と
いうものは作成できないということ。
アンサンブル予報では、初期値のわずかに異なる多数の数値予報を行い、その平均をとって予報可能な時間を延長していると
前述したが、同じ数値予報モデルによる1か月予報でも、大気の状態によって有効でなくなる時間は異なる事が知られている。
しかし、アンサンブル予報で得られる情報の利点は、各メンバーの「平均をとる」ことによって「気温が高めに推移するだろう」
などの予想ができるだけでなく、各メンバーの「ばらつき(スプレッドという)の程度を観る」ことによって
「予報が当たりやすい時期なのかどうか」、つまり信頼性の程度をあらかじめ知る事ができる点にある。
アンサンブル予報で個々のメンバーの予測に用いられている数値予報モデルは、気象庁の全球モデルに基づく
「1か月アンサンブル予報モデル」で、水平格子間隔:約110km、鉛直層数:0.4hPaまで40層、予報時間:34日となっている。
スプレッドについて:
アンサンブル予報によって求められた平均値(アンサンブル平均)に対して、各メンバーの予想値のばらつきが大きいと、
求められた平均値の信頼性が低くなる。そこで、各メンバーの予想値のばらつきの標準偏差から、予想された平均値の信頼性を知るために
「スプレッド」という量を求める。このスプレッドが大きい場合は、誤差の増幅も大きい事を示すので、予想された平均値の信頼性が
低いということになる。
1か月予報のしくみ:
現在、1か月予報は、毎週1回金曜日に発表されている。予報の形態は、地方季節予報の場合、日本を4地域または7地域に分け、
平年値を基準にして、1か月平均の気温や降水の多寡、日照時間等が平均値より「高い(多い)」「平年並」「低い(少ない)」の各段階に入る
確率をバーセントで表す。
平均値は、気候統計より30年間の気候値(普通の気候状態)から求められ、3階級の間の値(閾値)は、各値を大きさの順に並べて、
「高い(多い)」「平年並」「低い(少ない)」が等確率の33.3%ずつになるように決められる。
階級の閾値(境界値)について、従来「高い(多い)」「平年並」「低い(少ない)」は 30%:40%:30% の階級区分を参照してきた。
これが2001年から、3階級が等確率の33.3%ずつになるよう定義が変更された。
以下に、全般1か月予報の例を示す。
関東甲信地方1か月予報
(3月4日から4月3日までの天候見通し)
|
| (抜粋) | 平成XX年3月3日
気象庁 気候・海洋気象部発表
|
| (向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%))
|
| | | 低い(少ない) | 平年並 | 高い(多い)
|
| 気温 | 関東甲信地方 | 20 | 40 | 40
|
| 降水量 | 関東甲信地方 | 20 | 50 | 30
|
| 日照時間 | 関東甲信地方 | 30 | 50 | 20
|
上表から、気温については、1か月予報では平年並みの確率が「40%」、高いが「40%」だから、向こう1か月の気温は
平年並あるいは高くなる可能性を示している。また、降水量と日照時間については、1か月予報ではどちらも平年並みが「50%」と
なっているので、降水量、日照時間ともに平年並みになる確率が高い事を示している。
平均天気図:
長期予報に用いられる天気図は、短期予報や週間天気予報で使われる天気図とは異なり、5日間以上の「平均天気図」である。
短期予報や週間天気予報では日々の天気が予報の対象だが、1か月予報では日々の天気ではなく、
「より長い期間の平均的な天候の状態」が対象になる。また、着目する現象も、温帯低気圧や高気圧といった総観規模擾乱や
クラウドクラスターなどの中規模擾乱ではなく、より大きな空間スケールを持つ超長波、偏西風帯の変動、
亜熱帯高気圧の動向などである。このため、天気図も5日以上の時間平均をした天気図を用いる。その理由は、
代表的な温帯低気圧や高気圧は波長が4000km前後で、1日に約1000km東進するため、4~5日以上の時間平均をとると、
総観規模より小さな擾乱は除去され、それより長い大規模擾乱のみを表現できるから。
ある時刻の天気図では、総観規模の高気圧・低気圧や気圧の谷が見られるが、5日平均天気図では、それらは除去され、
等圧線や等高度線はより滑らかになって、波数が6以下のより大規模な擾乱のみが表現されている。このような平均天気図を
解析する事により、長期間の天候の傾向を支配する大規模な流れや気温分布の変動を把握する事が出来る。
東西流や南北流の強弱など偏西風の変動の予報については、平均天気図とは別に、東西指数と呼ばれる指標の実況値と予報値が
用いられている。
高度・平年偏差図:
1か月予報で使用する平均天気図には、必ず平年偏差(該当期間の平均値からその期間の平年値を差し引いた値)分布が
付加されている。これは、平均天気図では擾乱の振幅よりも季節変化の振幅の方が大きいので、
平均天気図だけを見ても変動がわかりにくいことが多いため。平年偏差の分布状態を見る事によって、はじめて平年との
相違を把握する事が出来る。
(1)500hPa高度・平年偏差図
500hPa高度場とその平年偏差の平均天気図からは、超長波、偏西風ジェット気流の位置と強さ、太平洋高気圧の
動向を把握する事ができる。さらに、これらから気温や降水量の傾向を推測する。
対流圏中・下層の気温の動向は、500hPa高度場の平年偏差を見る事により把握できる。500hPa以下の平均気温
(層厚気温)と地上~500hPa層厚とは比例するから(地上気圧の差は比較的小さいためこれを無視すれば)、
500hPaの高度とそれより下の層の平均気温も比例すると考えられる。したがって、500hPa高度場が負偏差(平年値より
高度が低い)のところは中・下層の気温が平年より低く、正偏差(平年値より高度が高い)のところは
高いと考えられる。
(2)西谷と東谷、偏差風
日本付近の500hPa 5日平均高度の平年偏差が日本の西側で低い時は西谷の流れ、東側で低い時は東谷の流れと言う。
高度の分布ではなく、平年偏差の分布からこのように定義されている。西谷の場合、日本付近には南西風が入りやすく、
ぐずつき傾向がある。また東谷の場合は、北西の風が入りやすく、雨量が少ない傾向が有る。
5日平均の流れは大規模な流れを代表しているので、地衡風が吹いていると考えられる。平年偏差は、5日平均の流れが
平年値からどれだけずれているかを示すものだから、等偏差線に平行で、偏差の値の高い方を右側に見て、
偏差値の傾度に比例するような強さの流れを考えると、それは平年の地衡風からのずれを示すものとなる。このことから、
西谷の場合は、日本付近では5日間の平均的な風向は南西となり、平年よりも湿った暖かい南西の風が日本に
流入しやすくなるので、曇りや雨の日が多くなる。一方、東谷の場合は日本付近では平年偏差の流れは北西となり、
平年よりも大陸から北西の風が流入しやすく、低気圧が日本の東方海上で発達しやすいので、冬季には日本海側で
雪・雨・曇りの日、太平洋側で晴天の日が多くなる。
なお、偏差図では正負値だけでなく、その関係を相対的に見る事が重要。たとえば、日本の西側に負偏差がなくても、
日本の東側が強い正偏差になっていれば、西谷の場合と同じように5日平均の風向は南西となり、冬なら平年よりも
曇りや雨の日が多く、夏なら高温で晴天傾向になる。
東西指数について:
東西指数とは、偏西風の流れの状態を表す概念で、1か月予報関係では北緯40度帯と北緯60度帯の高度偏差の差として
定義される。東西指数は、地衡風の関係を考慮すれば、北緯40~60度平均の東西風の平年偏差を表している事になり、
高指数のとき(北緯40度帯の高度場が高く、北緯60度帯の高度場が低いとき)は東西風の流れが平年より早いことを
表し、低指数の時は東西風の流れが平年より遅いことを表す。
一般に、高指数の場合と低指数の場合の特徴は以下の通り。
- 高指数の場合:
偏西風の蛇行が小さいため、流れは平年よりも速(強)くなる。日本付近では寒気が南下しにくく、高温となる事が多くなるため
冬は暖かく、夏は気温の高い安定した天気が続く傾向となる。
- 低指数の場合:
偏西風が南北に大きく蛇行するため、流れは平年よりも遅くなる。日本付近では、夏は北日本を中心に低温、
日照不足等の不純な天候になる事が多くなり、冬は気温が低く、日本海側の降雪量が多くなる傾向にある。
なおブロッキングは、低指数の場合の代表的な現象の一つ。
(3)季節ごとの天気図の特徴
- 冬(寒冬、暖冬)
寒冬の場合、東経90度付近でリッジが強まり、日本付近のトラフは平年より深まって負偏差域になる。
偏差風は、大陸から日本付近に向かうので、日本付近には例年よりも乾燥、寒冷な風が吹きやすく、低気圧は日本の
東方海上で発達することが多くなる。このため、日本海側は日照が少なく、太平洋側は晴れる日が多くなる。
一方、暖冬の場合は、東経90度付近は負偏差域となり、対象的に日本付近では平年よりトラフが弱まって正偏差域になる。
このため、冬型の気圧配置が弱く、平年より高温傾向になる。また、偏差風の方向は南寄りとなり、
平年よりも暖かく湿った気流が入りやすく、曇りや降水が多い傾向となる。
このように、東経90度のリッジと日本付近のトラフの強弱は、冬の天気図を見る時の基本の一つになっている。
暖冬型にはいろいろなパターンがあり、たとえばエルニーニョが発生したときの典型的な暖冬パターンは、日本の
南海上の高度場が高くて、日本付近は正偏差域に覆われる形になり、通常の暖冬型とは違ったものになる。
- 夏
夏は偏西風の動向だけではなく、亜熱帯高気圧の影響を特に大きく受ける時期。また、100hPaで顕著に表れるチベット高気圧の
動向にも影響を受ける。ここでは、冷夏年と暑夏年の平均天気図の特徴について説明する。
- 冷夏年の500hPaおよび100hPa平均図の特徴
日本付近では、年によっては梅雨明けがはっきりせず、8月になっても曇りや雨の日が続き、気温が低い事が有る。
このような夏を冷夏と言う。たとえば、500hPa高度場では、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱く、
日本付近は負偏差域になっており、日本付近では等高度線が密集している。高緯度では正偏差域になっており、
沿海州はリッジ場になっている。一方、100hPa高度場では、チベット高気圧の日本付近への張り出しは弱くなっている。
- 暑夏年の500hPaおよび100hPa平均図の特徴
日本付近は広く太平洋高気圧に覆われて正偏差域になっており、等高度線の密集帯は日本の北方、
サハリン付近まで北上している。一方100hPa高度場と同平年偏差図では、チベット高気圧が東へ延びており、広く日本付近を覆っている。
- 春・秋
一般に天気図の型を大きく分けると、日本付近を低気圧と高気圧が交互に通過し、天気が周期的に変わる「東西流型」を基本として、
移動性高気圧に覆われやすく晴れる日が多い「東谷型」、南海上に前線が停滞しやすく曇りや雨の日が多い「西谷型」の3つになる。
そのうち、春と秋には、東西の流れが卓越する東西流型の天気図が多く見られる。
チベット高気圧→夏季、チベット高原では強い日射のために著しく高温になり、広大な低圧部となっている。
また対流圏上層は、夏季モンスーンの降水による凝結熱(熱源)によって加熱されている。このため、対流圏上層(100~200hPa)
では著しく高温な高気圧が形成される。これをチベット高気圧と言い、その一部が日本付近まで張り出してくる事が有る。
台風
台風は、熱帯低気圧がつくりだす巨大な空気の渦巻き。このことに最初に気付いたのは、ダンピーアというイギリスの
航海者。
台風の予報
台風はメソαスケールの擾乱で、雲分布は通常の温帯低気圧と違い、対流雲が主体となっている特異な気象現象。
台風の中心が日本からおよそ300km以内に近づき、日本に被害を及ぼす可能性が生じた場合に、台風に関する予報
および情報が3時間ごとに発表される。さらに、台風予報以外に雨・暴風・波浪・高潮等に関する全般的な実況および
今後の見通しや防災上の留意点などが「台風に関する気象情報」として発表される。
台風の予報のためには、数値予報モデルの台風モデル(TYM)が稼働され、72時間先までの進路、大きさ、強さなどの
情報が提供される。この台風モデルは、水平格子間隔24km、鉛直層数25層で、約6500km四方の領域をカバーしており、
全球モデル(GSM)の稼働結果を境界条件として、台風の発生後に4回/日稼働されている。
原理的には、これまで学習してきた数値予報と同じだが、気象衛星・気象レーダー・地上および高層気象観測その他のデータに
基づき、台風の中心位置と強さ、大きさに関する情報がシステムに入力され、「台風構造」(台風ボーガス)が
決定され、これをベースに予測の計算が行われる。この台風ボーガスと呼ばれる台風データの人工的な埋め込み技術により、
台風の中心付近の構造のモデルの性能が良くなり、台風進路予報の精度が向上している。
気象庁では、2001年3月からのNAPS稼働にともない、台風モデルを次のように変更した。
- 水平格子間隔を40kmから24kmへ、鉛直層数を15層から25層へ改善
- 稼働回数を2回/日から4回/日に増加
- 台風の強度に関する3時間ごとの予報を現在の24時間先から48時間先までに延長
台風の構造とライフサイクル
台風の構造:
発達した段階の台風は、中心部の眼やスパイラルバンドの存在、前線を形成しないなど、温帯低気圧とは異なった
構造をしている。
台風の上層と下層の風の向き:
台風は、中心に近いほど温度が高く、密度も小さい。密度が小さいという事は、層厚が大きいということで、
周囲と中心の等圧面高度の差は上空へ行くほど小さくなる。そして、100hPa以上では、反対に周囲よりも
等圧面高度が高くなり、このため高気圧が形成される。
北半球の台風の場合、下層では風が反時計回りに回転しながら収束(気圧傾度力が外から中心に働く)
して上昇していくが、最上部では中心部が高気圧になっているため発散(気圧傾度力が中心から外向きに働く)し、
反時計回りに上昇してきた風は、中心部から外側に吹きだすように流れなじめる。そしてコリオリの力を
受ける事により、中心部から離れるにつれて時計回りの回転に変る。このように、台風の上層では風の向きが
時計回りになる。
- 台風の鉛直断面:
台風の眼の周辺は、上昇流が有り、潜熱放出で温度が高い。暖気核(ウォームコア)と呼ばれる。
また、台風の眼の内部では、下降流の断熱圧縮で温度が高い。
| ↑← | 上層は高気圧性循環で時計回りに発散 | →↓
|
| | | 壁→ | 眼 | ←壁 | |
|
| | 雲 | 壁↑ | ↓↓ | ↑壁 | 雲 |
|
| 雲 | 雲 | 壁↑ | ↓↓ | ↑壁 | 雲 | 雲
|
| → | ↑ | →↑ | | ↑← | ↑ | ←
|
| 下層は低気圧性循環で反時計回りに収束
|
雲:積乱雲群(雲クラスター)、壁:アイウォール
- 台風の平面図:
台風は前線をともなわず、等圧線はほぼ円形である。しかし、台風全体の形は左右非対称(進行方向右側に膨らむ)である。
第2種条件付き不安定で台風が発生・発達。強風域:15m/s以上、暴風域:25m/s以上、台風の進行方向右側は、左側に比べて風が強い。
台風の眼は、トロコイド(円が滑ることなく直線状を転がる時、円の中心に対して固定された点が円周上に無い場合に
、その点が描く軌跡)と呼ばれる軌跡を描いて進行する。中心付近の積乱雲群は、アイウォールを形成。中心を
取り囲むように積乱雲が組織化され、スパイラルバンドを形成。
台風は前線をともなわないが、温帯低気圧に変わると前線が発生する事が有る。また、台風が温帯低気圧に変わった後で
再発達すると、15m/s以上で定義される強風域の範囲が広がる事が有る。
日本で、通常「台風」と呼ばれている熱帯低気圧は、最大風速ごとに次のように国際的な分類がされている。
- 32.7m/s以上: T(Typhoon)
- 24.5m/s以上32.7m/s未満: STS(Severe Tropical Storm)
- 17.2m/s以上24.5m/s未満: TS(Tropical Storm)
- 17.2m/s未満: TD(Tropical Depression)
なお、国内の分類では上記1~3までが台風、4は熱帯低気圧。
- 温度分布:
発達した台風の中心付近では、周囲に比べて気温が高く、特に中層から上層にかけてその傾向が明瞭であり、
暖気核(ウォームコア)と呼ばれている。この現象は、水蒸気が凝結する際の潜熱放出による昇温、あるいは眼の中の
下降流の断熱圧縮による昇温が要因となっている。しかし、台風が温帯低気圧に変わると、こうした特徴はなくなる。
- 風、気流:
台風の風は、気圧傾度力とコリオリの力および遠心力がつり合った傾度風で近似できるが、地表付近では摩擦力が加わり、
中心に向かう流れが生じる。そして、台風の中心付近のアイウォールと呼ばれる積乱雲の壁の中には、40m/sに達する
強い上昇流がある。
一方、台風の眼の中には下降流が有り、その眼の周辺では風が非常に強く、台風の最大風速は一般に、眼をとりまく
アイウォール付近に現れる。また、台風の風速分布を水平面で見た場合、台風の進行方向に対して左右の
風速分布は非対称である場合が多く、左側よりも右側の方で風速が大きくなる。
- 循環:
台風の循環は、下層では低気圧性(北半球では反時計回り)だが、対流圏上層では空気が中心から外側に向かって吹きだしており、
高気圧性(北半球では時計回り)の循環になっている。
- 形状、パターン:
台風のスケールは、直径が数100km~1500km以上にも達するが、高さはおよそ10~15km程度で、薄くて平らな形状。
気象レーダーで台風を観測すると、多くの場合は、台風の眼を取り囲むアイウォールのエコーと、それを
取り巻く螺旋状をしたエコーが見られる。また、発達した台風を気象衛星の赤外雲画像の動画でみると、
上層雲が台風の眼を中心に時計回り(北半球の場合)に回転しながら、台風の中心から離れて行くのが観察される。
気象衛星画像からみた台風の雲分布のパターンは、台風のライフサイクルに応じた特有のパターンが現れる。
このパターンは台風の強さに関係している事が知られており、この関係を利用して台風の強度(中心気圧や最大風速)
を推定する。なお、観測点の少ない海洋上にある台風の強度は、気象衛星の画像による眼の形や大きさ、
スパイラルバンド(積乱雲の雲列)などをもとにして、ドボラック法といわれる方法で決められる。
ドボラック法:
気象衛星による雲画像を用いて熱帯低気圧や台風を構成する雲域の形状と雲頂温度の分布を解析し、台風域内の
最大風速と中心気圧を推定する手法の事。台風を取り巻く雲域の形状や雲頂温度は、そのときの台風の発達程度を反映しており、
特徴的な雲域の形状をある程度維持しながら発達・衰弱すると考えられている。
台風のライフサイクル
北太平洋西部や南シナ海で発生した熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が17.2m/s以上になったものが「台風」。台風の
発生から衰弱までの間に起こる現象や影響を説明する。
- 発生の条件
- 海面水温が26~27℃より高い海域である事
- 熱帯収束帯であること
- 風の鉛直シヤーが小さい事
- 地球の自転の効果(コリオリの力)が有る程度大きい事(赤道直下では発生しない)
などがあげられる。こうした条件の下で、熱帯低気圧のもとになる擾乱(偏東風波動、雲クラスターなど)が発達して台風となる。
なお、北緯5度以南の赤道付近では、渦(低気圧性の回転)をつくり出すコリオリの力が小さいため、台風は滅多に発生しない。
- 発生・発達のメカニズム(第二種条件付き不安定)
台風を構成する積乱雲群と台風とが、力学的な相互作用によって互いに発達を促進しあう過程は、「第二種条件付不安定」
(CISK:シスク)によるものと考えられている。
この過程は、上昇流で水蒸気が凝結して積雲対流を生じる時、放出される潜熱による加熱が上昇流を加速させ、より
大きなスケールの低気圧性循環を形成し、これが水蒸気を補給してさらに上昇流を加速させるという、積雲対流と
それらが多数集まったスケールの現象の相互作用によって、台風が発生・発達するというもの。これに対して、個々の雲を発達させる
通常の条件付不安定を「第一種条件付不安定」と呼んで区別している。
- 進路、進行
低緯度において熱帯低気圧から発達した台風は、これを移動させる大規模な流れが無ければ、地球の自転効果により北西または
北北西へ進む性質があるが、一般には太平洋高気圧の南の偏東風により西へ流される。
台風の(中心の)移動は、地形の影響の無い海洋上においても滑らかではなく、不規則な変動や周期的な蛇行(ex.トロコイド曲線)
が見られる場合がある。また、2つの台風が接近すると、互いに影響を及ぼしあい、両者の中間のある点の周囲を反時計回り
(南半球では時計回り)に回転するような動きをすることがある。この現象を「藤原効果」という。
- 転向点
台風を流す大規模な流れとしては、偏東風、太平洋高気圧の西側の縁辺を流れる風や偏西風等が有るが、
それらの中でも台風進路の転向点に大きく影響するのが偏西風。たとえば、7月から9月には北緯25~30度の比較的高い緯度で
台風が転向する事が多くなる。これは、太平洋高気圧の勢力が強い事による。そして10月になると北緯20~25度で転向し、
日本の南海上を北東進する事が多くなる。
- 衰弱
台風は、主として積雲の生成時に水蒸気の凝結により放出される潜熱が運動エネルギーに変換される事により、
発達・維持される。しかし、台風が上陸すると、陸面からの水蒸気補給が海面からに比べて少なくなる事、および
山岳等の陸面との摩擦により、その勢力が急激に弱められる。
- 影響等
台風の影響による気象現象には、次のようなものがある。
| 集中豪雨 | 台風にともなう風が前線に向かって吹く地域では大雨になりやすい。
大規模な前線が明瞭に認められなくても、局地的な前線が存在していれば、その前線付近を中心に大雨となりやすく、
また集中豪雨にもなりやすくなる。
|
| フェーン現象 | 台風による強い湿った風が山岳に吹きつけると、風上側では強風が吹き、
風下側でも風が吹く、高温乾燥となり、フェーン現状が発生しやすくなる。台風が日本海を通過する時に、北陸や山陰地方
で起こりやすい。
|
| 海面水温の低下 | 台風や熱帯低気圧が通過した後に、その経路上での海面水温が数℃低くなる場合が有る事が
観測されている。これは、上下層の海水が強風により混合される(海面下数10mの冷たい海水が湧き上がる)ことが大きな要因である。
|
| 海面の上昇 | 気圧の低下による吸い上げ効果で、海水面は1hPaあたり1cm上昇する。また、風上側に
向いた海岸や特に外海に開いた形の湾では、強風による吹き寄せのために海面が上昇する。したがって、満潮時には、
高潮に注意する必要がある。
|
熱帯収束帯(ITCZ):
北半球亜熱帯高圧帯から吹き出す北東貿易風と、南半球亜熱帯黒圧帯から吹きだす南東貿易風が収束する領域の事。
ITCZ(Inter Tropical Convergence Zone)。熱帯収束帯では、頻繁に上昇流が起こるため対流活動が発生しやすく、
色々な熱帯擾乱の多くはこの収束帯で起こっている。
偏東風波動:
低緯度の偏東風の中を、東から西へ移動する波動の事。北半球では、波動のトラフの東側で雲域と
降水域が現れる。周期は3~5日で、波長は約2500~4000km。
転向(点):
台風が、その進行方向が変わることを「転向」といい、転向が起こる進路上の場所を「転向点」という。
防災気象情報
防災気象関連情報の提供形態
注意報・警報の条件や気象情報のタイミングなどをよく理解しておく必要がある。実技でも重要。
台風が日本付近に来ると、偏西風に乗ってスピードを増し、その後は熱帯低気圧化して再発達することや、
台風から温帯低気圧に衣替えするときに減速することなどがわかっている。
注意報・警報・気象情報
気象災害を引き起こすかもしれない気象現象が観測されると、地方気象台は一般の人々に注意を促すために「注意報」や
「警報」、場合によっては注意報・警報を補完する形で「気象情報」を発表する。注意報・警報・気象情報を発表する時には、
あらかじめ決められた基準値に照らし合わせるが、その値は地域によって違いがある。
注意報と警報:
注意報と警報は決して一緒に出る事はない。大雨注意報と大雨警報は、府県内の同じ地域に対して同時に発表されない。
注意報は、気象災害が発生する恐れがある場合に発表される。警報は、重大な気象災害の発生する恐れがある場合に発表される。
いずれも各都道府県の予報区を担当する気象官署(主として地方気象台)と指定地区測候所から発表される。
ただし、府県内の同一地域に対して同じ種類の注意報と警報が出されることはない。注意報と警報の種類は以下の通り。
防災気象情報の特性
| | 全般・地方気象情報 | 府県気象情報 | 注意報 | 警報
|
| 概要 | 大雨、暴風、波浪などの可能性を予告するもの
| 注意報・警報が発表される前後などに雨量、風速などの経過や予測、防災上の注意を解説する
| 大雨、強風、波浪などによって災害が発生するおそれがある場合、その旨を注意する予報
| 大雨、強風、波浪などによって重大な災害が発生するおそれがある場合、その旨を警告する予報
|
| 発表時期 | 現象発生の半日から一日前に、状況に応じて2~3日前から
| 注意報・警報の発表の前後に、状況に応じて1~3時間ごと | 災害の原因となる現象が発生する3~12時間位前から
|
| 発表官署 | 気象庁本庁、管区気象台など | 主として地方気象台
|
| 対象地域 | 全国および北海道、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、沖縄の各地方予報区
| 都府県の範囲
※北海道は広域なので、地方気象台(稚内、旭川、網走、釧路、室蘭)と札幌管区気象台予報課、
函館海洋気象台がそれぞれの地域を担当している | 各都道府県(北海道では支庁)を2~8区域に細分して発表する
|
| 伝達の方法 | テレビ、ラジオ、新聞などの報道機関を通じた伝達
| - 各都道府県で定めた地域防災計画に基づく伝達(災害対策基本法による)
- テレビ、ラジオ、新聞などの報道機関を通じた伝達
| - 海上保安庁、都道府県、NHK、NTTおよび国土交通省などの伝達
- 地域防災計画に基づく伝達
- 報道機関を通じた伝達
|
気象情報:
台風が近づいてきた時に出る台風情報等がある。数年に一度の激しい雨のときには、記録的短時間大雨情報が発表される。
気象情報には、アラーム的機能と、補完的機能がある。
- アラーム的機能の気象情報: 対象とする注意報・警報が発表されていない時に発表するもの。
- 補完的機能の気象情報は: 対象とする注意報・警報が発表されている時に、注意報や警報を補って発表するもの。
決して注意報・警報に代わるものではない。
気象情報の中でも、ある地域で数年に一度しか起こらないような短時間の激しい雨を観測もしくは解析した場合、府県予報官署は
「記録的短時間大雨情報」を発表しており、より一層の厳重な警戒を呼び掛ける。
| 栃木県記録的短時間大雨情報
|
| 平成10年8月27日02時15分
|
| 宇都宮地方気象台
|
|
|
| 02時までの1時間に、那須町付近で100mmを超える激しい雨となっています。現在、栃木県北部に大雨・洪水警報を発表しています。
厳重に注意してください。
|
防災気象情報のうち、一番多い注意報と警報は大雨についてのもので、1地点で1年あたり大雨注意報は30回程度、
大雨警報は5回程度発表されている。なお、平成10年8月末に起きた栃木県那須町を中心にした豪雨災害では、那須町では5日間に
年間降雨量の2/3にあたる1254mmという雨が降った。このときには、警報は26回、記録的短時間大雨情報と大雨情報を合わせて
73回発表される等、まさに非常事態だった。
気象予報区と気象情報:
同じ降雪量でも隣の件では警報が出ない事もある。注意報・警報発表の基準値は、府県予報区の二次細分区域で異なる。
警報・注意報や記録的短時間大雨情報を発表する際には、府県予報区の二次細分区域を対象とした発表基準が有る。
警報の時は「警報基準」に、注意報の時「注意報基準」に照らし合わせて発表している。また、記録的短時間大雨情報にも
発表基準が有る。これらの基準値は予報区によって違っている。
たとえば、雪に強い地域と弱い地域では雪に対する備えと心構えが異なるので、北日本では基準値が高く、東日本や西日本
では基準値が低くなっている。雨の場合は逆に西日本・東日本の方が基準値が高く、北日本では基準値が低くなっている。
なお、府県予報区は、定常的な天気予報の対象となっている一時細分区域と、一時細分区域をさらに細分化し、
警報・注意報の対象となっている二次細分区域に分かれている。福島県を例にとると、次のようになる。
| 府県予報区 | 一時細分区域 | 二次細分区域
|
| 福島県 | 浜通り | 浜通り北部、浜通り南部
|
| 中通り | 中通り北部、中通り中部、中通り南部
|
| 会津 | 会津北部、会津南部
|
気象注意報・警報基準(雨、風、雪・洪水)
| | 札幌
(石狩・空知・後志地方) | 東京
(東京都東京地方) | 福岡
(福岡県)
|
強風注意報
(平均風速) | 陸上:12m/s
海上:15m/s | 13m/s
(八王子 16m/s) | 12m/s
|
| 大雨注意報 | 1時間雨量 | 20mm | 30mm, 多摩西部:50mm | 30mm
|
| 3時間雨量 | 30mm | 70mm, 多摩西部:90mm | 60mm
|
| 24時間雨量 | 50mm, 支笏湖方面:100mm | 130mm, 多摩西部:180mm | 100mm
|
大雪注意報
(24時間降雪の深さ) | 20cm | 5cm, 多摩西部:10cm | 10cm
|
暴風警報
(平均風速) | 陸上:18m/s
海上:25m/s | 25m/s | 20m/s
|
大雨警報
(雨量) | 1時間雨量 | 40mm, 12時間雨量:80mm | 50mm, 総雨量:80mm, 多摩西部:70mm | 50mm
|
| 3時間雨量 | 60mm | 90mm, 多摩西部:120mm | 100mm
|
| 24時間雨量 | 100mm, 支笏湖方面:200mm | 200mm, 多摩西部:250mm | 150mm
|
洪水警報
(雨量) | 1時間雨量 | 40mm, 12時間雨量:80mm | 50mm, 総雨量:80mm, 多摩西部:70mm | 50mm
|
| 3時間雨量 | 60mm | 90mm, 多摩西部:120mm | 100mm
|
| 24時間雨量 | 100mm, 支笏湖方面:200mm
ただし融雪期には雨量と融雪量(相当水量)の合計
| 200mm, 多摩西部:250mm | 150mm
|
大雪警報
(24時間降雪の深さ) | 40cm, 山間部:60cm | 20cm, 多摩西部:30cm | 50cm
|
全般海上警報と地方海上警報:
気象庁は船舶の安全と経済運航および沿岸における波浪や高潮による被害を軽減するために、海上警報を出している。
海上警報には、北西太平洋(東経180度から100度まで、赤道から北緯60度までの海域)を対象とする全般海上予報・警報と、
海岸から200海里以内(約560km)の日本近海を対象としている地方海上予報・警報がある。全般海上予報・警報は気象庁本庁が、
地方海上予報・警報は海洋気象台など主な気象台が発表し、海上保安庁を通じて船舶等へ周知される。
台風の進路予報と台風情報
台風は、日本をはじめ東アジアの国々に大雨や暴風、波浪、高潮等の大きな被害をもたらす、非常に激しい気象現象の一つ。
気象庁は、台風の発生から消滅までを常時監視するとともに、その進路などの予報を行っている。
台風予報は、警報等と同様に防災気象情報として関係省庁や地方公共団体等の防災関係機関に伝達されるとともに、
報道機関を通じて国民に注意や警戒をよびかけるもの。さらに、海上予報の一環として海上保安庁を通じて船舶にも伝えられている。
波浪予報や波浪注意報・警報などに使われる波高(波の頂上から谷までの高さ)は、一般に有義波高を用いる。
これは、ある地点を連続して通過する波のうち、波高値の大きい順に1/3の個数までの波の平均値を表したもの。
防災気象情報における台風の勢力の表現:
小さくても強い風を吹かせる台風もある。台風の勢力は「大きさ」と「強さ」を組み合わせて表現される。
台風の勢力は風を基準として大きさと強さが区分されている。台風の大きさは、風速15m/sの区域(強風域)の広さによって、
強さは中心付近の最大風速の大きさによって区分されている。防災気象情報として台風の勢力を表現する時にはこの「大きさ」
と「強さ」を組み合わせて、たとえば「大型で非常に強い台風」などというように表現される。なお、この
「大きさ」と「強さ」は必ずしも比例するものではない。強風域は狭くても中心付近が通過すれば 30m/s の暴風を吹かせるものもある。
台風の大きさと強さの段階と表現
| 大きさ | 強さ
|
| 強風域の範囲 | 表現方法 | 最大風速 | 表現方法
|
| 200km未満 | (表現しない) | 17m/s以上 25m/s未満 | (表現しない)
|
| 200km以上 300km未満 | 25m/s以上 33m/s未満
|
| 300km以上 500km未満 | 33m/s以上 44m/s未満 | 強い
|
| 500km以上 800km未満 | 大型(大きい) | 44m/s以上 54m/s未満 | 非常に強い
|
| 800km以上 | 超大型(非常に大きい) | 54m/s以上 | 猛烈な
|
台風は強風の他大雨ももたらすが、台風を分類する時には、雨の多少は考慮されない。
台風予報:
予報内容は、台風の位置や大きさ、強さ等。台風の進路予報は、48時間先までは3時間ごと、48~72時間先までは6時間ごとに発表する。
気象庁では、北西太平洋(東経100~180度、赤道~北緯60度)上に存在する台風について常時監視している。
また、予報内容については位置、大きさ、強さなどの実況および48時間先までの進路予報は3時間ごとに、72時間先までの進路予報は
6時間ごとに発表している。
台風の中心が日本からおよそ300km以内に近づき、日本に被害を及ぼす可能性が生じた場合には、気象庁は監視・予報体制を強化して
台風に関する予報や情報を3時間ごとに発表するようになる。また、台風が風速25m/s上の暴風域を伴っている場合には、台風の
実況等を1時間ごとに発表するようになり、よりいっそうの警戒を呼び掛ける。
台風の進路予報に用いられる台風予報円は、12,24,48,72時間先の各予報時刻に、70%の確率で台風の中心がその中に入ると予想される範囲を、
円形の領域で示しており、破線で表される。
一方、台風予報の時に実線で表される暴風警戒域は、台風の中心が予報円の中に進んだ時に暴風域に入るおそれのある範囲を示している。
台風に関する情報:
気象庁では、上記のほかに、次のような台風情報を発表している。
- 台風の「暴風域に入る確率」
48時間先までに台風の暴風域に入る可能性が出てきた場合は、警報・注意報の対象区域(全国362の予報区)ごとに
「暴風域に入る確率」を48時間先まで3時間刻みで発表(6時間ごと)している。これによって「いつごろ暴風域に入る可能性が高いか」
といった時間的な推移が分かる。
- 台風強度の72時間予報
台風の強さ(最大風速と中心気圧)については、72時間先まで予報している。
- 台風の1時間後の推定位置情報の提供
刻々と変る台風の状況をできるだけ早く知らせるため、観測から1時間後の台風の中心位置や勢力を推定して、
これまでの台風情報に加えて発表している。
緊急防災情報ネットワークと土壌雨量指数
緊急防災情報ネットワーク:
これまで気象台から発表される注意報・警報および気象情報は、おおむね文字形式で行われ、それがテレビなどの
報道機関を通じて住民に周知されてきた。しかし、文字だけで行われてきたため、情報の受け手が情報の内容を
理解するのに時間がかかる、ということが問題だった。そこで、気象庁ではこうした点を改善して、状況の緊迫度
をより伝えられるように「緊急防災情報ネットワーク」を運用している。
「緊急防災情報ネットワーク」では、雨雲が停滞する状況と詳細な予測情報に「画像情報」を取り入れる事により、
「解析雨量と降水短時間予報」を平面図を使って表現じている。その一方で、平面図につけるコメントは
「今後もこの激しい雨が続く」というように簡潔にして、情報の受け手が一見して状況を把握できるようにしている。
情報の伝達方法についても、地上回線が切断された場合にも情報が伝達されるように、地上と衛星回線の二本立てになっている。
防災情報が有効に活用される条件として、気象庁は以下の3点を挙げている。
- 情報の内容の正確さ・わかりやすさ
- 情報の発表・伝達の正確さ
- 利用者の正しい理解による的確な対応
土壌雨量指数:
土壌雨量指数とは、降水が土壌中にどの程度蓄えられているかを把握するための指数のことをいう。
大雨による土砂災害の発生は、土壌中に含まれる水分量と深い関係にある。そこで気象庁は、雨による土壌中の水分量を見積もるため、
レーダー・アメダス解析雨量、降水短時間予報および過去の履歴情報を用いて土壌雨量指数を算出し、大雨にともなう土砂災害の
危険性を判断する情報のひとつとしている。
利用方法としては、土壌雨量指数を数値の高い順に並べた「履歴順位」と、過去の土砂災害の発生状況とを比較して、大雨に関する情報
(「平成XX年の豪雨に匹敵する状況、あるいは上回る状況」など)に盛り込んで警戒を呼び掛ける事等が行われる。
土砂災害の危険性を判断する時の留意点として、以下の3点があげられる。
- 既に相当の降雨が有った後に、さらに大雨がある場合が最も危険
- 同じ雨量の場合、短期間に集中する方が危険
- 雨がやんだ後に小ぶりになったときにも発生する
20130421 kokokara
気象災害の概要
気象災害から国民の生命や財産を守る事は防災官庁である気象庁の重要な役割の一つ。
災害に対して的確な判断が下せるように、気象のさまざまな現象と災害との関係について、全般的な知識を身につける。
気象災害の種類と内容
最近では、大都市への人口の集中、山地の開発、急傾斜地での宅地の造成などで、住環境が災害に対して構造的に脆弱になっていて、
気象現象はそれほど激しくなくても、おおきな被害が生じる傾向にある。また、災害の複雑化の度合いが増していて、
暴風雨や地震などの自然現象が起きた時に人間の管理に手落ちが有ったために災害が発生した、という場合などは、
気象災害かどうかの判断が難しくなる。
気象災害には、大雨や台風等短期の気象現象によってもたらされるものと、長雨や少雨など比較的長期の気象現象によって
もたらされるものがある。また、そうした気象現象が直接的に作用して起きる災害もあれば、間接的に作用して起きる
災害もある。気象現象と災害の関係について系統的にみながら、個別の関連性を理解する事がポイントになる。
気象が及ぼす作用:
冷害・干ばつなどの異常気象の予報は困難。長期にわたる異常気象は、気象庁の発表する注意報・警報の対象ではない。
気象災害は、異常な気象現象が原因となって生じる災害のことだが、原因となる現象の種類や規模、被害を受ける対象は多岐にわたる。
このため、気象災害の分類方法にはいろいろあり、下記のように気象現象が被害対象に対してどのように作用しているかで
分類する方法もその一つ。
- 気象が直接的に作用して起きる災害
気象が持っている破壊力で起きる災害。台風や低気圧による強風害、大雨害、大雪害、降雹害など。
- 気象が間接的に作用して起こる災害
気象が被害対象物の性質を変えたり、災害を起こす環境をつくりだす場合。大雨のために堤防が決壊して起こる浸水、
洪水害、崖崩れ、土砂災害、雪崩、融雪洪水など。
- 気象が災害の拡大、激化をうながす災害
強風下の火災、低温による路面凍結による追突事故など。
二次災害:
すでに発生した災害が新たな災害要因となって引き起こされる災害。たとえば、地震による災害の場合、自身の揺れ
そのものによって出た被害は直接の災害(一時災害)。地震によって起こる火災は二次災害。このように、一つの気象現象が災害の
被害を拡大させて行く事が有る。
短期的な気象現象による災害の他に、特定の天候が定常的に続くことでもたらされる災害もある。低温や曇天が長期的に
継続するためにもたらされる冷害や、晴天・無降水が継続するためにもたらされる干害・多照などがそれにあたる。
なお、冷害や干ばつなど、比較的長期にわたる異常気象によって起こる気象災害の予報は、現在の技術では
まだ困難な状況。
気象庁は、気象災害の種類について、直接、間接に関係する気象・海象・水象の要素別に気象災害を分類している。
気象現象と気象災害名の対応
| | 気象現象など | 気象災害名
|
| 風 | 強風 | 強風害、塩風害、乾風害、竜巻害、陸上視程不良害、その他(雪害)、その他(風害)
|
| 竜巻
|
| その他(風)
|
| 雨 | 長雨 | 長雨害
|
| 少雨(長期) | 干害
|
| 大雨 | 洪水害、浸水害、たん水害、山がけ崩れ害、土石流害、地滑り害、強雨害、陸・海上視程不良害、
その他(雨害)
|
| 強雨
|
| その他(雨)
|
| 雪 | 雪崩 | 雪崩害
|
| 融雪 | 洪水害、浸水害、たん水害、山がけ崩れ害、土石流害、地滑り害
|
| 着雪 | 着雪害
|
| 少雪(長期) | 干害
|
| 大雪 | 積雪害、雪圧害、雪崩害、着雪害、陸・海上視程不良害、その他(雪害)
|
| 降雪または積雪
|
| その他(雪)
|
| 気温 | 低温(暖候期) | 冷害
|
| 低温(寒候期) | 凍結害、凍上害、植物凍結害
|
| 高温(夏期) | 酷暑害
|
| 高温(冬期) | 暖冬害
|
| 大気 | 雹(霰) | 雹(霰)害
|
| 雷 | 落雷害
|
| 霜 | 凍霜害
|
上記災害の他に、濃霧や濃煙霧により陸上や海上にもたらされる視程不良害、低温のため海水が船体に着いて凍結して
もたらされる船体着氷害などがある。
たん水害:
浸水後に水がひかないままの状態が何日も続くことによって起こる災害の事。たとえば、洪水等で農地が長時間
水につかることによって、生じる被害の事。
風害時の気象条件:
塩害、火災は強風の間接作用によって起こる。フェーン現象は、空気を乾燥させて火災の危険を高める。
風害には、台風や低気圧さらには竜巻などの強風の風圧の直接的な作用でもたらされる災害と、強風の間接的な作用で起こる
塩害、火災、フェーン現象などの災害がある。
春一番:
通常は、立春以降の春先に、昇温をともなってその年の最初に吹き込む強い南風のことをいう。その暖かく強い風により、融雪洪水、
雪崩などの気象災害や海難事故を起こすことがある。
- 突風
台風、低気圧の中心付近、前線(特に寒冷前線)、季節風、雷、竜巻などは突風をともなうので、強風の直接的な作用による
風害をもたらしやすい現象。突風は季節を問わず発生する。たとえば、春一番や冬型気圧配置による季節風などにともなって発生する。
- 塩害(塩風害)
塩風害は、海上の波頭が砕けて生じる塩水滴が空中に飛び散り、それが強風で陸上に運ばれる事で生じる災害で、
農作物に被害を与えたり、金属類の腐食を早める。また、塩分が送電線や変電所の絶縁部分についた場合、その後の雨によって、
絶縁部分に絶縁不良を起こさせ、停電につながることもある。降雨の少ない風台風のときに被害が出やすくなる。
塩害には、塩風害の他、海水の侵入などでもたらされる塩水害や、冬に起きる塩雪害がある。
- フェーン現象
主に日本海側で乾燥した熱風が吹く現象で、空気が乾燥して火災が生じやすくなる。フェーン現象は、日本海に台風や発達した
低気圧が通過する時に起きやすくなる。特に、春先に発達した低気圧が日本海を通過すると、気温が急に上昇するため、
多雪地帯では融雪による気象災害や雪崩を引き起こす。
水害時の気象条件:
気象だけが災害の原因ではない。局地的な大雨による丘陵地や急傾斜地での土砂災害が増えている。
水害は大雨や融雪などによってもたらされる災害で、洪水害、浸水害、土砂災害、山崩れ害などの間接作用の形であらわれる。
- 洪水害
洪水害は、大雨、長雨、融雪によって発生するもので、集中豪雨が起きやすい梅雨末期、夏から秋にかけての台風の通過時等に
生じやすく、また多雪地帯では気温上昇や大雨による融雪が起きる春先にも発生する。
洪水害には外水氾濫と内水氾濫があるが、最近は特に、都市化による内水氾濫が増えている。これは、コンクリート地面や
舗装道路の増加によって、降った雨が地中に浸透しにくくなった事が原因の一つとされている。
- 浸水害
洪水害が起きるとそれに付随して浸水害が発生する。浸水害は洪水や排水不良のために下水道や用水、湖沼などから水があふれ、
農地や市街地を冠水させる害。
洪水害や浸水害は、台風や集中豪雨の場合の他、雪の多い地域で、春先の急激な気温上昇や降雨によって、山地の雪が大量に
融けてもたらされることがある。この場合、下流の低地で洪水、田畑の冠水、家屋の浸水をもたらすことがあるので、
雪の融ける気象状況が予想される時には融雪注意報が出される。
- 土砂災害
土砂災害は雨や融雪によってもたらされるもので、山崩れ、崖崩れ、地滑り、土石流、落石などがある。
土石流は水が土石を流すのではなく、水を含んだ粥状の土砂が土砂自身の力で移動する現象の事で、雨にともなって発生し、
非常に大きな力で直進する。そのため、発生すると大きな被害となる。また最近では丘陵地や急傾斜地に住居域が拡大したことから、
こうした地域で土砂災害の起こるケースが増えている。
外水氾濫と内水氾濫:
河川の用語では、堤防を境にして堤防内の土地(居住地側)を堤内地といい、河川側の地域を堤外値という。
- 外水氾濫: 大雨などで水位が上昇して河川水が堤防を越えたり、堤防が決壊したりして河川水が堤内地に氾濫すること。
- 内水氾濫: 川に流れ込むべき水が堤内地で氾濫すること。短時間の大雨により、下水・用水溝の排水能力が追い付かずに
雨水があふれる場合や、流れ込む先の河川の水位の方が高いために排水が困難となって小河川や下水・用水溝に逆流し、
あふれる場合等。
土砂災害について:
土石流は、土砂や石が水と一体になって渓流や斜面を一気に流れ下る現象だが、これと似たような現象に次の様なものがある。
- 山津波: 山崩れによって直接生じる土石流の事をいう。地震時に発生しやすく、一般に規模が大きいものとされている。
- 鉄砲水: 短時間の強い雨などにより谷川の水位が急上昇し、堤を切ったように押し寄せる水のことをいう。
山崩れ・崖崩れの土砂が川の流れを堰き止め、それが崩れて土石流になる事もある。
土石流は大雨の末期に発生するといわれるが、そうでなくても発生する。一般的に降り始めてからの降水量が100mmを超え、
かつ1時間降水量20mmを超える強雨が降ると発生しやすくなる。また、その土地の年間降水量の1/10の降水量、というのも
目安になる。
落雷と雹害時の気象条件:
積乱雲が発達すると、雷雨に伴って雹が降る。雹に対する注意は、雷注意報の中で呼びかけられる。
雷には、夏、地上付近の熱と上空寒気のために起こる熱雷、主に寒冷前線の通過に伴って起こる界雷、台風等の上昇気流による
渦雷などがある。いずれも上空に寒気が流入する等の理由で、大気が極端に不安定な状態になるために起こる事が多くなる。
また、雷が発生する時には突風や雹が付随して発生する事が有るので、雷注意報を出す時には、これらの現象の注意も喚起する。
- 落雷害
落雷は、雲中の電荷が地表へ放電されて生じる現象をいう。落雷は直接作用で被害を及ぼし、人体への直撃による死傷や、
電線・電柱などの落雷による停電、企業・家庭の電化製品や電子機器の故障や誤作動などをもたらす。また、家屋や山林への
落雷は火災を発生させる事もある。
- ひょう害
雹は、発達した積乱雲の中で直径5mm以上になった氷晶で、春から秋にかけて雷とともに良く降り、特に5~6月の初夏に多くなる。
雹は農作物などに直撃して被害を与える。
北陸地方を中心に日本海側の地方では、冬季にシベリアからの寒気の吹き出しで生じる雪雲の中で雷が起こる。
しかし、雲形が雷雲としては不明瞭であり、また降雪や低い雲の影響で確認しづらいため、事前に把握する事が困難で、
突然被雷することが多くなっている。
雪害時の気象条件:
雪の害は「降る」「積もる」「崩れる」「融ける」といろいろ。着雪害は、湿った雪が電線などについて発生する。
雪害には、「降る」事によって生じるもの、降った雪が「積もる」ことによって生じるもの、さらに積もった雪が
「崩れる」あるいは「融ける」ことによって生じるものがある。
- 降る→吹雪による視程障害などがある。
- 積もる→家を押しつぶしたりする「雪圧害」、電線に湿った雪が付着して切断させたり、鉄塔の倒壊を招く「着雪害」、
交通障害や交通途絶をもたらす「積雪害」がある。
- 崩れる→雪が崩れて起こる「雪崩」は、特に我が国の場合、雪崩危険地域に居住地や交通路が広がっているため、
防災対策の重要性が大きくなっている。雪崩には春先に起きやすい「全層雪崩」と、真冬におきる「表層雪崩」がある。
- 融ける→水害時の気象条件のところで述べたように、洪水害、浸水害、土砂災害などが「融雪」にともなって生じる。
大雪が降る条件は、日本海側と太平洋側で異なる。日本海側の大雪は西高東低の冬型気圧配置で、気圧傾度が大きく
(等圧線の間隔が狭い)、大気の中層(500hPa面付近)の寒気が強い(たとえば輪島上空500hPaでマイナス35℃以下)ときに起きる。
「全総雪崩」は、積もっている雪と地面の間に雪解け水が入って発生する。「表層雪崩」は、既に積もっている古い
雪の層の上に積もった新雪が、古い雪の層の上を滑って落ちて発生する。
日本海側の大雪でも、山沿いや山間部が大雪になる「山雪型」と、沿岸の平野部で大雪になる「里雪型」では、
それぞれ特徴がある。山雪型は、西高東低の気圧配置で、北西風が強く吹く場合に起こりやすくなる。一方、里雪型は、
等圧線が日本海から沿岸にかけてやや低気圧性の湾曲した状態(袋状)であると、沿岸近くに小低気圧ができやすくなり、
沿岸の平野部に大雪をもたらすもの。
また、太平洋側の大雪は低気圧が太平洋側を通るようになる春先が多くなる。低気圧の中心が八丈島の南を通れば、
関東地方は雪、北を通れば雨というのは1つの実用的な判断としてよく知られている。
太平洋側の雪の予測にあたっては気温も重要な判断基準の一つで、850hPa面で気温がマイナス6℃以下なら雪が
降りやすくなる。さらに地上気温が1~2℃のときに雪が降り続く、という目安があることも予報上留意すべき点。
警報・注意報の伝達
警報・注意報は、以下のようなルートで一般市民に伝達される。こうした伝達体制には、政府機関・地方公共団体・
指定公共機関など、気象庁が気象業務法等で義務付けられている伝達と伝達先(法定伝達先)のほか、周知に努める
伝達と伝達先がある。気象庁では警報・注意報を発表する際には法定の伝達先の他、新聞や民間のテレビ・ラジオなどの
報道機関や、鉄道・バスなどの交通機関にも伝達して、防災気象情報の周知を行うとともに、防災に対する注意を促している。
警報・注意報の伝達体制
| 気象官署→ | →報道機関→ | ラジオ・テレビ・新聞→ | 一般市民
|
| →NHK→ | ラジオ・テレビ→
|
| →NTT→ | 電話→ | 市町村→ | 電話・有線放送・放送・広報車等→
|
| →都道府県→ | 電話・FAX・防災行政無線電話→
|
| →海上保安庁→ | 無線通信等→ | 航海中・入港中の船舶
|
| →国土交通省→ | 通信→ | 航行中の航空機
|
| →防災関係機関(国土交通省ほか) | .....→
|
| →警察・消防など | .....→
|
| →交通機関→ | 列車運行・道路交通安全確保→
|
| →NTT→ | 天気予報電話(ダイヤル177)→
|
気象庁が発表する防災情報は、自然災害に関わる気象・地象・水象に関して、現在起こっている、あるいは起こるおそれのある
事象についての情報を対象としている。被害情報、退避勧告などは、気象庁が発表する防災情報の対象とはなっていない。
練習問題
一般・第1章練習問題
1-1.地球の大気圏高度約80kmくらいまでの乾燥空気の主成分の割合として、多い順に並べた次のうち、
正しいものをひとつ選べ。a
- 水素・酸素・二酸化炭素・窒素
- 水素・二酸化炭素・窒素・酸素
- 二酸化炭素・水素・窒素・酸素
- 窒素・酸素・二酸化炭素・アルゴン
- 窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素
1-2.地球の大気に関する次の記述のうち、誤っているものとひとつ選べ。a
- 原始の地球大気の主成分は、太陽の組成と同じく水素とヘリウムであった。しかし、太陽からの多量の
太陽風が地球に到来し、水素やヘリウムが吹き払われてしまい、その後、地球内部から噴出したガスが長い間に変化して、
現在の地球大気になったと考えられている。
- 二酸化炭素は、空気の主成分に比べると微量ではあるが、有効な温室効果気体として地球の温暖化に大きな
影響を与える。近年、化石燃料の消費などにともない、その大気中の濃度は少しずつ増えている。
- 酸素は、生物の呼吸活動および有害な太陽紫外線を吸収するオゾンの生成に関係しており、
生物には不可欠の成分である。その大気中の濃度は地球誕生以来ほとんど変わっていない。
- オゾンは、主に成層圏に存在して太陽紫外線を吸収し、成層圏の温度形成に重要な役割を果たしている。
また、オゾンには赤外線放射を吸収する温室効果気体としての働きもある。
- 水蒸気は、主に対流圏に含まれ、その量は地域と季節で大きく変動し、単位体積の空気に含みうる最大量は
主に気温に依存する。
1-3.地球大気の鉛直構造に関する次の記述のうち、誤っているものをひとつ選べ。a
- 大局的に見ると、対流圏では高度が上がるとともに気温が下がり、成層圏では高度が上がるとともに
気温が上がっている。
- 成層圏において、高度約20kmあたりから気温が上昇するのは、主としてオゾンが太陽からの紫外線を
吸収し、熱エネルギーに変えることによって大気が暖められるためである。
- 高度約80kmには、大気成分の分子や原子が短い波長の紫外線やX線などによって電離されてできる
自由電子やイオンの密度の大きい層があり、電離層という。
- 大気はその温度分布の違いから下層より成層圏、対流圏、中間圏、熱圏の順に分布している。
- 成層圏と対流圏の間を対流圏界面といい、その高度は、低緯度よりも高緯度の方が低い。
1-4.成層圏オゾンに関する次の記述において、下線部(a)~(d)の正誤の組み合わせ(1)~(5)のうち、
正しいものを一つ選べ。a
成層圏においては、太陽から放射されている紫外線の作用により、酸素分子が乖離されて酸素原子となり、
さらにこれが酸素分子と結合してオゾン分子がつくられる。一方、オゾン分子は別の波長域の太陽紫外線の
作用で酸素分子に乖離する。オゾンは主として(a)極地上空の成層圏で生成されており、
大気の運動によって輸送されて全地球的な分布が決定される。地表から大気上端までの単位断面積の
気層に含まれるオゾン総量の緯度分布は平均的に見ると低緯度地方で(b)少なく、
緯度60度を中心とする高緯度地方で(c)多い。近年、人間が輩出した(d)フロンなどを
原因とするオゾン層の破壊が懸念されている。
| | (a) | (b) | (c) | (d)
|
| (1) | 誤 | 正 | 正 | 正
|
| (2) | 誤 | 正 | 正 | 誤
|
| (3) | 正 | 誤 | 誤 | 正
|
| (4) | 誤 | 誤 | 誤 | 正
|
| (5) | 正 | 正 | 正 | 誤
|
1-5.大気の熱力学に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 静力学平衡の式は、ある高度における気圧が、それよりも上層にある大気の重さに等しいことを
あらわしている。
- 乾燥した空気塊を断熱的に1000hPaまで変化させたときの温度を温位といい、乾燥断熱変化をしている限り、
それに合わせて温位も変化する。
- 相当温位は、水蒸気まで含めた実質的な空気塊の暖かさの尺度であり、凝結の際に放出される潜熱のために、
常に温位よりも温度が高い。
- 持ち上げ凝結高度とは、湿潤空気が上昇し、空気中の水蒸気が飽和して凝結する高度のことで、
これはほぼ雲底高度と考えてよい。
- ある厚さをもった気層が上昇するとき、相当温位が高度とともに減少している状態を対流不安定という。
1-6.高気圧に覆われた晴天の日でも、午後から雲が多くなり、ときには積乱雲が発達して雨が降ることがある。
このことに関する次の文章で、空欄(A)~(E)を埋める語句の組み合わせ(1)~(5)のうち
正しいものを一つ選べ。a
風の弱い晴天時、夜間の放射冷却によって陸地面が冷え、接地逆転層ができる。この層は(A)となっている。
日の出とともに強い日射によって地面が加熱されて、地面に接する大気の最下層は(B)となり、
その上に(C)が鉛直方向にほぼ一様な対流混合層ができ、その厚さは時間とともに増していく。
地面付近から上昇する空気塊は(D)的に冷却し、混合層の上端で飽和することがある。そのとき
混合層より上の待機の成層が条件付不安定なら、空気塊は(E)的に上昇を続ける。
このような場合に積雲や積乱雲が発生する。
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)
|
| (1) | 絶対不安定 | 条件付不安定 | 相当温位 | 乾燥断熱 | 湿潤断熱
|
| (2) | 絶対不安定 | 条件付不安定 | 相当温位 | 湿潤断熱 | 乾燥断熱
|
| (3) | 絶対安定 | 絶対不安定 | 温位 | 湿潤断熱 | 乾燥断熱
|
| (4) | 絶対安定 | 絶対不安定 | 温位 | 乾燥断熱 | 湿潤断熱
|
| (5) | 絶対安定 | 条件付不安定 | 相当温位 | 湿潤断熱 | 乾燥断熱
|
1-7.フェーンに関する次の文章で、空欄(A),(B)を埋める記号と数値の組み合わせのうち、
正しいものを一つ選べ。a
高度2000mの山脈があり、風上側斜面の山麓および中腹3か所の高度と気圧は次の通りであった。
| 地点 | 高度 | 気圧
|
| 山麓 | 0m | 1000hPa
|
| (ア) | 800m | 920hPa
|
| (イ) | 1000m | 900hPa
|
| (ウ) | 1600m | 850hPa
|
この山脈の山麓にあった温度26℃、露天温度18℃の気塊が、風上側の斜面に沿って断熱的に上昇し始めた
この気塊は上記3地点のうち地点(A)で飽和に達する。さらに上昇し続け、山脈の頂上を越えて風下側の斜面を
下降し平地(高度0m)に降りてきたとき、その温度は(B)となった。ただし、簡単のために水蒸気の混合比wはw=0.6e/p,
大気の乾燥断熱減率は10℃/km、湿潤断熱減率は 5℃/km、飽和水蒸気圧の温度依存性は表に
示された値で与えられているものとする。ここでeは水蒸気圧、pは空気圧である。また、凝結した水分は
直ちに全て降水になるものとする。
| 飽和水蒸気圧の温度依存性(温度:℃、飽和水蒸気圧:hPa)
|
| 温度 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10
|
| 飽和水蒸気圧 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12
|
| | (A) | (B)
|
| (1) | (ア) | 32℃
|
| (2) | (イ) | 31℃
|
| (3) | (イ) | 30℃
|
| (4) | (ウ) | 29℃
|
| (5) | (ウ) | 28℃
|
1-8.温位が高度と共に高くなる大気中で、平地で未飽和の気塊が山地を越える時の温位の変化を次の3つの場合について
考える。a
- 山頂に達しても雲が発生しない場合
- 山腹で雲が発生するが、降水は起きない場合
- 山腹で雲が発生し、降水が起きる場合(ただし、山頂では雲が残るものとする。)
をそれぞれの場合の定性的な温位変化の組み合わせとして最も適当なものを次のうちから選べ。
ただし、いずれの場合にも気塊と周囲の空気との間の混合および熱の出入りは無い物とする。
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
|
3本ともAで下がり
Bで上がり、
Cで元に戻る
| Aで下がりBで上がるが、
3だけ元の温位より低い
| 3本とも
Aで上がりBで下がり、
Cで元に戻る
| 1は変化なし、
2,3はA-Bの間で上がり
B-Cの間で下がり、
2は元に戻るが
3はちょっと上がったまま
| 1は変化なし、
2,3はA-Bの間で下がり
B-Cの間で上がり、
2は元に戻るが
3はちょっと下がったまま
|
1-9.降水過程に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 雪片と雨滴では、雪片の方が空気抵抗が大きく落下速度が小さい。
- 海洋上のエーロゾルは、陸上のものに比べて大きく、また単位体積当たりに存在するエーロゾルの数も多い。
- 過冷却な雲の中で雲粒と氷晶が共存する時は、氷晶の方が速く成長する。
- 併合過程で雨滴が成長するには、降水粒子の大きさがまちまちである方が良い。
- 大気中にエーロゾルが多量に含まれると大気の視程を悪化させる。
1-10.降水過程について述べた文章中で、下線部(a)~(d)の正誤に関する次の1~5のうち、正しい物を一つ選べ。a
地面近くの空気塊が、何らかの原因で上空に持ち上げられると気温が下降するとともに相対湿度が増加していき、
ついには飽和に達する。空気塊の相対湿度が100%を超えると、水蒸気が凝結して微小な水滴が出来そうであるが、
空気塊が清浄な場合にはなかなか水滴が生じない。これは、微小な水滴が成長するためには、表面張力に逆らって
仕事をしなければならないが、この仕事を成し得るためには大きな過飽和度(100%を超える相対湿度)が必要になるからである。
しかし実際の大気中では、(a)エーロゾルが存在するために、過飽和度がごくわずかでも水滴が生じることが多い。
このようにして生じた半径1~20μmの水滴は、空気の上昇と共に水蒸気の(b)拡散過程により成長する。
やがて、水滴が有る程度以上大きくなると、十分な(c)落下速度を持つようになる。特に、様々な大きさの水滴が混在していると、
(c)の近いから、大きい水滴が小さい水滴を併合して、その半径が加速度的に大きくなり、雨滴として地上に達する。
このような過程だけによって降る雨を(d)暖かい雨ということがある。
- (a)のみ誤り
- (b)のみ誤り
- (c)のみ誤り
- (d)のみ誤り
- すべて正しい
1-11.次の文章の空欄を埋める語句として適当なものを、次の中から一つ選べ。a
微小な水滴が空気中を落下し、落下速度が一定となる時、水滴に働く重力mgと逆向きに働く空気による抵抗力 6rπηV が
つり合う事が知られている。このとき半径2μmの水滴と半径6μmの水滴の落下速度の比は( )である。ただし、m:水滴の質量,
g:重力加速度, r:水滴の半径, η:空気の粘性係数, V:水滴の落下速度。
(1) 1:9, (2) 1:6, (3) 1:3, (4) 1:2, (5) 2:3
1-12.地球大気の放射特性に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 波長0.3μm以下の太陽紫外線は酸素分子およびオゾンにより吸収されるので、地表にはほとんど達しない。
- 地球大気の成分でもっとも効果的な温室効果気体は二酸化炭素、ついでアルゴンである。
- エーロゾルは、太陽放射を散乱したり吸収したりする事により、地表面に達する太陽放射を減少させる。
- 雲は太陽放射を反射し地表の冷却に寄与する一方で、赤外線を吸収・射出することにより保温するという
放射効果を併せ持っている。
- 二酸化炭素の増加は対流圏の温度を上昇させるが、成層圏では逆に温度を下げる効果を持っている。
1-13.大気放射に関する次の文章で、空欄(a)~(d)を埋める 1~5 の語句の組み合わせのうち、正しい物を一つ選べ。a
下の図は地球大気における単位面積当たりの放射エネルギー輸送量(W/m2)を、模式的に表したものである。
図の矢印と数値はそれぞれの放射エネルギーの流れの向きと量を表している。地球・大気系の熱バランスがとれているとすると、
大気上層から宇宙空間に向かう短波放射量は(a)で、地球・大気系の平均アルベドは(b)と推定される。また、大気に対する
放射過熱量は(c)と推定され、これは地表面からの潜熱と(d)の輸送量の和とつりあっている。
| 短波放射 | 長波放射 |
|
| ↓340 | ↑ | | ↑240 | 大気上層
|
| ↓187 | ↑14 | ↓320 | ↑390 | 大気下層(地表面)
|
| | (a) | (b) | (c) | (d)
|
| 1 | 340W/m2 | 約35% | +103W/m2 | 凝結熱
|
| 2 | 100W/m2 | 約70% | +103W/m2 | 蒸発熱
|
| 3 | 100W/m2 | 約30% | -103W/m2 | 顕熱
|
| 4 | 240W/m2 | 約30% | -97W/m2 | 凝結熱
|
| 5 | 100W/m2 | 約35% | -103W/m2 | 顕熱
|
1-14.地球大気の放射特性に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 黒体とはすべての波長の放射を完全に吸収する理想的な物体をいい、黒体が射出する放射の全エネルギーは、
絶対温度(K)の4乗に比例する。地表面や厚い雲は、赤外放射の波長領域では近似的に黒体とみなせる。
- 水蒸気や二酸化炭素などの気体による赤外放射の吸収や射出は、気体ごとに特定の波長域でなされており、
これらを吸収帯と言う。地球大気には、たとえば11μm付近のように、吸収帯のほとんどない波長域がある。
こうした波長域のことを窓領域(大気の窓)という。
- 地表面の放射冷却は、風の弱い晴天の夜に比べて曇天の夜の方が概して弱い。これは、雲や大気からの下向き
赤外放射を受けて、地表面が正味に放射する赤外放射量が減るからである。
- 空気分子による太陽光の散乱はレイリー散乱と言い、散乱の強さは波長の4乗に反比例し、短い波長の光ほど
強く散乱される。この波長依存性が、青空や赤い夕陽の色の現れるもとである。
- 地表面の約70%は海であり、太陽放射に対する反射率は0.1より小さい。ところが、大気を含め地球全体の
反射率(アルベド)は約0.3である。これは残りの地表面を占める陸面の反射率が高いからである。
1-15.大気中の力の釣り合いについて述べた文章中で、下線部(a)~(d)の正誤に関する次の(1)~(5)のうち、
正しい物を一つ選べ。a
地表面の摩擦や熱的な影響を直接受けない自由大気中の水平規模の大きな流れは、ほぼ(a)コリオリの力と
(b)気圧傾度力のつり合う地衡風平衡にある。このような流れの地表面付近では、(a)と(b)に加え
(c)地衡力が働くため、等圧線を横切る流れが生ずる。渦運動の場合、水平規模が大きくても、極率や風速が
大きいと、(d)遠心力を無視することはできず、(a)と(b)、(d)がつり合う傾度風平衡が成り立つ。
一方、竜巻などの小さな渦では、(a)は重要ではなく、(b)と(d)がつり合う旋衡風平衡が成り立つ。
- (a)のみ誤り
- (b)のみ誤り
- (c)のみ誤り
- (d)のみ誤り
- すべて正しい
1-16. 500hPa面において、地点A(東経135度、北緯25度)での高度を5800m、地点B(東経135度、北緯35度)での高度を5200mとする。
このとき、A-B間の500hPa面で地衡風平衡が成り立つとした場合、地衡風速と風向について正しいものを次の1~5から
一つ選べ。ただし、コリオリパラメータ f: 7.3X10-5/sとし、A-B間の距離は1100km、重力加速度gを10m/s2とする。
a
- 西風 50m/s
- 東風 50m/s
- 西風 75m/s
- 東風 75m/s
- 西風 100m/s
1-17.下図のような円形の等圧線を持った低気圧、高気圧の周辺での空気塊の運動について考える。気圧傾度力の大きさが
同じ場合に、コリオリの力と気圧傾度力とが平行した地衡風速と、さらに遠心力を考慮した傾度風速の強弱関係に関する
次の1~5のうち、正しい物を一つ選べ。なお、下図の矢印は、北半球での風の向きを示している。a
傾度風速は地衡風速に比べて、
- 低気圧では弱く、高気圧では強くなる。
- 低気圧では強く、高気圧では弱くなる。
- 低気圧、高気圧ともに強くなる。
- 低気圧、高気圧ともに弱くなる。
- 低気圧、高気圧ともに同じ。
1-18.大気力学に関する次の1~5の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 温度風とは、鉛直方向の地衡風のベクトル差(鉛直シヤー)のことである。一般に温度風は、等温線(平均温度の線)に対して
平行で、北半球では高温域を右に見る向きになる。
- 地上風は、気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力がつり合って吹く。地上風の風向と等圧線の角度をαとすると、摩擦力
F=fVtanαで求められる(f:コリオリパラメータ、V:地上風速)。
- エクマン層の風の鉛直分布を描くと、高さと共に螺旋になる。これをエクマン螺旋という。
- 大気上層で発散が見られる所には地表面で高気圧が、収束が見られる所には地表面で低気圧が存在する。
- 渦とは、巨視的な運動の間に挟まれて生じる微視的な回転の事であり、その渦の回転の強さの事を渦度という。
渦度は角速度の大きさによって強さが決まる。
解と解説
解答:5:
3番目に二酸化炭素をあげてしまいそうになるのに注意。増えたといってもアルゴンの方が多い。
解答:3:
最初酸素はほとんど含まれていない。その分はCO2だった。光合成で約30億年かけて現在の量になった。
解答:4:
下から、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏。
解答:1:
オゾンは赤道上空の成層圏で主に生成される。オゾン層量の緯度分布は低緯度上空で少なく、緯度
60度付近を中心とした高緯度上空で多くなる。フロンガスは、オゾンを破壊し、オゾンホールを作る。
解答:2:
乾燥した空気の温位は、乾燥断熱変化をしている限り変化しない。相当温位は潜熱分常に温位より
高い。持ち上げ凝結高度=雲底高度、対流不安定は、前線面や山腹において気層が上昇して積雲が出来る要因。
解答:4:
接地逆転層は、下が冷たいんだから「絶対安定」、飽和するまでは「乾燥断熱」、飽和せずに上昇するのは「絶対不安定」、
飽和していなければ「温位」は変化せず、大気成層が条件付き不安定で上昇するなら「湿潤断熱」。
解答:2:
水蒸気の混合比が変らないことを利用して、各地点で飽和するかどうかを比較。飽和するまでは乾燥断熱減率(10℃/km)で温度が下がるものとして
計算。
山麓で26℃、露点温度18℃、表より、飽和水蒸気圧=20hPa、飽和するときの水蒸気混合比=0.6*20/1000
| 地点 | 高度 | 気温 | 気圧 | 飽和水蒸気圧 | 飽和時の水蒸気混合比 | 飽和しているか?
|
| (ア) | 800m | 26-8=18℃ | 920 | 20 | 0.6*20/920= | まだ
|
| (イ) | 1000m | 26-10=16℃ | 900 | 18 | 0.6*18/900=0.6*20/1000 | ちょうど飽和
|
ここから湿潤断熱で16 - 5=11℃が山頂、下りは乾燥断熱で+20℃で31℃。
解答:4:
- 山頂に達しても雲が生じない(未飽和)場合は、乾燥空気の温位は高度が変化しても一定。
- 山腹で雲を生じる(飽和して水滴ができる)が、降水が無い場合は、凝結による潜熱の放出で
山腹から温位が増加し、下降時に降水が無いのでまた潜熱貰って蒸発して元に戻る。
- 降水が有るので、潜熱は降水分失われて、もとには戻らない。
解答:2:
海洋上のエーロゾルは、陸上のものよりも大きいが、数は海洋上の方が少ない。陸上=1010個/m3、
海上=109個/m3。大きな雨粒が小さな雨粒を併合して成長するので、大きさはまちまちである
必要がある。
解答:5:
- わずかな過飽和度でもエーロゾルのおかげで、水滴が生じる。
- 一旦水滴ができたら、過飽和状態なら1~20μmでも拡散過程で凝結していく。
- 大きくなった水滴は、落下速度が大きくなり、小さい水滴を併合していく。
- 降水の拡散過程で氷晶の状態を経て降る雨が「冷たい雨」。経なければ「暖かい雨」。
解答:1:
寸法で3倍。重さで3*3*3=27倍、空気抵抗は、寸法に比例しているから3倍、キャンセルして9倍。
解答:2:
アルゴンは温室効果気体ではない。対流圏の二酸化炭素は、地表面や雲から上向きに出て行く赤外放射を吸収して
対流圏を暖めるので、その分だけ成層圏に達する赤外放射が少なくなり、成層圏の温度を下げている。
解答:3:
- 地球大気の上端からの太陽放射(短波放射)の入射は340であり、地球放射(赤外線の長波放射)
は240なので、地球からの短波放射は340-240=100[W/m2]。
- 地球・大気系の平均アルベドは、大気上端に入射する短波放射340に対する、地球からの短波放射100の
割合の事なので、100/340=0.294≒30%。
- 大気中での放射収支は、短波放射および長波放射を図の矢印で、大気への入射を+、大気からの放射を-とすると、
340+14+390-100-187-240-320=-103[W/m2]。
- 地表から大気への熱輸送量は、潜熱と地表が大気を加熱する顕熱。
解答:5:
大気を含めた地球全体からの太陽放射に対するアルベド(反射能)≒0.3のうち、大気中の雲による反射が約0.2。
したがって、地球全体からの反射率がもっとも大きいのは、雲。海じゃない。
大気による散乱のうち、入射する電磁波の波長がそれを散乱させる粒子の半径よりもずっと大きい場合を「レイリー散乱」、散乱させる
粒子の半径とほぼ同じ場合を「ミー散乱」という。
解答:3:
地衡風平衡とは、コリオリの力と気圧傾度力がつり合っている状態。地表付近では、コリオリの力、気圧傾度力、摩擦力が働く。
水平規模が大きく曲率が大きい渦運動の場合、遠心力も入って来る傾度風平衡。
解答:3:
等圧面上の地衡風平衡の式は、密度がキャンセルされて、f*V=-g*⊿z/⊿n, V=g*⊿z/(⊿n*f),
V=10*(5200-5800)/(7.3*10-5*1100*103)=74.7m/s。気圧傾度は、
北半球で、低緯度から高緯度に向かっているので、西風。
解答:1:
傾度風速は、低気圧の場合は気圧傾度力から遠心力を引いた力、高気圧の場合は気圧傾度力と遠心力を足した力で決まる。
気圧傾度力が同じなので、高気圧の方が大きくなる。
解答:4:
発散が高気圧、収束が低気圧。気圧傾度力:Pn, 摩擦力:F, コリオリの力:fV とすると、F=Pn*sinα, fV=Pn*cosα、
両辺割り算すると、F/(fV)=sinα/cosα, F=fVtanα。
一般・第2章練習問題
2-1. 大規模な大気の運動に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 発達中の傾圧不安定波の構造は、上空の気圧の谷が地上の低気圧の中心の西側に位置している。
- 東西に平均すると、赤道付近の対流圏下層では、通常東よりの風が卓越している。
- 温暖前線や寒冷前線は、もともと存在している南北の温度傾度が水平収束や変形をともなう温帯低気圧の流れのために、
幅100km程度の狭い範囲で強化されたものである。
- 北半球の移動性高気圧や温帯低気圧は、地表の熱を南から北へ輸送する事により大気の熱収支に重要な役割を果たしている。
- 東西に平均された風の場を南北鉛直断面で見ると、各半球で低緯度から中緯度にかけてのフェレル循環、中緯度の
ハドレー循環、高緯度の極循環の3つの平均子午面循環が見られる。
2-2. 温帯低気圧の構造やエネルギーについての(a)~(e)の文章の正誤に関する次の1~5の記述のうち、
正しい物を一つ選べ。a
(a)温帯低気圧の運動エネルギーは、水平温度傾度に起因する有効位置エネルギーが変換されたものである。
(b)温帯低気圧は、熱を輸送する事により、全体として南北温度差を強める。
(c)発達期の温帯低気圧は、南北の熱輸送のため上空ほど気圧の谷が東に傾く構造を持つ。
(d)発達期の上層の気圧の谷の西側には上昇気流、東側には下降気流が有る。
(e)温帯低気圧は、原理的には大気中の水蒸気が存在しなくても発生する。
- すべて正しい
- (a)のみ正しい
- (a)と(e)が正しい
- (b)のみが誤り
- (b)と(c)が誤り
2-3. 傾圧不安定波にともなうリッジとトラフに関する次の文章で、空欄(A)~(E)を埋める語句の組み合わせのうち、
正しい物を一つ選べ。a
下の図は北半球の鉛直断面図におけるリッジとトラフの位置を模式的に示したものである。
地衡風を仮定すると、図の点アでは(A)が吹いている。また、点ア上層の高度場は比較的低く、下層の高度場が
比較的高いことから、厚層が小さく、気温は(B)。一方、点イでは(C)が吹いており、気温は(D)。以上のことから、
リッジとトラフにともなう南北流によって熱が(E)へ輸送される事がわかる。
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)
|
| 1 | 南寄りの風 | 低い | 北寄りの風 | 高い | 南から北
|
| 2 | 南寄りの風 | 高い | 北寄りの風 | 低い | 北から南
|
| 3 | 南寄りの風 | 高い | 北寄りの風 | 低い | 南から北
|
| 4 | 北寄りの風 | 低い | 南寄りの風 | 高い | 南から北
|
| 5 | 北寄りの風 | 高い | 南寄りの風 | 低い | 北から南
|
2-4. 中小規模の大気の運動に関する次の文章の正誤についての1~5の記述のうち、正しい物を一つ選べ。a
(a)積乱雲にともなって発生する降水粒子は、冷却などによって下降気流をつくり、積乱雲の衰弱の要因になる。
(b)気団性雷雨は一般風の鉛直シヤーが弱い時に発生し、寿命は1時間以内である。しかし、一般風の鉛直シヤーが強い時にはスーパーセル型
ストームが発生・発達し、寿命は数時間にも及ぶ。
(c)スパイラルバンドは、台風の目の壁雲の外側に存在する螺旋状の降雨帯で、その風上端で新しい積乱雲が次々に発生し、
風下端で消滅している。
(d)海陸風は、昼は海風、夜は陸風となり、それぞれの上空にも地表面と同じ向きの風が存在する。
- (a)のみ誤り
- (b)のみ誤り
- (c)のみ誤り
- (d)のみ誤り
- すべて正しい
2-5. 積雲対流に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 建造物や農作物に被害を与えるばかりだけでなく、離着陸時の航空機の安全性に重大な影響を与えるダウンバーストは、
積乱雲などの対流性の雲から発生した強い下降気流が地面にあたった後、水平に広がる現象である。
- 風が鉛直方向に一様な場に発生する積乱雲は、大気の不安定度が水平方向に均一であるため、長時間にわたって
維持する事が多い。
- 積乱雲が線状に組織化されたスコールラインは、その下層のガストフロントの通過時に、明瞭な気温の下降と気圧の上昇が
観測されることが多い。
- スーパーセル型のストームは、一つの上昇流を持つ巨大な対流セルからなり、しばしば雹や竜巻、ダウンバーストなど
激しい現象を引き起こす。
- マルチセル型のストームは、多くの対流セルで構成されており、一つ一つのセルが系統的な世代交替を繰り返すため、
ストーム全体としては長時間維持される。
2-6. 台風に関する次の文章における下線部(a)~(d)の正誤の組み合わせ1~5のうち、正しい物を一つ選べ。a
台風は積雲対流に伴って放出される(a)潜熱をそのエネルギー源として発達する渦であるため、
統計的には(b)海面気温が26.5℃以下の海上ではほとんど発生しない。ある程度渦が強くなった後の台風の発達には、
大気境界層の中の気流によって運ばれる(c)顕熱が積雲対流を強め、一方積雲対流は(a)を放出して渦を強めるという、
渦と積雲対流との相互作用により発達を続ける。
台風を取り巻いて流れる円周方向の風速成分は大気境界層の(d)上端で最大になる。発達した台風では、その
眼の周りを壁雲という強い対流雲が取り囲んでおり、その外側にスパイラルバンドという組織化された積雲対流域が存在する。
台風の眼の領域の上部対流圏は、周辺より際立って高温になっている。
| | (a) | (b) | (c) | (d)
|
| 1 | 正 | 誤 | 正 | 誤
|
| 2 | 正 | 誤 | 誤 | 正
|
| 3 | 誤 | 正 | 正 | 誤
|
| 4 | 誤 | 誤 | 正 | 正
|
| 5 | 正 | 正 | 誤 | 誤
|
2-7. 地上から50kmまでの帯状平均(東西に平均)された気温の緯度・高度分布を模式的に示した次の図のうち、
北半球が夏の時の場を最もよく表しているものを一つ選べ。陰影の濃さは、右下に示すスケールの気温(K)に対応している。また、
波線は対流圏界面を示す。a
- 20kmが最低、そこで北極最も冷たく高度50kmで南極暖かい。
- 南極高度10~50kmで冷たく、北極高度50kmで暖かい。
- ほぼ左右対称で、南極高度20kmでやや冷たい。
- 高度40kmで最も冷たく、南極の方がやや冷たい範囲が広い。
- 20kmが最低、そこで南極最も冷たく高度50kmで北極暖かい。
2-8. 成層圏について述べた以下の(a)~(d)の文章の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
(a)オゾンは主として熱帯上空の成層圏において光化学反応によって作られ、中・高緯度へと輸送される。
(b)赤道上空の成層圏下層では、東風と西風が交代する準二年周期振動という現象が観測される。
(c)冬の北半球高緯度の成層圏では、通常、極を取り巻いて流れる西風の渦が卓越しているが、この渦が急激に崩壊し、
これと共に極側で大きな降温が起こる事が有る。
(d)中緯度においては、成層圏から中間圏にかけての冬半球では西風、夏半球では東風が卓越する。
- (a)のみ誤り
- (b)のみ誤り
- (c)のみ誤り
- (d)のみ誤り
- すべて正しい
2-9. 異常気象と気候変動に関する記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 温暖化によって海氷の面積が少なくなると、海氷による日射の反射が減り、地球は一層多くの太陽放射を吸収するので、
温暖化をさらに促進する。
- 温室効果などによる温暖化により、大気に含む事の出来る水蒸気は増加するので、降水量も増加するが、地域によって
乾燥化するところもある。
- 大規模な火山の噴火に起因する成層圏エーロゾルは太陽光を散乱するので、地表面が受け取る太陽放射エネルギーは
減少する。しかし、成層圏エーロゾルは直ぐに落下するので、この影響が1か月以上続くことはない。
- エルニーニョ発生時には、太平洋赤道域の一部で海面水温が高くなり、その地域の大気は海面から暖められる。
また、海面からの盛んな蒸発によって対流活動が活発になり、大気全体が温められるので、その地域の天候に大きな影響を与え、
さらに赤道域に限らず中高緯度にも影響する。
- 化石燃料の燃焼などに起因する対流圏の硫酸や硝酸エーロゾルは、雨粒に溶けて強い酸性雨となって降るため、
地表の生態系に重大な影響を及ぼしている。
2-10. 人為的要因による気候変動に関する次の(a)~(d)の文章の正誤についての記述のうち、正しい物を一つ選べ。a
(a)半乾燥地帯などにおける過剰放牧などに起因する砂漠化は、地表面のアルベドを増大させる事により地表面の熱収支を変化させ、
気候に影響を及ぼしている。
(b)焼畑農業や森林伐採などによる森林の減少は、大気と地表面とのエネルギーや水蒸気の交換に影響を与え、気候変動の要因の
一つになっている。また、森林は炭素循環に深く関わっているので、森林の減少は、この面でも気候変動に影響を与えている。
(c)人間活動によって放出される熱エネルギは、直接大気を暖め温暖化をもたらすが、現在放出されているエネルギーは、
地表面-大気系が吸収する太陽放射エネルギーの0.01%のレベルであり、その直接の影響は人口の密集した都市域に限られている。
(d)化石燃料の消費や農業あるいは工業活動に伴い、大気中に放出される二酸化炭素・メタン・フロンなどの気体濃度の増加は、大気の
温室効果を増大させて地球の温暖化をもたらす。
- (a)のみ誤り
- (b)のみ誤り
- (c)のみ誤り
- (d)のみ誤り
- すべて正しい
2-11. 北半球で測定された近年の二酸化炭素濃度の時間変化について述べた次の文章で、下線部(1)~(5)のうち、
誤っているものを一つ選べ。a
大気中の二酸化炭素濃度は季節変化をしており、その振幅は一般に赤道付近よりも北半球中高緯度の方が(1)大きく、
また夏に濃度が(2)最低になる。これは、(3)海洋の温度の季節変化が原因である。また、この変化を除けば、
二酸化炭素濃度は年々(4)増加している。このことが地球の(5)温暖化の原因の一つと考えられている。
解と解説
解答:5:
東西に平均された風の場を南北の鉛直断面でみると、
- 低緯度から中緯度→ハドレー循環→地表付近で東風
- 中緯度→フェレル循環→地表付近で西風
- 高緯度→極循環→地表付近で東風
北半球の温帯低気圧は、低緯度側の暖気を前方(東側)から取り入れ、高緯度側の寒気は後方(西側)から取り入れる。
また、移動性高気圧は、この逆のメカニズムが働く。いずれも、北半球中緯度における南北の熱輸送に重要な役割を担っている。
解答:3:
- (a)温帯低気圧のエネルギー源は、水平温度傾度に起因する有効位置エネルギーが運動エネルギーに変換されたもの→○。
- (b),(d)温帯低気圧では、低緯度側の暖気を前方(東側)から取り入れ、このとき暖気は上昇していく。高緯度側の寒気は
逆に後方(西側)から取り入れ、寒気は下降する。したがって、南北の水平温度傾度は弱まる。それ以前にエントロピ増大の法則→×。
- (c)温帯低気圧の東側に暖気、西側に寒気があるということは、等圧面の層厚が東側で厚く西側で薄く、必然的に気圧の谷は
高さと共に西に傾く事になる→×。
- (e)水蒸気の潜熱発生は、上昇気流を強化し、有効位置エネルギーを作り出すので、発達を促す効果はあるが、温帯低気圧の
発達そのものに不可欠ではない。このことは、数値シミュレーションによって乾燥大気中の傾圧不安定だけで、温帯低気圧の
一生を再現することからも証明されている→○。
(a)と(e)のみ正しい。
解答:4:
- 気圧傾度力とコリオリの力とが釣り合って吹いている地衡風は、北半球では低緯度側の高気圧を右にして吹く。
- 傾圧不安定波によって、気圧の尾根は北へ、気圧の谷は南へと張り出す。
- 等圧面の高度差である層厚は、その気層の平均気温に比例する。
これらのことから、トラフの左側である点アでは、北から南への「北寄りの風」が吹き、層厚が小さいので
気温は「低い」。トラフの右側である点イでは、南から北への「南寄りの風」が吹き、層厚が大きいので気温は
「高い」。高緯度側の寒冷な空気が低緯度側へ移動し、低緯度側の温暖な空気が高緯度側へ移動するため、
熱は「南から北」へ輸送される事になる。
解答:4:
- (a)降水によって発生する積乱雲下部の下降気流は、上部への暖湿気の補給を断ってしまうため、積乱雲は急激に衰弱する→○。
- (b)気団性雷雨とスーパーストーム型ストームの違いに注意→○。
- (c)スパイラルバンドは、一般に台風の眼の壁雲より背の低い積乱雲出構成されている→○。
- (d)海陸風は、垂直方向にぐるっと循環している。上空では、地表面とは逆向きの反流が吹く→×。
解答:2:
風が鉛直方向に一様な場であるときに発生する積乱雲では、雲粒を生成する上昇流と下降する降水粒子に伴う下降流とが
ほぼ同じ高度で生じる。このため下降流が上昇流を妨げる事になり、大気の不安定度は長時間維持される事は無く、
積雲対流の活動は数十分程度で終わる。なお、鉛直シヤーが強い場合には、積乱雲の寿命は長くなる。
解答:2:
- (a)台風の積雲対流を発生させるエネルギー源は、水が蒸発する時に得た蒸発熱を、凝結時に潜熱として放出することで得られる→○。
- (b)台風が勢力を強めるには、そのエネルギー源となる水蒸気を多量に含んだ高温空気の上昇が必要で、その条件として、
海面水温が26.5℃以上であることが統計的に知られている。海面気温ではない→×。
- (c)発達した熱帯低気圧の渦により上昇する空気中の水蒸気が、潜熱を放出することで積雲対流が強められる。
顕熱ではない→×。
- (d)台風の渦としての風速成分が最大となるのは、積雲対流の渦の境界層の上端になる→○。
解答:5:
- ア.対流圏の気層は赤道付近が最も厚いため、対流圏界面の高度は赤道付近が最も高くなる。
また対流圏では、高度と共に気温が下がるので、赤道付近の対流圏界面(高度約20km)の気温は、同じ高度の中緯度や高緯度の気温に比べると
低くなっている。これは、中緯度や高緯度では既に成層圏に入っているので、高度があがっても気温は下がらないため。
- イ.成層圏中層(高度約20~30km)の気温は、北半球の夏(南半球の冬)では、夏極で比較的高く、冬極で低くなっている。
以上の特徴を表現している図は、アに該当するのが1と5、この中で、イに該当するのが5。
解答:3:
冬の北半球高緯度の成層圏における突然昇温。降温ではない。成層圏では極を中心にした低気圧性の西風である極渦が吹いているが、
冬から初春にかけ、対流圏内に生じる超長波の活動による影響を受けて、この極渦は崩壊する事が有る。その際、
極を中心とした下降気流によって断熱昇温が起きるため、気温は大きく上昇する。
解答:3:
大規模な火山噴火では、微粒子の火山灰が高さ20~30kmの成層圏に達し、これらは成層圏エーロゾルとして
太陽光を散乱するため、地表面へ到達する太陽放射エネルギーは減少する。また、微粒子の成層圏エーロゾルは
成層圏で浮遊しており、なかなか地表へは降下してこないので、エーロゾルによる太陽放射エネルギーの減少は、
数か月~数年間継続する事がある。
海氷は、海水面よりアルベドが大きいので、海氷面が少なくなると、温暖化スパイラルの可能性あり。
温暖化が進むと、飽和水蒸気圧が大きくなって、大気中に含みうる水蒸気量が増え、降水量が増加する可能性と、
飽和水蒸気量が大きくなっても、空気中の水蒸気量が変らないと、相対湿度が下がって乾燥する可能性が考えられる。
したがって、降水量の増える地域と、乾燥化が進む地域の両方が考えられる。太平洋赤道域の現象であるエルニーニョ現象は、
テレコネクションのために、中・高緯度の天候にも影響する。
解答:5:
すべて正しい。
解答:3:
海洋の温度よりも、中緯度の日照による光合成の変動の方が二酸化炭素濃度の変動に大きく影響する。
一般・第3章練習問題
3-1. 気象業務法の目的および定義に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象業務法の目的は、気象業務の健全な発達を図る事により、災害の予防、社会秩序の維持、産業の興隆など公共の福祉に寄与するとともに、
気象業務に関する国際的な協力を行う事にある。
- 「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定のことをいう。
- 「予報」とは、観測の成果にもとづく現象の予想の発表のことをいう。
- 「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報のことをいう。
- 「気象機器」とは、気象、地象および水象の観測に用いる器具、機械および装置のことをいう。
3-2. 気象庁が行う警報に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象庁は、気象、津波、高潮、波浪、洪水についての一般の利用に適合する警報をした場合には、直ちに、
その気象事項を国土交通省に通知しなければならない。
- 気象庁は、津波についての一般の利用に適合する警報をした場合には、直ちに、その警報事項を
警察庁または都道府県警察に通知しなければならない。
- 気象庁は、気象、地象、津波、高潮、波浪についての航空機および船舶の利用に適合する警報をした場合には、
直ちにその警報事項を国土交通省や海上保安庁に通知しなければならない。
- 気象庁は、気象、高潮、洪水についての水防活動の利用に適合する警報をした場合には、直ちにその警報事項を
国土交通省、都道府県、NTTに通知しなければならない。
- 気象庁は気象、津波、高潮、波浪、洪水についての一般の利用に適合する警報をした場合には、直ちに
その警報事項を日本放送協会に通知しなければならない。
3-3. 次の(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。1~5のうちから正しいものを一つ選べ。a
- (a)気象庁以外の者が行える予報業務は、気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水についてである。
- (b)予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務を行う事業所ごとに、必要数の、専任の気象予報士を置かなければならない。
- (c)許可された予報業務を休止・廃止した場合には、その日から60日以内に気象庁長官に届け出なければならない。
- (d)予報業務の許可を受けた者が気象業務法の規定に違反した場合、気象庁長官は、期間を定めて業務を停止させる
ことができるほか、許可そのものを取り消す事ができる。
1.0個、2.1個、3.2個、4.3個、5.4個
3-4. 気象庁以外の者が行う予報業務に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 予報業務の許可を申請する時には、申請書に予報業務の目的と範囲を記載する必要がある。なお、
予報業務の目的とは、特定向け予報や一般向け予報など予報業務の提供の目的の事をいい、予報業務の範囲とは、
予報の種類、期間、予報の対象となる地域のことをいう。
- 観測施設を設置する場合は、気象庁長官に届け出なければならない。
- 気象業務の許可を受けた者が気象観測を行う時には、一定の技術上の基準に従って行う事になっている為、
気象庁長官の検定を受けて合格した気象測器を使用しなければならない。
- 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の目的および範囲に関わる気象庁の警報事項を、当該予報業務の利用者に迅速に
伝達するように努めなければならない。
- 津波、高潮、洪水の予報業務の許可を受けている民間気象事業者のうち、気象庁の警報を適時に受ける事が出来ない地域で
業務を行っていると気象庁長官から指定を受けた事業者は、当該予報地域で津波、高潮、洪水のおそれが生じた場合、
当該予報業務の目的と範囲内で津波、高潮、洪水の警報をしなければならない。
3-5. 次の行為のうち、予報業務の許可を受けなければできないものを一つ選べ。a
- 学校の教師が、校長から依頼を受けて、運動会の開催の可否の判定のため天気の予想を行う。
- 観光協会から請け負い、インターネットの観光地紹介のホームページに、気象庁の発表したその地の天気予報を入力する。
- 商社の依頼に応じて、外国の天気予報を収集して提供する。
- スーパーマーケット業界に対し、売上予測に必要な局地的な気象の予想を提供する。
- テレビのウェザーキャスターとして天気予報の解説を行う。
3-6. 気象予報士に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験に合格しなければならない。
- 気象予報士となる資格を有する者は、気象庁長官の登録を受け、気象予報士になる事ができる。登録申請にあたっては、
期限は設けられていないので、いつでも登録を申請できる。
- 気象予報士が自ら予報業務を行おうとする場合には、気象庁長官の許可を受けなければならない。
- 気象予報士は、氏名や住所など登録内容に変更があったときには、すみやかに、その変更内容を気象庁長官に
届け出なければならない。
- 偽りその他不正な手段により気象予報士の登録を受けた者は、気象予報士の登録が抹消される。このような形で
登録を抹消されたものは、以後、気象予報士になることができない。
3-7. 気象予報士に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。a
- (a)予報業務のうち現象の予想と発表は、気象予報士に行わせなければならない。
- (b)気象予報士は、3年ごとに登録を更新しなければならない。
- (c)気象予報士が交通事故を起こし、罰金刑を受けた場合、気象予報士の登録を抹消される。
- (d)気象予報士は「気象予報士登録抹消申請書」を提出する事により、登録を抹消できる。
1.0個、2.1個、3.2個、4.3個、5.4個
3-8. 気象予報士であっても行ってはならない事に関する次の記述のうち、該当するものを一つ選べ。a
- 自分が勤める会社の社員旅行の日の天気を、幹事に委託されて予想する。
- 気象庁が行った天気予報を電光掲示板に表示する。
- 予報業務の許可を受けた者が契約企業に対して、気象庁の警報基準に従って高潮警報を出した。
- 予報業務の許可を受けている市役所に勤め、その市の天気予報を市民向けに行う。
- 全国ネットのテレビやラジオの気象情報番組で天気予報を解説する。
3-9. 以下の(a)~(c)の文の正誤に関する次の1~5のうち、正しい物を一つ選べ。a
(a)気象庁長官の命を受けて、私人の所有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを拒んだ場合、罰金が処せられる事が有る。
(b)研究や教育のために行う観測である場合は、必ずしも記述上の基準に従わなくてもよい。
(c)政府機関や地方公共団体が、気象庁長官に届け出て既に設置してあった観測施設を廃止する時には、
気象庁間に届け出なければならない。
1.(a)のみ正しい、2.(b)のみ正しい、3.(a)と(c)が正しい、4.(b)と(c)が正しい、5.すべて正しい
3-10. 次の1~5の行為のうち、気象業務法に罰則が規定されていないものを一つ選べ。a
- 河川の流量を予測するために電力会社が設置している雨量計を壊した。
- 許可を受けないで、気圧の予報の業務を行った。
- 許可を受けないで、風向・風速の観測値を広告塔に表示した。
- 許可を受けないで、フェリー会社に対して波浪の予報業務を行った。
- 気象予報士が、自分の行った気象観測の成果を、許可を受けないで、国外の気象業務を行う機関が受信する事を目的に、
無線通信により発表した。
3-11. 災害対策に関する次の文章内の下線部1~5のうち、誤っているものを一つ選べ。a
災害対策基本法は、(1)国土ならびに国民の生命、身体および(2)財産を災害から保護するため、防災に関し、
(3)国、地方公共団体及び民間のすべての機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、
計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する(4)財政金融措置その他必要な災害対策の
基本を定める事により、(5)総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の
福祉の確保に資することを目的とする。
3-12. 災害対策基本法に関する次の文章で、空欄(a)~(d)を埋める語句の組み合わせ1~5のうち、正しいものを一つ選べ。
a
災害対策の総合性を確保する等のため、総理府に(a)を会長とする(b)が置かれている。この(b)は、防災業務計画や地域防災計画の作成の
基準となる(c)の作成・実施の推進、非常災害時の緊急措置計画の作成・実施の推進などを行う。また(a)が指定する
指定行政機関は、(c)にもとづいた所管事務に関する(d)の作成・実施等を行う。
| | (a) | (b) | (c) | (d)
|
| 1 | 内閣総理大臣 | 中央防災会議 | 防災基本計画 | 防災業務計画
|
| 2 | 内閣総理大臣 | 災害対策本部 | 防災業務計画 | 防災業務計画
|
| 3 | 内閣総理大臣 | 中央防災会議 | 防災業務計画 | 地域防災会議
|
| 4 | 国土交通大臣 | 災害対策本部 | 防災業務計画 | 地域防災会議
|
| 5 | 国土交通大臣 | 中央防災会議 | 防災基本計画 | 防災業務計画
|
3-13. 以下のa~dの事項の発表者の組み合わせとして、次の1~5の語句の組み合わせのうち、正しいものを一つ選べ。
a
- (a)都道府県またはその細分地域を対象として、その地域内で洪水の発生するおそれのある場合に行う洪水警報
- (b)2以上の都道府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずる
おそれがあるとしてあらかじめ指定された河川を対象として、流量、水位を示しておこなう洪水予報
- (c)洪水または高潮により災害が発生するおそれのある場合に河川・湖沼・海岸について行う水防警報
- (d)災害が発生し、または発生するおそれのある場合に、必要と認められる地域の居住者、滞在者等に対して行う非難のための
立ち退き勧告
| | (a) | (b) | (c) | (d)
|
| 1 | 気象庁長官 | 気象庁長官 | 国土交通大臣 | 市町村長
|
| 2 | 気象庁長官 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 都道府県知事
|
| 3 | 気象庁長官 | 気象庁長官および国土交通大臣 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 市町村長
|
| 4 | 国土交通大臣 | 気象庁長官および国土交通大臣 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 都道府県知事
|
| 5 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 | 気象庁長官 | 都道府県知事
|
3-14. 次の防災関係情報のうち、気象庁から発表されないものを一つ選べ。a
1.海上警報、2.火災警報、3.乾燥注意報、4.洪水警報、5.津波警報
3-15. 以下の記述のうち、誤っているものを一つえらべ。a
- 災害対策基本法で定められている指定公共機関とは、内閣総理大臣が指定する公共的機関および公益的事業を営む法人のことである。
公共的機関のうち、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会は法律に明記されている。
- 都道府県には、都道府県知事を会長とする都道府県防災会議が置かれており、都道府県地域防災計画を作成・実施するほか、
災害が発生したときには、関係機関の連絡調整を図る。
- 気象庁長官は、気象等の状況により洪水又は高潮のおそれがあると認められるときには、その状況を国土交通大臣や
都道府県知事に周知しなければならない。
- 国土交通大臣は、水防警報を行った時には、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知するよう努めなければならない。
- 気象庁長官や各気象台長などは、気象の状況が火災の予防上危険であると認める時には、その状況を、その地を
管轄する都道府県知事に通報しなければならない。この通報を受けた都道府県知事は、これを市町村長に通報しなければならない。
解と解説
解答:1:
業務法第1条に「...気象業務の健全な発達を図り、もって災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与する...」
とあり、「社会秩序の維持」が間違い。
解答:1:
気象庁が国土交通省に通知しなければならないのは、気象、高潮、洪水についての水防活動の利用に適合する警報。
解答:4:
(c)の60日が誤り。30日が正しい。
解答:5:
民間気象事業者は、警報を出すことはできない。
解答:4:
4は、自分の立てた予想を外部に提供するので、「予報業務」となり、許可が必要。
解答:5:
偽りその他不正な手段により気象予報士の登録を受けた者は、気象予報士の登録を抹消される(業務法第24条の25)が、その
処分の日から2年を経過したら、登録する事が出来る(業務法第24条の21)。
解答:2:
(a)予報業務のうち、気象予報士でなければできないことは、現象の予想だけ。発表は気象予報士でなくてもできる。
(b)登録更新についての規定はない。(c)交通事故は関係ない。正しいのは(d)だけ。
解答:3:
気象庁の判断基準に従っていても、気象庁以外の者が警報を出すことはできない。
解答:5:
すべて正しい。
解答:3:
3既に発表されている風向・風速の値の発表なのでOK。
解答:3:
「国、地方公共団体及びその他の公共機関」が正しい。
解答:1:
総理府には内閣総理大臣を会長とした中央防災会議が置かれている。中央防災会議が作成・実施するのは、防災基本計画であり、
中央防災会議で指定する指定行政機関が作成するのは防災業務計画。
解答:3:
普通の警報→気象庁長官、ややこしい川→気象庁長官及び国土交通大臣、水防警報→国土交通大臣または都道府県知事、避難勧告→市町村長。
解答:2:
火災警報は、市町村長が出す。問題のそのほかは、気象庁が出す。
解答:4:
4→国土交通大臣は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼、海岸について、その必要がある時には水防警報を行い、
その警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。しかし、報道機関に協力を求めて一般に周知することはない。
専門・第1章練習問題
4-1. 気象庁の地上気象観測に関する次の記述から、誤りを一つ選べ。答えと解説
- 地上気象観測における観測時刻は、国際的には協定世界時(UTC)に統一されている。国際気象通報式に表す時刻は
UTCを用いるが、その他はおおむね日本標準時(JST)を用いる。
- 気温の観測は、地上約1.5mの高さを基準としており、多雪地では雪面上約1.5mになるように測器の高さを調節する。
- 現地気圧を海面更正する時には、観測地点と平均海面の間の気温と湿度が観測地点の値に等しいと仮定して、静力学平衡の式と
状態方程式を用いて平均海面での気圧値を算出する。
- 気圧変化の型は、観測時間3時間内の気圧変化の特徴を示すもので、9種類の分類中から最もよく表現しているものを選ぶ。
気圧変化の量は、観測時と3時間前の気圧の差で、観測時の気圧が高い場合を正とする。これらは、気圧等変化線図の解析や寒冷前線通過の
判断資料に利用される。
- 塩化リチウム露点計は、塩化リチウムに吸湿性が有る事を利用して露点温度を求める測器である。相対湿度は、
その露点温度における飽和水蒸気圧とそのときの気温における水蒸気圧との比を百分率で表したものである。
4-2. 気象庁の地上気象観測に関する以下の記述のうち、誤っている物を一つ選べ。答えと解説
- 雲形別の雲量は、その雲によって覆われた部分の全天空に対する割合であり、2種類以上の雲形の雲が有るときには、
それぞれの雲量の合計は全雲量と一致する。
- 雲形は、WMOの規定に従って10種類に分類する。この分類はよく現れる高さによって上層の雲、中層の雲、下層の雲に
大別されるが、下層の雲には雲頂が中・上層まで達するものもある。
- 日射の観測は直達日射量、全天日射量、日射時間などについて行う。直達日射とは、地表に直接到達する日射を言う。全天日射は、水平面に
入射する直達日射と全天からの散乱日射等の総和を言う。日射時間は、直達日射量が、ある一定の値以上に達した時間と定義されている。
- 可照時間とは、太陽の中心が東の地平線または水平線に現れて西の地平線または水平線に没するまでの時間の事である。なお、
可照時間に対する日照時間の相対比を日照率と言う。
- 全雲量については、全ての雲に覆われた部分の全天空に対する見掛け上の割合を0~10の整数および0+、10-として
観測する。
4-3. 気象庁の地上気象観測に関する次の文章で、下線部1~5のうち、誤っているものを一つ選べ。答えと解説
風向・風速計は、平らで開けた場所を選んで、地上10mの高さに設置する事を基準としている。
1.10mより高いところで観測したデータは、地表の摩擦を考慮した換算式によって10mの高さに換算して通報する。
風向は2.風の吹いてくる方向をいい、南風といえば南の方向から吹いてくる風の事を言う。風速は、空気が移動した
距離とそれに要した時間との比である。風向・風速は絶えず変動しているので、瞬間値と平均値について観測する。瞬間風向・風速は、
ある時刻の風向・風速であり、3.平均風向・風速は、観測時前30分間の平均値である。雨や4.雪、あられ、ひょうなどの
固形のものも含めて全ての水を言い、降水量は、ある時間内に水平な地面に溜まった水の量のことである。
降水量を正確に測るために、5.降雨計は、できるだけ気流が水平で、乱れが少ない場所を選んで設置する。したがって、
ビルの屋上や屋根の上に設置するのは好ましくない。
4-4. 地域気象観測システム(アメダス)に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- アメダスとは、自動気象観測装置で観測された気象データを自動的に収集するシステムである。アメダス観測所は全国で約1310ヶ所
あり、これは17km四方に1ヶ所の割合である。
- アメダスでは、速報性を重視する事から観測値に対する品質管理はなされていない。
- アメダスで得られる気象要素は、降水量、気温、風向・風速、日照時間および積雪である。
このうち殆どの地点で観測されているものは降水量だけである。
- アメダスの観測所で強い雨や風を観測した場合は、毎正時以外であっても、自動的に通報される。
- 全国約1310ヶ所のアメダス観測所のうち、約850ヶ所では降水量の他に、風向・風速、気温、日照時間の4要素を観測している。
この4要素の観測は、約21km四方に1ヶ所の割合で実施されている。また、豪雪地帯では約290ヶ所に積雪計が設置されて、
積雪の深さを観測している。
4-5. 気象庁の高層気象観測に関する次の文章で、下線部1-5のうち誤っているものを一つ選べ。a
気象現象を理解するには、大気の立体構造の把握が不可欠である。高層気象観測は、(1).対流圏から成層圏にかけての
大気の状態を観測するもので、代表的なものに、気圧、気温、湿度を観測するラジオゾンデ観測と、高度約5kmまでの
風向・風速を観測するウィンドプロファイラ観測がある。
ラジオゾンデ観測では、気圧、気温、湿度の各センサーと無線送信機を気球に吊り下げて飛揚し測定値を地上で受信する。
気球の上昇に伴って変化する気圧、気温、湿度の値から、気体の状態方程式と(2).静力学平衡の式を使って気球の高度を計算する。
ウィンドプロファイラ観測では、地上から上空に向けて発射した電波の周波数と、大気の乱流で散乱した電波を受信したときの周波数の
違いにより、観測点上空の風向・風速を測定する。気象庁では、(3).周波数1.3GHzの電波を用いて、高度約5kmまでの風を
(4).1時間ごとに観測している。
高層気象観測の結果は、(5).数値予報に用いられるほか、高層天気図の作成やエマグラム解析などhに利用される。
エマグラムとは、大気の熱力学的状態を解析するための線図で、大気が安定化不安定化を判別する場合などに使われる。
4-6. 気象庁の高層気象観測に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象庁では、日本標準時で毎日9時と21時にラジオゾンデ観測を行っている。
- ラジオゾンデ観測では、気圧、気温及び湿度の各センサの入ったラジオゾンデを気球に吊り下げて行う。
ラジオゾンデ観測は、高層気象観測所で行われる。
- 高層風は、ラジオゾンデの高度と地上の方向探知機で測定される方位角、高度角から計算する。
方位角の単位は度で、北から時計回りに一周して再び北に至るまでを0~360度とする。いま、上昇中のラジオゾンデが
方位角90度付近にあり、その方位角値が時間と共に減少しているとすると、その高度における風の南北成分は南向きである。
- ウィンドプロファイラは、災害をもたらす集中豪雨にとって重要な役割を果たす下層大気の流れを精密に観測できるため、
メソ数値予報の精度向上に特に大きな効果がある。
- ウィンドプロファイラは、全国31ヶ所に設置されている。
4-7. 気象庁のラジオゾンデ観測に関する次の記述の位置、誤っているものを一つ選べ。a
- ラジオゾンデ観測に使用するラジオゾンデには、気圧計、温度計、湿度計、風向風速計が搭載されている。
- 高層気象観測で得られたデータは、国際気象通報式に基づき、指定気圧面の値(気温、風向・風速など)と特異点の値に分けて
世界中に通報されている。指定気圧面とは、気圧が1000,925,850,700,500hPa等の等圧面であり、特異点とは、気温や湿度の変動点および
風の特異点(最大風速の点、風速が静穏である点など)をいう。
- ラジオゾンデの高度は、大気中を上昇しながら観測した気圧、気温、湿度値から、気体の状態方程式と静力学平衡の
関係を使って気層の厚さを計算し、これを積分して求める。
- 日中のラジオゾンデ観測においては、日射が気温センサーの感部に当たって気温の観測値に影響を与えるので、
日射補正を行う。
- 高層気象観測によって得られた各等圧面における風向・風速、高度、気温、湿数などの観測値は、
高層天気図に記入され、等高度線や等温線等が描かれた高層天気図ができる。
4-8. 気象レーダーに関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象レーダーは、レーダーアンテナからパルス状の電波を発射し、その電波が大気中の降水粒子(雨粒や雲粒など)
によって反射されて戻って来るまでの時間から、降水粒子までの距離と方位を測定する。
- 気象レーダーは、降水エコーをキャッチする事を本来の目的としているが、同時に、山や海岸などの地形から
反射してくる地形エコーも観測する。このため現在では、シークラッターやエンゼルエコーなどを含め、地形エコーを
完全に除去している。
- 気象レーダーの探知範囲は、レーダーアンテナが設置された高さにより異なる。また、レーダーアンテナの直径が大きいほど
探知範囲は大きくなる。
- 気象レーダー観測では、受信したレーダーエコーの強さによって、降水の程度を判断する。受信したレーダーエコーの
強さの事をエコー強度といい、これに影響を与える要因の関係を数式に表したものを、気象レーダー方程式と言う。
- 気象ドップラーレーダーは、移動中の目標である降水粒子から反射される電波のドップラー効果を利用して降水粒子を測定する。
4-9. 気象レーダー観測に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- レーダーエコーには、ある高度で水平に広がるエコー強度の強い部分が見られる事が有る。これはブライトバンドと呼ばれ、雪が
融けながら落下している層に対応している。
- 降水の監視に用いられる気象レーダー画像は、レーダーアンテナの高度角を順次変化させて得られた複数の画像データのエコーを、
高度がほぼ一定となるように合成して作られる。
- 降水粒子がレーダーから遠ざかる時は、反射した電波の周波数は送信電波の周波数よりも低くなり、近づく時は高くなる
ことを利用して動径方向の風速を測定している。
- 水と氷ではレーダーの電波を散乱させる性質に違いがある。このため目標が水なのか氷なのかを判別したうえで、
降水強度を算出している。
- レーダー・アメダス解析雨量図は、レーダー観測で求めた1時間積算降水強度を同時刻のアメダスの降水量で補正して作成される。
4-10. 気象ドップラーレーダーは、降水粒子のレーダーからみた動径方向の速度成分を測定する。
このレーダーから見た動径方向の速度成分をドップラー速度といい、通常はレーダーから遠ざかる場合を
正(+)、近づく場合を負(-)で表す。地表付近の観測結果を表した下図の1-5のエコーの模式図のうち、
図の中心部付近で地上付近の収束を明らかに推定できるのはどれか。a
4-11. 「ひまわり」の観測データに関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 可視画像では、太陽に照らされている地球部分のみが表現される。したがって光の射さない夜間は写らない。
- ジェット気流に沿い、流れの方向に対してほぼ直角の走向を持つ規模の小さな巻雲の列が観測される事が有る。
この巻雲の列のことをトランスバース・ラインという。
- 寒冷前線の南側の暖域内で、際立った縁を持ち、毛筆の穂先状またはニンジン状をしたテーパリング・クラウドを観測する事が有る。
これは活発な積乱雲の連なって構成されたものである。
- 気象庁が配信している赤外画像は、雲頂高度が高い(雲頂温度の低い)雲ほど白く表示される。
- 「ひまわり」に搭載されている水蒸気センサは6.5~7.0μmという波長帯の赤外放射を測定している。この波長帯は水蒸気に吸収されやすい
性質がある。一般にこの波長域の赤外放射では、高度が600hPa付近の大気から放射される赤外線が衛星に最も大きく影響する事が
知られている。
4-12. 「ひまわり」の可視・赤外画像に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 可視画像は、赤外画像より分解能が良く、またコントラストがはっきりしているので、日中の下層雲の観測に適している。
- 赤外画像では、霧や層雲などは地表や海面などとの識別が困難である。
- 赤外画像は、雲や地面から放射されている赤外線の放射エネルギから等価黒体温度を求め、それを画像化している。
一般に高い雲ほど温度が低いので黒く写り、地表面は温度が高いので白く写る。
- 可視・赤外画像の雲の写り方の違いから上層、中層、下層の雲を識別することができる。
- 可視・赤外画像に写る台風にともなう雲域の特徴から、台風の中心位置や強さが指定できる。
4-13. 以下の文章は、図に示した気象衛星「ひまわり」の画像に関するものである。下線部分(a)~(d)の記述の
正誤に関して、次の1~5のうち正しい物を一つ選べ。a
図1はある日の15時(06UTC)の赤外画像、図2は同時刻の可視画像である。
中国大陸にある雲域Aは可視画像では白く写っているが、赤外画像ではあまり白くなく、(a)鉛直方向にはそれほど
発達していない雲域である。雲域Bは北側へ丸く盛り上がっているが、これは(b)発達中の低気圧に伴って観測される雲域の
特徴である。日本の東海上にある雲域Cは赤外画像にはほとんど写っておらず、(c)霧か、かなり背の低い下層雲と見られる。
一方、フィリピン方面にある雲域Dは赤外画像、可視画像とも真っ白に写っており、(d)発達した積乱雲群であると考えられる。
1.(a)のみ誤り, 2.(b)のみ誤り, 3.(c)のみ誤り, 4.(d)のみ誤り, 5.すべて正しい
解と解説
解答:3:
地上気象観測全般にわたっての知識を問う問題。現地気圧を海面更正するには、基本的には静力学平衡の式と気体の状態方程式が使われるが、
地面より下で平均海面までの間(そこに気柱が有るものと想定)の気温と湿度をどう仮定するかは、国際的には統一されていない。
日本では、観測地点より下の海面までの気温は、観測地点の気温が気温減率0.5℃/100mで変化すると仮定し、
想定した気柱の平均気温を算出する。
空気が湿っている為の影響は、気温と湿度との統計的関係から平均気温の関数として水蒸気補正項を用いる。これらを
静力学平衡の式と気体の状態方程式に代入して、海面更正をする。したがって、問題文中の「観測地点と平均海面の間の
気温と湿度が観測地点の値に等しいと仮定」は間違い。
解答:1:
雲と日射量の観測についての問題。雲形別の雲量とは、ある雲形の雲だけで占める部分の全天空に対する割合の事。
2種類以上の雲が部分的に重なっている事が有るが、この場合は重なって隠された部分も推定して観測する事にしているので、
一般に雲形別の雲量の合計と全雲量とは一致しない。したがって1の記述は誤り。
雲量は、1~10の整数で表す。全天空が雲に覆われた場合が10、雲が全く無い場合が0。なお、雲量が1に満たない場合は
0+、雲量が10であっても雲の無い部分(隙間)がある場合は10-と表す。
解答:1:
地上気象観測のうち、風向・風速と降水量の測器の設置方法と測定方法についての問題。風向・風速は、測器の高さが
地上10m以上であっても実測値を観測値として通報しており、換算式は用いていない。
解答:2:
アメダスの観測値は、定時(毎正時)あるいは臨時(降水量または風速がある基準値を超えた時)に、電話回線を通して、
自動的に東京・大手町の地域気象観測センターに集められ、データに誤りがないかどうかをチェック(品質管理)した後、
気象官署や自治体、報道機関などに配信される。
解答:4:
ウィンドプロファイラ観測では、上空の風向・風速の観測が10分ごとに行われており、その風向・風速(10分平均値)の鉛直分布は
1時間ごとにまとめられ、気象庁の中央監視局に伝送される。これらの観測データは品質を行った後、メソ数値予報モデルに入力・
解析され、実況監視資料として1時間ごとに配信される。1時間ごとに観測ではなく、10分ごとに観測して1時間ごとにまとめて...
配信。
ラジオゾンデ観測では、気圧、気温、湿度の値から、状態方程式と静力学平衡の式を使って高度を算出する。
つまり、気圧面間の空気の密度がわかると、その気圧差に相当する気層の厚さが計算できるので、これを
積分すれば地上から気球までの高度が求められる。しかし、最近ではGPSで測定しているに違いない。
解答:3:
方位角が減っているという事は、南から北に向かっているという事。
ウィンドプロファイラ観測により、豪雨や豪雪など局地的な気象災害の要因となる下層大気の流れを
連続的に把握することが可能となった。観測データはメソ数値予報モデルの初期値として利用される。
ウィンドプロファイラは全国31地点に配置されており、うち25地点は気象官署内、6地点は国・県・町の
敷地に設置されている。
解答:1:
風向・風速は、地上から気球を追跡して行われているので、風向・風速計は搭載していない。
日中のラジオゾンデ観測では、日射を受ける事により、気温の感部が周囲の空気よりも高くなり、日射誤差(=感部の温度-気温の真値)を
生じるため、日射補正を行う必要がある。
解答:2:
レーダービーム内にある降水粒子が大気の乱流や風速のため激しく運動するため、降水エコーは激しく変動する。
これに対して地形エコーは、ほぼ静止しているとみてよいので、変動が無い。この差を利用して
地形エコーを除去する処理が行われる。しかし、シークラッターやエンゼルエコーなどの非降水エコーは、
パルスごとにエコーの強さが変化するために、完全に除去するとこは出来ない。
解答:4:
水の方が氷よりエコー強度が大きくなる(多分結晶内部で減衰)。しかし、気象レーダー観測ではエコーの
強弱しか判別できないので、雨や雪かの識別は不可能。
雨滴の方が氷滴よりもエコー強度が大きいため、氷滴が落下中に雨滴に変わるとエコー強度が5-6倍になる。
この現象がブライトバンド。
気象庁では、個々のレーダーによる観測範囲の限界を補うため、複数のレーダーで観測された高度2kmのエコーを
合成して降水の監視を行っている。
解答:4:
矢印を描いたらすぐわかる。正(距離が延びるから+)と負(距離が縮むから-)の意味を逆にしないように注意。
収束は矢印がぶつかる方(低気圧)、発散は矢印が離れる方(高気圧)。
解答:5:
600hPaでなくて、400hPa付近。水蒸気センサーは6.5~7.0μmの波長帯の赤外放射を測定しているのは正しい。
この波長帯は水蒸気に吸収されやすい(吸収率0.5~1)。高度600hPa付近だと、衛星に到達する放射比率は400hPa
付近の半分程度になるらしい。
解答:3:
赤外画像は、温度が高いところは焼けて黒く、低いところほど白く写る。
可視画像では分解能(赤外線に比べて波長が短い)も良く、コントラストもはっきりしているので
下層雲や霧などが明瞭に写る。それに対して、赤外画像では、雲頂温度が地表よりも5~10℃ほどしか
低くない下層の雲を識別する事は困難。可視画像では、下層雲や中層雲が白く写り、赤外画像では、
中層雲や上層雲が白く写る。したがって、この両者の画像を組み合わせれば、上層、中層、下層の雲を
ある程度識別できる。台風は、可視画像、赤外画像ともに白く写るので、台風にともなう雲域の特徴から
台風の中心位置や強さが推定できる。
解答:5:
可視画像と赤外画像を組み合わせて雲の識別を行う問題。可視画像は厚い雲や下層雲、および新しい雪氷等が白く写る。
一方、赤外画像では、温度の低いところほど白く、高いところほど黒く写る。この性質を利用して、
- (a)中層雲で、鉛直方向にはそれほど発達していないと考えられる。
- (b)雲域が北側へ丸く盛り上がっているので、発達中の低気圧にともなう雲と考えられる。
- (c)霧、あるいはかなり背の低い下層雲と見られる。
- (d)下層から上層に向かって鉛直方向に発達している雲の集団、つまり積乱雲群と考えられる。
全て正しい。
専門・第2章練習問題
5-1.現象のスケールと予測可能性に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 気象現象のスケールとは、現象の時間的な長さと空間的な広がりを意味するものである。その時間スケールと
空間スケールとの間には、強い正の相関関係がみられる。
- 気象現象のスケールは便宜的に、地球規模、総観規模、メソスケール規模に分けられるが、メソスケールの現象は
さらにメソα、β、γのスケールに細分化される。
- メソγより小さいスケールの規模も存在し、おおよそ2km以下の現象はミクロスケールと言われる。
- アンサンブル予報は、主として長期予報に用いられるが、総観規模スケール、メソスケールを対象とした短期予報にも
有効に使う事ができる。
- 数値予報の予測精度は、現象のスケールに比例しない。すなわち、現象が小さいほど予測が困難であり、
また現象のスケールが大きいほど予測の精度が悪くなる。
5-2.大気中のさまざまな現象について述べた(a)~(d)の分の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- (a)超長波は、水平波長が1万kmにも及ぶ大気中で最大のスケールの現象である。その発生には、ヒマラヤ山脈やチベット高原
などの大規模な地形による力学的な効果が関係している。
- (b)たとえば積乱雲のように、運動の鉛直スケールと水平スケールが同等の大きさの現象では、鉛直方向の運動の
力学的な影響は小さく、良い精度で静力学平衡の近似が成り立つ。
- (c)高気圧は、その成因によって構造が異なる。日本付近の天候を支配する太平洋高気圧は、対流圏上層にまで存在しているが、
冬のシベリア高気圧は、対流圏下層にしか存在しない。
- (d)温帯低気圧より水平スケールの小さい梅雨前線上に発生する低気圧は、対流圏上層には明瞭な構造が見られない事が多い。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-3.予測可能性に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 観測網の密度と観測の精度、数値予報モデルの精度、コンピュータの計算処理速度などが、現象の予測可能性に密接に関係している。
たとえば、観測データに誤差が含まれていると、予想時間経過にともない、カオス的な結果が出力され、予報の信頼性が低下する。
- 総観規模現象の予測可能性は、10日から2週間が限度と言われているが、短期予報(本日、明日、明後日の予報)に対しては
実用上、十分に精度よく予報できる。
- 局地的な大雨の予測に対して、現在の数値予報モデルの精度は十分ではないが、時間的空間的な誤差を考慮する事により、
大雨のポテンシャリティー(潜在性)の予想には有効である。
- 数値予報による現象の予測可能性は、時間の経過にともなって減少する。しかし、数時間先程度の現象の予想に関しては、
精度の良い結果が得られる。
- 数値予報モデルで表現できる現象の最小スケールは、そのモデルの格子間隔の5~8倍とされており、格子間隔以下の
スケールの現象の効果については、パラメタリゼーションにより近似的に取り入れられている。
5-4.数値予報に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- 数値予報では、高層気象観測によって得られる風向・風速、気温、湿度などを初期値として使用し、大気密度や温位の時間変化を予想する。
- 数値予報では、物理量の値の変化がすべてゼロであっても、気象状況の時間変化があると予想される。
- 格子点の値(GPV)は、およそ20km四方の範囲の物理量の代表値である。観測点が格子点と一致した場合は、観測値が解析値とされ、
第一推定値は用いられない。
- 数著予報では、離散的な格子点で物理量の分布を表すが、観測値が得られない場合は、隣接格子点の値を平均して得られる値を
用いる。
- 数値予報には、用途に応じたモデルが有る。短期予報には領域モデルが稼働されるので、全球モデルの稼働は必要でない。
全球モデルは、地球規模のスケールの現象を予想するために稼働される。
5-5.プリミティブ方程式に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 水平方向の運動方程式における空気塊にかかる加速度は、風の移流量、コリオリの力、気圧傾度力、摩擦力の和に等しい。
- 鉛直方向の運動方程式は、静力学平衡と地衡風平衡を前提として成り立っているが、積雲対流の効果はこの式には組み込まれていない。
- 気体の状態方程式によって、将来の気温の予想値を求める事ができる。
- 総観規模のスケールの現象を予測するには、プリミティブ方程式を用いる事が有効である。
- 熱力学方程式によると、空気塊が断熱圧縮を受けたり、空気塊中で水蒸気の凝結が起きた時、その空気塊の温度は上昇する。
5-6.数値予報の作業について述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- (a)予報作業の順序は、前の予報→観測→品質管理→客観解析→初期値化→予報であり、観測値は貴重なデータであるから、
すべて初期値として用いる。
- (b)客観解析とは、初期値化のためのデータを格子点に割り付ける作業であるが、観測値の得られない地域の初期値としては、
第一推定値(前回の予想結果)が用いられる。
- (c)数値予報のために収集された観測データには、品質管理によって「誤り」と判断され、客観解析に使われないものもある。
- (d)数値予報モデルの初期値として、客観解析値をそのまま利用すると、不自然なノイズが発生するので、
これを防ぐために行われるのが初期値化である。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-7.数値予報で出力される物理量に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 数値予報プロダクトとしての物理量は、天気図に掲載されたりガイダンスへの入力として使われたりするが、それぞれの物理量は
プリミティブ方程式に見られるように、相互関係は存在する。
- 地上天気図に表示されている気圧は、その観測地点の上空の単位面積当たりの大気の重さである。
- 鉛直P速度は、1時間あたりの気圧の時間変化量で表される。
- 高層天気図には気圧の表示は無いが、等高度線の形状から高低気圧の分布状況を推定できる。
- 相当温位は、水蒸気量を推定するのに有用であり、降水現象と密接に結びついている。
5-8.数値予報プロダクトについて述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- (a)数値予報プロダクトで示される積乱雲にともなう上昇流の大きさは、実際のものに比べて小さく見積もられる。
- (b)数値予報の誤差は、予報時間と共に増大し、予報の有効性も時間と共に失われていくが、通常は水平スケールの大きい
現象ほど予報の有効寿命が長いといえる。
- (c)自由大気においては、風は気圧傾度力、コリオリの力、遠心力のつり合った「傾度風平衡」の状態を維持しながら
物理量を輸送するが、特に移流による輸送効果が大きい。
- (d)数値予報モデルに組み込まれている地形では、山の高さや小さな谷まで表現されているので、地形が主な原因によって生じる
現象も十分に表現できる。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-9.数値予報プロダクトの利用に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 500hPa面での渦度場の追跡は、総観規模擾乱の動向の把握については有効だが、中小規模擾乱については有効ではない。
- 日本付近で発達中の温帯低気圧では、低気圧の中心の東側で暖気の上昇が有り、西側では寒気の下降が有る。
- 高層天気図における現象の表現は、格子点間隔の5倍以下のものは困難であり、さらにその現象発現の潜在性の推定もできない。
- 等温度線を横切る風が強く、寒気移流や暖気移流が見られる場合に温帯低気圧が発達する。
- 梅雨前線は通常、相当温位の場で見ると等値線の集中帯として明瞭に把握できる事が多いが、温度場で見るとあまり明瞭ではない。
5-10.天気予報ガイダンスに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- ガイダンスとは予報支援資料の事で、たとえば数値予報プロダクトでは直接出力されない「晴れや雨」などの
天気現象を表現し、天気予報の作業を行いやすくするものである。
- カルマンフィルターは、線形の予測式を用いて統計的関係式を作成するのは従来のMOSと同じだが、係数更新については、
従来のMOSでは係数を過去数年分のデータを用いて求めるのに対して、カルマンフィルターでは誤差が大きくなってきたら、その誤差を
最小にするようにきめられる。
- ニューラルネットワークでは、数値予報結果に系統的誤差(バイアス)があっても除去することはできない。
- カルマンフィルターもニューラルネットワークも数値予報モデルの変更が有った時は、実用化するのに数年分の予報データの
蓄積を必要とする。そして、新たな機能を利用して、過去に経験(学習)しなかったような現象も予想値として出力できる。
- 擾乱の位相のずれはカルマンフィルターでは補正できないが、ニューラルネットワークでは補正できる。
5-11.ガイダンスと降水確率予報に関する次の文章で、下線部1~5の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
数値予報の結果から、ある特定の場所の気温、降水量等を予測する手法の一つにMOS方式が有る。MOS方式では、統計的関係式を使用するが、
1.この関係式の作成には、予測しようとする気温や降水量等の観測値と、それと同じ時刻の数値予報モデルの予測値を用いる。
2.この方式を用いると、数値予報モデルに系統的な誤差がある場合でも、それをかなり取り除く事ができる。さらに、
3.MOS方式には、数値予報モデルが更新されても、すぐに対応できるという利点がある。
気象庁が現在発表している降水確率予報は、従来のMOS方式とは違ったガイダンス作成手法であるカルマンフィルターによって
作成されている。なお4.降水確率予報とは、予報対象時間内に1mm以上の降水が有る確率を示すもので、
5.「06時から12時までの降水確率は50%」という予報は、6時間の予報対象時間のうち、3時間程度は雨が降るであろうという
ことを示すものではない。
5-12.気象庁が発表している降水確率予報について述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。
a
- 6時間降水確率予報は、ニューラルネットワークによって行われ、予報対象時間に1mm以上の雨または雪の降る確率を10%刻みで
予報するもの。
- 予報対象地域の面積が広くなると、降水確率も高くなる。
- ある地域の12時間後までの6時間おきの降水確率がすべて30%であるとき、その地域の12時間の降水確率は30%になる。
- 降水量が大きく予想された場合、降水確率の数字も大きく予想される。
1.(a)のみ正しい、2.(b)のみ正しい、3.(c)のみ正しい、4.(d)のみ正しい、5.すべて誤り
5-13.気象庁における降水短時間予報に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 降水短時間予報は、数値予報の領域モデルでは不可能な6時間先までの降水の予報を目的としており、
防災気象情報の作成に利用されている。
- 降水短時間予報は、日本全国を2.5km四方の区切った地域を対象としている。
- レーダー・アメダス解析雨量図は、レーダーエコー合成図とアメダスデータによって作成される。
- 降水短時間予報のためには、気象レーダー、アメダス、数値予報等からの結果が手順に従って処理される。
さらに、気象衛星からのデータも必須である。
- 降水短時間予報は、降水域の実況補外による予測とメソ数値モデルによる予測とを結合して作成される。
5-14.気象庁から提供されているレーダー・アメダス解析雨量について述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の
1~5の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- (a)水平スケールの大きい降水では、平均して約17km四方に1ヶ所の割合で設置されているアメダス雨量計の実測雨量で
レーダーデータを補正できるため、解析雨量の精度は良い。
- (b)解析雨量は、気象レーダーの観測値をアメダス雨量計で補正して解析しているので、アメダスデータのない
山岳部や海上での値は誤差が大きい可能性がある。
- (c)解析雨量の解析には、気象レーダーのデータを雨量に換算して、それを3時間積算した値が使用されている。
- (d)解析の際に除去しきれなかった地形エコーやシークラッターは、解析雨量として出力され、誤差の要因となる。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-15.次の図は、気象庁で行っている気象レーダー観測から降水短時間予報までの流れを示している。
各段階での処理について述べた次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
| 気象レーダー+気象レーダー+気象レーダー | | | メソ数値予報モデル
|
| | | | | | | |
|
| A | | | | | 数値予報結果
|
| ↓ | | | | | ↓
|
| レーダーエコー合成図→ | B | →レーダー・アメダス解析雨量図→ | C | →補外予測→ | D | →降水短時間予報
|
- 処理A:レーダーエコーに含まれる地形エコーを除去する。
- 処理A:エコー強度データや1時間積算降水強度データ等を作成する。
- 処理B:レーダーの1時間積算降水強度データをアメダスの1時間雨量データで補正する。
- 処理C:アメダスで得られる気温の観測値を利用して雨雪の判別を行い、予報精度を高めている。
- 処理D:降水域の実況補外予想とメソ数値予報とを、それぞれ重みを決めて結合する。
5-16.気象庁では、発表した各種予報について、その精度を統計的な手法を用いて検証・評価している。
これに関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 通常、予報の有効性は、特別な予報技術を必要としない持続予報や気候値予報と比べて、どの程度改善したかによって
評価される場合が多い。
- 2乗平均平方根誤差(RMSE)は、気温予報等の量的予報の精度を表す指標として用いられており、その値が小さいほど精度が良い。
- 比較的まれにしか生じない気象現象の予報は、適中率だけでは評価できない。このため、スレットスコアを計算して精度を
検証するが、その値は小さいほど精度が良い。
- 放水の有無の予報の検証に用いる「適中率」と、注意報・警報の「適中率」は定義が異なり、分割表からの計算方法が違う。
- 降水確率などの確率で表す予報の精度については、プライアスコアなどを計算して検証するが、その値が小さいほど精度が良い。
5-17.降水確率予報の統計的評価を夏季の分割表について、次の1~5のうち、適中率とスレットスコアが正しく計算されている
組み合わせを一つ選べ。ただし、数値はすべて小数点第1位で四捨五入し、百分率で示している。a
| | 予報
|
| 降水あり | 降水なし | 計
|
| 実況 | 降水あり | 9 | 7 | 16
|
| 降水なし | 4 | 10 | 14
|
| 計 | 13 | 17 | 30
|
| | 適中率 | スレットスコア
|
| 1 | 60 | 35
|
| 2 | 73 | 45
|
| 3 | 68 | 40
|
| 4 | 63 | 45
|
| 5 | 70 | 40
|
5-18.気象庁では「降水あり」「降水無し」の2種類について、予報に対する実況の2x2分割表を作成し、その表中の数値から
適中率、見逃し率、空振り率、スレットスコアなどを計算して総合的に評価を行っている。ある期間の予報について、下記の様な
結果を得た。これについて述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
| 適中率:80% | 見逃し率:3% | 空振り率:17% | スレットスコア:67% |
- (a)季節や地域によって予報の難易度が異なるため、適中率が高いからといって、必ずしも予報技術が優れているとは限らない。
- (b)冬季の太平洋側における雨や雪など比較的まれな現象でも、適中率が高ければスレットスコアが低くても、
この予報の利用価値は高いといえる。
- (c)見逃し率が非常に小さいので、降水によって大きな損害を受ける産業などでは、この「降水無し」の予報は十分活用できるものである。
- (d)防災上は、空振り率よりも見逃し率を低く抑える方が重要である。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-19.降水確率予報の評価方法の一つにブライアスコアがある。下記の10日間の予報事例について、
ブライアスコアを正しく計算しているものを1~5のうちから一つ選べ。a
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 予報 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1
|
| 実況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1. 0.016、2. 0.040、3. 0.048、4. 0.016、5. 0.48
5-20.中緯度における大気の大きな流れを説明した次の文章について、
下線部1~5のうち、誤っているものを一つ選べ。a
地球大気は、緯度によって太陽から受ける熱量に不均一が生じるため、一般に北半球の中緯度地方では低緯度側(南)で暖かく、
高緯度側(北)で冷たい。温帯低気圧の発達は、この南北の温度傾度が有る流れの場の1.傾圧不安定性によるものである。
北半球においては、夏より冬の方が南北の温度傾度が2.小さいため、低気圧が発達しやすい。また温度風の関係から、
上層ほど3.西風が強くなるが、南北の温度傾度が増大し、風の4.鉛直シヤーがある限界を超えると、
5.波長が数千kmの傾圧不安定波が発達し、南北の温度傾度が弱まる。
5-21.中緯度偏西風帯の温帯低気圧に関する次の文章で、空欄a~fを埋める語句の組み合わせ1から5のうち、
正しいものを一つ選べ。a
発達期の中緯度偏西風帯にある温帯低気圧は、高層天気図において、トラフ(気圧の谷)の西側には[a]の移流があり、
東側には[b]の移流がある。このとき地上天気図を見ると、低気圧が発達して、寒冷前線や温暖前線はともに活発になっている。
地上の低気圧の中心からみると、上層のトラフは西に位置している。これを東西方向の鉛直断面図で見ると、トラフの西側は、
東側に比べて空気の密度が大きく、2つの等圧面ではさまれた大気層の厚さは薄い。またこのとき、東側では相対的に[c]し、
西側では[d]している。この構造による[e]エネルギーから[f]エネルギーへの転換が、低気圧を発達させている。
| | a | b | c | d | e | f
|
| 1 | 寒気 | 暖気 | 暖かい空気が上昇 | 冷たい空気が下降 | 有効位置 | 運動
|
| 2 | 寒気 | 暖気 | 冷たい空気が下降 | 暖かい空気が上昇 | 有効位置 | 運動
|
| 3 | 暖気 | 寒気 | 暖かい空気が上昇 | 冷たい空気が下降 | 有効位置 | 運動
|
| 4 | 暖気 | 寒気 | 冷たい空気が下降 | 暖かい空気が上昇 | 運動 | 有効位置
|
| 5 | 暖気 | 寒気 | 暖かい空気が上昇 | 冷たい空気が下降 | 運動 | 有効位置
|
5-22.北半球における低気圧に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 温帯低気圧において、鉛直方向に収束域と発散域がある場合に、その中間にある非発散層付近では鉛直流の速さが最大となる。
- 発達する温帯低気圧の特徴の一つに、上層の正渦度の極大域が地上低気圧の中心に対してやや西側にあるということがある。
- 寒冷低気圧は、一般に対流圏内での気温は周囲より低いが、圏界面より上では逆に周囲よりも気温が高くなっている。
- 発達中の温帯低気圧のともなう寒冷前線のすぐ西側では、地上から上層に向かって風向が時計回りに変化している。
- 寒冷低気圧は、偏西風帯から切り離されているため、通常の温帯低気圧に比べて移動速度が遅い。また、上層の寒冷渦に
対応して、地上には明瞭な低気圧は存在しない事もある。
5-23.気象庁で行っている長期予報(1か月予報)とアンサンブル予報の手法に関する次の記述のうち、
正しいものを一つ選べ。a
- アンサンブル予報を行った場合、メンバー同士が離れた予想をするほど、特異な天候変化の起こる可能性が高く、予報の精度は良くなる。
- 数値予報の精度は、予報時間が長くなるにつれて境界値(海水面の温度や地面の乾湿の状態等)に対する依存性が低下してくる。
- 1か月予報用の予報モデルは、週間予報用の全球モデルより水平方向の解像度が粗いが鉛直方向の解像度は細かく、計算のための
層(レイヤー)数は約2倍ある。
- アンサンブル予報のためのメンバー数には現実的な制約があるため、初期値の与え方を工夫することなどでメンバー数の少なさを
補っている。
- アンサンブル予報で個々のメンバーを計算する数値予報モデルに大きな系統的誤差があっても、メンバーを増やすことによって、
予報精度を上げる事ができる。
5-24.季節予報で対象とする気圧系や、季節予報で取り扱う天気図などについて述べた次の文章(a)~(d)の
下線部の正誤について、下記の1~5の中から正しいものを一つ選べ。a
- (a)季節予報では、総観規模の擾乱よりも大きい超長波や偏西風帯の変動、亜熱帯高気圧の動向などを主に取り扱う。そのため、
季節予報では、温帯低気圧や移動性高気圧などの総観規模の擾乱を取り除くために、5日以上の期間で平均した平均天気図を
用いるようにしている。
- (b)月平均500hPa平年高度偏差から作られる偏西風の東西指数が低指数を示す場合、偏西風の蛇行が大きく、南北の熱交換が活発に
行われており、ブロッキング現象が発生している事もある。
- (c)暖候期の日本付近の天候傾向を支配する重要な擾乱の一つにチベット高気圧があるので、チベット高気圧の動向を見るために、
北半球月平均500hPa高度・平年偏差図などが用いられる。チベット高気圧が日本を覆うほど強まると、暑夏になることが多い。
- (d)下図A,Bは、ある年の1月の月平均500hPa高度・平年偏差図である。日本およびその周辺の高度と偏差分布からすると、
図Aの年は、図Bの年に比べて日本およびその周辺で冬型の気圧配置が弱く、日本付近の気温は高いと考えられる。
| 図A | 負偏差、北西からの風
|
| 図B | 正偏差、南西からの風
|
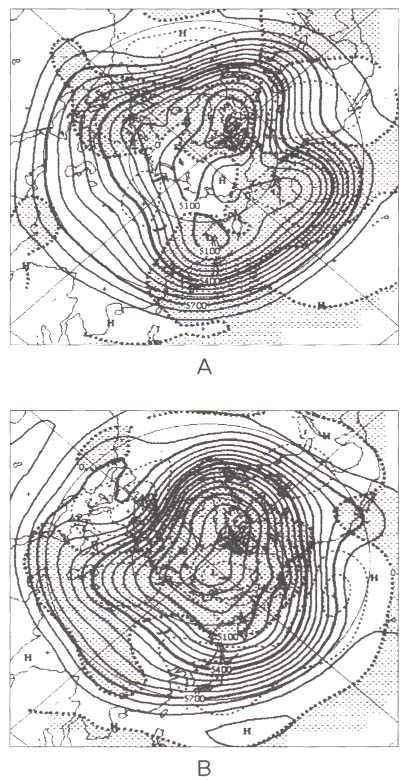
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-25.集中豪雨と積乱雲に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 梅雨前線付近などで集中豪雨が発生する時には、強い積乱雲が前線上に並んだりする。
- 集中豪雨では、地形によって降水が強化される効果が大きいので、下層の風向・風速と地形との関係が重要となる。
- 集中豪雨が発生している時、「ひまわり」の赤外画像では、真っ白に写っている積乱雲群が見られる事が有る。
- 一つの巨大な積乱雲からなるスーパーセル型ストームは、一般場の風の鉛直シヤーが強い状況で発生し、長時間にわたって持続する。
- 個々の積乱雲のライフサイクルを気流で見てみると、発達期(成長期)は雲中のどこでも上昇流、成熟期には主に上層に下降流、
衰弱期(消滅期)には下降流だけになる。
5-26.降雪に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 冬季に、日本海側で大雪が降るのは、大陸から吹き出す季節風が、暖かい日本海から顕熱や潜熱の補給を受けて大気下層を成層不安定にさせ、
活発な対流活動を起こすからである。
- 太平洋側において降水が雨になるか雪になるかは、850hPa面の気温が-6℃となる線を境界として決定される。その際、
湿度などは判定基準が複雑となるため考慮しない。
- 山雪型と呼ばれる大雪は、西高東低の気圧配置にあって、日本付近で季節風の吹き出しが強まると発生する。
- 里雪型と呼ばれる大雪は、寒気の中心が日本海西部にある時に、主に平野部によく見られる。
- 太平洋側の降雪は、南岸低気圧が通過する時に発現することが多い。
5-27.海陸風や逆転層など地表付近の現象について述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものを一つ選べ。a
- (a)海陸風は、海面と陸地の温度差(気圧差)によって生じる局地風で、日本では冬に比べて平均的に風の弱い夏に明瞭に現れる。
- (b)海風は、陸風よりも風速が強く、海風の及ぶ距離は海岸から陸地へ約20~40km以上といわれているが、陸風の方は10km以下までしか
及ばない。
- (c)晴天の夜間に起こる放射冷却により、地表面に近いほど気温が下がる事によって形成される逆転層を「沈降性逆転層」という。
- (d)地形や温度差の影響で形成される小規模な前線のことを『局地前線』という。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
5-28.台風に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 最大風速が17.2m/s未満の熱帯低気圧は、台風とはいわない。
- 台風モデルの稼働によって、72時間先までの進路、大きさ、強さなどの情報が提供される。
- 台風のエネルギー源は、積雲対流によって放出される凝結の潜熱である。
- 台風は、メソスケール規模の擾乱であるが、全域にわたり層状性の厚い雲が存在する。
- 台風の進路予測のため、台風ボーガスという台風データの人工的な埋め込み技術が使われる。
5-29.台風の構造に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- 台風にともなう風は、その進行方向に向かって右側で、風速が最大となる。
- 台風の中心付近の上空は、高気圧性回転の渦になっていて、暖気核が有り、その成因は、寒冷渦の暖気核と同じである。
- 台風は一種の低気圧であり、傾圧不安定性がその発達に重要な意味を持っている。
- 地表付近の風速を検討する場合、コリオリの力、気圧傾度力、遠心力の3者を考慮するが、摩擦力は考慮しなくてもよい。
- 台風の中心付近のアイウォールと呼ばれる積乱雲の壁の中には、40m/sに達する強い下降流がある。
5-30.台風のライフサイクルについて述べた(a)~(d)の文の正誤に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものを一つ選べ。a
- (a)コリオリの力が弱い北緯5度以南の赤道付近では、台風はほとんど発生しない。
- (b)低緯度で発生した低気圧がおおむね西の方に進むのは、太平洋高気圧の南の偏東風に流されるからである。
- (c)台風進路の転向点に大きく影響するのは、偏西風である。
- (d)台風が上陸すると勢力が急に弱まるのは、陸面からの水蒸気の補給が海面からのものより少なくなることや、陸面との摩擦が
影響している。
1.(a)のみ誤り、2.(b)のみ誤り、3.(c)のみ誤り、4.(d)のみ誤り、5.すべて正しい
解と解説
解答:4:
アンサンブル予報は短期予報には使われない。長期予報の時間経過に伴う精度低下を何とかするために使う。
1の時間スケールと空間スケールに強い正の相関関係が有ることは、とても重要。5の数値予報の予測精度と現象のスケールが
比例しないのは、観測や数値予報モデル、コンピュータでの計算処理速度などが要因になっている。
解答:2:
積乱雲の様な現象(鉛直スケールと水平スケールの運動の大きさが同等の現象)では気流の上昇速度が大きすぎて、
静力学平衡が成立しない。
解答:4:
数時間先の予報は、現在の数値予報のシステムでは不可能。そこで、ナウキャスト(短時間予報)として、気象レーダーやアメダス、
気象衛星などのリアルタイムデータを数値予報結果に加味・修正して、予報精度を高めている。
総観規模の予測可能性は10日~2週間程度。数値予報で表現できる現象は格子間隔の5~8倍。
解答:1:
数値予報のキーとなるのは、高層気象観測。大気は上層から下層まで連続しており、相互に影響を及ぼし合っている。
したがって、どうしても高層のデータが必要になる。
- (2)数字で表された物理量の変化量がすべて0なら、物理量は時間変化しているとはいわない。
- (3)観測点が格子点と一致しても、観測値がそのまま解析値にはならない。解析された結果が初期値(解析値)となる。
- (4)観測値が得られない場合は、第一推定値が格子点に割り付けられる。
- (5)短期予報では、まず最初に全球モデルが稼働されて、その境界条件を貰い受けて領域モデルが稼働する。
全球モデルは地球規模だけでなく、総観規模のスケールの現象を予想の対象としている。
解答:3:
気体の状態方程式には時間の項が入っていない。
解答:1:
観測データに誤りが有る場合は、品質管理によりチェックされ、除外される。
解答:2:
現地気圧ではなく、海面更正された値。これは、気圧が高度によって変化する事を補正するためのもの。700hPa鉛直P速度における
鉛直P速度の値は、上昇流はマイナス、下降流はプラス。
解答:4:
数値予報モデルに組み込まれている地形では、細かい地形は表現しきれていない。植物の植生なんかも、おおざっぱ。
数値予報のデータには気象要素(物理量)のほかに、海面水温や地形効果、雪の状態などさまざまなものがあり、それらを
正確にデータとして取り入れることが難しいため、それが予報の限界の一因となっている。
解答:3:
潜在性は推定できる。500hPa面における渦度の追跡、発達中の低気圧での暖気上昇(東)と寒気下降(西)、温帯低気圧の発達
と寒気移流・暖気移流との関係、梅雨前線の解析など重要。
解答:1:
- (2)カルマンフィルタは、係数が常に予報誤差が最小になるように決められており、誤差が大きくなったらと言うわけではない。
- (3)ニューラルネットワークは系統的誤差(バイアス)を除去する仕組みを取り入れている。
- (4)カルマンフィルタも、ニューラルネットワークも、数値予報モデルの変更があっても、短時日で実用レベルに達するが、
未経験の現象に対しては、適切な予想値を与える事はできない。
- (5)擾乱の位相(移動速度)のずれを補正する事は、カルマンフィルターもニューラルネットワークもできない。
解答:3:
モデルの変更が有ったら、従来のMOSでは直ぐには対応できない。1~2年かかる。その他の記述はとても大事。
解答:5:
- (a)6時間降水確率予報は、カルマンフィルターで作成される。
- (b)降水確率は、予報対象地域の全地点に共通の値。地域の大きさと確率の値とは無関係。
- (c)6時間ずつに分けて、降水がない確率の掛け算と引き算で計算((1-0.3)*(1-0.3)=0.49, 1-0.49=0.51=51%)。
- (d)降水確率は、100回中の何回1mm以上の雨か、という確率なので、量は関係ない。
解答:4:
気象衛星からのデータは使っていない(夜は使えないし...)。使うのは、
- メソ数値予報モデル
- 気象レーダー(降水強度)
- アメダス(雨量の実況値)
- パターンマッチング(降水域の移動速度)
- 数値予報/700hPaの風の予想値(降水域の移動速度の第一推定値)
- 数値予報/850hPaの気温・風の予想値(地形性降水の発達・衰弱を把握する)
- 国土地理院の地形データ
降水短時間予報は、レーダー・アメダス解析雨量の実況補外による予測と、メソ数値予報モデルによる予測とを、
時間変化に伴う精度変化に対応した重みづけで結合し、1時間ごとの降水量を6時間先まで予測するもの。
解答:3:
3時間ではなく1時間(3時間だと間に合わない)。
解答:4:
雨と雪の区別はしない。雪は全部溶かして観測する。他の内容は重要。
解答:3:
誤差は小さい方が精度が良いが、スレットスコアや適中率は大きい方が精度が良い。
解答:4:
適中率=(9+10)/(9+7+4+10)=0.63..=63%,スレットスコア=9/(9+7+4)=0.45=45%
解答:2:
- (a)地域によって、雨が多かったり降らなかったりするから。
- (b)起こりにくい現象の予測は、スレットスコアで。
- (c),(d)損害が大きい現象の「見逃し」は、絶対にやばい。
解答:3:
((0.1-0)2+(0.3-0)2+(0.6-1)2+(0.8-1)2+
(0.4-0)2+(0.1-0)2+(0.1-0)2)/10=0.048
解答:2:
冬の方が、傾きがきつくなるので、差が大きい。
解答:1:
書かれていることはとても大事。
解答:4:
北半球における低気圧の特徴。発達中の低気圧にともなう寒冷前線の東側(前面)は暖気移流域となっており、
地上から上層に向かって時計回りに、反対にすぐ西側は寒気移流域となっており、上層に向かって反時計回りに風向が変化する。
上層では偏西風だから、まっすぐになる、と理解する。
解答:4:
まあ、常識で考えたら分かる。2については、初期値や境界条件の微妙な差が、後々大きく影響するのが、カオス(非線形成)
ということ。メンバ数を増やしても、系統的誤差はキャンセルできない(それぞれに同じだけ掛かる誤差なんだから、
数でどうこうできない)。/p>
解答:4:
A→負偏差で北西(シベリア)から冷たい風が吹いてくる(日本海側大雪)。
B→正偏差で、南西から暖かい風が吹いてくる(太平洋側雪かも)。他の項目は、とても大事。
解答:5:
成熟期の積乱雲は、下層、中層に下降流。おそらく、下のほうから、下降流が優勢になる。他の項目も大事。
解答:2:
湿度も大事。
解答:3:
接地逆転層。沈降性逆転層は、高気圧などで強制的に下降流が生じたとき、断熱圧縮であったまることによって生じる。
解答:4:
台風の雲は積乱雲(対流雲)、雲の中に上昇流。台風ボーガス(モデル)の元になるのは、ドボラック法。
発生、発達するのが海上で、直接測定できるデータが少ないから。
解答:1:
台風の暖気核は潜熱が原因、寒冷渦の暖気核は、成層圏の暖気が降りてくる。台風の原動力も潜熱。台風も地表の摩擦力に影響を受ける。
アイウォールの中は、強い上昇流。
解答:5:
そのとうり。
専門・第3章練習問題
6-1.気象庁で行う予報、注意報、警報、気象情報に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮警報が発表されていた時に、同じ地域を対象として大雨、洪水警報、強風、波浪注意報に
切り替えられると、暴風、波浪、高潮警報は解除された事になる。
- 大雨警報が発表された後、必要に応じて発表される大雨に関する気象情報や低気圧に関する気象情報では、
大雨警報発表後の降雨の実況や今後の雨についての具体的な見通しが解説される。
- 気象情報には、対象とする注意報や警報が発表されていない時に発表される事が有る。
- 警報・注意報は、府県予報区を細分化した一次細分区域に対して発表される。
- 大雨注意報や大雨警報等で「レーダー・アメダス解析雨量図」を使う場合には、解析雨量であることを明示したうえで、
「○○市付近でおよそ何10ミリ」のように幅を持たせた表現をする。
6-2.気象庁で行う予報、注意報、警報、気象情報について述べた(a)~(c)の文章の正誤に関する次の1~5の記述のうち、
正しいものを一つ選べ。a
- (a)記録的短時間大雨情報は、気象庁が行わなければならない予報のひとつである。
- (b)波浪予報や波浪の注意報・警報で使われる波高には、有義波高を用いる。これは観測した波を高さの順に並べ、
高い方から3分の1の個数の波の平均をとったものに相当する。
- (c)局地的な大雨が予想され、災害が起こるおそれのある地域が府県内のごく限られた地域のみと予想される場合には、
標題に当該市町村名を付加した大雨注意報や大雨警報が発表される。
1.(a)のみ正しい、2.(b)のみ正しい、3.(a)と(b)が正しい、4.(b)と(c)が正しい、5.すべて正しい
6-3.台風予報に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 台風に関する全般気象情報で予報する台風の進路予報のうち、48時間先までの進路予報は3時間ごと、72時間先までの進路予報は6時間ごとに
発表される。
- 台風予報では、暴風警戒域は円形表示されるが、衰弱期の台風では、暴風警戒域の半径は、予報円の半径と同じになる事が有る。
- 台風の勢力は、風速15m/sの強風域の広さと、中心付近の最大風速の大きさによって区分されている。なお、ここでいう
最大風速とは、10分間平均風速のことである。
- 台風が弱まっていったん弱い熱帯低気圧になった後、再発達して台風になった場合は、弱まる前につけていた番号を再度つける。
- 台風が温帯低気圧に変わっても、日本への影響が引き続き大きいと判断される時には、その低気圧の中心気圧や進路などの予報が、
特定低気圧に関する情報として発表される。
6-4.台風情報について述べた(a)~(c)の文章の正誤に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選べ。a
- (a)台風情報は、海上予報の一環として海上保安庁を通じて船舶にも伝えられる。
- (b)台風の中心が日本からおよそ300km以内に近づき、日本に被害を及ぼす可能性が生じた場合には、気象庁は
監視・予報体制を強化して、台風に関する予報や情報を1時間ごとに発表する。
- (c)15m/sの強風域の半径が500km以上、800km未満の台風のことを「大型の台風」と呼ぶ。
| | (a) | (b) | (c)
|
| 1 | 正 | 正 | 誤
|
| 2 | 正 | 誤 | 正
|
| 3 | 誤 | 正 | 正
|
| 4 | 正 | 誤 | 誤
|
| 5 | 誤 | 正 | 誤
|
6-5.緊急防災情報ネットワークと土壌雨量指数に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 緊急防災ネットワークでは、画像情報を取り入れ「解析雨量と降水短時間予報」を立体図で表現する一方で、
文字情報は簡潔にし、情報の受け手が一見して状況を把握できるようにしている。
- 緊急防災情報ネットワークでは、確実に情報が伝達されるように、伝達方法が地上回線と衛星回線の二本立てになっている。
- 土壌雨量指数とは、降水が土壌中にとの程度蓄えられたかを把握する指数の事で、大雨に伴う土壌災害の危険性を判断する情報の
ひとつとしている。
- 土壌雨量指数は、レーダー・アメダス解析雨量、降水短時間予報、過去の履歴情報を用いて算出される。
- 土壌雨量指数は、過去の土砂災害の発生状況と比較して、「平成XX年の豪雨に匹敵する状況」といった大雨に関する情報を
盛り込んで警戒を呼び掛ける形で利用されている。
6-6.次の(a)~(d)のうち、気象が直接的に作用して起きる災害はいくつあるか。正しいものを一つ選べ。a
- (a)落雷の人体への直撃による死亡
- (b)大雨のために堤防が決壊して生じた床上浸水
- (c)気圧配置のために吹いた強風のために燃え広がる火災
- (d)台風のもたらす強風による車庫の倒壊
1.0個、2.1個、3.2個、4.3個、5.4個
6-7.気象と災害に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 着雪害は、湿った雪が電線などの地物に着くことにより発生する。
- 着氷害は、過冷却水滴や海水が地物、船体などについて凍結することにより発生する。
- 雹による災害は、春から秋にかけて多く発生し、冬にはほとんど発生しない。その理由のひとつに、冬には被害の
受けやすい農作物が栽培されていないことがある。
- 暖かい湿った空気が冷たい海面上を流れ、冷やされて発生する霧は、船舶衝突や交通障害の原因となる。
- 塩風害は、海上の波頭が砕けて生じる塩水滴が空中に飛び散り、それが強風で陸上に運ばれて生じる災害である。
降雨を多く伴う台風の時に被害が出やすくなる。
6-8.気象災害に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 近年、大雨や台風による大河川の氾濫、高潮被害などの大規模な水害の被害が増加傾向にある。
- 丘陵地、急傾斜地への居住域の拡大にともない、短時間の局地的な強雨を直接の原因とする崖崩れなどの
土砂災害による被害が増えている。
- 激しい雨を観測してから内水氾濫が発生し、浸水被害がピークに達するまでの時間は、都市化の進展とともに短くなっている。
- 土砂災害は、大雨にともなって発生するが、雨が降りやんだといってその危険性がなくなるわけではない。
- 気象庁は、浸水害、がけ崩れ害に対する警告を大雨警報に含めて発表する。
6-9.気象災害に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。a
- 大規模な地震や火山噴火の後には、大雨とはいえない程度の降雨によっても山崩れやがけ崩れが発生する事が有る。
このような現象は、大雨に関する注意報や警報の対象には含まれるない。
- 1日の雨量が500mmを超えるような大雨の発現は、西日本、東日本が中心であり、北日本ではまれである。しかし、
北日本ではこれより少ない降水量の大雨でも重大な災害が発生する事が有る。
- 冬期から融雪期にかけて発生する雪崩は、表層雪崩や全層雪崩などに分類される。雪崩の発生は、降水量、気温、天気などの
気象条件に関係する。
- 比較的長期にわたる異常気象(天候)によって発生する干ばつや長雨の災害については、気象庁が発表する注意報・警報
の対象とはなっていない。
- 台風や冬型の気圧配置にともなう強風や暴風は、広い範囲で風害を引き起こすおそれがあるが、地形の影響によって
風のほとんど吹かない地域が現れる事が有る。また、予想された以上の風速になることもあるため、地域の風の特性を知り
防災対策をとる必要がある。
6-10.気象庁が警報・注意報を発表する際に直接伝達する伝達先について、次の(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。
1~5のうちから正しいものを一つ選べ。a
- (a)市町村役場
- (b)テレビ局
- (c)鉄道会社
- (d)新聞社
1.0個、2.1個、3.2個、4.3個、5.4個
解と解説
解答:4:
一次ではなく二次細分区域が正しい。
- (1)注意報・警報については、常に新しく発表されたものが、先のものにとって代わるので、正しい記述。なお、府県内の同一地域に対して
同じ種類の注意報と警報が同時に出されることはない。
- (2)大雨警報を捕捉する形で発表される気象情報の事。
- (3)気象情報は、それ単独で出されて、警戒を喚起する役割(アラーム的機能)をもつ。
- (5)大雨注意報・警報で、レーダー・アメダス解析雨量を使う場合には、解析雨量である事を明示したうえで、幅を持たせた表現を用いる。
解答:2:
- (a)気象庁は、それぞれの二次細分区域の基準値に従って「記録的短時間大雨情報」を出す事があるが、
気象業務法の法令で義務付けられているものではない。×
- (b)波高のデータを高い方から低い方へ順に並べた時、最大波高から数えて1/3までの波高に着目して(観測を繰り返して)
その平均値を求めると、目測観測で推測した波高に近い事が知られている。これを有義波高といい、波浪の予報、注意報、警報のときに
使われる。○
- (c)大雨注意報、警報を出す時、たとえば二次細分区域で採用されている「○○平野北部」「XX沿岸」などの名称はあるが、特定の
市町村の名称は入れない。×
解答:2:
- (2)台風が衰弱するにつれて暴風域(風速25m/sの地域)の半径は次第に小さくなるので、暴風警戒域の半径も次第に予報円の半径
に近づく。しかし、台風の進路予報で暴風警戒域が描かれていない場合は、暴風域が存在していない(もともとなかったか台風の衰弱にともない
消滅した)ため、暴風警戒域そのものがないから。暴風警戒域が予報円と重なる事はありえない。×
- (1)台風の進路予報は、現在、48時間先までは3時間ごと、72時間先までは6時間ごとに行われている。○
- (3)中心付近の最大風速と言う場合は、瞬間最大風速ではなく、10分間の平均風速のだということに注意が必要である。○
- (5)台風が温帯低気圧に変わっても、日本への影響が引き続き大きいと判断されれば、特定低気圧に関する情報として発表される。○
解答:2:
1時間ごとではなく、3時間ごとに発表。
解答:1:
立体画像ではなく平面図。大雨による土砂災害の発生は、土壌中に含まれる水分量に深い関係が有る。それを
見積もるために土壌雨量指数は考え出された。数字が大きいほど土壌に含まれる水分量が多い事を表し、したがって土砂災害の
危険性が高いと判断される。
解答:3:
(b),(c)は間接的に引き起こされたもの。
解答:5:
雨が多く降る場合は、流されて薄められて、塩害はましになる。冬には、強い上昇流にともなう積乱雲が発生しにくく、
雲中の小さな氷の粒が雹まで成長できないことも、冬の雹害が少ない理由のひとつ。
解答:1:
河川の改修工事や護岸工事のため、近年では大河川の氾濫や高潮被害は減少傾向にある。
- (2)最近の大雨による崖崩れなどの土砂災害は、丘陵地や急傾斜地への居住域拡大にあるといわれている。
- (3)都市のアスファルト舗装が進んだ事にともなって、内水氾濫がよく発生するようになっている。
- (4)雨が降りやんでも、それまでに土砂中に水分が多く含まれていれば、土砂災害が起こる危険性は十分にある。
- (5)浸水害や、崖崩れなどの地面現象注意報・警報は、気象注意報・警報に含めて発表する事になっている。
解答:1:
降雨により山崩れや地滑りなどの地面現象による災害または重大な災害が起こるおそれのある場合には、地面現象注意報または
地面現象警報が出されるが、これらは気象注意報・警報(このなかに大雨注意報・警報が含まれる)に含めて発表されることになっている。
したがって、大雨とは言えない程度の降雨によっても山崩れが発生して(重大な)災害が起こるおそれのある場合には、大雨注意報・警報の
対象となる。
- (2)北日本の大雨注意報・警報の基準値は、概して西日本や東日本のそれより小さい値になっている。
- (3)表層雪崩は真冬に、全層雪崩は春先の融雪期に起きやすくなる。
- (4)注意報・警報の発表基準としては、数週間以上の長期にわたるものは対象にならない。
解答:4:
- (a)気象庁が直接、市町村役場に伝達することはない。×
- (b)(d)テレビ・ラジオ局、新聞社などの報道機関には伝達する。NHKは法定伝達先。
- (c)交通機関へは伝達する。通知を受け取った交通機関では、列車の運行や道路交通の確保に努める。
したがって、3個が正しい。